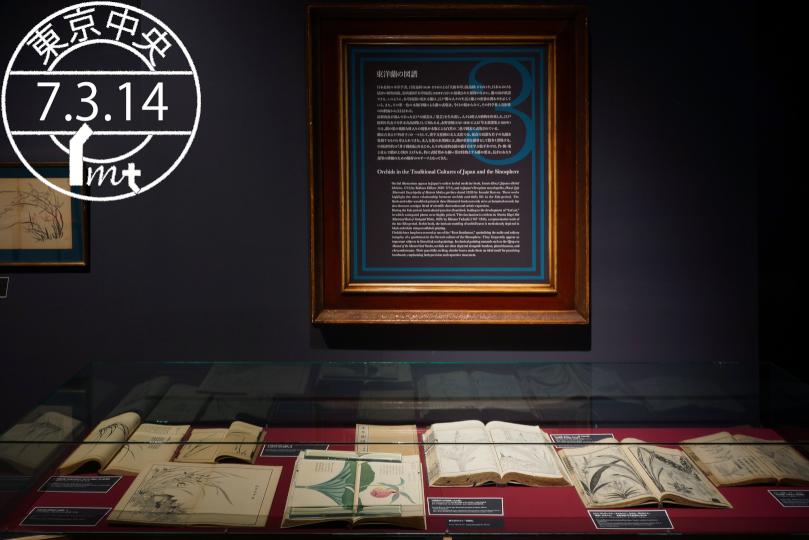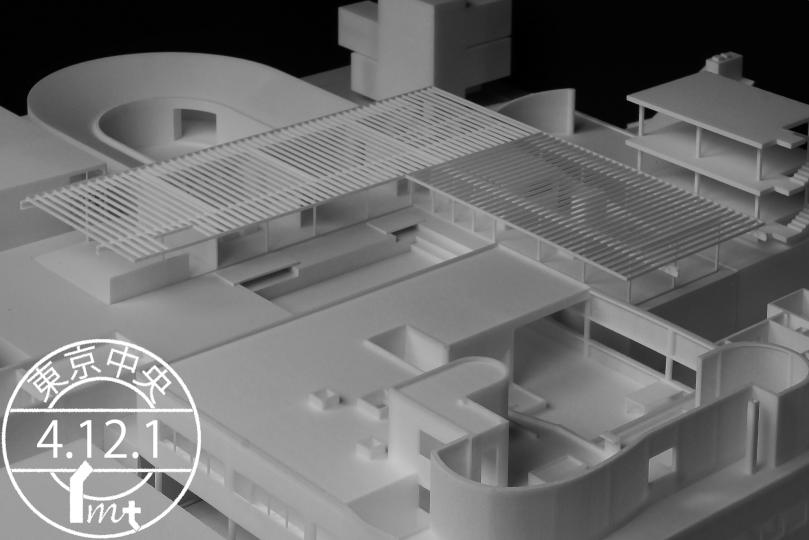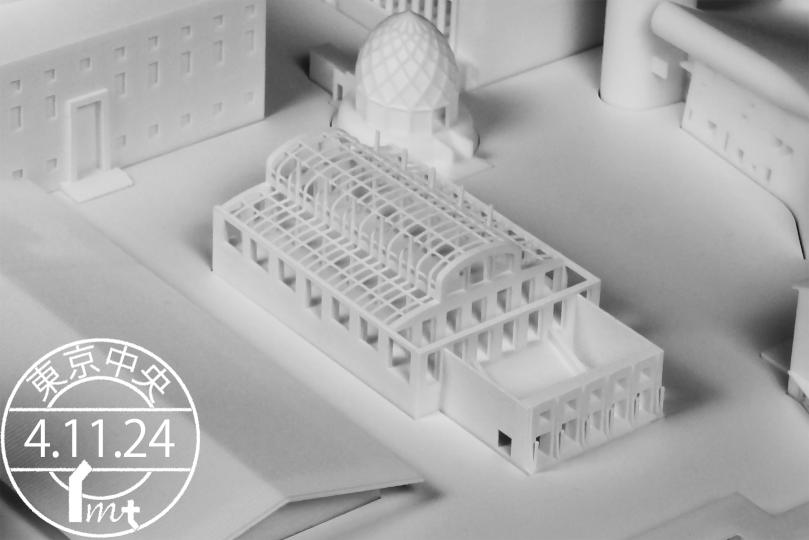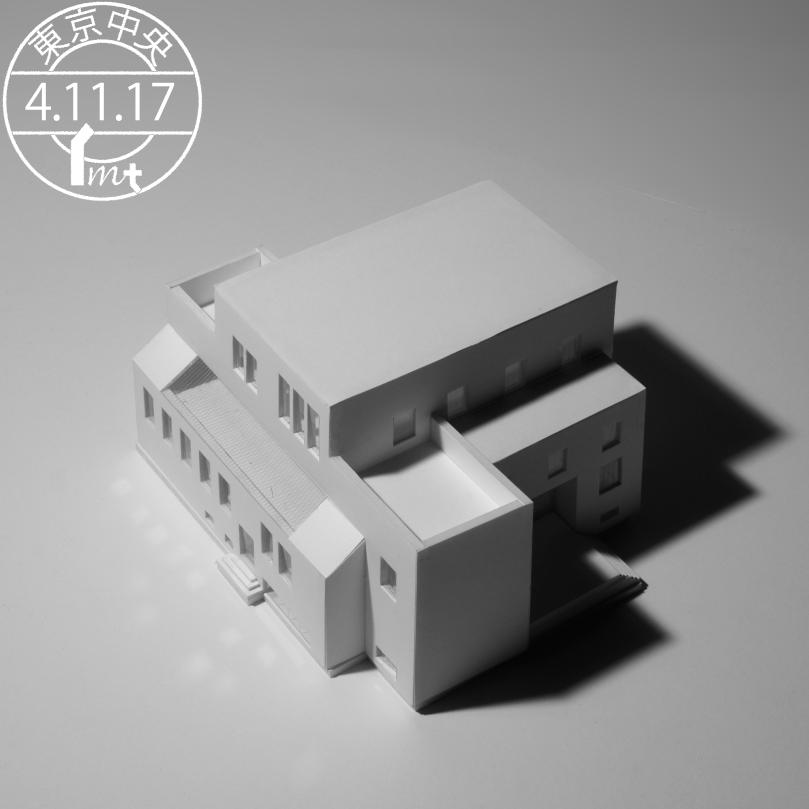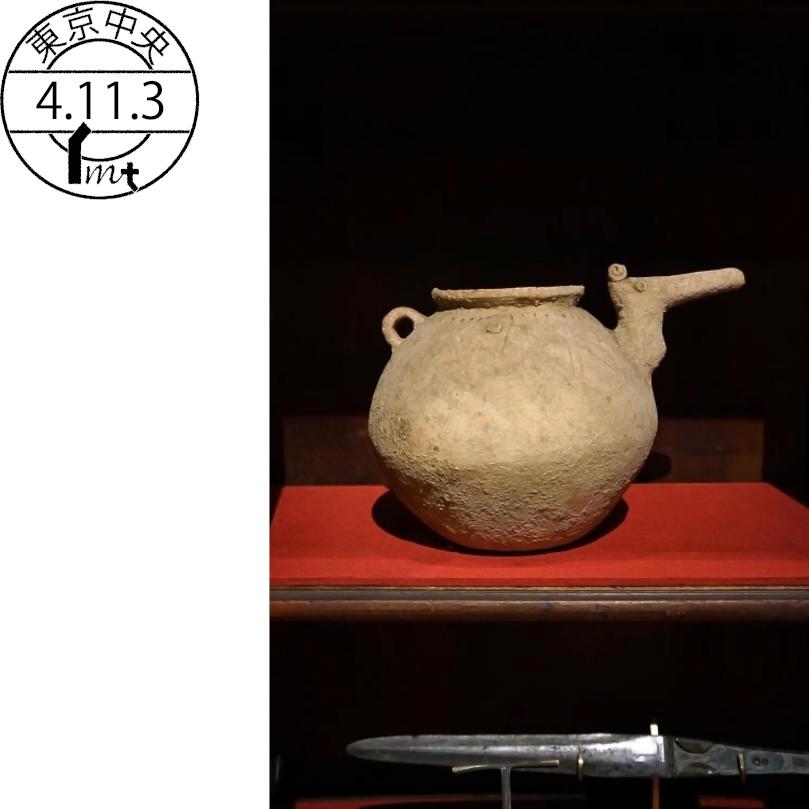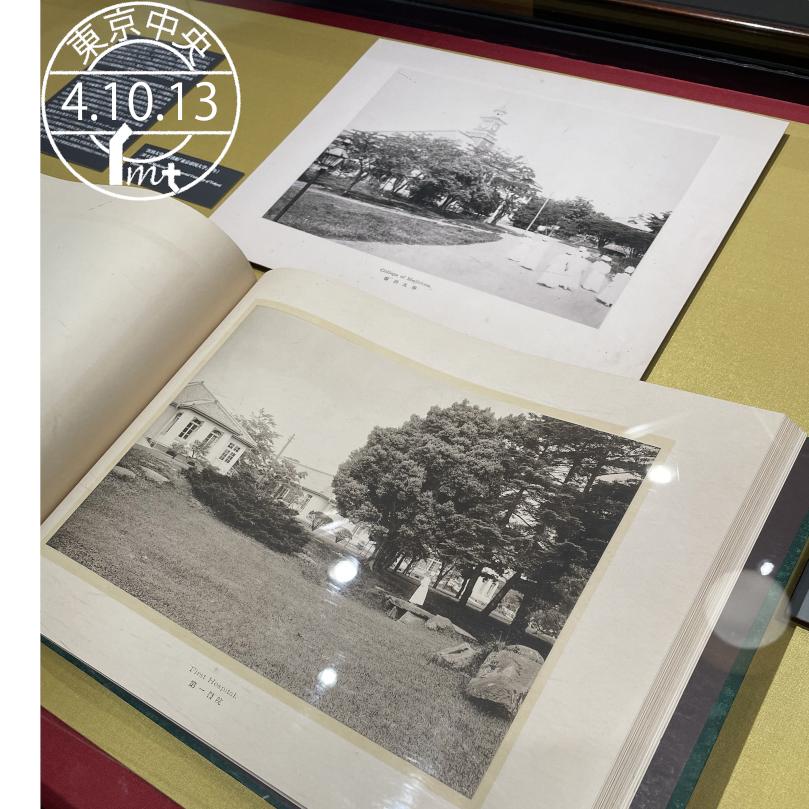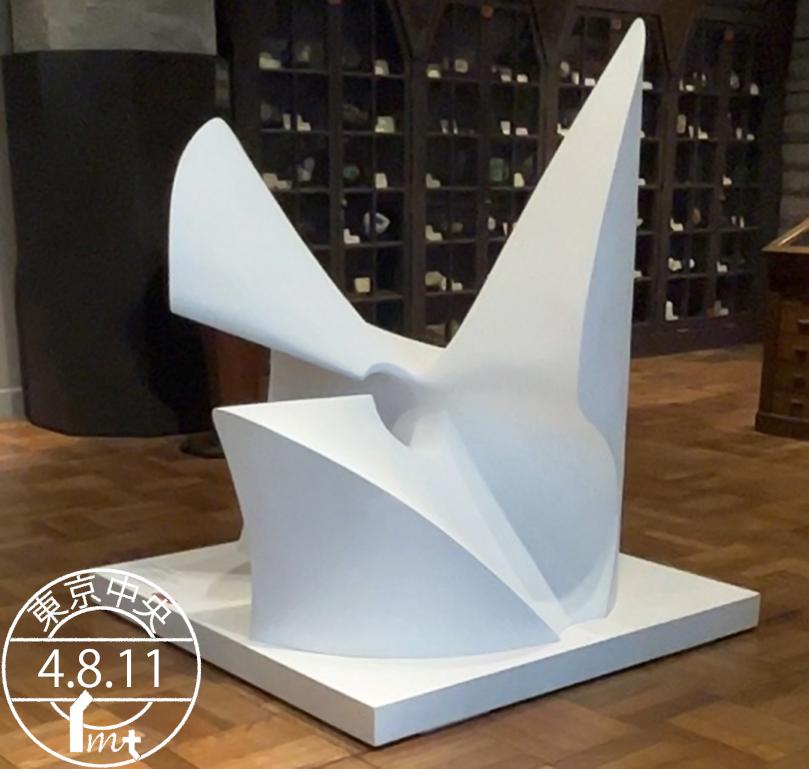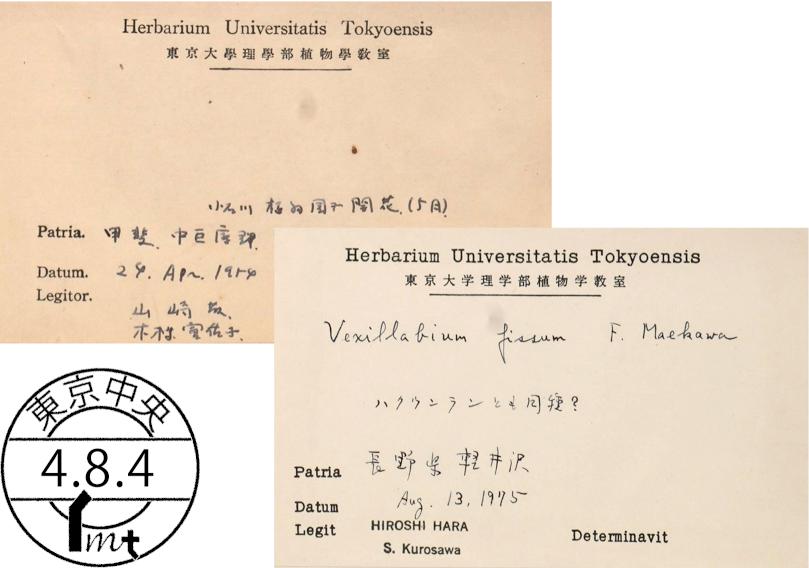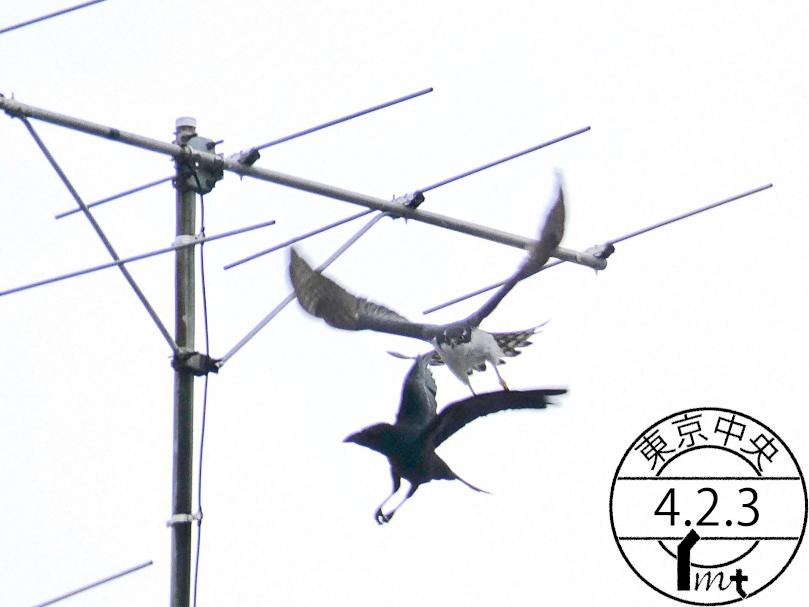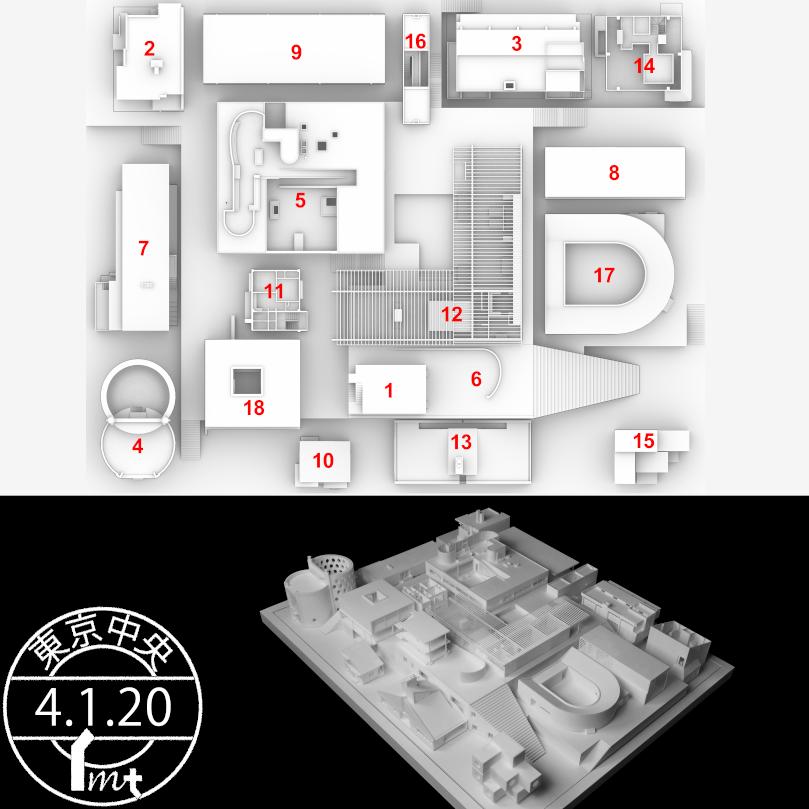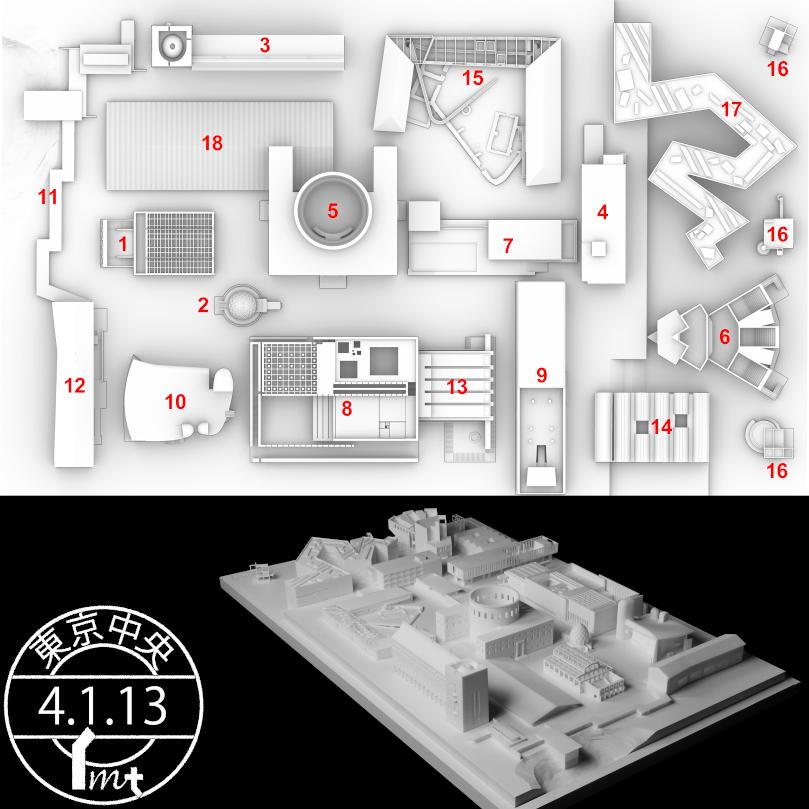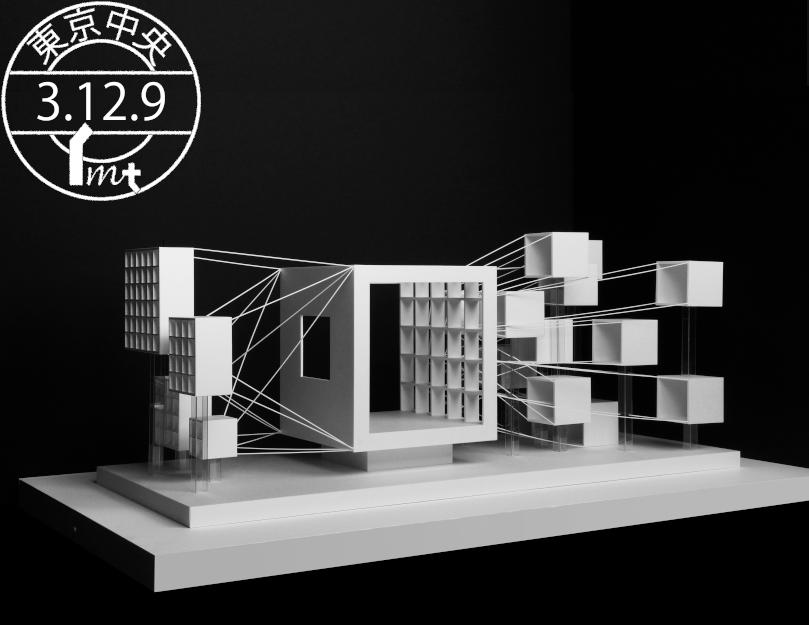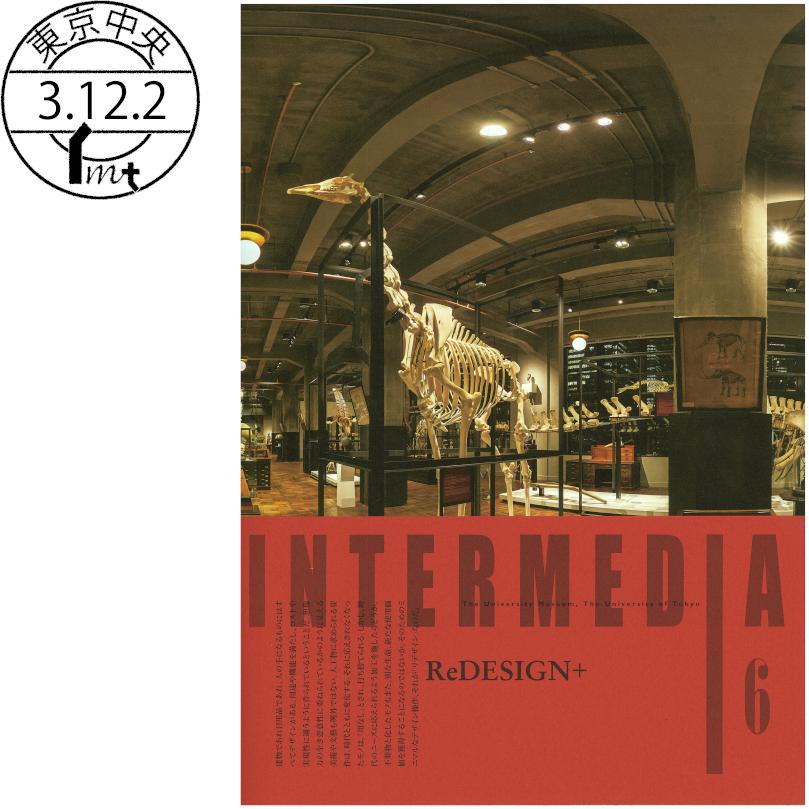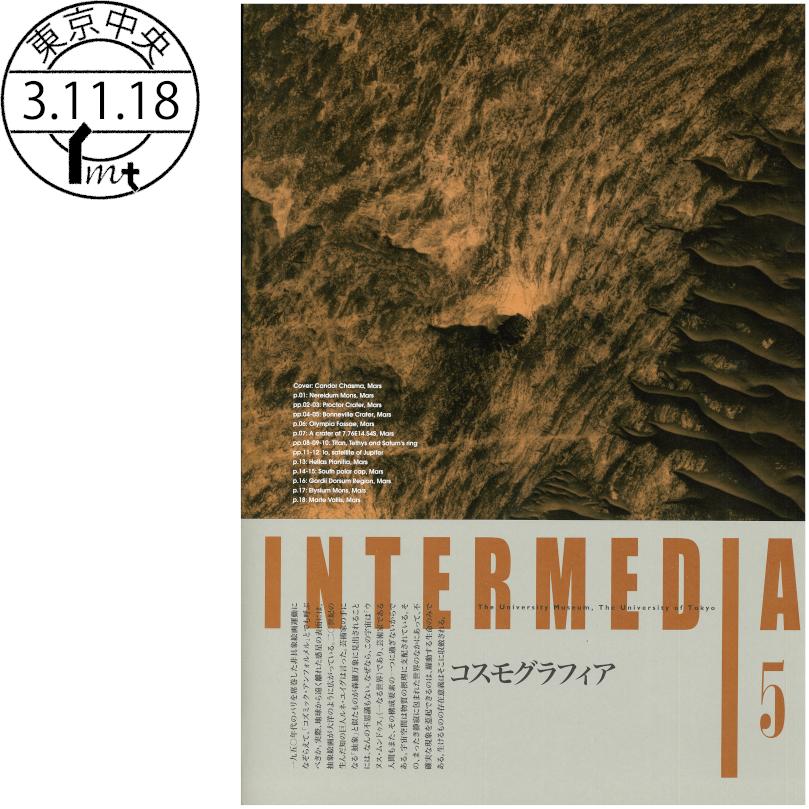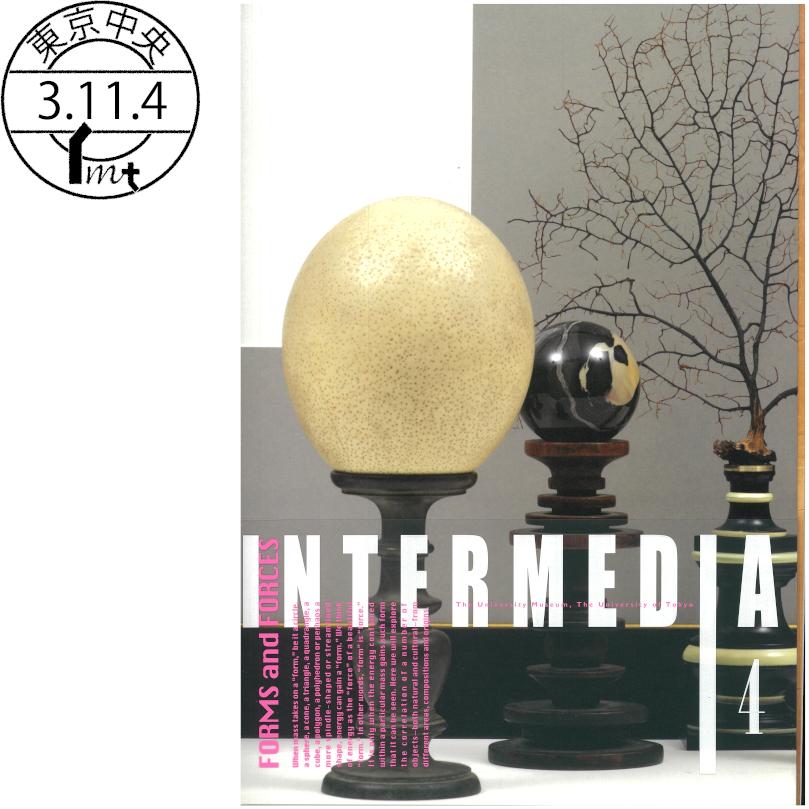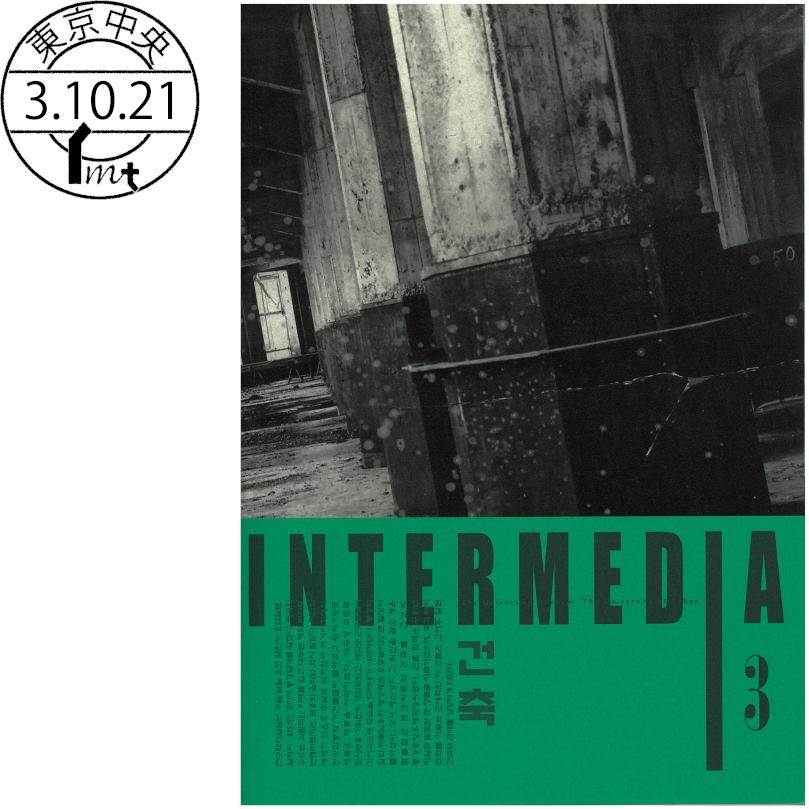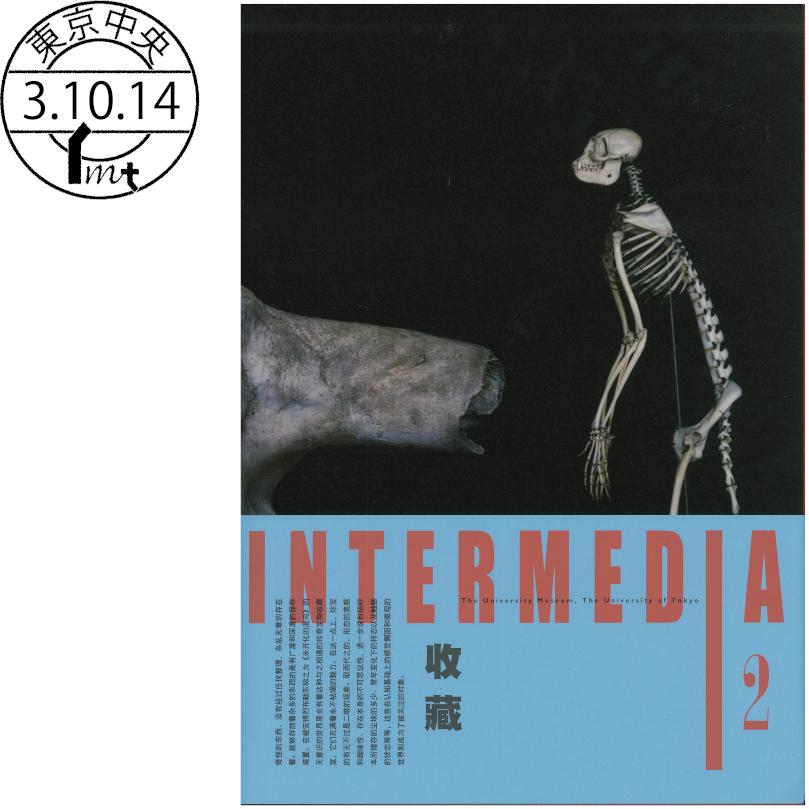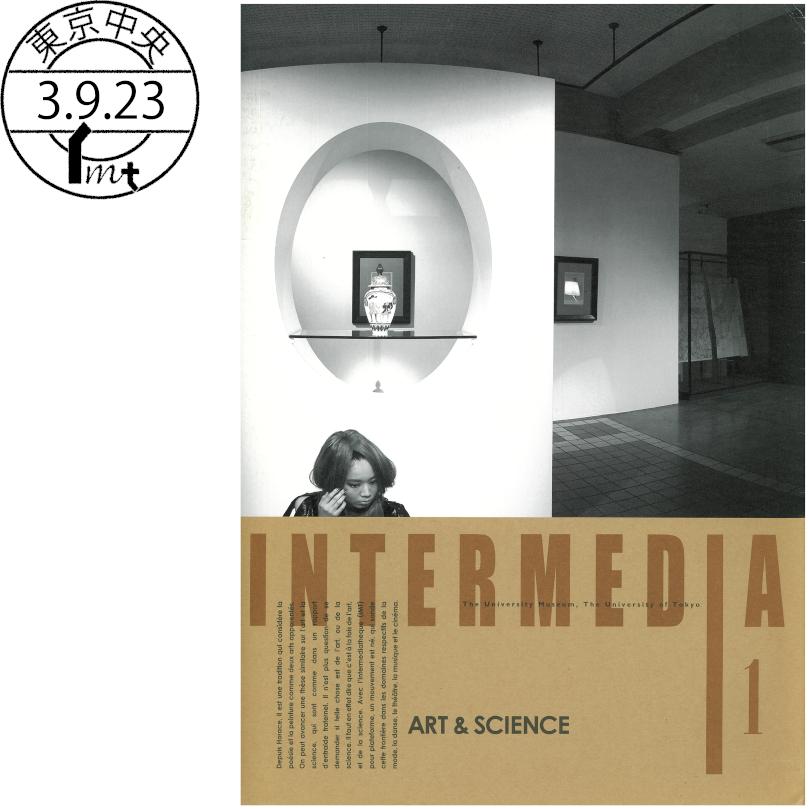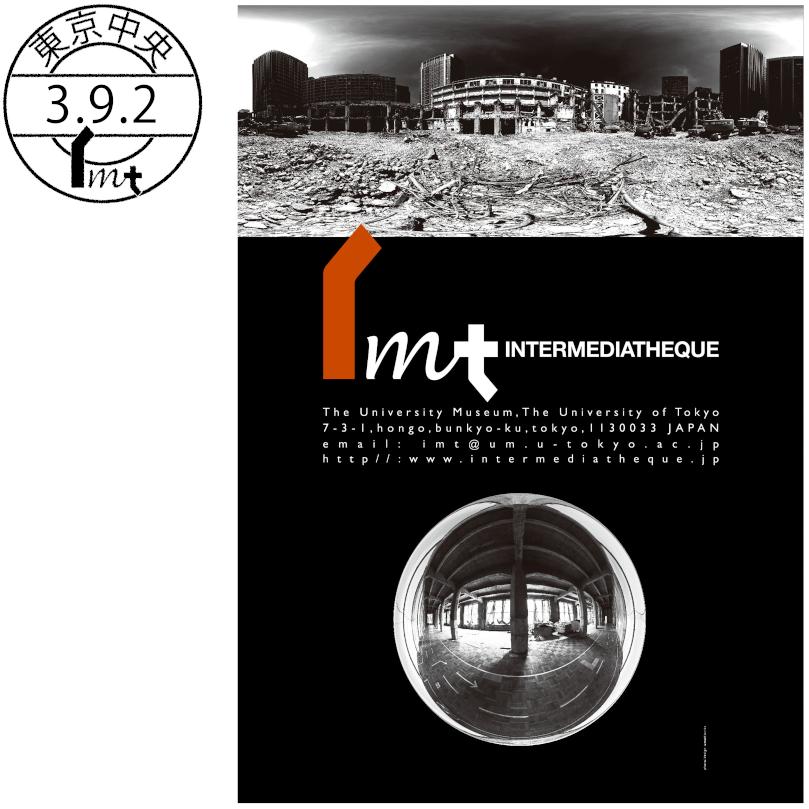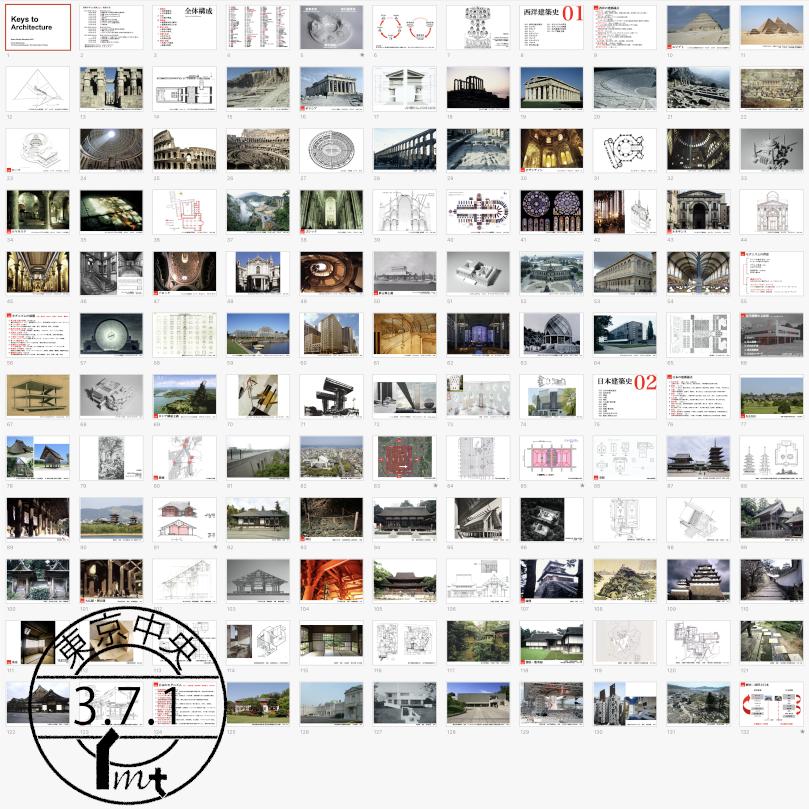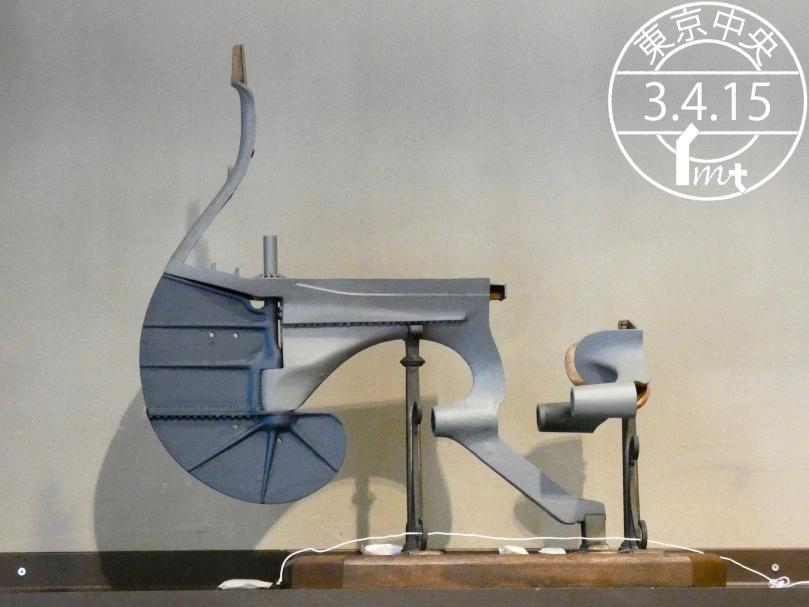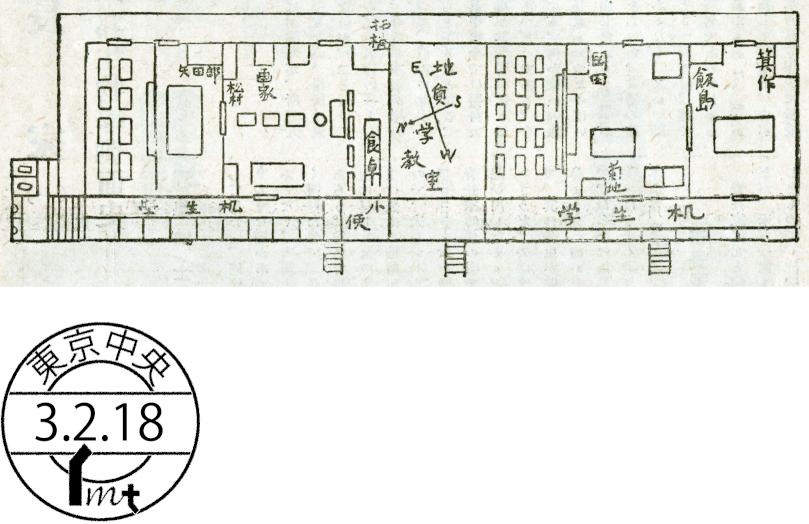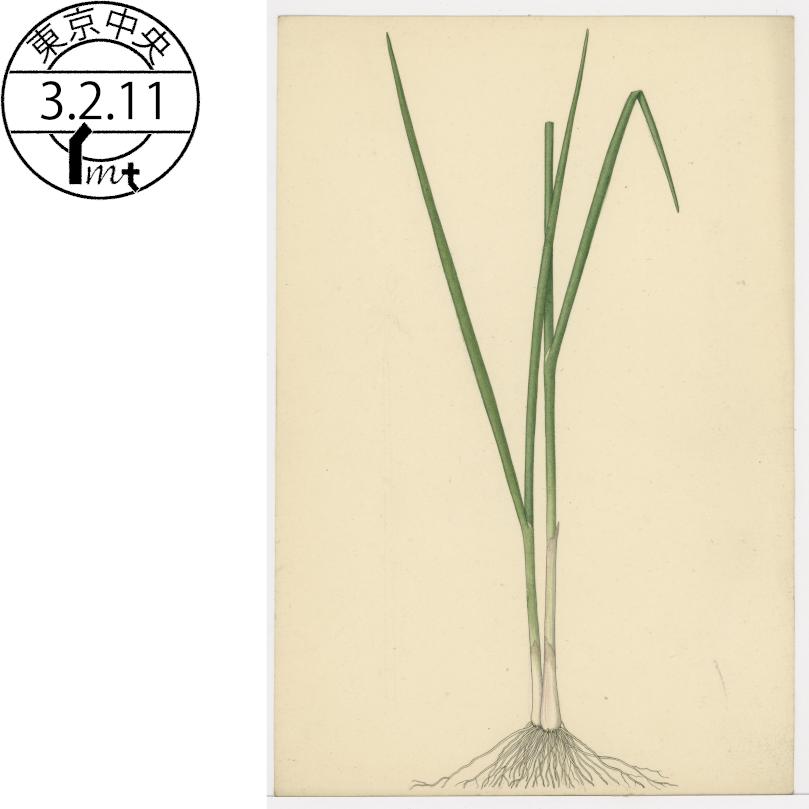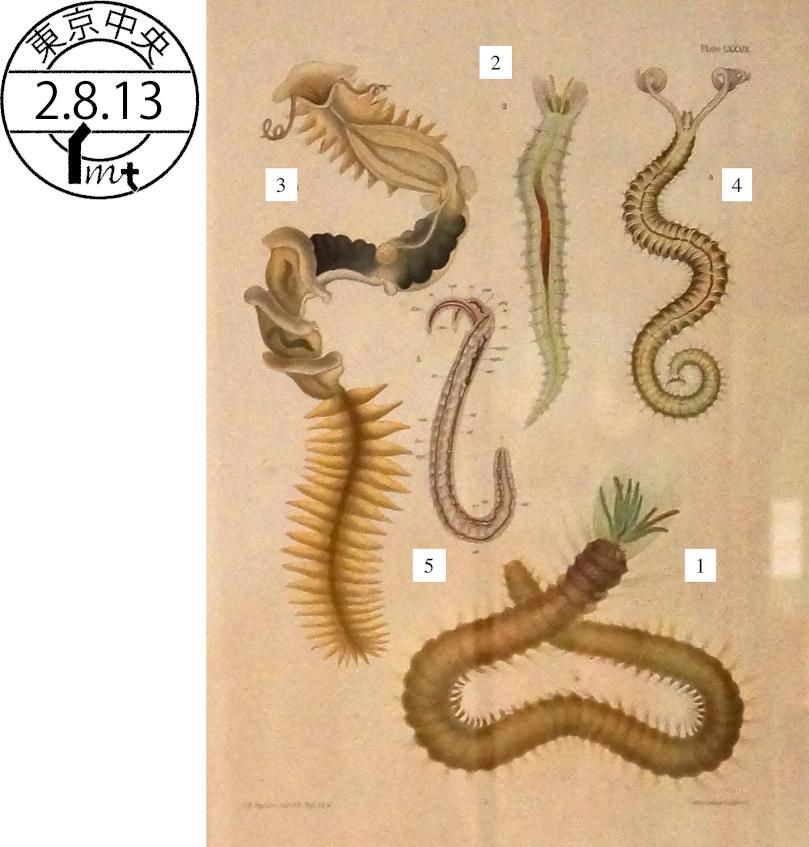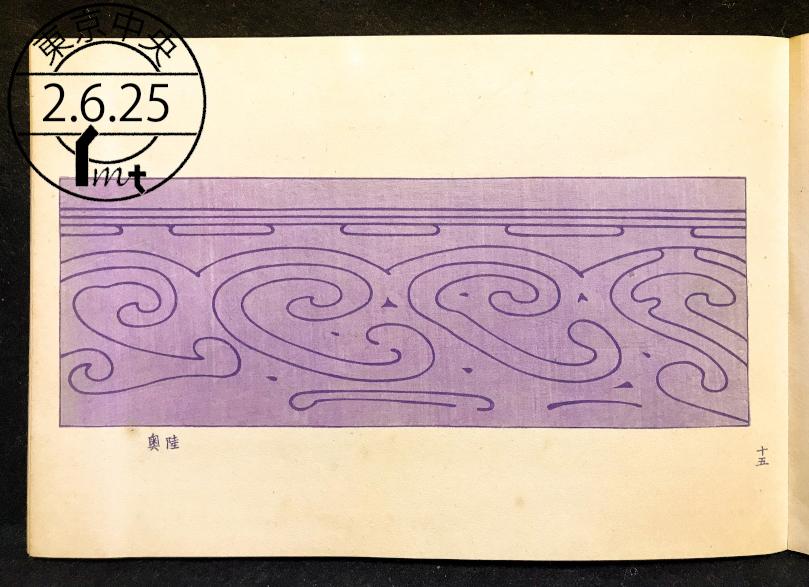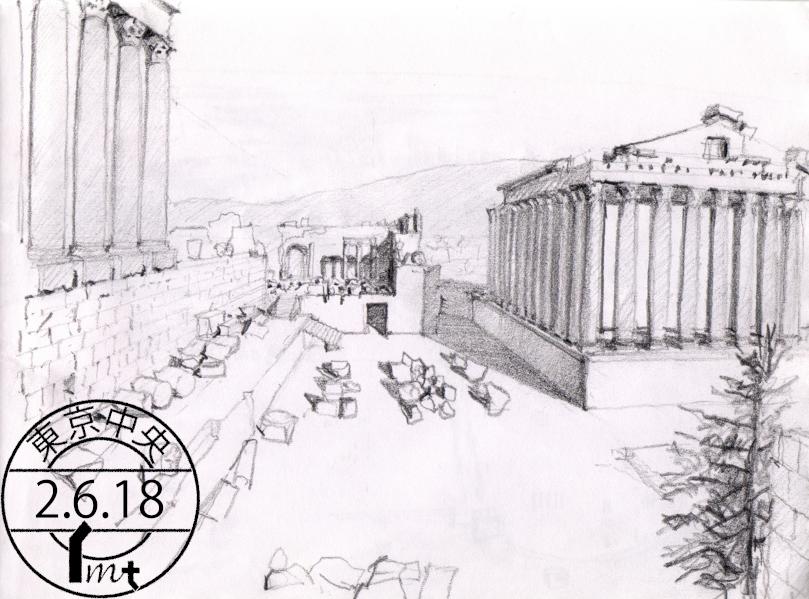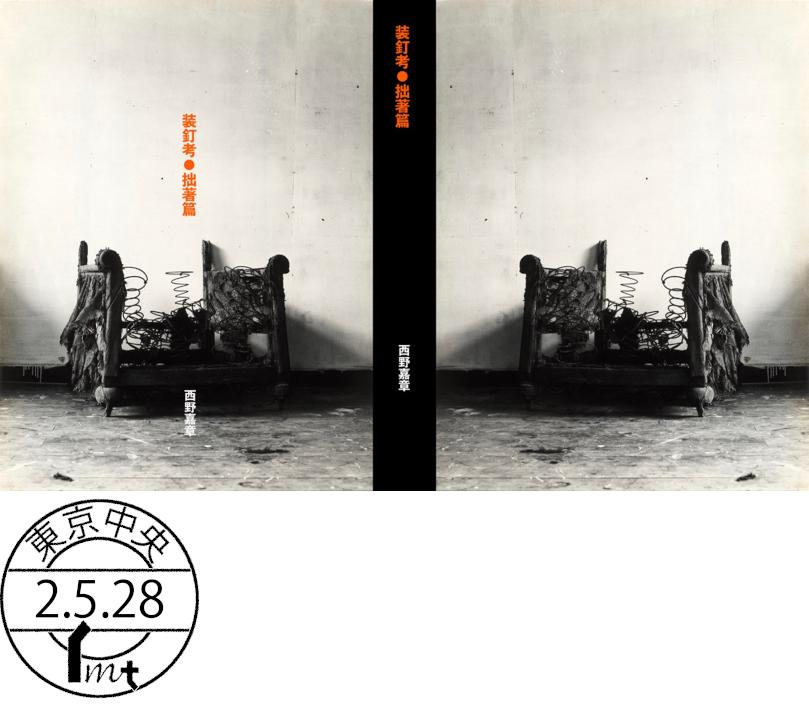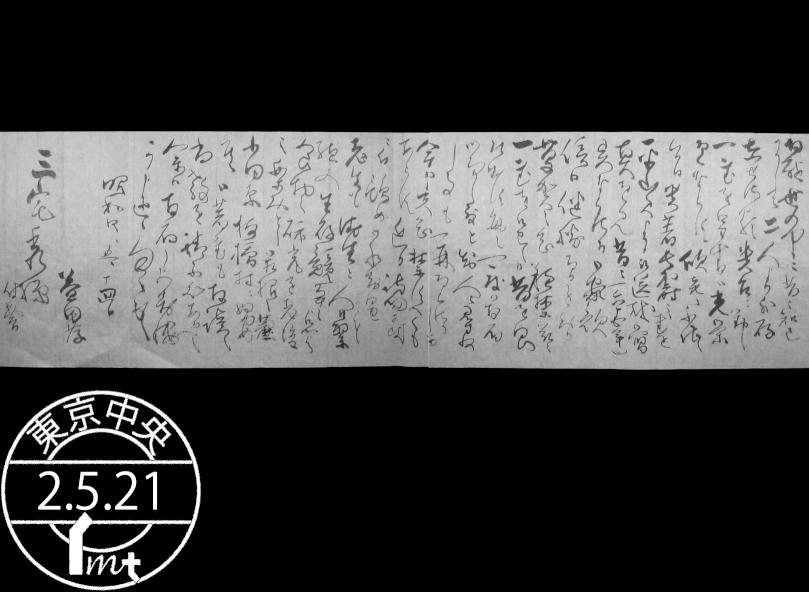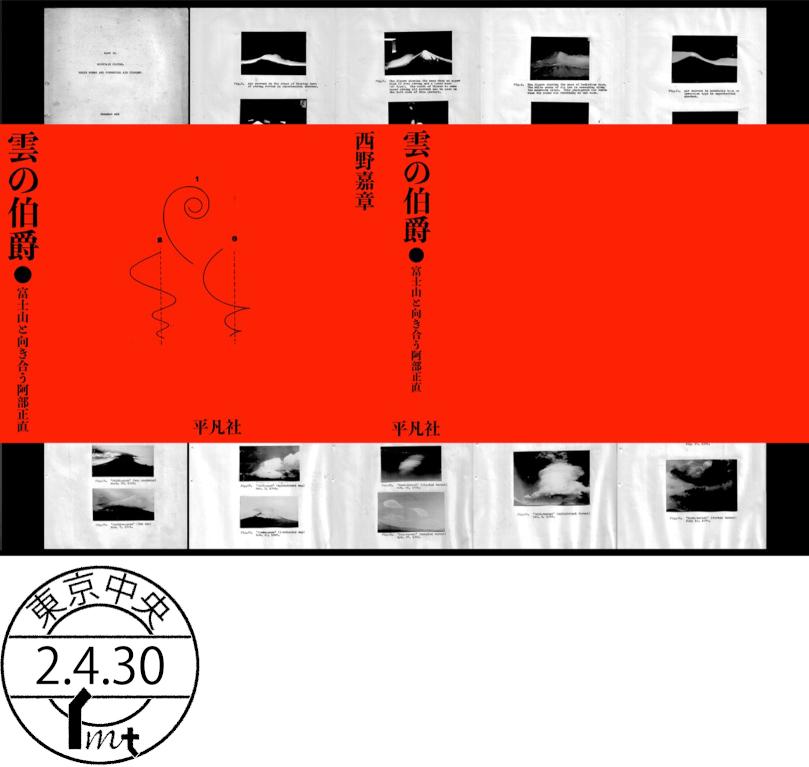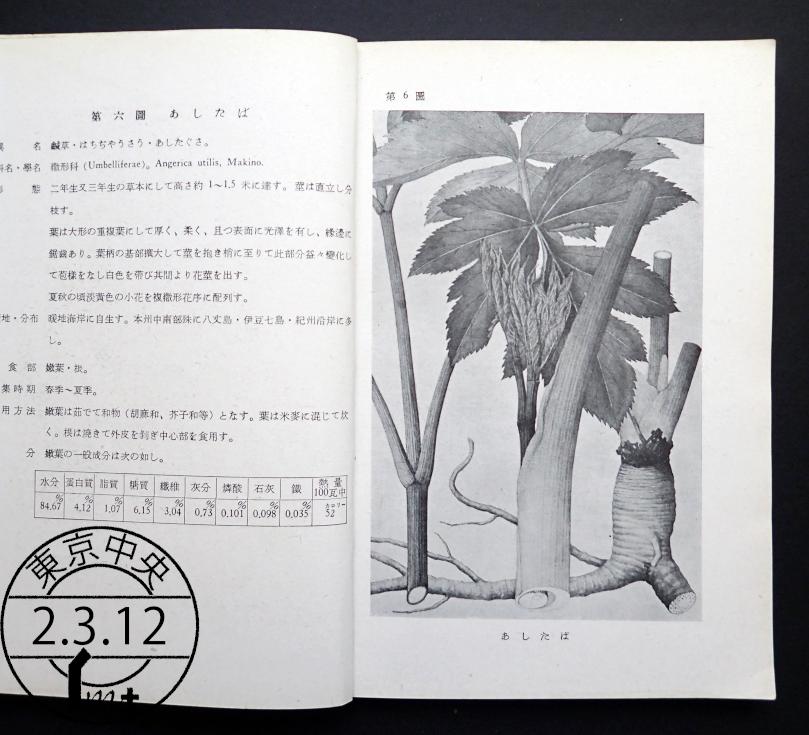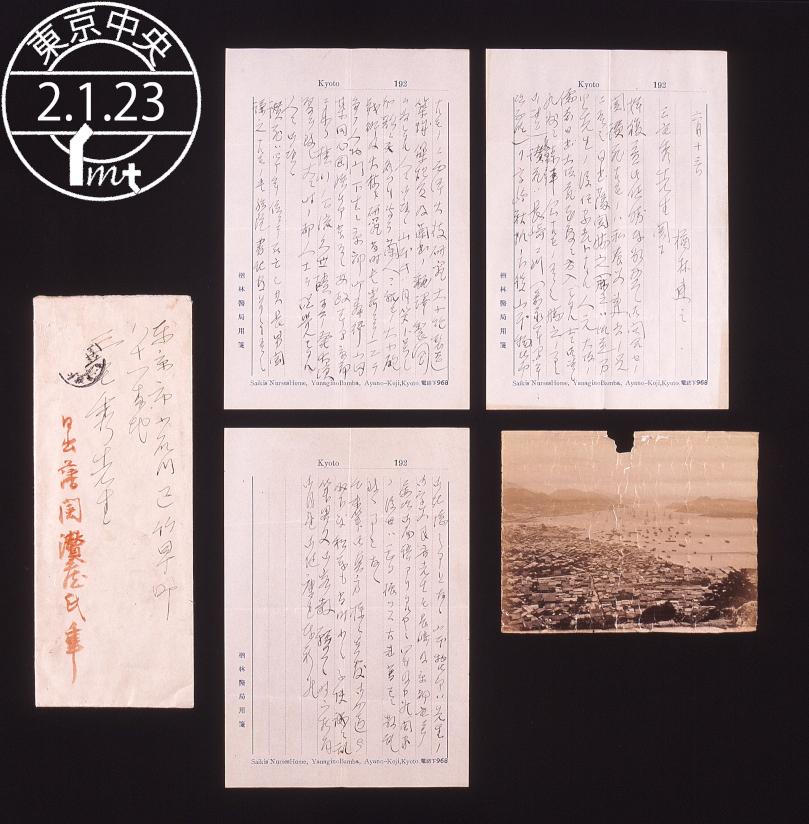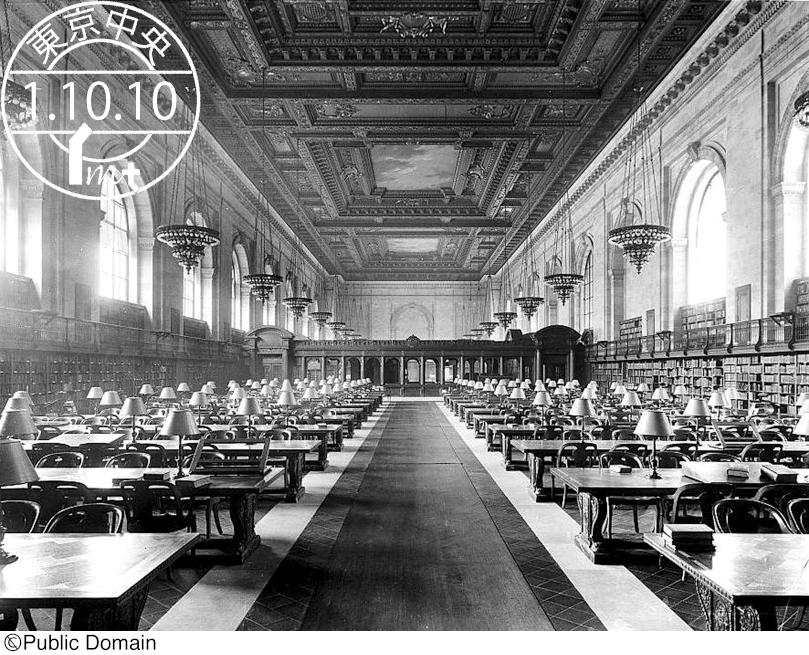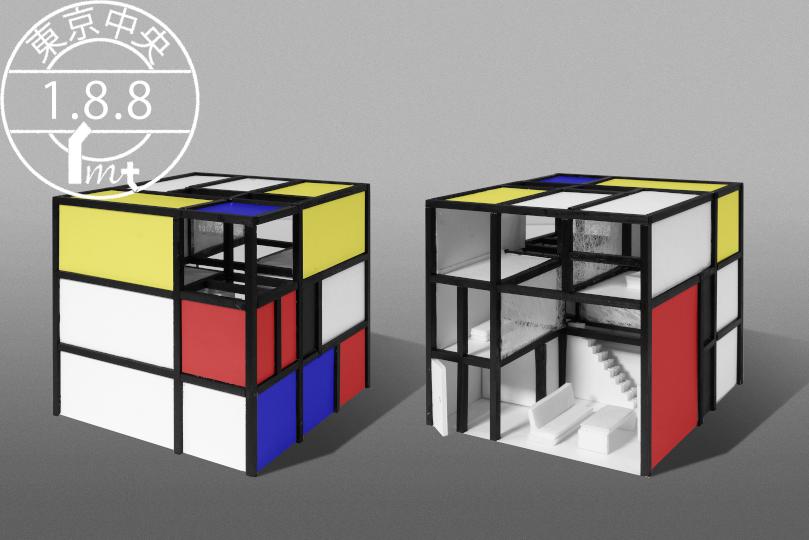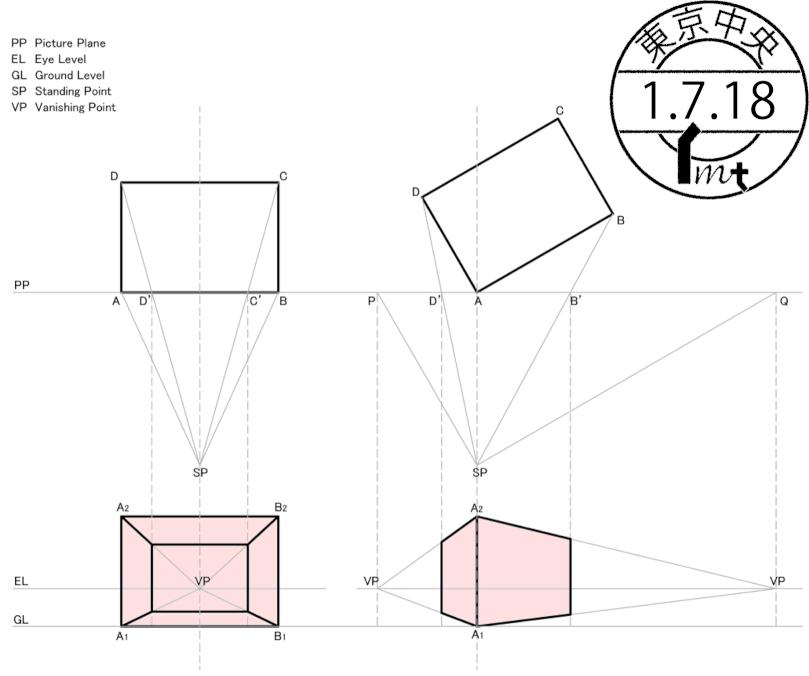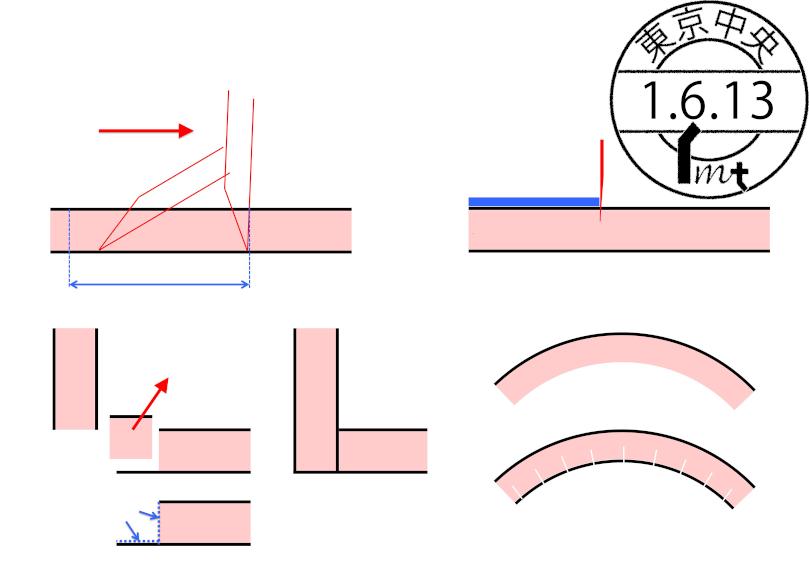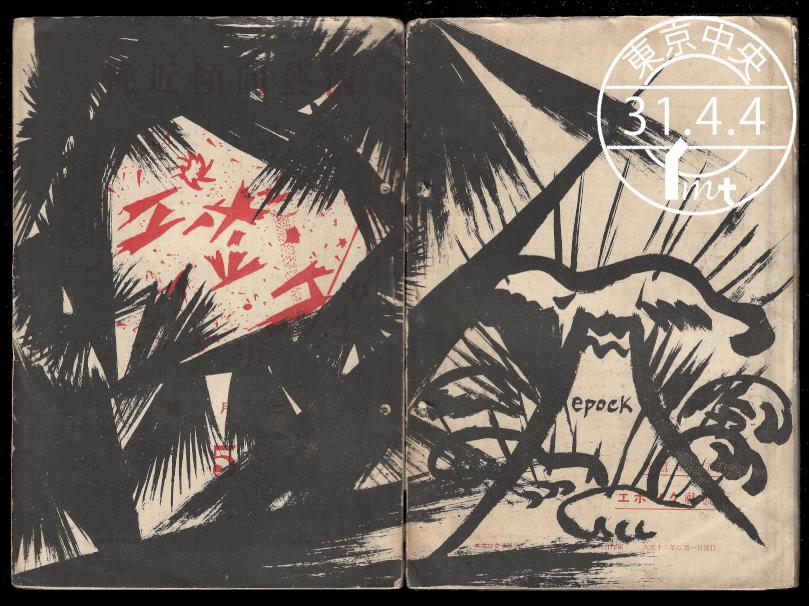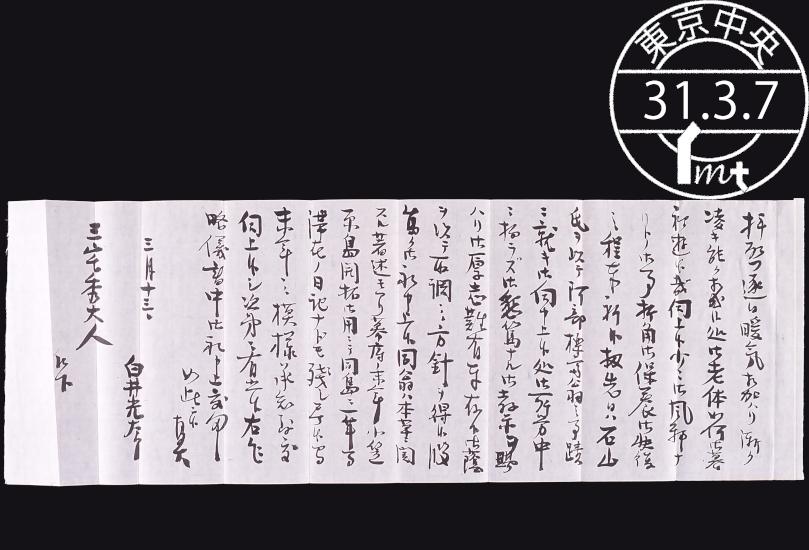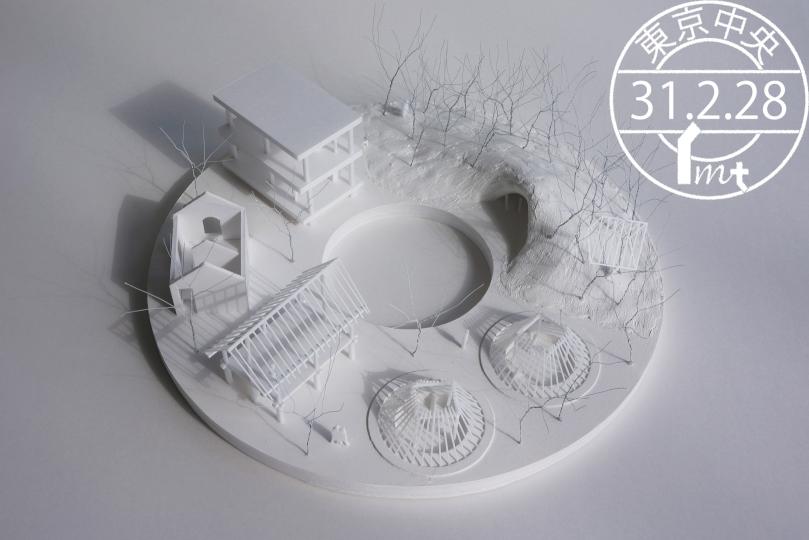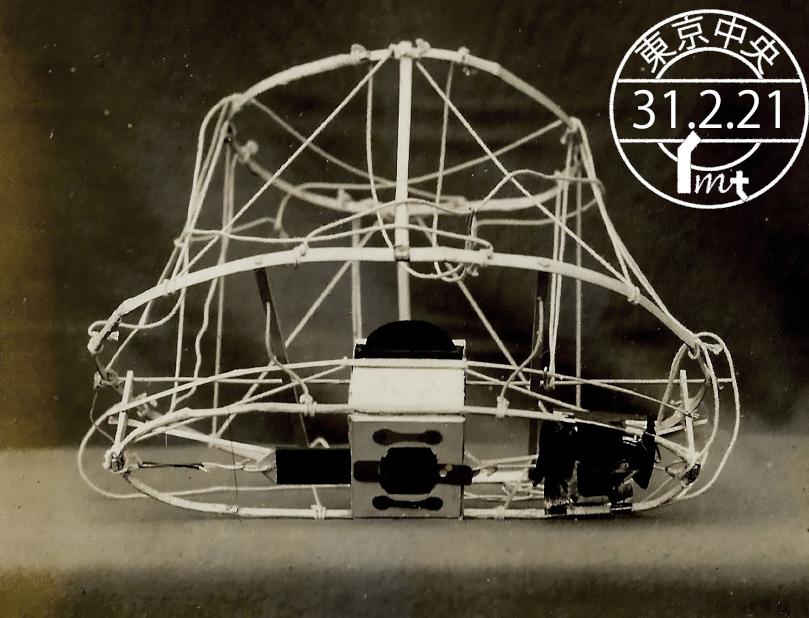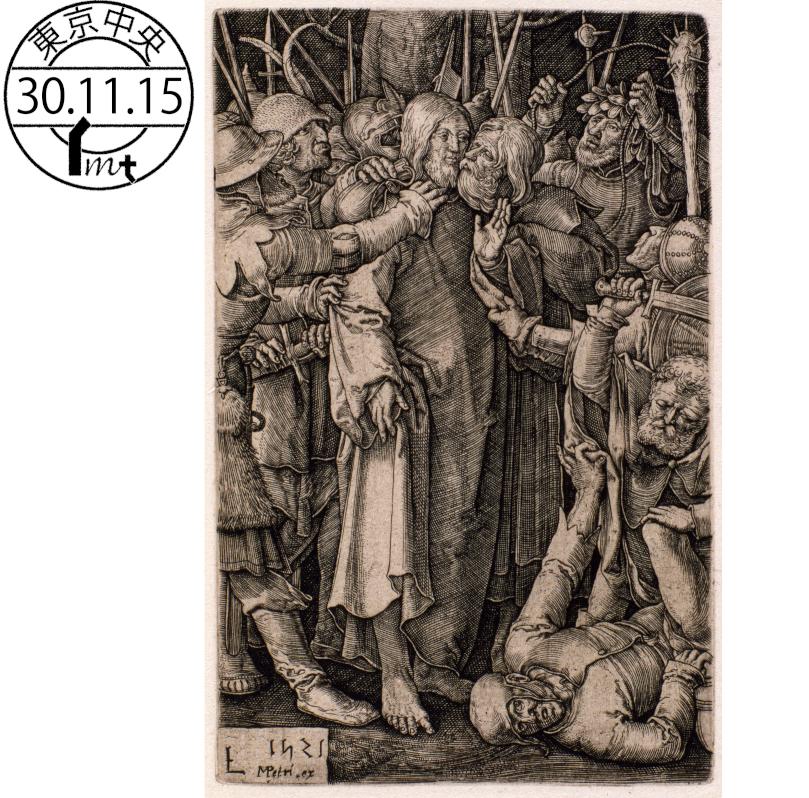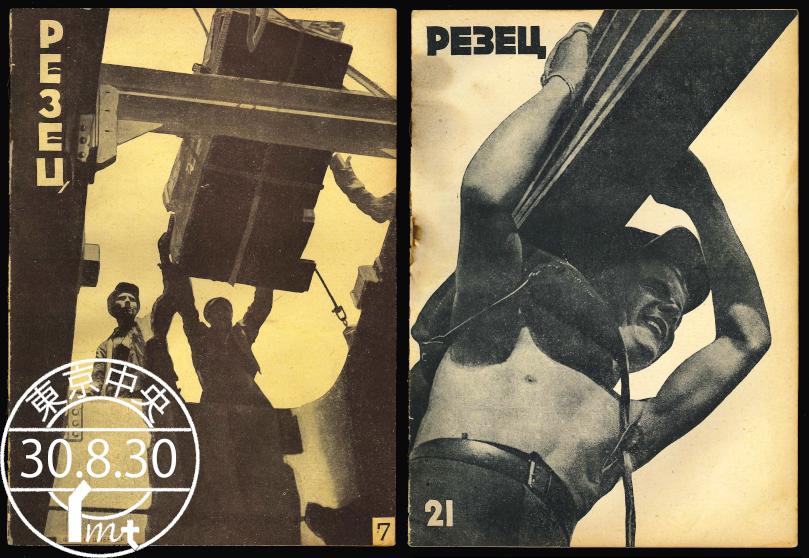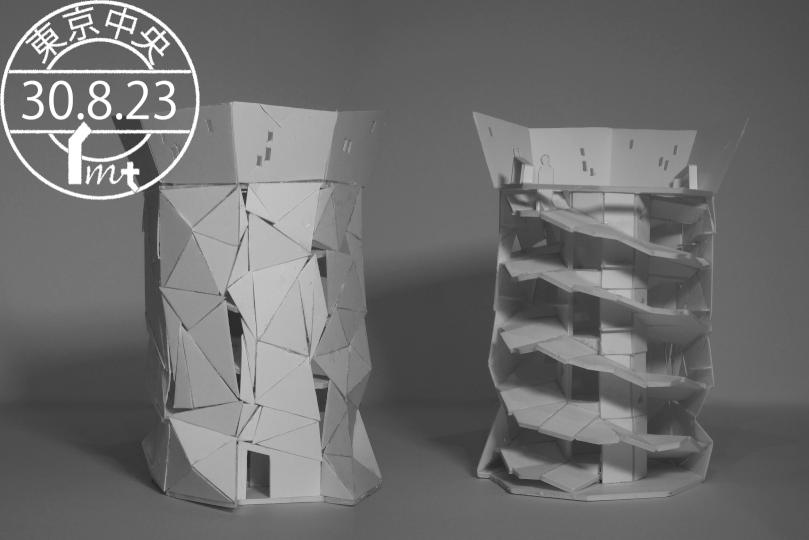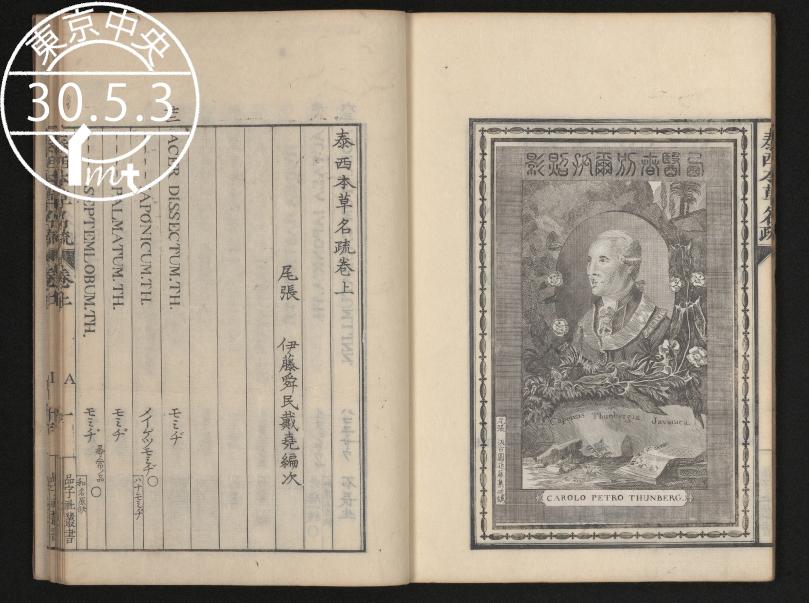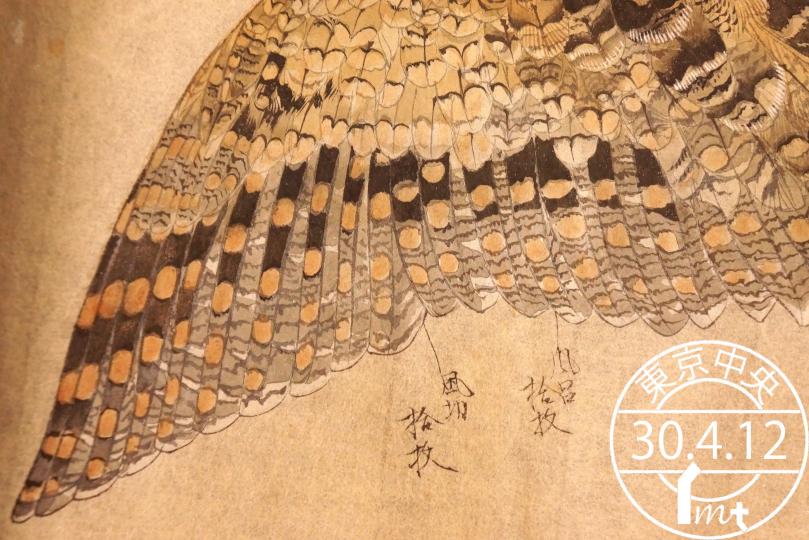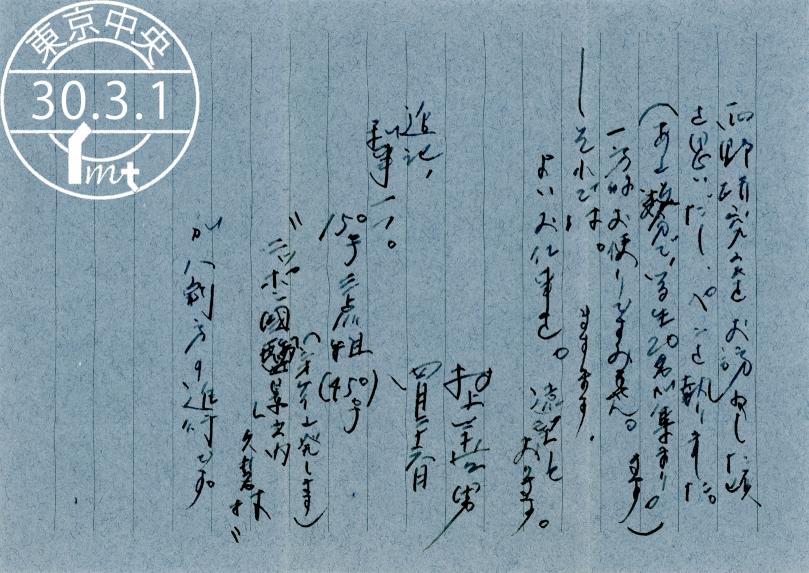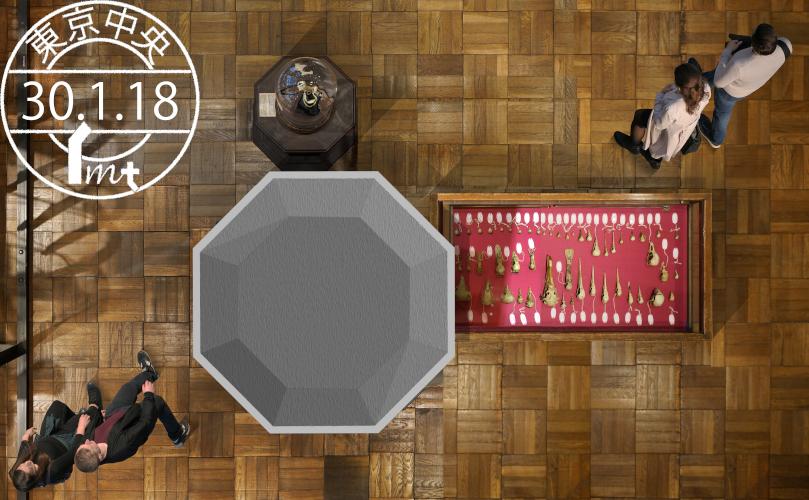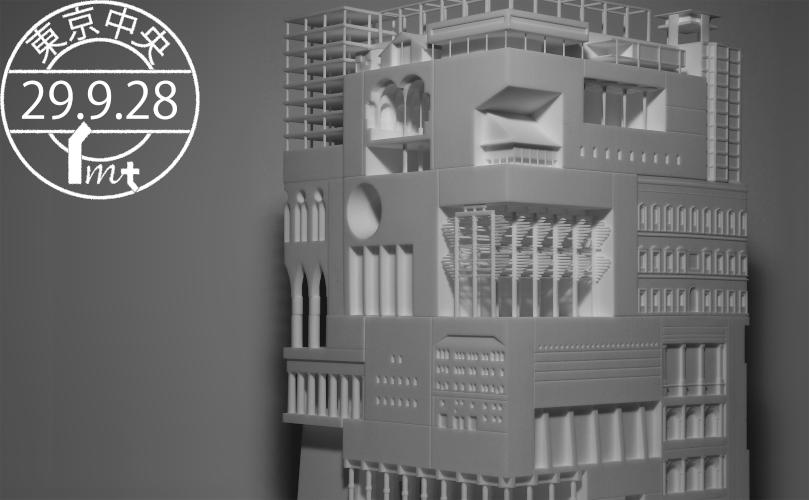台北植物園の蘭温室と池
The Orchid Greenhouse and Small Pond at the Taipei Botanical Garden
台湾の農業部林業試験所標本館には、20世紀初頭、台北植物園内にあった林業試験場時代に撮影されたガラス板写真が残されている。そのなかに、当時の林業試験場の蘭温室の内部を写したものがある(画像右)。この温室の建物が現存すると聞き、2024年12月、『台湾蘭花百姿』の図録の印刷会議のために国立歴史博物館に行き、そこからすぐ裏手にあたる台北植物園を訪れた際に、ぜひ見てみたいと現地に赴いた。温室の前で、案内くださっていた園長の范素瑋さんに、『台湾植物写真集』に載る、台北植物園で1927年4月に撮影されたカトレヤの写真(画像左)を見せて、後ろに映る小さな池から撮影場所が特定できないかと聞いてみた。すると、温室の正面にあり、いまはホテイアオイがびっしりと群生している小さな池がそれであることが判明した。写真と同じと思われる池の縁石も見つけた。『台湾植物写真集』のカトレヤの写真は屋外で撮影されている。中央アメリカとコロンビア地方原産のカトレヤが、当時、台北では屋外で栽培されていたのかと疑問に思っていたのだが、蘭温室から鉢植えを屋外に持ち出し、すぐ近くの池の前で撮影したのだろうという状況が推定できた。鉢が写り込んでいないのは、自然光のもと、カトレヤの花をより自然に園内の風景に溶け込ませたいという写真家の芸術的感性のためかもしれない。『台湾蘭花百姿 – 東京展』の展示会場では、蘭温室の写真と池の前で撮られたカトレヤの写真が、偶然にも実際の位置関係に近いかたちで展示することができた。つまり、池を背景にしたカトレヤを正面に眺めて、右後ろに振り返ると、蘭温室の内部が見える。東京展は6月8日まで。
寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)
Ayumi Terada
『蘭花譜』が伝えるもの
What A Record of an Orchid Collection Suggests
実業家の加賀正太郎が京都の大山崎山荘の温室にて栽培した蘭を記録した『蘭花譜』には、台湾固有種のタイリントキソウを描いたものがある。これは、台湾の蘭が戦前の日本で蘭愛好家の手により栽培されていた歴史を物語る。今回の『台湾蘭花百姿』展では、『蘭花譜』より、大山崎山荘で作出された栽培品種の図譜も紹介している。展示更新後の東京展の後期展示(4月15日−6月8日)では、日本画家の池田瑞月が下絵を手がけ、精緻で色彩豊かな多色刷り木版画で表された大判の植物図譜「シプリペディウム・ユーフラシア・オオヤマザキ」と「シンビジウム・ドッテレル・オオヤマザキ」の2点を会場にて見ることができる。これら栽培品種の図譜を『台湾蘭花百姿』展に組み入れたのは、日台の蘭栽培交流史をその背景に見出せるからである。大山崎山荘で蘭栽培に従事した後藤兼吉は、新宿御苑の出身で、蘭栽培の知識を惜しみなく後進に授けたといわれる。後藤が蘭栽培を指導したなかには、のちに台湾で活躍した技術者らが含まれていた。また、後藤のもとから、つまり大山崎山荘から、実生や開花株が台湾に渡り、それが台湾における洋蘭栽培の発展に寄与している。日台の蘭栽培交流史は、まだまだ私のなかで調べが足りていない。『蘭花譜』は、さらにそのテーマでの調査研究を広げていける可能性をもった資料体であるだろう。
寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)
Ayumi Terada
東洋蘭の図譜
Orchids in the Traditional Cultures of Japan and the Sinosphere
「東洋蘭の図譜」とは、やや大きなテーマであるが、特別展示『台湾蘭花百姿 – 東京展』のなかで、他のパートとのつながりにおいてぜひ取り上げたいと考え、パート3に設定したものである。蘭は、台湾のみならず、日本を含む東アジアの漢字文化圏において、人々と深い関係性を築いてきた。古来より、四君子の一つとして、孤高で高潔な君子の気風を象徴するものと考えられてきた蘭は、パート4「台湾蘭と⾃然・芸術・⼈間」で映像にて紹介している「国立歴史博物館の蘭」が示すように、文人文化の水墨画の重要な題材として数多く登場する。人々が伝統的な絵の描き方を学ぶ絵手本によく取り上げられてきた蘭の画題は、この人気を象徴する証拠資料といえる。日本最初の本草学書、貝原益軒による『大和本草』諸品図や、日本における最初の植物図鑑、岩崎灌園『本草圖譜』に収載された植物のなかに現れる蘭の数々は、パート1「⽇本⼈植物学者による台湾ラン科植物調査」の中心にあった、東京大学黎明期に発展を遂げた近代植物学に対して、その礎となった江戸時代の本草学における蘭への科学的なまなざしを示している。また、その木版印刷による蘭の表現は、今日の眼からみて、その科学性と美術性の両側面から注目され、パート2「台湾蘭の栽培と観賞」の美術・デザインのモチーフとなった蘭の表現やパート4の植物画と比較したときの類似と差異の点においても興味深い。東京展の会場では、パート3を見た後に、パート4に進むだけでなく、もう一回り展示を見ていただくと、時代やジャンルを架橋して「台湾の蘭の博物誌」を楽しむことができる。
寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)
Ayumi Terada
初公開の山田壽雄ラン科植物画
First Public Display of Yamada Tishio’s Orchid Illustrations
特別展示『台湾蘭花百姿 – 東京展』のパート4「台湾蘭と自然・芸術・人間」では、山田壽雄の描いたラン科植物画を初公開している。本資料は、2023年12月に東京大学総合研究博物館が寄贈を受けた新規収蔵資料で、58点のなかから、本展示では、台湾蘭を描いた5点を紹介する。前期展示(4月13日まで)では、ツバメセッコク・ベニバナセッコク・タイワンセッコクの三種を描いた1点に、コチョウランおよびホウサイの図を合わせて、計3点を公開している。山田壽雄は、福島県に生まれ、植物学者の牧野富太郎に描画指導を受け、植物を専門に描くようになった画家である。牧野は、自身で植物の精密な図を描き、その詳細な解説文を綴ることのできる稀有な植物学者であった。その牧野の要求に応えて植物を描くことのできる者と言えば、山田の植物画家としての優れた力量が窺い知れるであろう。本展示で紹介する台湾蘭の図は、李王家東京邸で栽培されたものを山田が描き留めたものであり、台湾蘭が戦前の日本で栽培されて花をつけた記録として、園芸史や蘭愛好の文化史の観点からも興味深い資料である。後期展示(4月15日から6月8日)では、カンランとカクチョウランをご覧に入れる。
寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)
Ayumi Terada
ミュージアムとジェンダー(5)
Museum and Gender 5
近年、自分が展示企画に携わるときは、どんな展示であっても、ジェンダーの視点を取り込むことを意識している。特別展示『台湾蘭花百姿』では、企画の初期段階で、ミュージアムとジェンダーの問題について、台湾の国立歴史博物館の共同キュレーターと話したことがあった。本展示にて、東京大学コレクションから展示物を選定したなかでは、現代の標本図作家である中島睦子さんの『日本ラン科植物図譜』原図が、唯一の女性による仕事である。しかし、中島さんが女性だからこの展示物を選んだわけではない。「台湾の蘭の博物誌」という展示テーマに合致した資料で、その図が優れているからこそ、多くの人に紹介したいという考えが先にあった。その一方で、本展示で取り上げた、日本による台湾統治時代を中心とした東京大学コレクションにはどうしても男性の名前ばかりが並ぶなかで、中島さんという女性の存在が本展示に現れていることの意味は、ジェンダーの視点から、やはり強調しなくてはならないと考える。台湾の国立歴史博物館のコレクションから本展示のために選ばれた美術作品のなかに、大正6年に台湾に生まれた柴原雪の《静物》がある。私が国立歴史博物館の常設展示室にて、洋蘭のシンビジウムが描かれている作品として偶然目に留め、それを共同キュレーターに伝えたところ、台湾美術史上の重要な女性画家を本展示に加えることができる発見だと言われた。ちょうど最終的な展示物候補を日台キュレーターでまとめつつあった段階にあり、柴原作品を展示リストに追加することができた。明治40年に台湾に生まれた陳進の《春蘭》(写真左)は、当初から展示リストに上がっていた国立歴史博物館の中心的コレクションの一つである。陳進は、帝展に台湾女性として初入選を果たした画家として知られる。図録の編集中に、共同キュレーターより、国立台湾美術館所蔵の陳進作品に蘭を描いているものが3点見つかったとの知らせがあった。すでに図録構成をほぼ固めた段階ではあったが、台湾美術史上の重要な女性画家である陳進の蘭の作品であれば載録すべきであるという意見はお互いに一致した。柴原・陳もまた、女性画家の作品だからという理由だけで選定したわけではないが、女性画家に注目してほしいというジェンダーの視点を含んでいる。中島さんのラン科標本図と柴原・陳作品を含む「国立歴史博物館の蘭」の映像は、東京展では、会場の中心に位置するパート4「台湾蘭と自然・芸術・人間」で紹介している。
寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)
Ayumi Terada
台湾胡蝶蘭
Phalaenopsis Orchids in Taiwan
「台湾の蘭の博物誌」をテーマとした特別展示『台湾蘭花百姿』のなかで、胡蝶蘭は、別格の存在感を放っている。実は、「胡蝶蘭」という漢字の名前をつけたのは、台湾総督府にて植物調査に従事した日本人植物学者の田代安定である。そのことを示す資料が国立台湾大学の田代安定文庫に残っている。東京展では、文化史的観点から「台湾蘭の栽培と観賞」をテーマにしたパート2で、胡蝶蘭に注目してみてほしい。台湾に産する胡蝶蘭は、葉は艶やかに緑濃く、花は純白で蝶が羽を広げたような優美な姿をしている。日本統治時代に人気を集めた胡蝶蘭は、台湾の豊かで美しい自然を象徴する植物として、台湾総督府の各種記念絵葉書をはじめ、当時の印刷物にたびたび登場する。1910年代には、台湾各地で胡蝶蘭の栽培ブームが起こり、それ以降、品評会や競技会なども開催されるようになったという。装飾的な盆栽鉢に植えられ、花の見頃を芸術写真のような風情で撮られた胡蝶蘭の写真絵葉書も、この頃に台湾で数多く作られている。展示の準備段階の2024年3月に台湾を訪れた際、さまざまな場所で鉢植えの胡蝶蘭を見かけたのはもちろんのこと、台北の街中や台湾大学構内にて、樹木に着生して自然に花を付けている胡蝶蘭を目にした。こういう光景が台湾の人々の身近にあることが、台湾胡蝶蘭の文化史につながるのだと得心する経験であった。
寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)
Ayumi Terada
植物学者と植物画家の息吹
The Spirit of Botanists and Botanical Artists
東京大学総合研究博物館と国立歴史博物館(台湾)の協働による特別展示『台湾蘭花百姿 − 東京展』が2025年2月15日に開幕した。本展示では、東京大学コレクションから「台湾の蘭の博物誌」を伝える自然史から文化史までのさまざまな資料を選定し、公開している。パート1「⽇本⼈植物学者による台湾ラン科植物調査」では、田代安定、早田文蔵、瀬川孝吉の3人の植物学者を中心に、日本統治時代(1895−1945年)に、日本人植物学者らが台湾で採集した植物標本を紹介している。山中や渓谷を含む台湾全島調査に従事した植物学者らによる標本採集には、熱意なくしては実現し得ない、今日では計り知れぬ多くの困難が伴ったことだろう。標本と並んで注目してほしいのは、植物図譜である。早田文蔵が著した『臺灣植物圖譜』全10巻のなかから、本展示で取り上げたラン科植物の図は、画家の速水不染が原図を手がけている。小石川植物園にて、台湾から持ち込まれた標本をつぶさに観察してその特徴を描き留める仕事にあたった速水は、標本採集のプロセスに想いを馳せ、それに対する敬意と自分の仕事への自負心を抱いていたことが彼の回想録からわかる。標本や図譜を目の前にして、植物学者と植物画家の息吹を感じることは、パート1の展示鑑賞の醍醐味ではないだろうか。
寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)
Ayumi Terada
辰年の標本
Year of the dragon
収蔵展示室Studioloのデスクには、少なくとも一体の動物標本が載っている。その年の干支にちなんだ標本である。幸い、干支の多くは標本があるので、剥製か骨格標本を置くことができる。だがトラの標本はないので、トラツグミ(鳥類)の剥製を寅ということにしておいた。ちなみに生物で「トラ」や「Tiger」とつくのは、だいたいトラジマ模様からつけられている。トラツグミも黄色と黒のウロコ模様があり、遠目にはトラジマのようにも見える。さらに困ったのは今年、辰年だ。タツノオトシゴがあれば完璧なのだが、これまた標本がない。しばらく考えて、トビトカゲにお出まし頂いた。トビトカゲはインド南部と東南アジアに分布し、胴体側面に皮膜を広げて滑空する。この「翼」は長く伸びた肋骨で支えられており、普段は胴体に沿って畳まれている。前肢・後肢に加えて、独立した翼を持つ脊椎動物は、おそらくこれだけだ。そういう意味でも背中に翼が生えたドラゴンぽい。実際、属名はDoraco、ラテン語でドラゴンのことである。
松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)
Hajime Matsubara
インドネシア・ミュゼオグラフィー
Museography in Indonesia
2023年10月25日に、インドネシアのバンドン工科大学アート・デザイン学部長のアンドリアント・リクリク・クスマラ教授をインターメディアテクに迎え、「インドネシアにおけるミュゼオグラフィー – インドネシア・ナショナル・ギャラリーの発展と実践」と題した特別講演をしていただいた。1987年に開館したナショナル・ギャラリーの活動の展開をこれまでずっと主導してきたリクリク先生のお話のなかで、特に印象に残ったのは、国立機関であるナショナル・ギャラリーは政治体制が変わるたびにその影響を強く受けてきたという点である。インドネシアのプライベート・ギャラリーが増加した2000年代は、ナショナル・ギャラリーが改革の停止を余儀なくされた時代であり、こういった公私の文化機関の共鏡から、今日、世界的に注目されるインドネシアのアートシーンの発展の背景がよく理解できた。リクリク先生はその動向を見て、バンドン工科大学にアートマネージメントとキュレーターシップのマスターコースを2013年に設立しており、その修了生たちがアートシーンのさらなる発展に寄与している点も興味深い事実であった。リクリク先生によれば、現在、ナショナル・ギャラリーでは年間に18本もの展覧会が開催されており、その数の多さの理由には外部資金による企画の実施が挙げられる。ナショナル・ギャラリーに外部資金を入れることについては長らく批判があり、それが実施されるようになった今も、政府予算による展覧会と比べて、外部資金による展覧会の開催期間は2週間程度と非常に短い制約下にある。そのなかで、リクリク先生は自身が外部資金を得て企画した、画家スリハディ・スダルソノ(Srihadi Soedarsono)のいくつかの展覧会を事例として紹介しながら、インドネシア社会の歴史を描いた重要な美術家を取り上げた一連の展覧会はナショナル・ギャラリーとして大事な活動であった、そして展示開催期間だけでなく設営準備期間がどんなに短くてもナショナル・ギャラリーとしてのクオリティが担保された展覧会を行うことが重要であると話していた。ナショナル・ギャラリーとはいかにあるべきかをミュゼオグラフィーの観点から改めて考えさせられる事例とコメントであった。リクリク先生の提供による最新情報では、教育文化省傘下の機関であるナショナル・ギャラリーは、2024年に新たな体制と建物を獲得し、2025年にはその準備のための臨時休館に入る予定であるという。今後の展開にもぜひ注目していきたいと思う。
寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)
Ayumi Terada
日本画、漫画、アニメ
Japanese drawings, Manga, Anime
8月12日より特別展示『アヴェス・ヤポニカエ<9> ––表現のダイヴァーシティ』を開催する。今回取り上げたのは、「鳥類写生図」に見られる表現の幅だ。当初、この企画は「日本画による博物学的描写だって素晴らしいのだ」を意識して始まった。一方、その描きぶりが典型的な日本画とは全く違う点も気になった。時に自分自身が、「リアルに描かれているから上手い」と感じてしまっているのも問題だった。図版としてはリアルな方が良いに決まっているが、絵画としてはリアルだから上手いというものでもないのだ。ピカソやブラックを下手くそとは言わない。身近なところなら、我々が慣れ親しんだ漫画もそうだ。『ガラスの仮面』でもなんでもいいが、あの顔をはかなり生物学的に無理がある。考えてみれば、この粉本には嘴や足指のクローズアップ、ポーズ集なども入っており、さながらアニメの設定資料である。最初から漫画やアニメを想起させるような資料でもあるのだった。
松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)
Hajime Matsubara
三四郎池にて
At Sanshiro Pond
『知の開放 知の冒険 知の祝祭 東京大学 学問の過去・現在・未来』を見る機会があった。蓮實重彦総長が就任した1997年に制作された吉田喜重監督による東京大学の広報映像である。大学紹介の動画であるだけでなく、夏目漱石の『三四郎』の登場人物を通して、日本の近代化を振り返り、今後を垣間見る作品となっている。吉田喜重が演出・構成と語りを担当する。漱石は西洋合理主義によって人間の全容を解明する立場に距離を置いており、その明らかでないものを「夢」に託した。三四郎池に佇む里見美禰子との出会いが、小川三四郎の「夢」の始まりであり、「矛盾」の出発点になる。ストレイシープたる三四郎にとって、「夢と矛盾」は新しい時代を照らし出す両面である。映画では1997年当時の旧東京医学校本館(現総合研究博物館小石川分館)が医学部一号館と合成されて三四郎の夢の時間を振り返る舞台となっている。また本郷の懐徳園は広田先生の自宅という設定で、ここでも映画らしい空間の飛躍がある。くわえて、大学における実際のできごとも記録されている。創立120周年記念事業「東京大学–−学問の過去・現在・未来」における安田講堂および総合研究博物館での展示風景、建築学科の設計課題のエスキース風景、柏キャンパスの建設現場も登場する。三四郎の想いに立ち戻ってその先の世界を見せたこと、そして何より、吉田喜重の眼を通してイメージを再構築したことが本作の魅力につながっている。しかしこれが大学の広報映像としていかなる効果を及ぼしたのかはわからない。広報に期待される現在性からはむしろ隔たっているように見える。映像は歴史に時間と空間の輪郭を与えるが、その大胆な構想力こそが伝えられるべきものであろう。
松本文夫(東京大学総合研究博物館特任教授)
Fumio Matsumoto
カトレヤをする
Faire Catleya
フランスの小説家マルセル・プルーストの畢生の大作『失われた時を求めて』には、カトレヤが登場する印象的なシーンがある。第1篇『スワン家のほうへ』の第2部「スワンの恋」の主人公スワンは、高級娼婦オデットへの恋と嫉妬を自覚したある夜、彼女を探してパリの街をさまよう。ようやく見出したオデットは、彼女のお気に入りの花であるカトレヤの花束を手に持ち、同じ蘭の花を白鳥の羽飾りにつけて髪に飾り、襟ぐりの大きく開いたドレスの胸元にやはりカトレヤの花を刺していた。オデットを家まで馬車で送ることを申し出たスワンは、彼女の胸元のカトレヤが馬車の揺れでずれたのを直すという口実で、彼女の体に触れることになる。その後、二人の間でのみ通じる言い回しとして「カトレヤをする」という比喩的な愛の表現が生き延びる。これほどまでに、恋の小道具としてカトレヤを魅惑的に描いている小説は他に類を見ないだろう。「スワンの恋」の時代は19世紀後半。19世紀のヨーロッパ上流社会では、蘭熱狂と言われる、異国に産する珍奇な蘭の収集ブームが起こり、次第に温室での栽培や品種改良も盛んに行われるようになる。この背景に思いをめぐらすと、コロンビアの植物探検調査によってムティスが描かせた植物画コレクションや加賀正太郎が京都・大山崎山荘の温室で栽培した蘭を記録した『蘭花譜』に表れるさまざまなカトレヤが、私の中でプルーストの恋愛小説の世界にゆるやかにつながり、目の前の植物画がよりいっそう艶やかに眩く見える気がした。特別公開『カトレヤ変奏−蘭花百姿コロンビアヴァージョン』は5/16より第5回展示を公開し、6/4で終了する。
寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)
Ayumi Terada
ジュエリーとレディメイド
Jewelry and Readymade
特別展示『極楽鳥』に登場するジュエリーは、19世紀半ばから20世紀半ばに亘る約100年の間に作られた。ジュエリーは年代順に並んでいない。しかし美術史の大きい流れを意識しながら個々の作品の製作年を確認すると、工芸としてのジュエリーが同年代の芸術と連動していることが明確に伝わる。写実主義、象徴主義、アール・ヌーヴォーそして前衛。時代の美意識がそれぞれの宝飾品にも反映されている。なかでも興味深いのが、写真の右下に写っている1920年台のブローチである。ダイヤモンドを主とした貴石の繊細な加工を強調するように、鳥の羽そのものが使用され、生物の滑らかな動きを再現している。その美的理念はともかく、これは同年代の前衛芸術の創作を根本的に変革した手法、レディメイドそのものだ。ちなみにケースの左端に展示されている19世紀後半のブローチは、鳥の尾っぽが揺れるように、ワイヤを巻いたバネで胴体に繋ぐ仕掛けを導入している。時代によって、鳥の動きを表現するための技法が劇的に変化している。
大澤啓(東京大学総合研究博物館特任研究員)
Kei Osawa
植物画家マティス
Francisco Javier Matís Mahecha, Botanical Artist
特別公開『カトレヤ変奏―蘭花百姿コロンビアヴァージョン』では、木版画『蘭花譜』の展示更新に合わせて、植物学者ムティスが率いたコロンビア植物探検調査により現地コロンビアで描かれた植物画のうち1点も入れ替えを行っている。第4回展示で紹介するのは、『新グラナダ王国の王立植物探検隊の植物相』第11巻 第51図版「プシコプシス・クラメリアナ」である。ムティス・コレクションの植物画は、署名の入っていないものが大半を占めるが、本図には、フランシスコ ハビエル・マティス マエチャ(1763−1851)という植物画家の署名が確認できる。マティスは、1783年から1812年まで、ムティスの指揮するコロンビアの植物相の記録に最も長きにわたり参画した植物画家で、署名を残している画家のなかではその作品数が最も多い。花の解剖図のすべて、少なくとも大部分を手がけたと考えられており、ムティスからは解剖を担当する熟練した植物学者としても信頼を寄せられていたという。そして、ドイツの博物学者・地理学者のフンボルトは、南米探検調査の際にマティスの仕事に触れ、彼を「世界最高の花の画家」と称したと伝わる。最近目にしたある論文では、近年、一部にマティスの署名の入った小さな鉛筆画21点が新たに発見され、そのうち10点の図像が展示中の「カトレヤ・トリアナエ」(写真右の彩色画)を含むムティス・コレクションの植物画に一致したが、分析の結果、鉛筆画がコピーであり、マティスの署名もコピーされたものであるとして、マティスの贋作という結論が示されていた。署名のない「カトレヤ・トリアナエ」がマティス作品であると判明したのか、鉛筆画が下図であったとしたらマティスの植物画制作プロセスの一端がわかったのかと期待して読んだ論文であったが、その斜め上を行く、マティスとは贋作が作られるほどの植物画家であるという興味深い事実を確認することになった。第4回展示は4/25−5/14まで。
寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)
Ayumi Terada
本質と抽象化
Essence and Abstraction
特別展示『極楽鳥』に並ぶ宝飾品の名作から目玉を選ぶのは困難である。しかし会場の奥の部屋に列品されている、フランス人宝飾作家ピエール・ステルレ(1905-1978年)による作品は、いつ眺めても新たな発見がある。同年代のアヴァンギャルド芸術に敏感だったステルレは、その関心の的であった「動き」や「速度」の表現をジュエリーにおいて試みている。写実的な表現を完全に排除した鳥のブローチのシリーズには、抽象彫刻の大家コンスタンティン・ブランクーシ(1876-1957年)による『空間の鳥』はもちろん、その時代の先端技術であった航空工学の影響をも見受けられる。ステルレは鳥のブローチを作るにあたって大きい、特徴的な貴石を鳥の胴体に見立て、金属と小さい石で頭部、翼や尾を表現している。その結果、極度に抽象化された作品は特定の鳥ではなく「飛翔する生物」の本質を捉えている。造形がここまで極端だと、色彩には写実的な役割がなく、恣意的な要素になる。これもまたフォーヴィスムから抽象絵画まで、同年代の芸術の理念に呼応している。
大澤啓(東京大学総合研究博物館特任研究員)
Kei Osawa
未完成の定義
Definition of Unfinished Work
特別公開『カトレヤ変奏―蘭花百姿コロンビアヴァージョン』の3回目の展示更新では、『蘭花譜』より、「リンコレリオカトレヤ・エンプレス・オブ・ロシア『オオヤマザキ』」(写真左)を公開する。淡いグレーの背景に白い花が目を引く多色刷り木版画である。唇弁に注目してみると、フリルの細かな形状や黄色のグラデーション部分のぼかしによる色彩の表現は見事の一言に尽きる。この花の左には、角度を変えてやや右から見た花が線画で表されている。植物画では、彩色画に比べて線画は植物の構造的特徴が捉えやすい。そのため、歴史的に名高い植物学雑誌『カーティス・ボタニカル・マガジン』など、西洋で18世紀後半から19世紀頃に作られた、銅版や石版に手彩色された植物画を見ていても、メインとして配置した植物と重ねて後ろに、あるいはその脇に描かれた同じ植物や部分拡大図は彩色されていないことがままある。本図の花の表現もそういうことだろうと何となく思っていたところ、ミシガン大学美術館所蔵の『蘭花譜』のデジタルコレクションの解説に、本図について、中央の花の後ろに色がついていない別の「スケッチ」された花があるのは、これが未完成のイメージの一つであったことを示すと書かれているのを見つけた。私が確認した限り、『蘭花譜』の木版画83点のうち、本図を入れて8点に同様の未彩色の線画部分がある。確かに、美術作品として眺めると、これらの線画部分はいかにも本来彩色されるべきだったのにそれが施されていない未完成絵画のようにも思える。しかし、下絵から何種類もの版を作り、それを刷り重ねる木版画の制作工程を考えれば、『蘭花譜』を手がけた加賀正太郎も、彫師・摺師も、これらの図を完成させて世に送り出しているはずである。ただし、最初に私が受け止めていたように、植物の構造的特徴を伝えるために部分的に線画で表したと言ってよいかどうかは定かではない。本図と一緒に展示する「カトレヤ・メンデリー『グロリア・ムンディ』」と「レリオカトレヤNo. 106『オオヤマザキ』」(写真右)では、同じような構図で正面を向いた花と角度の異なるもう一つの花の両方に彩色が施されている。想像の域を出ないが、日本の伝統文様にある破れ垣のように、不完全なものに美しさを見出す美意識のもと、『蘭花譜』のなかに本図のような表現が一部取り込まれたのだとしたら、完成しているが未完成という形容も的確となるかもしれない。第3回展示は3/28−4/23まで。
寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)
Ayumi Terada
激突
The Duel
特別展『極楽鳥』の鳥パートの解説はかなり自然科学に寄せてある。美のために作られたジュエリーに対し、生きて繁殖してこその生物の姿をきちんと対比する必要があると考えたからだ。そう考えると、妙な対抗心も湧いてくる。だが相手は名だたるメゾンの名品も含む宝飾品であり、そちらが目的の来館者も多いだろう。鳥にさして興味のない人々にも、鳥の魅力は伝わるものだろうか? そういう不安も抱きつつカタログ用に標本撮影の日を迎えた。そして光を浴びたニジキジを見た瞬間、不謹慎にも「勝てる」と思ってしまった。宝石にも貴金属にも一歩も引けを取らない羽毛の輝きは、角度によって赤銅色、黄緑、青と色を変え、時に漆黒に沈む。これこそが進化の生んだ奇跡であり、美という一点を持ってもヒトに負けはしないと、鳥に言われているようだった。ただし、この自信は宝飾品がIMTに到着した瞬間に揺らいだ。ジュエリーの圧倒的な存在感は、やはり現物を前にしてこそなのだ。
松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)
Hajime Matsubara
異国趣味
Exoticism
特別展示『極楽鳥』では、鳥をテーマにしたジュエリーとそのインスピレーションのもととなった鳥の剥製を合わせて展示することによって、宝飾作家が様々な技法をもって鳥を表現するプロセスを多角的に紹介している。とはいえ大抵の場合、ジュエリーのモティーフとなっている「鳥」の種を同定するのは困難である。その背景には、特定の鳥ではなく、鳥のエッセンスを捉えようと、表現のデフォルメと抽象化を重ねる芸術家の創作行為がある。そのなかで作家たちの想像力を刺激したのが、大航海時代以来、西洋の芸術家を魅了した「異国趣味」である。この世とあの世を行き来する象徴的な存在として多くの神話に登場する鳥だが、近代ヨーロッパの芸術では未知の世界の使者として扱われることも少なくない。想像上のエキゾチックな鳥が、自然豊かな地域の象徴として、華やかにして奇抜な色彩のジュエリーのインスピレーションとなる。その代表例が、展示のタイトルにもなった極楽鳥である。
大澤啓(東京大学総合研究博物館特任研究員)
Kei Osawa
卒業記念写真(ベルツおよびスクリバが写る)
Graduation Photograph with Baeltz and Scriba
東京大学総合研究博物館研究部所蔵三宅コレクションのなかに、帝国大学医科大学本館前にて撮影された卒業記念写真がある。本写真の裏面に鉛筆書きより、1892(明治25)年という撮影年がわかる。中央には、独逸人教師二名が写る。前から三列目に立つのが、エルヴィン・フォン・ベルツ(1849–1913)で、チュービンゲン、ライプチヒの各大学に学んだ後、1876(明治9)年に来日し、はじめ生理学と薬物学を、後に内科学を教えた。ほかに、産婦人科学なども担当し、東京医学校時代から東京大学医学部に二十六年間の長きにわたって在任した。前から二列目に座るのが、ハイデルベルク、ベルリン、フライブルクの各大学で学んだユリウス・カール・スクリバ(1848–1905)で、1881(明治14)年に東京大学医学部に招かれ、外科のほかに、皮膚梅毒、裁判医学、眼科なども担当し、1901(明治34)年に退任するまで在職二十年に及んだ。本写真に見える詰襟姿の人物が学生、背広姿が当時の教師陣である。本写真の旧蔵者で、東京大学初代医学部長を務め、撮影当時は帝国大学医科大学長の職を辞して貴族院議員となっていた三宅秀(1848–1938)はスクリバの右隣に座る。本写真の撮影場所である医科大学本館は、1876(明治9)年竣工、東京医学校が神田和泉橋通から本郷旧加賀屋敷跡(当時文部省御用地)に移転新築された際に作られた。屋上に時計台のある木造二階建ての擬洋風建築で、南向きの正面中央に立派なバルコニーのある玄関を備えていた。本写真の背景にその玄関の様子が見える。コロタイプ印刷で作られた本写真は、外側四方が切断されており、左下の印字も欠けているが、小川一眞(1860–1929)製と読み取ることができる。小川は、渡米してボストンで写真術とコロタイプ印刷術を学び、帰国後の1885(明治18)年に写真館を開業し、のちにコロタイプ印刷会社も経営した。1900(明治33)年の写真帖『東京帝国大学』をはじめ、東京大学に関係した写真製版印刷を多数手掛けている。今日、卒業シーズンを迎えると、学びの窓に学生と教師が立ち並ぶ卒業記念写真は定番として撮影されるが、本写真はおそらく日本で最初期の卒業記念写真であると考えられる。特集『学びの窓―アカデミアの東京大学医学部ゆかりのコレクション』では、3月21日から4月23日まで、本写真の拡大複製の特別公開を行う。
寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)
Ayumi Terada
展示の天地
How should the top and bottom of a picture be determined?
実業家の加賀正太郎が京都・大山崎山荘の温室にて栽培した外国産蘭を記録した大型植物図譜『蘭花譜』(1946年)に収められた木版画は、それぞれ四角に窓が抜かれた二つ折の台紙に、名称等を記したスリップを添えて貼付されている。なかには、台紙に対して本紙を傾けて貼っているものもあるので、作り手が窓から絵がどう見えるかを意識し、角度まで微調整して図譜を仕上げていたことがわかる。特別公開『カトレヤ変奏―蘭花百姿コロンビアヴァージョン』では、『蘭花譜』を5回に分けて4点ずつ紹介している。第2回(3/7−3/26)にて展示するもののなかに「エピデンドラム・パーキンソニアナム」(写真右下)がある。本種はラテンアメリカ産の蘭で、エピデンドラム属はカトレヤの仲間と言われる。この図譜は、台紙の折りとスリップの向きによれば、葉や花が下から立ち上がる画面を正体としていると考えられる。しかし、着生ランの本種が生育する様子を撮影した写真を見てみると、多くは樹上などから垂れ下がっており、花部の白色の唇弁が下向きに広がっている。これに比べると、絵の花の上下が逆さになるのは不自然である。さて、展示する時の絵の天地は、図譜を仕上げた作り手の意図に従うか、植物の自然な状態を示すか。加賀正太郎は「蘭花譜序」にて、『蘭花譜』の下絵を手がけた日本画家の池田瑞月が大山崎山荘の温室で蘭を写生して研鑽を積み、いっそう自分の意にかなう木版画の下絵を得たと述べている。瑞月がこの蘭についても温室にて生きた姿を見て描いているのであれば、垂れ下がって生育する様子を写し取っているだろう。この点も考え合わせて、植物の自然な状態を表す向きで展示することに決めた。そう判断したのだが、やはり展示したのとは天地を逆さにした画面、すなわち、右下に重心を置き、左上に余白を取った構成の方が、すっと縦に立ち上がる葉、そして画面中央の花から左下の花へと視線が誘導され、絵として美しく感じられる。これこそが瑞月の選んだ構図かもしれない。この図譜を次に展示する機会があれば、また改めて天地を悩んでみることにしようと思う。なお、第2回の展示では、『蘭花譜』とともに今回の特別公開で紹介しているコロンビアの蘭の植物画のうちの1点を、「エピデンドラム・パーキンソニアナム」と同じ属の「エピデンドラム・ティプロイデウム」(写真右上)に更新している。これらの比較も楽しんでほしい。
寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)
Ayumi Terada
極楽の鳥
Birds in Paradise
インターメディアテク十周年記念特別展示『極楽鳥』が1月20日よりオープンした。このタイトルはL’ECOLEによるジュエリー展の名称「Birds in Paradise」を踏襲した形だが、日本語タイトルとしては「極楽鳥」を当てた。生物種としての極楽鳥(フウチョウ)の英名はBird “of” Paradiseである。鳥担当として真っ先に考えたのは「宝石にも負けない鳥の美しさを」だった。次に、普段は収蔵展示室から出たことのない山階鳥類研究所所蔵標本を展示室に解き放つことができたら、であった。そして、「この機会に、インターメディアテク にあるオオフウチョウの標本を全部並べられたら」とも考えた。フウチョウは鳥の美の代表格であり、進化の驚異であり、発見の物語であり、人間が鳥に付与したイメージであり、乱獲と保護の歴史でもあるからだ。だからオオフウチョウ達、すなわちBirds of Paradiseがこの展示空間に解き放たれたなら、それはもう「天国にいる鳥たち」でいいんじゃないか、と思うことにした。Bird inと Birds ofで微妙に違うのは、そういう理由である。
松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)
Hajime Matsubara
夜の森
The Forest at Night
特別展示『極楽鳥』の薄暗い会場に入ると、ペンダントライトから月光のようにさす照明のなかで、フクロウのペンダントが浮かぶ。その背景にあるアンティーク調の木製棚に並ぶ標本は、その造形的多様性から「驚異の部屋」を連想させる。棚に照明が当たるところには、小型の鳥の剥製標本が並ぶ。それらを見守るように、右側にはフクロウの大きい剥製。奥には、江戸時代屈指の図譜『梅園禽譜』からコノハズク属の絵がかかってある。会場に入った来場者は説明を受けることもなく、突如に夜の森に佇む鳥たちに迎えられる。ジュエリー、剥製、図譜という異なるメディウムによる「鳥」が並び、言葉を介さずに対話を呼びかける。明るい空間に通り抜けると、朝の鳥に出迎えられ、展示の企画趣旨や展示物の解説が目に入る。前室とも呼べるこの夜の森の空間は、非言語的な展示デザイン方法をもって展示コンセプトを瞬時に伝える試みでもある。
大澤啓(東京大学総合研究博物館特任研究員)
Kei Osawa
特別展示『極楽鳥』開幕
Special Exhibition “Birds in Paradise” Opens
インターメディアテク十周年に合わせて特別展示『極楽鳥』がオープンした。鳥をモチーフとしたジュエリーの歴史的名作と鳥類剥製標本および図譜との競演は、当館にとって様々な意味で新しい試みである。まず、開館以来はじめて三階の全スペースに亘って特別展示を展開した。また「レコール ジュエリーと宝飾芸術の学校」との共催により宝飾品と博物学との対話が実現した。普段、収蔵展示室「STUDIOLO」に列品されている山階鳥類研究所所蔵の剥製群を間近で眺める珍しい機会も得た。製作意図、材質、スケールの異なる「作品」と「標本」の共存は、調和の取れた展示方法を必要とする。自由に配置されている小さな展示ユニットから成る常設展示とは対照的にここでは順路を設け、夜から日中そしてさらに想像の世界へと進むシナリオによって展示を構成した。もちろん、鳥の声も欠かせない。再生に使用したのは当館所蔵の蓄音機。この詩的な演出が生み出すのは、鳥をめぐってアートとサイエンスを結ぶ多角的な展示である。標本について言えば、中でもハチドリ類ジオラマは必見であろう。合わせてオーデュボンによる『アメリカ産鳥類図鑑』の図版を常設の時よりも追加し、見やすい位置に展示できたことも特筆したい。Birds in Paradiseの名の通り、普段は収蔵庫にいる鳥たちを「解き放つ」、それも本展示の見所の一つとした。
大澤啓(東京大学総合研究博物館特任研究員)・松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)
Kei Osawa, Hajime Matsubara
カトレヤ変奏
Cattleya Rhapsody
2023年2月7日より、特別公開『カトレヤ変奏―蘭花百姿コロンビアヴァージョン』が始まる。本展示は、コロンビアのボゴタ現代美術館(ミヌト・デ・ディオス大学文化団体)と東京大学総合研究博物館との国際協働によるモバイルミュージアム・プロジェクトの東京展となる。2021年にインターメディアテクで開催した特別展示『蘭花百姿―東京大学植物画コレクションより』(同名の書籍は2022年に誠文堂新光社より出版)のスピンオフとして企画された。コロンビアの現在の国花はカトレヤ・トリアナエというカトレヤの一種である。このことは、本企画に着手する初めてのオンライン・ミーティングにて、コラボレーターから教えてもらって私も初めて知った。その後、展示物候補としてさまざまな蘭の植物画を具体的に見ていったところ、カトレヤ・トリアナエに導かれるかのように「カトレヤ変奏」というタイトルにたどり着くことができた。展示紹介のアイコンには、コロンビアと日本で描かれた二つのカトレヤ・トリアナエの図を用いている。右はムティス『新グラナダ王国の王立植物探検隊の植物相』(マドリード王立植物園デジタルライブラリ所蔵)、左は加賀正太郎『蘭花譜』(東京大学総合研究博物館所蔵、2/7−3/5まで展示)より。
寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)
Ayumi Terada
謹賀新年2023
Happy New Year 2023
謹賀新年。
お正月の過ごし方は年々、変化し続けているようだが、多くの方にとって、年の変わり目に普段と違うことをする習慣は何らかのかたちで続いているのではなかろうか。賀状の交換や特別な食事、めったに会わない親族や知人たちとの会合等々。
それらは古来、人々が続けてきた暦を管理するための智恵の一つなのだと思う。狩猟採集時代であれば、季節をうつろう獲物や食用植物を得るタイミングを知るために暦が必要であったし、農耕が始まってからは種まきや田植え、収穫時期の適切な判断を下すためのカレンダーが求められた。文字が無い頃、みなが暦を共有するには、何らかのタイミングで記憶に残るような祭事、つまりイベントを催すことがもっとも効果的であったに違いない。その名残が今も続いているのだろう。
インターメディアテクは、本年、開館10周年を迎える。2013年3月の開館以来、日本郵便株式会社と東京大学の協働のもと、多くのみなさまのお力添えを得て、これまで事業を続けてこられた。心より御礼申し上げる次第である。また、引きつづきのご支援を賜りますことを改めてお願い申し上げる。
この節目を記憶し、私どもの現在地と将来を確認すべく、本年にはメモリアルなイベントを予定している。まずは、今月20日にオープンする特別展『極楽鳥』の開催である。この展覧会は、10年間、変わらなかった常設展示フロアの一部配置を変更したものとなる。乞うご期待とさせていただきたい。
一方で、この節目は次の10年を見すえる機会ともなる。インターメディアテクでは、重厚なヒストリーをもつ学術標本を丸の内という現代ビジネス空間において審美的な方法をもって開陳する、という独創的な試みを続けてきた。それに支持をいただいてきた大きな理由はさまざまあって、一つは場違いな空間に迷い込んだと来館者に感じさせる意外性かも知れないが、他方では、来館者がいだく学問への敬意とその未来への期待なのだと受けとめている。
次の10年の半ばに、東京大学は創立150周年(2027年)を迎える。これまた暦に刻むべき記念行事の機会となろう。インターメディアテクにおいても、本学の伝統と創造を学術標本をもってお示しする行事を催すことになるはずである。学術の歴史の重みは自ずと増し続けるに違いない。一方で、未来への期待の行方はそれを担う者の自覚と行動にかかっている。新年の節目にあたり、本年、さらにはその先に向けて一同、思いを新たにしているところである。
写真:インターメディアテクで展示中のノウサギ剥製
西秋良宏(インターメディアテク館長・東京大学総合研究博物館館長/教授)
Yoshihiro Nishiaki
スウェーデンでの展覧会
Exhibition in Sweden
ストックホルムにあるミュージアムÖstasiatiskaにて開催中の『Juxtaposing Craft』展に参加している。展覧会には、スウェーデン、ノルウェー、フィンランド、日本の4カ国から多様な作品が出品され、同時にÖstasiatiskaの収蔵品も並んでいる。この展覧会は、制作材料を通じて、持続可能な資源に対する考え方を発信する展覧会でもある。展示設営のために10月初旬からストックホルムに滞在し、現地のスタッフと一緒に作業を進めた。インターメディアテクで展示設営を行う立場としては、自身の作品の設営を進めつつも、現地のスタッフが使用している道具や、作品の固定方法が気になってしまう。日本と違い、地震対策として入念に作品を固定する必要はない点は、羨ましくも感じる。また、作品保護のためのガラスケースや、壁面への固定方法も興味深く、インターメディアテクに取り入れたい点が多くあった。ミュージアムでの展示方法は、新しいアイデアを取り入れつつ日々進化しており、このような展覧会に参加する事で得られる収穫は非常に大きい。
菊池敏正(東京大学総合研究博物館特任助教)
Toshimasa Kikuchi
ベルギーの大地球儀
Large Globe from Belgium
2022年の11月28日から12月2日まで、東京国立文化財研究所で世界動物考古学会議の西アジア分科会が開かれた。日本では久しぶりの完全対面式の国際会議である。その参加者らがインターメディアテクを見学したいと言うから案内役を引き受けた。インターメディアテクでは動物骨格や剥製をたくさん展示している。動物を研究している海外からの参加者約40名はみなさん興味津々、充実した時間を過ごせたことを感謝して帰っていかれた。また、インターメディアテクの世界観に感銘を受けたとのメッセージもよせられた。
案内中、ベルギーからの参加者もおられたので、常設展示中のベルギー製大地球儀を紹介し、その由来について話したところ、実に熱心に質問してこられる。また、解説文をしゃがみ込んでまで読んでおられる。どうしてそんなに興味がわいたのか当惑しつつも尋ねてみると、何と、この地球儀がベルギーから日本にやってきた昭和初期の両国間関係をテーマとした特別展が、現在、ルーヴァン大学図書館で開催中なのだと言う。
と言われても、大地球儀がどんなものかをご存じない方には合点がいかないことだろう。この地球儀の由来や意義については、2016年にインターメディアテクで開催した日本・ベルギー国交樹立150周年記念展の紹介文をまずはご覧いただきたい。[リンク先]
要は、1914年、ドイツ軍の攻撃にてルーヴァン大学の図書館が焼失。日本は、その復興支援を決定。1923年、今度は関東大震災にて東京帝大図書館が焼失。にもかかわらず、日本側は国内に残存する貴重書を集めてルーヴァン大学に約1万4000冊を寄贈。これに対し、ベルギー側は東京帝大図書館復興のための義援金を提供。この義援金で東京帝大はベルギー地理学協会に地球儀の製作を発注。そうして、ようやく1937年に日本側に到着したのが展示中の大地球儀というわけである。
なぜ、そんなに熱心に日本側が支援や交流をすすめたのか。単なる善意や学術目的だけでなく、日本文化の西洋への紹介、日本の国際的地位向上、等々、第二次大戦前の国際情勢にもとづく政治的判断があったからに相違ない。大地球儀は、それらをひっくるめた昭和初期の歴史を紐解くための希有な物証なのである。ベルギーから参加した動物考古学者もそれを理解したからこその関心ぶりだったのであろう。
実は、インターメディアテクで開催した2016年の展覧会紹介文には、東京帝大がルーヴァン大学に寄贈した約1万4000冊の書籍は、1940年、再びの戦禍の中、灰燼に帰したと述べてある。[リンク先]
しかし、今回のルーヴァンの展覧会によって、それらが良好な状態で保存されていたことを知った。寄贈書の大半は江戸期の作品を中心とした、今や稀覯本の数々。江戸文化を研究するのに実に優れた資料であるのみならず、大地球儀と同じく、昭和の歴史を語る第一級の標本群である。それらが、無傷で残されていたことはまことに喜ばしいと言うよりない。西アジアの動物考古学会議という、およそ無関係に見える集会に係わったことで、畑違いの昭和の歴史にまで思いを馳せることとなった。情報源としての学術標本の奥深さを改めて実感した次第である。
ルーヴァン大学の展覧会の会期は10月28日から2023年の1月15日まで。図録(解説本)は無料でダウンロードできる。[リンク先]
西秋良宏(インターメディアテク館長・東京大学総合研究博物館館長/教授)
Yoshihiro Nishiaki
天敵
The predator
先日、ある農地でカラスを観察していた。ミヤマガラスの集団と、さらに柿に群がるハシブトガラスもいたのだが、突然、カラスたちが大騒ぎを始めた。単に騒いでいるのではなく、サッと舞い上がったり、集団で狭い範囲を旋回したりしている。何か危険な相手でも近づいたのか? だが騒ぎは一向に収まらない。これは妙である。カラスの様子を見る限り、どうやら脅威は去っていない。となると…… 捕食者がそこを動けない、つまり、今まさにカラスを襲って仕留めているのでは? そう思って見えるところまで移動した。段差の上に止まった数羽のハシブトガラスが鳴きながら下を覗き込んでいる。あの下か。伸びた二番穂の間に、褐色と黒が見えた。弱々しく動く黒はカラスだろう。褐色の方がバサリと翼を開き、黒い横斑の並ぶ風切羽が見えた。それは若いオオタカだった。この時、私たちはすぐ近くにいたのに襲撃の瞬間に全く気付かなかった。その完璧な奇襲こそが猛禽の真髄であり、獲物にとっての恐ろしさなのだと痛感した。
松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)
Hajime Matsubara
開かれたエル
Open L
ハリウッドの丘に建つスタール邸(1960)は、アメリカで最もよく知られた住宅建築の一つである。戦後の新しい住宅モデルを模索したArts and Architecture誌の企画による実験プロジェクト「ケース・スタディ・ハウス」の22番に指定されている。ロサンゼルスの夜景をバックに、ガラス張りの居間でくつろぐ人物をとらえたジュリアス・シュルマンのモノクロ写真が有名で、憧れのモダン住宅のアイコンとなってきた。設計者のピエール・コーニッグは、土台をコンクリートで固め、建築本体は鉄骨とガラスとコルゲートパネルという限られた工業製品で構成した。この平屋住宅の明晰なコンセプトは、エル(L)のかたちをしたプランに集約される。エルの1辺は眼下の街並に向けて崖から突き出し、居間と食堂に270°の劇的なパノラマを提供する。エルのもう1辺は崖と並行した奥側に寝室群と浴室を配列している。すなわち、崖から内側に向けてプライバシーの変化が設定されている。そしてエルの2辺で囲まれた外部空間には空を映し出すプールがある。仮に建築の構成を「辺」で抽象化して示すと、1辺の直線型、2辺のエル型、3辺の両翼型、4辺の囲み型が考えられる。このなかで「エル型」は空間が内側で自己完結せず、外部との関係がより流動的になる可能性をもっている。エル型の平面計画は難しいが、スタール邸では廊下を省き、外部を日常利用することで開かれた簡潔な空間構成を実現した。エル型の流動性は断面方向にもあり、高所から俯瞰展望する視点が敷地内に遍在している。写真のエル型の建物がスタール邸。屋根板を外した状態で表現してあり、また周辺状況は異なる(空間博物学展の「20世紀の建築」で展示中)。
松本文夫(東京大学総合研究博物館特任教授)
Fumio Matsumoto
モダンへの架け橋
A Bridge to Modernity
オットー・ワグナー(1841-1918)はウィーンを中心に活躍したオーストリアの建築家である。ウィーンでは皇帝フランツ・ヨーゼフの勅命で旧市街地を囲う城壁が撤去され、19世紀後半に大規模な都市改造が行われた。リングシュトラーセという環状道路を新設し、拡張された都市域にモニュメンタルな建造物を配していった。ワグナーはウィーンの建築都市の計画や建設、そして鉄道インフラの整備にも関わった。彼の主著に『近代建築』(MODERNE ARCHITEKTUR、初版1895年)がある。ウィーン美術アカデミーの教授に就任したワグナーの講義をまとめたもので、「建築青年に与えるこの芸術領域への手引き」という副題がつけられている。建築家、様式、構成、構造、芸術実務についての心構えが説かれているが、このなかに「芸術は必要にのみ従う」(Artis sola domina necessitas)という有名な言葉がある。ゴットフリート・ゼンパーの『様式論』に由来する考えで、現代の要求に合致した合理的な建築への到達を若者に訴えている。ワグナー自身は歴史主義的な建築から出発し、ウィーン分離派を経て、機能的・合理的な方向へとシフトしていった。その晩年の代表作がリングシュトラーセの東端にたつ「オーストリア郵便貯金局」(1906年)である。ここには「表層」と「空間」の革新的な表現がある。外装の大理石板は装飾リベットを付して非構造要素であることを明示している。建物の中央ホール「カッセンハレ」は、屋根の全面をフロストガラスの天窓で覆い、床にガラスタイルを敷き詰めた前例のないアトリウムである。20世紀の到来を告げる高度に抽象化された光の空間は、それでもなお、ワグナーの歴史意匠や様式装飾への習熟の痕跡を感じさせる。歴史主義からモダンへの架橋のさなかに、見る者の心に迫る何かがある。写真はカッセンハレ周辺を抜き出した部分模型(空間博物学展の「20世紀の建築」で展示中)。
松本文夫(東京大学総合研究博物館特任教授)
Fumio Matsumoto
哲学者の建築
Architecture by a Philosopher
哲学者ルートヴィヒ・ウィトゲンシュタインが設計した住宅が1928年にウィーンに完成した。クリムトの肖像画でも知られる姉のマルガレーテ・ストンボローの邸宅である。建築家アドルフ・ロースの弟子のパウル・エンゲルマンが設計を始めていたが、途中からウィトゲンシュタインも参加して主導した。直方体を組み合わせた、整然とした立面の、無装飾な建築である。そこにロースやモダニズムの影響を読み取ることもできるが、むしろ時代の動向を超越した孤高の精神の産物にみえてくる。建築における構成の論理的な整合性、部位の配列規則や対称性、技術的な精度に対する強いこだわりがあったことが知られている。1/2ミリの施工誤差も許されなかった。このようなウィトゲンシュタインの徹底した厳密性が、哲学者としての思索と無縁であったとは考えにくい。前期の主著『論理哲学論考』(1922)は、「世界と言語」の対応関係から哲学の諸問題を解決しようとした書として知られる。「世界は事実の総体」であり、事実は成立した「事態」であり、事態は「対象(物)」のつながりで成立している。「事態と対象」を世界の基本単位と規定し、一方で論理形式を共有する「命題と名辞」を言語の単位とする。そして世界と言語は「像が現実を写しとる」という「写像」の関係で結ばれているとした。「像」とは現実の模型であり、要素命題などの形で表現される。筆者には『論考』の内容に立ち入る素養はないが、ウィトゲンシュタインの建築が、論考と同様の思考の枠組のもとで、彼の構想を空間に写しとるプロセスを徹底して繰り返してきたように思える。しかし論考の末尾にあるように、「語りえないことについては、沈黙しなければならない」。
松本文夫(東京大学総合研究博物館特任教授)
Fumio Matsumoto
オリエント考古美術の話(6) 嘴状水差し型土器(続)
Beak-spouted Jar of Ancient Persia (Part 2)
嘴状水差し型土器の中には注口がたいへん長いものもある。写真の作品は先端が鋭くとがっていることもあって、まさしく「嘴状」とよぶにふさわしい。では、そもそも、どんなトリを模して作られたのだろうか。オリエントの宗教世界に登場する、嘴が長いトリと言えば、古代エジプトのトート神が思い浮かぶ。そのモデルはトキである。末期王朝期にはトキのミイラが大量に作られた。しかし、嘴状水差し型土器の出現はエジプト末期王朝期よりもはるかに古いし、エジプトにいたのはアフリカトキであって、それらがイラン北部に生息していた証拠は得られていない。また、月にかかわるトート神の嘴は三日月状に垂れ下がっているが、ペルシャの注口は直線的である。こうしたことから、直接の関係があるとはみられていないのが現状である。だが、知己の中東鳥類考古学者に聞いてみると、北イランにも、少なくともブロンズトキという仲間がいたそうである。翼が光沢をもった赤銅色をしていることから、そう呼ばれるのだという。また、ブロンズトキは近年、日本列島にも飛来するようになり注目されているらしい。トキにもさまざまいて、さらにまた別の仲間が日本の天然記念物(Nipponia nippon)に指定されていることは周知である。一体、トキというトリは、どんな経緯をもってアジアの東西で人々を魅力してきたのだろうか。古代ペルシャの土器との関係はわかっていないのだが、たいへん気になっている。
●写真6 東京大学の調査団が発掘した注口部が長い嘴状水差し型土器(レプリカ。実物はイラン国立博物館蔵)
西秋良宏(インターメディアテク館長・東京大学総合研究博物館館長/教授)
Yoshihiro Nishiaki
オリエント考古美術の話(5) 嘴状水差し型土器
Beak-spouted Jar of Ancient Persia (Part 1)
今回、取り上げるのはトリの嘴のような注口をもった土器である。専門的には嘴状水差し型土器と言う。写真ではわかりにくいが、注口は樋(とい)のようになっていて上半分は開いている。こうした土器はイラン北部の青銅器時代から鉄器時代、西暦で言えば前3千年紀から1千年紀前半にさかんに製作された。青銅器時代の作品には彩文が付けられていたり、複数の土器を連結したりなど、華美なものが多い。また、性器を強調した男性土偶をともなっていることもあって、男性集団にかかわる儀礼の道具として作られたとの説もある。一方、鉄器時代になると無文でシンプルな作品が主になる。展示品は、無装飾で容器部が算盤玉形をしていること、取っ手が小さいことなどからみて鉄器時代、しかもその後期、前1千年紀前半の作品であろう。注口の根元の両側には小さな粘土粒、上には突起がつけられていて、眼やトサカを表現しているようにもみえる。嘴状水差し型土器は、墓の副葬品として見つかることがふつうだから、やはり当時の儀礼、宗教とかかわる品物だったと考えられている。液体をそそいだのだろうとは推測できるが、儀礼の中身はわかっていない。ただ、興味深いのは、ゾロアスター教が教義をととのえはじめた前1千年紀半ばにはプツリと消えてしまう点である。逆に言えば、この種の土器は、文字記録が無い頃のペルシャ原始宗教がどんな風であったかをさぐる有力な手がかりを提供しているのである(続く)。
●写真5 展示中の嘴状水差し型土器
西秋良宏(インターメディアテク館長・東京大学総合研究博物館館長/教授)
Yoshihiro Nishiaki
肖像を掲げる
Display of Portraits
特別公開『独逸医家の風貌』(2022年9月13日−12月11日)にて展示した肖像のなかに、サーベルを携帯する軍服姿のポンペを写した石版印刷がある(写真左上)。近代医家三宅一族旧蔵コレクションの一つである本肖像は、下部の印字より、オランダのデンハーグで作られたものであることがわかる。オランダの海軍軍医であったポンペは、安政4(1857)年に長崎に来日し、西洋医学伝習の教師として、独逸医学の導入以前に日本近代医学の発展の礎を作る。その間に日本で撮影された写真(『ポンペ日本滞在見聞記』の口絵)に同じく軍服姿のものがあるため、このようなポンペの軍服姿は長崎で彼の門人も見る機会があったものかもしれない。東京帝国大学医学部教授を務めた入澤達吉による、昭和4(1929)年のポンペの生誕百年記念演説の文字起こしが、同年の『中外医事新報』第1148号に残る。そのなかに、彼の父・入澤恭平がポンペに従学した一人であり、入澤家の神棚の脇にポンペの肖像が掛けられていたのを子どもの時から見て育ったという回想がある。入澤が演説の際に持参して聴衆に見せたという肖像を掲載した図版によれば、入澤家で達吉少年が見ていたポンペの肖像は、『独逸医家の風貌』展に展示したものとほぼ同じであるが、左胸の勲章が一つと数が少ない。ポンペの肖像は石版印刷でヴァージョン違いが作られるほど需要があり、実際に流布していたのだろう。入澤の回想は、家のポンペの肖像が戊辰戦争でも焼けず、関東大震災でも土蔵に入れてあって無事だったことにも触れている。肖像を残し、それを掲げ、長きにわたり大切に扱う。このエピソードは、ポンペがその門人や日本の医学関係者にいかに敬愛されてきたかをまさに物語るものにほかならない。『独逸医家の風貌』展で公開した、三宅家に伝わったポンペの肖像がどのように扱われていたかは調べることができていないが、状態の良さからして大事にされていたことは間違いないだろう。ミュージアムが未来に守り継ぐ資料である肖像画や肖像写真には、このような人々の「想い」も伝わっている。
寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)
Ayumi Terada
オリエント考古美術の話(4) ガラス容器と交易
Glass Vessels and Trade of the Ancient Orient
ガラス製作のルーツは、ファイアンスという半分、土器のような焼き物にある。紀元前5千年紀には登場した。今で言うガラスに近い製品が現れたのは前3千年紀である。後に、ローマ時代になって吹きガラス技法が開発されると製作できる品物の幅は一気にひろがった。展示中のガラス製品は、そうしたガラス工芸の発展が展開したオリエント地域、特に地中海沿岸のローマ時代以降の作品である(写真)。限られた地域でしか製作できないのだから奢侈品であることが多く、交易用のアイテムとして重宝された。近年では、ガラス製品を先端的な考古科学分析手法により解析し、その流通をさぐる研究がさかんにおこなわれている。インターメディアテク展示標本についての研究例はないのだけれど、日本列島にまで運ばれてきた作品があったことは前回、書いたとおりである。そこで話題にした正倉院白瑠璃碗に似たササン朝ペルシャのガラス碗が、より古いローマ時代の碗と比べて、ずいぶん分厚くがっしりしていたことにお気づきだろうか。シルクロードの交易をふまえた長距離輸出のためという意見があるほどである。そうかもなあと思う一方、意図して分厚い作品を作ったのか、分厚い作品だけが遠くまで運ばれ得たのか。その証明は難しかろうとも思う。
●写真4 展示中のガラス容器
西秋良宏(インターメディアテク館長・東京大学総合研究博物館館長/教授)
Yoshihiro Nishiaki
ミュージアムとジェンダー(4)
Museum and Gender 4
写真帖『東京帝国大学』は、のちに帝室技芸員を拝命する著名な写真師の小川一眞が設立した小川写真製版所が手がけ、明治33(1900)年に仏パリの万国博覧会に出品するために作られた。明治30年代初頭の東京帝国大学を記録した本写真帖は、前総長や当時の総長をはじめとする教授たちの肖像や校舎設備の状況を収めており、東京大学の歴史を語る際にたびたび用いられる資料である。特別公開『独逸医家の風貌』(2022年9月13日−12月11日)では、本写真帖より「医科大学」および「第一医院」の二点を取り上げた。この理由として、今日も大学キャンパス内に残る独逸医家関係の文化資源、すなわち前者には時計台のある旧東京医学校本館が、後者には庭好きなベルツの住んだ教師館の隣にあった旧富山藩庭の庭石が確認できるという点が一つ。そしてもう一つは、ジェンダーへの関心から、これらの写真に看護婦の姿が写る点に注目したからである。時計台の建物に向かって進む看護婦らの群像と、旧富山藩の庭石のところでカメラ目線で佇む一人の看護婦。小川が彼女たちを写したのは、構図上の意図として絵になると思ったからなのかもしれないが、教授陣も学生も男性ばかりの当時の東京大学で、看護婦のいる風景がキャンパス内の日常であったことも事実であろう。日本では、医学は独逸を採用したのに対し、看護学はナイチンゲール方式の看護教育が高く評価されていた英国を範とした。東京大学では、明治22(1889)年、帝国大学医科大学看病法講習科を第一医院(附属病院)に開設している。日本で看護が女性の職業として位置づけられるのは、近代的な看護婦養成が行われるようになった明治20年代以降のことである(周知のように現在では看護婦という名称は消え、看護師となっているが、ジェンダーギャップの大きな職業の一つである)。私にとって、『独逸医家の風貌』展でのこれら二点の写真の展示は、ミュージアムがジェンダーの視点で既存資料を見直すとその資料に新たな光が当たるということを実感する経験となった。
寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)
Ayumi Terada
オリエント考古美術の話(3) 「正倉院宝物に似たカット・グラス」(続)
Sasanian Glass Vessel and Ancient Japan (Part 2)
で、深井教授を感激さしめたササン朝ペルシャのガラス碗が総合研究博物館にあるのかと言えば、ない。それどころか、深井報告を機に1960、1970年代に大量に持ちこまれた類似のガラス碗が日本各地の博物館、美術館に所蔵されているにもかかわらず、肝心の東京大学には一品も残されていない。人気の故か、散逸してしまったようなのである。これでは、シルクロード東西文化交流史の研究を開いた大学として残念きわまりない。そのような不平を長らく抱いていたところ、2008年になって、瑠璃碗の引取先を探しているという話がまいこんできた。そこで、迷うことなく入手したのが展示品である。譲ってくださったのは、1964年から1965年にかけてテレビ番組作成のためイラク・イラン江上波夫調査団に同行したクルーのお一人である。テヘランの骨董店で入手なさったとのこと。見栄えはともかく、本作品、きわめて興味深い。何がかと言うと、深井教授が1959年に朝日新聞、後に美術史学雑誌『国華』で発表したガラス碗(写真)と瓜二つの作りだからである。ササン朝のカットグラスにもさまざまある。例えば、特徴的な円形切り子の数も多様である。ところが、本作品は、深井教授が最初に報告した碗と全く同じで三段、各15個ずつ。さらに言えば、全体の寸法もミリ単位の違いしかない。どうして、こんなに似通ったガラス容器の生産が可能だったのか。工房が同じだったのだとは思うが、ササン朝工芸の技術力には舌をまく。要するに、展示のガラス碗は、東西文化交流をモノから論じる契機をつくった標本がどんな碗であったかー今は散逸してしまったのだがーそれを伝える代替の一品ということになる。展示をご覧になる方々には、この標本から半世紀以上も前の深井教授の感激を感じていただけるだろうか。
●写真3 深井教授が報告した最初のカットグラス(現在、所在不明)
西秋良宏(インターメディアテク館長・東京大学総合研究博物館館長/教授)
Yoshihiro Nishiaki
インターメディアデザイン その九
Intermedia Design 9
その八につづき、特別展示「PHOTO LOGIC(フォトロジック)- 田中良知×IMT」について。メインの会場(GREY CUBE)で被写体となっているのは、東大総長をはじめ、東大教授、研究者、人間国宝の職人、学生、子ども、現役のチンドン屋までさまざま。本展に向けた撮り下ろし写真である。カメラを向けられることに小慣れた者などそうはいない。どのような肩書きであれ、年齢であれ、職業的モデルでない人物の「肖像」が、いかに特別な作品になり得るかという、その写真芸術としての純粋性を垣間見る機会となった。来館者による「写っている人が生き生きとしていて明るい気持ちになれた」という感想は、職業的モデルの領域にいない人物への親近感であり、楽しい、おもしろいという多勢の言葉を的確に表現したものかと思う。それが今般の時代性の裏返しだとしても、今にして思えばこのような写真展を見たことがない。隣接するサブ会場(BIS)にあるのは、撮影イベントに参加した子供たちやその親御さん。その写真から感じる印象は、メイン会場のそれをさらに上回る。「昨日の自分が作品としてそこにいる」、参加型展示の一例ではあるが、生きた展示とはこういうものかというひとつのあり様を見た思いがする。それに触発されてか「100人ポスター」の制作に取りかかることになった。
関岡裕之(東京大学総合研究博物館特任准教授)
Hiroyuki Sekioka
相良知安、ベルツ、文化資源
Sagara Chian, Baeltz, and Cultural Resources
2021年8月にサウンドレイヤーアプリ「onIMT」の音声レイヤー『独逸医学の導入と相良知安—医学生が語る医学史』を公開した。特別公開『独逸医家の風貌』(2022年9月13日−12月11日)は、このレイヤーと連動した企画となっている。同レイヤーでは、明治新政府に独逸医学の採用を進言したことで知られる相良知安に光を当てた。『独逸医家の風貌』展では、知安に関する資料として、三宅コレクションより、独逸医学導入に尽力した知安を日本医学制度創設の功績者として顕彰するために東京大学構内に建立された記念碑の拓本を紹介している。この記念碑は現在、元の場所から移設され、附属病院の入院棟玄関前、道路を挟んだ藤棚のところにある。そして、記念碑の近く、記念碑と入院棟玄関の間の道路の中央にある丸い小さな木立には、「ベルツの庭石」と呼ばれる、旧富山藩(加賀前田家の支藩)の庭石が移設されている。ベルツの住んだ教師館が旧富山藩の庭園の隣にあり、ベルツが庭を愛でていたことにちなむ名がつく。知安の弟・相良元貞は、独逸医学導入を政府が決定してまもなく、明治3(1870)年に政府派遣の第一回留学生の一人として独逸(ベルリン大学)に赴く。留学中に重い病気にかかり、ライプチヒ大学付属病院に入院し、同大学で臨床諸学科を学んでいたベルツの献身的な治療を受けた。そのことがのちのベルツの日本招聘の一因をなしたといわれる。現在、本郷キャンパス内で見ることのできる独逸医家関係の文化資源として、石に姿を変えて、知安とベルツが隣人になっているのも縁が深いようで興味深い。写真は左が相良知安先生記念碑、右がベルツの庭石。
寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)
Ayumi Terada
オリエント考古美術の話(2) 「正倉院宝物に似たカット・グラス」
Sasanian Glass Vessel and Ancient Japan (Part 1)
展示中のコレクションの中に、紀元3〜7世紀ごろのササン朝ペルシャ産カットグラスが一点、含まれている。表面が乳白色に風化しているのでガラスとは思えないかも知れないが、元来は、透きとおった瑠璃色をしていたはずである。類似の作品として最も保存良好な国内作品は、奈良正倉院宝物庫にある皇室の白瑠璃碗であろう。当時の日本にそのような製作技術があるわけもない。したがって、シルクロードをへてはるばる西方から持ち込まれたのだろうとは皆が推測してはいたが、では、どこで作られた碗なのかというと誰も答えられないというのが1950年代までの状況であった。そこに風穴を開けたのが、1959年、江上波夫調査団に同行しイランで古美術調査をおこなっていた若き日の深井晋司(1926-1984)、後の東洋文化研究所の教授である。立ち寄ったテヘランの骨董屋で偶然、似たようなカットグラスを見つけたのだという。深井教授は、その時、「いったい正倉院のガラス器と同じ作品がこんなこっとう屋の、しかもがらくたの中にあるのか、そんなはずはない」と正直な感想を記している(「正倉院宝物に似たカット・グラス」朝日新聞1959年11月11日朝刊)。それは、ササン朝ペルシャと古代日本の歴史が学術の世界で結びついた瞬間であり、そのドラマを伝えた朝日新聞の記事は日本にシルクロード・ブームを巻き起こした(続く)。
●写真2 インターメディアテクで展示しているササン朝ガラス碗
西秋良宏(インターメディアテク館長・東京大学総合研究博物館館長/教授)
Yoshihiro Nishiaki
内科講堂の独逸人教師肖像写真 余話
A Side Story of Photographic Portraits of German Teachers
特別公開『独逸医家の風貌』(2022年9月13日−12月11日)の企画を構想するに至ったきっかけの一つは、東京大学医学部附属病院内科講堂にかつて掛けられていた独逸人教師の肖像がなぜかくも大きなサイズの写真なのか、そしてそれがいつから掲げられるようになったのかと考えたことだった。総合研究博物館所蔵三宅コレクションに、明治初年代に横浜で撮影されたホフマンの名刺版肖像写真がある。この像が内科講堂の肖像写真と同じであることから、内科講堂の肖像写真はこの名刺版写真を拡大複製したものという推測がついた。しかし、三宅コレクションのホフマン肖像裏面の彼の自署と、拡大複製写真の右下に添えられた自署は同じ筆跡ではあるが、厳密に同一ではない。おそらく同じ肖像写真がどこかにあり、それから複製が作られたのだろうと予想される。この手がかりとなりそうな記事は見つかっている。入澤達吉は、昭和9(1934)年6月に発表した記事「明治初年来朝の独逸人教師と其写真」(『中外医事新報』1208号)のなかで、昭和8(1933)年秋、大学構内にミュルレルの銅像はあるが、ホフマンは写真すら掲げていないとの話になり、ホフマンに直接教えを受けた卒業生で存命の二人に尋ねてその肖像写真を手に入れたと述べている。その写真は横浜の外国人の写真店で撮影したもので、二枚とも裏にホフマンの自署があったという。本記事に掲載された図版の像も見比べて、二枚が三宅コレクションのものと同じ肖像写真であると判断できる。入澤は、ウェルニッヒの写真についても方々に尋ねた結果、ようやく故・宇野朗所蔵のアルバムに見つかり、この同じアルバムからシュルツェの写真も借用して複写をしたと語る。本記事の図版にある、入澤が入手したウェルニッヒの肖像写真は内科講堂に掛けられていたものと同じ像である。関東大震災の復興キャンパス計画により、内科講堂の入る建物が竣工するのは昭和13(1938)年であるから、この時までに入澤が探して手に入れたホフマンとウェルニッヒの肖像写真から拡大複製が作成され、二人に先んじて震災以前の内科講堂に明治期より掲げられていたベルツの肖像写真(明治42[1909]年の卒業記念写真帖に確認できる)とともに、これらが新内科講堂の壁面に並べられたと考えておかしくない。あとは物証が見つけられないかというところである。
寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)
Ayumi Terada
オリエント考古美術の話(1) ペルシャ古代文物展示ケース
Antiquities of Ancient Persia
インターメディアテクでは古代エジプトをふくめ、いわゆるオリエント地域の考古美術品をいくつか展示している。比較的まとまっているのが、3階COLONNADE 3にならぶ古代イランにかかわる標本群である(写真)。多くは、江上波夫(1906-2002)名誉教授が収集したもので、江上コレクションと呼ばれている。江上教授はユーラシア各地で半世紀以上もの間、考古学調査を続けたフィールドワーカーだっただけでなく、無類のコレクターであった。集められた標本は途方もない量におよぶが、総合研究博物館は教授が1965年の東京大学退官までにおこなった発掘調査の出土品のほとんど全てと、私的収集品の一部を保管している。後者は教授の没後、御遺族から寄贈されたもので、インターメディアテクの展示品はその一部、および関連する標本ということになる。イランは、江上教授が1956年、第2次大戦後の日本人による海外学術調査の口火を切られた国であり、その後も、幾度となく足を運び、資料収集を続けられた縁の地である。現在、展示中の作品のいくつかについて思うところを、不定期になるとは思うが、このコラムで書いてみたい。
●写真1 COLONNADEの古代ペルシャ考古美術展示ケース
西秋良宏(インターメディアテク館長・東京大学総合研究博物館館長/教授)
Yoshihiro Nishiaki
インターメディアデザイン その八
Intermedia Design 8
現在開催中の特別展示「PHOTO LOGIC(フォトロジック)- 田中良知×IMT」についてお話ししようと思う。この企画を立ち上げるにあたっては二つの思いがあった。一つは、写真というものが、スマートフォンやSNSの普及によって、いまや誰もが使用する日常に浸透したツールであるにも関わらず、プロの写真家による写真作品となれば、フォトギャラリーか写真専門のミュージアムに出向かなければ、ほぼ接する機会がない。もちろん職業的な領域や趣味嗜好の違いはあるにせよ、この時代だからこそ、プロの写真とは何かを問う機会があってもよい、そうあるべきではないか思った。もう一つは、この3年に及ぶコロナ禍によって、人々のあらゆる活動が制限され、さらにはマスク生活によって、顔の半分を覆われることになり、精神的にも閉塞感を抱くようになったこと。とくに子供たちと社会との接点は希薄になったと思う。そんな状況下で、写真をテーマしたコミュニケーションが図れないか、そんな思いに至るきっかけとなったのは、ポートレイトを得意とする田中良知氏の写真に接したことであった。子供から長老まで、その屈託のない表情は、どこか新鮮で、なぜか癒された。また、そんな写真を撮る田中氏の技法や信念とは何か、この機会をIMTで設けたい。とくに子供たちに観てもらいたい。会期を夏休みに当てたのもそういう理由である。主に学術の領域で展示を行なっている当館として、今回は、芸術文化の発信と体験、そして社会貢献を眼下に置いたものである。
関岡裕之(東京大学総合研究博物館特任准教授)
Hiroyuki Sekioka
海辺のアオバト
Green Pigeon on the beach
神奈川県大磯の海岸には夏の朝夕、アオバトの群れが見られる。数十羽の群れが山側から飛来すると海上を旋回し、岩場に降りるのだ。目的は、海水を飲むことである。日本の数カ所で確認されているこの不思議な行動は、ミネラルバランスの調整ためと言われている。アオバトは果実とドングリが主食で、動物質の餌をほとんど食べない。その結果、カリウムに対してナトリウムの摂取量が少なすぎるため、海水(塩、つまり塩化ナトリウムが豊富だ)を飲むとする説である。観察していると彼らは波を被る場所に近づき、波が引いた瞬間を狙って、取り残された海水を飲んでいる。時には次の波を被って慌てて飛ぶ。あるいは、侵食によってできた穴に溜まった海水を飲む。時には海面に首を伸ばし、海水を直に飲んでいることもある。非常に興味深い行動だが、関東一円のアオバトが皆、ここで海水を飲むわけでもないだろう。あるいは、そんなに大事な行動ならあちこちの海岸で見られてもいいはずでは? やはり不思議な行動なのである。
松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)
Hajime Matsubara
数理模型
Mathematical Model
インターメディアテク3階に展示中の様々な数理模型は、19世紀末に制作されたものを基に複製した標本である。複製にはシリコンによる雌型を準備し、オリジナルと同じ材料である石膏を使用して制作している。現代ではこのような複製方法が可能である一方、19世紀末、最初に作られた原型ともなる数理模型の制作方法については、不明な部分もある。原型の制作には、石膏か粘土を使用し、数ミリ単位で積層を繰り返し、丁寧に形状を削り出したのではないかと推測できる。しかしながら、実際にはそう順調に出来上がるものでもないだろう。現在、インターメディアテク2FにF R Pで制作した大型の数理模型を展示中である。原型の数理模型とは全く異なるサイズではあるが、積層の方法を使用して形状の削り出しを試みた。10cm毎に模型の輪郭線を出力し、その形を重ねつつ、階段状になった部分を徐々に整えていく。シンプルな方法ではあるが調整は難しい。当時の制作技法が明確に判別出来ない中で、試行錯誤を繰り返し、現代の技術とも摺り合わせつつ、制作に取り組んでいく事は、新たな発見もあり興味深い経験でもあった。
菊池敏正(東京大学総合研究博物館特任助教)
Toshimasa Kikuchi
ミュージアムとジェンダー (3)
Museum and Gender 3
特別展示を書籍化した『蘭花百姿−東京大学植物画コレクションより』(東京大学総合研究博物館編、2022年5月、誠文堂新光社)の巻末資料「主要人物略伝」には、28人の名が挙がる。最も多いのは植物学者の16人であるが、彼らの研究活動を支えた植物画家9人と植物採集者1人についても取り上げている点に注目してほしい。本書は、1877(明治10)年に創学した東京大学における植物学研究の傍らで制作された植物画を中心に、明治期から現代まで、東大コレクションの植物標本、図譜・書籍、絵葉書、写真等により蘭の博物誌をたどることを主旨とした。本書で紹介した植物画や植物標本というモノからは、植物学者を中心に正史的に語られる植物学史や大学史では脇役や縁の下の力持ちとなり、ほとんど登場しない植物画家や植物採集者の姿を浮かび上がらせることができた。モノを基本とするミュージアムの重要な役割の一つは、こういったところにあると思う。一方、同じく巻末資料の「人名索引」にあがる数をカウントしてみると、全部で184人のうち女性は9人と圧倒的に少なく、もし本企画の時間軸を現代までとしなかったら、登場する女性の数はゼロであったかもしれない。写真は、本書で紹介したラン科植物標本(1975年採集)と写真資料(1954年撮影)に貼付された標本ラベルで、東京大学理学部の技官として研究をおこない、1960年代の東大ヒマラヤ調査隊にも隊員として参加した黒澤幸子(1927−2011)と、小石川植物館で植物栽培を担当し、後に植物学教室教授の山崎敬(1927−2007)と結婚した木村冨佐子(1927−)の名前がみえる。社会の多様性を可視化していくために、ミュージアムがジェンダーの視点をどのように取り入れていくのか。モノが伝えている情報を丹念に拾うとともに、時にはモノの背後に存在する人々や状況を描き出すことも必要だろう。また、正史的な視点からは見落されてしまうようなモノ自体を掘り起こしていくことも求められる。このやりがいのある課題は引き続き目の前に大きく聳えている。
寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)
Ayumi Terada
記憶の蓄積
Accumulation of Memories
ローマの東方30kmにあるティブル(現ティヴォリ)は古代ローマ時代から貴紳の保養地として知られる。皇帝ハドリアヌスは即位後の118年にこの地で自身のヴィラの造営を開始した。先代のトラヤヌスのときにローマ帝国は最大版図となるが、ハドリアヌスは帝国拡大から国境防御へと基本戦略を転換する。英国北部のハドリアヌスの長城など各地に建設されたリメス(防御壁)はその成果である。ハドリアヌスは在位中の多くの期間を属州の巡察に費やし、各地で造営や修復の事業を指揮した。一方で彼はティブルに戻ると、訪問した属州での記憶を建築として再興していった。たとえば、アテナイのアゴラの柱廊やエジプトの運河を模したカノポスなどが規模を縮小してつくられた。ほかにもアカデメイアやリュケイオンなど、巡察地に関わる名を与えられた多数の場所が組み込まれていた。もはや「別荘」という建築単体のスケールを超え、ハドリアヌス自身の記憶が集積され、ローマ帝国の原風景が縮約された場所として遺されたのである。こうしてティブルのヴィラでは、長年にわたる個人の想い出が空間的に再創造され、比類なき複雑な全体性をまとうことになる。いま現地に赴く者は、記憶が蓄積された廃墟の都市をひたすら歩きわまる。そのなかで全体の結節点となるような場所がある。「海の劇場」という名の円形の施設は、水路で囲われた皇帝の隠棲地である。政治と情愛と病苦に難渋した皇帝は、晩年は此処に籠ることが多くなる。『ハドリアヌス帝の回想』でユルスナールは皇帝の回想を「さまよえる いとおしき魂」という言葉で締めくくっている。広大な世界の記憶が一人の人間を介して強い場所性へ凝縮される。博物学への普遍的な問題提起のように思えてくる。
松本文夫(東京大学総合研究博物館特任教授)
Fumio Matsumoto
アカデミアでの国際会議
International Conference at Academia
インターメディアテクにおける集会場と言えば、アカデミアである。昭和初期に東京大学の階段教室で使われていた什器の一部を移設してしつらえた定員50名ほどのこじんまりとした講義室である。歴史を感じさせる木製の長机や赤い布団がそなわった木製椅子、さらには壁に掲げられた歴代教授の肖像画など、来館者にかつての大学がもちあわせていた気品を感じてもらう格好の場となっている。コロナ禍で集会が制限される前には、頻繁に、海外の研究者のセミナーや国際会議に利用していた。各席の机に設けられている丸い凹みはインク壺をおくためのものなのだが、ペットボトルの置き場だと勘違いする今時の出席者を注意するのが定番だった。コロナ禍前に開催した最後の国際集会の一つが、2019年12月の第9回西アジア新石器時代石器研究集会である。1993年のドイツ大会を皮切りにして約3年おきに開催してきた集会で、アジアでは初めての開催であった。主会場を本郷キャンパスとして一週間、実施した会議のうちの半日をアカデミアで過ごしたものだが、17ヶ国、100名を超える出席者は一様にインターメディアテクの審美的空間と世界観に感銘を受けていた。その会議の収録集が先月、オランダの出版社から刊行された(総合研究博物館の関連ツイート)。600ページを超える大部な英文図書である。巻頭の序文には添付のようなアカデミアでの記念写真を掲げた。全ての出席者を受け入れるには少々せまかったのだが、膝をかかえて床に座るのもよし。今風に言えば、どうみても「密」。それが許された社会がつい最近まであったことと、短いのだか長いのだか、そのことを懐かしく思うだけの時間が急激に過ぎたことに思いをよせている次第である。
西秋良宏(インターメディアテク館長・東京大学総合研究博物館館長/教授)
Yoshihiro Nishiaki
オイヌサマのいる所(その2)
Where the sacred wolves are (2)
武甲御嶽神社にある、オオカミを象った4体の狛犬(狛狼?)について。4体、すなわち2対がすぐそばに並ぶのも面白いが、オオカミの表現もずいぶん違う。こちらの1対は顔立ちに一般的な狛犬、つまり獅子の面影を残しており、より古いもののようにも見える。前回ご紹介したもう1対はより写実的に「イヌ」っぽい。体つきも今回のものの方が細く、この方が古来日本人の思い描いていたオオカミの姿に近いようにも思える。ニホンオオカミは一応、ハイイロオオカミの亜種(Canis lupus hodophilax)となっているが、その正体はいまだにはっきりしていない。つい最近も、更新世に日本にいた大型のオオカミと、最終氷期に大陸から来たオオカミが交雑し独自に進化したもの、という研究結果が出た。ちなみに亜種名であるhodophilaxとはラテン語で「道を守るもの」ーー山に入った人間を里の領域まで見送ってくれるという、「送り狼」の伝説にちなむ。
松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)
Hajime Matsubara
展覧会の後で
After the Special Exhibition
2021年6月19日から9月26日まで開催した特別展示『蘭花百姿−東京大学植物画コレクションより』と同名の書籍が2022年5月に誠文堂新光社から刊行の運びとなった。この特別展示を本格的に準備していた2021年の冬から春にかけては、コロナ禍による2回目と3回目の緊急事態宣言が続けて発出されていた。ミュージアムも感染症予防のために臨時休館の措置をとることがあった頃である。会期を迎える前にインターメディアテクの臨時休館は解かれたが、状況次第で再び会期中に休館になるのではないかとも危惧していた。結果的に予定通り開館を続けることができたものの、会期中の最後までまん延防止等重点措置と4回目の緊急事態宣言下にあり、あまり多くの人に展示を見に足を運んでもらえないかもしれないという予測はそのまま現実とならざるを得なかった。こう書くと随分暗い話に聞こえるかもしれない。しかし、この状況は翻って、本展示の内容を伝える出版物は時間と空間の制約を超えて「蘭の博物誌」を紙上で新たに展開するものとしようという、前向きでやりがいのある取り組みへと向かわせてくれた。コロナの影響が続いた2年超をいま振り返ると、できなくなってしまったことや計画変更を余儀なくされたことも多くあったが、私にとって本書の刊行はウィズコロナの時代だからこそ機会が与えられ実現できた仕事となった。蘭花百姿の名に違わぬ多彩な図版と充実した解説・エッセイを本書に収載するために尽力くださった執筆者や関係者の皆様にはここに改めて心より御礼申し上げたい。そして、本書に自負する学術的意義とは別に、非常に感覚的な願いを述べるならば、コロナ禍中で生まれた本書ゆえに、手に取ってくださった人たちが明るい気持ちになり、笑顔でページをめくってもらえるような本になっていたらいいなと思っている。
寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)
Ayumi Terada
オイヌサマのいる所(その1)
Where the sacred wolves are (1)
埼玉県、武甲山の麓の武甲御嶽神社にある4体の狛犬は、いずれもオオカミを象っている。秩父は山岳信仰や狼信仰の拠点の一つであり、オオカミは犬神、あるいは大口之真神として敬われ、「オイヌサマ」と呼ばれたのだ。写真の「狛狼」の製作年代はわからないが、大きな頭、深く裂けた口、ずらりと並ぶ牙、垂れ気味の丸耳、肋骨が浮くほど痩せた体は江戸時代の絵図にも見られるオオカミの特徴だ。実際にどうだったかはともかく、そのように認識されていたのは確かだろう。また、写真の像は前肢の筋肉を現すような彫りが際立っている。まるで仁王像のようにも見えるそれは、犬とは違う強力な生物であることを示しているようだ。ニホンオオカミは明治38年を最後に確認されておらず、絶滅したと考えられている。秩父では2006年にオオカミの目撃情報とされるものがあるが、この像を見ながら、さすがにいないだろうという判断と、この山にはオオカミが似つかわしいという思いが交錯した。
松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)
Hajime Matsubara
反転博物館 2
Flipped Museum 2
反転授業を応用した反転博物館という教育方法をインターメディアテクの小中学校対象教育実験プログラム「アカデミック・アドベンチャー」に導入するとしたら、どのような可能性があり、どのような効果が見込まれるだろうか。反転博物館のアイディアを知った時に構想したのは、2020−2021年度に実験的に取り組んだオンライン版と従来の対面でのプログラムの組み合わせである。まず、オンライン版への参加を通じて、子どもたちが学校や自宅にいながら展示物の観察の仕方やものの見方・楽しみ方を知り、大学生のインターメディエイト(展示の案内役)と一緒に画面越しにそれを体験する。その後にインターメディアテクを訪れ、対面でインターメディエイトと実際の展示物を観察しながら存分に対話をし、自分の発見を言葉にして他の人の意見と比べる。これにより、大学生がサポートする子どもたちのミュージアム体験やものを通じた学びをより充実したものにできるのではないか。反転博物館を主要な議論のトピックの一つに掲げて2022年2月に開催されたアジア大学連盟(AUA)の大学博物館に関するカンファレンスにてこの構想を発表してみたところ、大学博物館における教育デザインの一つのモデルとして海外の大学関係者に関心を寄せてもらうことができた。新年度に入り、インターメディアテクでは対面でのアカデミック・アドベンチャーの募集を再開するとともに、大学生の2022年度ボランティア活動も始動した。次は、この反転博物館の教育方法を実践に移し、その効果の検証をしていく段階となる。ぜひ小中学校の教育関係者の皆様にご協力をお願いしたいと考えている。
寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)
Ayumi Terada
中浜万次郎撮影の三宅艮斎写真
Gonsai Miyake photo by Manjiro Nakahama
漂流者として名高い中浜万次郎(1827-1898)は、1860(万延元)年遣米使節の別行隊に通弁主任として登用され、咸臨丸で渡米した。そのさい、サンフランシスコで写真術を学び、湿板写真機と薬品を購入して日本へ持ち帰った。伊豆韮山代官江川英龍(1801-1855)の手附として江戸本所に住んでいた万次郎は、自宅で知人の写真撮影を行った。そのうちの一人、万次郎の主治医であったという蘭医三宅艮斎(1817-1868)夫妻を1862(文久2)年に撮影している。万次郎が撮影した湿板写真の原板には、ガラス面に独特な黒い樹脂が塗られ、ポジ画像を明瞭に見えるよう工夫されている。写真技術のみならず、写真を装飾したケースに入れて鑑賞するという文化も導入した。艮斎は1848(嘉永元)年に本所で外科医院を開業している。本草学に造詣が深く、兵学などの知識も豊富だった艮斎は、好奇心の旺盛な人物だったようだ。万次郎がもたらした最新の写真技術にも大いに興味を惹かれたに違いない。
白石愛(東京大学総合研究博物館特任助教)
Ai Shiraishi
ハンガー窃盗犯
Raiders of the Lost Hanger
カラスの営巣の季節である。都市部のカラスはしばしば、針金などの人工物を巣材に用いるが、中でもよく使われるのがハンガーだ。巣に使われているのはよく見るのだが、盗み出す瞬間を目撃することは意外に少ない。このハシブトガラスはマンションのベランダにヒョイと止まり、じっと下を覗き込むと姿を消し、再び姿を見せた時はハンガーをくわえていた。おそらくベランダに床置き型の物干しがあったのだろう。くわえて来た時は持ちやすいよう、ハンガーの途中の凹部をくわえていたが、一度置いてくわえなおし、ハンガーの首もと部分をくわえた。これがもっともバランスよく持ち運べる位置なのだ。カラスがハンガーを運んで飛んでいる時は必ずここをくわえている。カラスはハンガーをくわえたまましばらく辺りを窺うと、さっと飛び立って旋回し、マンションの後方へ飛び去った。追跡すると案の定、そこには作りかけの巣があった。ごっそりとハンガーが積み上げられている。どうやらこのカラスはハンガー窃盗の常習犯のようだ。
松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)
Hajime Matsubara
反転博物館 1
Flipped Museum 1
2022年2月にアジア大学連盟(AUA)の大学博物館に関するカンファレンス「アジア文明のための反転博物館を共同キュレーションする:ブレンド型研究と教育のアプローチ(Co-Curating Flipped Museums for Asian Civilization: A Blended Research and Teaching Approach)」がオンラインで開催された。本カンファレンスに参加するにあたり、初めて「反転博物館」というアイディアに出合い、これについて考える機会を得た。反転授業(flipped classroom)という言葉は、聞いたことがある人も多いかもしれない。従来は授業で教員から学生への知識伝授が行われ、宿題として学生が各自で復習や応用に取り組んでいたのに対し、これを反転させ、学生がオンラインリソース等を用いて事前学習として知識習得を行い、授業は質疑応答・ディスカッションや演習のためのアクティブラーニングの場とする教育の方法である。反転授業は、学生の理解度のみならず、学びの主体性や協調性を高める効果があるといわれている。反転博物館とはこれを応用したものであると理解すると、インターメディアテクの小中学校対象教育実験プログラム「アカデミック・アドベンチャー」の目下の課題に結びついた。大学生ボランティアが小中学生の展示案内役(インターメディエイト)を務めるこのプログラムでは、コロナ禍により、対面での実施ができないなか、2020− 2021年度の2年間はオンライン版の実験に取り組んできた。今後再開する対面でのアカデミック・アドベンチャーとオンライン版とをどのように運営していくか。反転博物館のアイディアから、オンライン版のアカデミック・アドベンチャーを来館前の事前学習に位置づけ、対面でのプログラムと組み合わせてみてはどうだろうかと構想している。
寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)
Ayumi Terada
新館長のご挨拶
Message from new Director
本年4月より、インターメディアテクの館長をつとめている西秋です。2013年の開館以降、本施設の発展に尽くされた西野嘉章前館長の甚大なご功績にまずは謝意と敬意を表しつつ、さらなる展開をめざしていきます。最初のHAGAKIですので自己紹介させていただきますと、私はオリエント地域の考古学を専攻しています。1984年のシリア発掘を皮切りに、西はブルガリアから東はウズベキスタンまで中東一帯で毎年のように発掘調査に従事してきました。特に関心をもっているのは現在の文明社会のよってきたるところを、文明発祥の地と言われるオリエントの考古学的証拠をもって解き明かすことにあります。そのため、数十万年前の絶滅人類の時代からメソポタミア古代文明まで、関連するさまざまな遺跡、標本の研究に携わっています。さて、インターメディアテク、和名で言うところの「間メディア実験館」。泥にまみれた考古学と似つかわしくない施設のようにも見えるかも知れませんが、大きな共通点があります。モノは古来、実証物として何にもかえがたいほどの強力なメッセージを発するメディアであり続けてきました。考古学は、そのメッセージを読みとき、インターメディアテクは実物=モノこそを各種メディアの結節点としてメッセージを発信します。メディアの技術や方式が急速に変遷する今日、それらを十分にふまえたうえでなお、実物を基軸としたミュージアムを展開することは今後も新たなチャレンジであり続けるに違いありません。インターメディアテクの試みに、引きつづきのご理解をお願いする次第です。(写真:ウスベキスタンの洞窟調査(左前方が西秋))
西秋良宏(インターメディアテク館長・東京大学総合研究博物館館長/教授)
Yoshihiro Nishiaki
二〇二二年三月三一日に
On March 31st, 2022
本年正月に齢七十を迎え、来る三月末日をもって退職することになる。思えば、弘前大学で十年、東京大学で二十九年、都合三十九年に亘る教員生活であった。北奥羽から東京への転勤、大学から博物館への移籍、教室教官からミュージアム・スタッフへの転職は、それまで美術史学を以てすべてと認じていたわたしの関心領野に、飛躍的な拡張をもたらし、新たな活動領域への展望を拓く契機となった。着任時の職場は「東京大学総合研究資料館」であった。全学共同利用機関として位置づけられる施設ではあったが、事実上、旧理学部の強い影響下にあり、動物、植物、鉱物、地質を専門とする研究者の多く行き交う場所であった。そのため、美術史学の習いとして文献渉猟、美術逍遙を専らとしてきたわたしは、既存のコレクションの保存管理活用においても、学内外における学術標本の取得収集活動においても、およそ経験したことのない営みのなかに身を置かざるを得なくなった。こうした未知の環境下に迎え入れられたときには、好奇心の赴くまま、自然体で生きるにしくはない。所謂「アマチュアリズム」なるものも、そうそう悪いものではなかったのである。もちろん、ときに失態を演じることもあり、それはそれで苦い思い出として残っている。しかし、「知らぬが仏」の強みも、なくはなかった。専門家の到底なし得ぬ大胆な取り組みを、実現に至らしめることができたからである。美術史学だけでなく、数学、植物学、歴史学、情報科学、博物館学など、異なる専門分野の学会誌に査読論文を掲げることができたのも、博物館に身を置いていた御陰であった。資料館からの改組にあたっては、ユニヴァーシティ・ミュージアムという、国公立の博物館とも、私立のそれとも異なる、「第三種ミュージアム」の位格を確立し、そこでの研究教育の基盤となる学術標本コレクションの再評価を促したいと考えた。また、小石川植物園にある旧東京医学校本館を博物館分館へ転生させるにあたっては、ハコモノの大きさ、イヴェントの集客力ばかりを指向するメガ・ミュージアムの対極にあるものとして、静謐さ、親密さ、美麗さに包まれたマイクロ・ミュージアムを、二十一世紀新世代の性向、感性に適う文化創造装置として現出させたいと願った。そして、足かけ十四年に亘って関与することとなったインターメディアテクでは、東京大学と日本郵政グループを産学協同で架橋し、それまで誰も眼にしたことのない博物学的世界のパノラマ景観を東京の表玄関の丸の内に定置させようと思った。たしかに、職業上の専門は何かと問われれば、答えに窮するような立ち位置のままに過ごした教員生活であった。しかし、自分の抱く世界観を、コレクション、展示、出版を通じて物象化してみせるという、類い稀な経験を重ねることができた。このことを改めて幸せに思う。いずれのプロジェクトにも、博物館職員はもちろん、学生・院生を含む学内外の多くの方々からの有形無形の支援があった。そのことに対し、この場を借りて心よりお礼を申し上げ、退職の挨拶としたい。
西野嘉章(インターメディアテク館長・東京大学総合研究博物館特任教授)
Yoshiaki Nishino
東京タワーをジャックする
Jacking Up the Tokyo Tower
モバイルミュージアム『音景夜景 --- トウキョウヘオモイヲハセル』展が始まった。昨年の『粗と密 --- 音景 × コレクション』展に続き、サウンドスケープで変容された空間に展示物を埋め込む試み、第二弾である。地上150mの展望デッキという、博物館とは異なる空間での展示は、挑戦的で好奇心を誘う一方、予想外のことが起こり、困難を極めた。満を持して、ようやく今日、音を出すことができた。東京中の音が集まる東京タワー上空のノイズと、北海道札幌市郊外のすずらん国営公園の鱒見の滝の音を同時に聴いたらどうなるのか。最初のsoundscapeは『S/N ratio Tokyo 二つのノイズの交差』と題したミックスノイズで、人工的な音と自然の音の境界線を問う。都会に住む人間は、没入してしまい、意識することがない騒音。しかし、それらを切り出し、異なる空間へ対立的なノイズと配置することで、改めて意識にのぼってくるであろう。案外ベストマッチかもしれない。
森洋久(東京大学総合研究博物館准教授)
Hirohisa Mori
オオバン、コバン
Large and small
バンという鳥がいる。水の上を泳いでいるのでカモのように見えるが、クイナの仲間である。日本で「バン」と付く鳥にはバンとオオバンがおり、どちらも真っ黒でよく似ているが、属が違うので系統的には少し違う。バンは嘴から額(額板)が赤、オオバンは白なので、そこを見れば間違う恐れはない。近年、オオバンが急に増え、水辺に行けば必ず見られる鳥になった感がある。一方のバンはめっきり見る機会が減った。かつてはオオバンとコバン(大鷭、小鷭)と呼んでいたようで、IMTにある古い標本にも「コバン」と記されたものがある。どこかの時点で、大小しかないなら「バン」と「大きいバン」と名付けた方がシンプルだ、ということになったのだろう。実際、サイズ差はかなりなものだ。バンは全長せいぜい35センチでハトほど、対してオオバンは40センチほどある上、体のボリューム感が全然違う。写真の手前はハシビロガモだが、オオバンはカモ類に匹敵するサイズである。この大柄な体でスイスイ泳ぎ、水に潜り、ヨシ原をかいくぐって歩き回り、走り、飛ぶ、奇妙な鳥たちだ。
松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)
Hajime Matsubara
成長計画
Growth Plan
博物館や図書館では施設の「成長」が課題となる。収集資料が増えるにつれて保管場所や展示空間が不足し、建物の増床や増築の可能性が検討される。「成長」は近代建築に潜在する課題であるが、あらかじめ計画するのは容易ではない。これを意識的に取りあげた建築家はル・コルビュジエである。彼は1939年の無限成長美術館計画において、四角い螺旋状の展示室を外に拡張していく仕組みを考えた。付加成長の戦略であり、上野の国立西洋美術館(1959)にその発想の痕跡を認めることができる。一方、磯崎新は大分県立大分図書館(1966)の設計に際してプロセス・プランニングを提唱した。建築プログラムを動態的にとらえ、延伸可能な樹状のスケルトンによって全体が構成されている。結局、上野も大分もイメージのように増築されることはなかった。成長の成功事例として、デンマークのルイジアナ近代美術館がある。海に面した森に建てられた美術館は、1958年の竣工から7段階にわたって増築されてきた。回廊と展示室がネックレスのように繋がれ、アートの理想郷ともいうべき現在の姿に至っている。その根底にある思想は、建築を閉じずに開くこと、そして空間を分けずに結ぶことである。さて「成長」の問題は、建築における時間の考え方に行きつく。ノルウェーのヘドマルク博物館(1979、写真)は、異なる時代の建築が一体化された施設である。敷地にある13世紀と18世紀の遺構を残したまま、その上に20世紀の博物館が重ねられた。設計者のスヴェレ・フェーンは新しい素材や構造を慎重に挿入し、新旧の要素を自律的に共存させている。博物館の成長は空間的であるとともに時間的である。その継承の理念が問われている。
松本文夫(東京大学総合研究博物館特任教授)
Fumio Matsumoto
列品計画
Display Plan
展示列品を考えるうえで興味深く、対照的にも見える二つの施設がパリの国立自然史博物館にある。進化大陳列館(写真)と古生物学・比較解剖学館である。進化大陳列館は、エコール・デ・ボザールの建築家ルイ=ジュール・アンドレが設計し、1889年のパリ万国博覧会のときにオープンした。新古典主義的な外観を維持しつつ、1994年にポール・シュメトフによって改装され、内部は鉄骨を駆使した壮大なアトリウム空間となっている。中央ホールにはアフリカの哺乳類の剥製が大行進のように並べられている。方舟に乗り込むかのようなその隊列は、フィールドの再現というよりも、動物の多様性の縮約された表現である。ここでは「選択と配列」という展示上の意図が感じられる。一方、古生物学・比較解剖学館は、パリ万博の機械館で知られるフェルディナン・デュテールの設計で1897年に完成した。「動線計画」のコラムで紹介したアルテ・ピナコテークに似た、直進型の細長い平面形の施設である。この比較解剖学の展示室は骨の殿堂とも呼べる場所で、約1000点の骨格標本で埋め尽くされている。脊椎動物に共通する骨格の構成から、系統群の相違点にも注目している。ここでは骨格という形式をベースとして「全容の開示」が意図されている。二つの施設の展示列品は、ミュージアムにおけるコンテンツとアーカイヴの可能性を示している。物語を選び取るのか、すべての題材を見せるのか。このような部分と全体の取り扱いには、さらなる展開の余地がありそうである。ミュージアムのネットワーク化による全体像の横断的拡張、異種要素の埋め込みや再編的な読解によるアーカイヴ自体の変容、限られたオブジェクトによる最小コンテンツとしての外部展開などである。
松本文夫(東京大学総合研究博物館特任教授)
Fumio Matsumoto
採光計画
Lighting Plan
空間への光の導入は建築設計の重要な検討課題である。ミュージアムにおける採光計画の取り組みを複数の事例でみていきたい。展示空間における自然採光の導入は、ロンドンのダリッジ絵画ギャラリー(1817、写真)に始まる。壁面に開口部をほとんど設けず、屋根に配した多数のスカイライト(天窓)から光を取り込んでいる。この画期的な方法はその後の展示採光の基本形となった。スカイライトの考え方を一段と進化させ、比類なき水準に高めたのがフォートワースのキンベル美術館(1972)である。サイクロイド型の断面をもつ曲面屋根の頂部を走るスリットから入った自然光は、下部の金属パネルで反射して曲面屋根の室内側を照らし、そこでさらに反射して展示空間を満たしていく。反射を重ねることでシャープな直射光は柔らかい拡散光に転じ、未曾有の光の空間領域をつくりだす。一方で反射ではなくフィルタリングによる光の制御を試行したのがバーゼルのバイエラー財団美術館(1997)である。展示室の天井を全面的に開き、そこに5層からなる光の制御レイヤーを挿入した。上から、直射光をさえぎる半透明ガラス、紫外線除去をになう複層ガラス、コンピュータ制御のルーバー、展示室側のガラス天井、金属メッシュ天井である。実際のところ、ミュージアムにおける自然採光は敬遠される傾向にある。太陽光からの作品保護、均質な光環境の確保、幅広い演出の可能性といった観点から、現在ではLED照明器具によるライティングが主流となっている。しかしミュージアムはことごとく閉じた人工環境に向かうのだろうか。万物が属していた光の空間のダイナミズムを継承すべきではないか。インターメディアテクは自然採光と人工照明が共存する貴重な実例の一つである。なお紫外線対策済みである。
松本文夫(東京大学総合研究博物館特任教授)
Fumio Matsumoto
動線計画
Circulation Plan
ミュージアムの「動線」すなわち人の動き方には概ね4つのタイプがある。第一は「極少の動線」。これは動線が発現する間際の、動かずとも一覧できる強い場所性に結びつく。安曇野の碌山美術館(1957、写真)はその珠玉の実例である。100㎡に満たない小さな展示室には、荻原碌山のブロンズ像が窓からの光を受けて同じ向きに配されている。ミュージアムの最小形であり、一つの完成形を感じさせる。第二は「直進する動線」。展示物が増えてくると、空間を横につないで直列の配置計画となる。ミュンヘンのアルテ・ピナコテーク(1836)は、英文字のIに似た細長い外形をもつ。始点と終点がある明快な動線計画で、欧米に多くの類例がつくられた。第三は「回帰する動線」。展示室をぐるりと巡って出発点に戻ってくる構成で、ベルリンのアルテス・ムゼウム(1830)に始まる。ギリシアの列柱とローマのドームを抱えた新古典主義の名作であるが、周回型空間群という新しい提案を組み込んで近代ミュージアム建築の原型となった。第四は「自由な動線」。人の動き方を決めつけない応用自在なユニバーサル・スペースが前提となる。ベルリンのニュー・ナショナル・ギャラリー(1968)は、その思考の純粋性を残す大空間である。さて、インターメディアテクはどのタイプだろうか。実はすべてのタイプにあてはまる、あるいは、すべての動き方を選択できる施設である。固有性のある場所が散在し、全体として細長い平面形をもち、しかし順路は決められておらず、自由に往還や周回を重ねることができる。来訪者が動線を発見して楽しめるミュージアムである。
松本文夫(東京大学総合研究博物館特任教授)
Fumio Matsumoto
一巻の終わりに
In the end of the scroll
現在開催中の「Aves Japonicae(7)」では川邊華挙の鳥類写生図第捨七巻を最初から最後まで、3回に分けて展示している。展示企画中のためこの巻物を広げた時、最後にサプライズがあった。巻物が細くなり、「これで最後だな」と思った時、何か手触りが違うと感じたのだ。ほどき終えた巻物から出てきたのは、一本の毛筆だった。他の巻ではスギか何かを削った棒を芯にしていたのに。筆には墨の跡が残り、使われていたことが伺える。丸筆だが、穂先が傷んでいるようで元の形はよくわからない。チビた書筆もあり得るかと思ったが、触ってみると中心部に硬い心毛がなく全体に柔らかいので、どうやらこれは画筆である。いずれにしても、「この巻のみ悪徒に貸し出すこと厳禁」と墨書された大事な粉本の果てに筆がいたことに、何やら画家の魂が込められているかのような感慨を感じて、この筆も展示してある。いや、単に手元にちょうど良い古い筆があったので芯代わりに使っただけ、ということも大いにあり得るのだが。
松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)
Hajime Matsubara
オオタカ
Goshawk
オオタカ。この写真は成鳥で、暗灰色の背中と真っ白な下面のコントラストが美しい。胸から腹には細かい横斑があるが、遠目には見えない。先日、鳥を見つつ散歩に行った際、カラスくらいの鳥が飛んで来てアンテナに止まるのが見えた。翼をピンと伸ばしたまま羽ばたく姿に「これは!」と思ったら、まさにオオタカだった。止まったオオタカにハシブトガラスが猛然と突っ込んでくる。天敵であるオオタカが縄張り内にいるのが許せないのだろう。こういう時、猛禽はだいたい面倒そうに逃げる。彼らはカラスと戦っても益がないからだ。だが今回は違った。絡みに来たカラスに向かってオオタカが反撃したのである。おそらくオオタカもこの辺りで繁殖する気なのだ。この後、一撃をかわしたカラスはオオタカを追って上昇するも振り切られ、上からもう一撃くらいそうになって逃げて行った。強気なカラスとはいえ、いわば戦闘機として進化したタカ相手に空中戦を挑んでも勝ち目はない。
松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)
Hajime Matsubara
ボーダーズ
Borders
教養前期の授業「映像デザイン実習」の今年度の課題テーマは”Borders”とした。5分以上10分以内の映像作品をグループで制作する。テーマの解釈と作品の構成は自由である。何のborderか(政治的、文化的、身体的、心理的・・・)、borderをどうするのか(なくす、つくる、あばく、こえる・・・)、映像としてborderをどう表現するか(見えるとは限らない)。borderは強い言葉なので、その理念的な形式性にとらわれすぎない方がよいと感じていた。学生たちの4本の力作を見て、その懸念は払拭された。朝起きたらシマウマになっていた主人公をめぐる、人と人の境界の発生と溶解と遷移。日本とシンガポールを舞台に、友情が国境を乗り越えていくプロセス。「ボーダー柄」が世界から消滅したことを知り、悲嘆にくれる主人公の新たな出会い。そして4つめの作品”Alienation”(写真)は、社会の少数者が向き合うbordersを主題としている。東京で一人暮らしをする外国人Aは、社会生活や入社面接などで日本社会との間に見えない境界線を感じている。彼女はレンタルフレンドKAFUKAとの会話で癒されるが、それは形式的な関係にすぎない。Aは心の声で対話を深め、人間と人間、人間と自然との間に存在する数々のborderに思い至り、自分との和解の旅にでる。思弁的で内省的なプロットに思えるが、誰もが抱える普遍的な課題へと展開し、bordersとの共存の期待をもって終わる。精緻なテキストと都市の気配を組みこんだ見応えのある作品で、その実験志向はどこかアラン・レネを想起させた。今年度はPEAKの学生が3人参加して、国際色豊かな授業進行となった。考えてみれば、大学はborderが集積する場所である。さまざまな分野や帰属の境界を超えるために、確かに「旅」が必要だろう。
松本文夫(東京大学総合研究博物館特任教授)
Fumio Matsumoto
20世紀の建築(住宅建築編)
Architecture in the 20th Century (Residential Architecture)
20世紀の住宅建築を集めた模型を製作した。縮尺1/100の模型18点を3Dプリンタで出力し、公共建築編と同様に集合的に配置した。竣工年順に作品と特徴を列記する。1.ドミノ・ハウス:柱と床スラブからなる近代建築の祖型(アーキタイプ)。2.シュレーダー邸:家具から空間へと進化した面と線による「デ・ステイル」。3.ロヴェル・ビーチ・ハウス:空間形態と新たな言語によって具現化する「空間建築」。4.メーリニコフ自邸:孤高のアヴァンギャルドの凍結された隠棲地。5.サヴォア邸:「柱と壁の分離」がもたらす近代建築のデザイン・ボキャブラリー。6.マラパルテ邸:海原を臨む断崖上のソラリウムにいたる大階段。7.ブロイヤー自邸Ⅱ:キャンティレバーで支持された浮遊するロングボックス。8.イームズ自邸:大量生産部材の活用による新しい生活空間のデザイン。9.ファンズワース邸:ガラスとスチールで囲われたユニヴァーサル・スペースの原点。10.立体最小限住宅No.3:極小の居住空間に込められた平面と断面の創意。11.51C型:食寝分離と就寝分離を実現した2DK住居の原型。12.スタール邸:都市の眺望に全面的に開かれた近代住宅のアイコン。13.母の家:見なれた外形に内包された多様性と対立性。14.シーランチ・コンドミニアム:海沿いの荒涼たる自然環境に向き合う集合住宅。15.中銀カプセルタワービル:交換可能な住居ユニットからなるメタボリズムの記念碑。16.住吉の長屋:生活の中心に外部空間を挿入した長屋。17.中野本町の家:家族の記憶が込められた内なるユートピア。18.ボルドーの住宅:住まいの中心を貫く生活空間としてのエレベータ。以上で取り上げた建築の方向性として、壁の非構造化、線・面・空間の造形、建設の工業化、機能無限定の空間、最小限の空間、新陳代謝、新生活の提案といった特性が見えてくる。「20世紀の建築」は本館の特別展示『空間博物学の新展開—UMUT SPATIUM』で展示中である。
松本文夫(東京大学総合研究博物館特任教授)
Fumio Matsumoto
20世紀の建築(公共建築編)
Architecture in the 20th Century (Institutional Architecture)
20世紀の公共建築を集めた模型を製作した。縮尺1/300の模型18点を3Dプリンタで出力し、都市の街並みのように集合的に配置した。竣工年順に作品と特徴を列記する。1.ウィーン郵便貯金局:半透明のガラスで覆われた新世紀の光学的空間。2.ドイツ工作連盟展ガラス・パビリオン:ガラスの多面体のクーポラを頂く小さな美の神殿。3.ストックホルム市庁舎:伝統素材と歴史様式で見る20世紀の北欧ロマンティシズム。4.バウハウス校舎・デッサウ:カーテンウォールによる建築外装の非構造化と透明化。5.ストックホルム市立図書館:知のミクロコスモスを象徴する壮大な書籍の円環。6.ルサコフ労働者クラブ:ホールの空間傾斜と多視点性を体現した構成主義の外観。7.バルセロナ・パビリオン:ミニマルな空間構成と壁/床材の緻密な肌理。8.ダンテウム:『神曲』の空間的解釈−−百柱の森から地獄・煉獄・天国の間へ。9.広島平和記念資料館:被災地の再建計画から始まった戦後の日本建築の出発点。10.ロンシャンの教会:量塊的な躯体を多様な光で充たした「言語化しがたい空間」。11.ルイジアナ近代美術館:海と森と建築と美術品が共生する理想郷。12.カステルヴェッキオ美術館:歴史的建造物の保存と転生。13.大分県立大分図書館:成長する建築を規模とスケルトンから構想。14.キンベル美術館:「沈黙と光」の思惟から導かれた奇跡の空間。15.ヘドマルク博物館:12世紀と18世紀の遺構の上に重ねられた20世紀の博物館。16.ラ・ヴィレット公園:点・線・面のシステムをモンタージュした都市公園。17.ベルリン・ユダヤ博物館:失われたアイデンティティの「空洞」が建築を貫通。18.那珂川町馬頭広重美術館:木造建築に限らない「木の建築」の可能性を提示。以上で取り上げた建築の方向性として、自然との共生、保存と転生、空間の自律、システムの重層、透明性と明るさ、天然素材の評価といった特性が見えてくる。「20世紀の建築」は本館の特別展示『空間博物学の新展開—UMUT SPATIUM』で展示中である。
松本文夫(東京大学総合研究博物館特任教授)
Fumio Matsumoto
3DVR
当館の小石川分館は耐震基礎診断の結果、耐震性能が不十分である可能性が判明し、2021年1月から休館中である。重要文化財である分館建物の現状を記録し、見ることができない展示を発信するために、3次元バーチャル・リアリティ(3DVR)によるデジタル・コンテンツの製作が行われた。完成した3DVRは特別展示『空間博物学の新展開/UMUT SPATIUM』のウェブサイトで公開されており、ユーザが自ら操作して建物内の空間を移動し、展示を観覧することができる。本館の特別展会場では、その操作をキャプチャした記録動画を上映している。3DVRの撮影には赤外線3Dセンサを備えた全方位型の高解像度カメラが使われ、小石川分館の内外の多数の場所で撮影が行われた。池を飛びこえる移動、高所からの俯瞰見渡し、屋根の小屋組の探索など、通常の来館では体験できない視点も含まれている。3DVRのコンテンツは3次元データ(メッシュ、点群、画像データ)を統合してクラウド上にアップロードしたURLからなる。センサで測距した3次元の空間情報が取得されており、建築や展示を空間的に再現するだけでなく、身体動作をともなう自由な空間移動を体験することができる。また写真や映像、キャプション、ハイパーリンクなどの付加情報を空間内に埋め込むことが可能であり、コンテンツのプラットフォームとして活用できる。博物館における新たな展示表現の可能性に期待できる。(3DVR製作:徳永雄太氏/ARCHI HATCH)
松本文夫(東京大学総合研究博物館特任教授)
Fumio Matsumoto
「新たな日常」へ
Towards "New Normal"
二〇二二年四月にインターメディアテクは開館から十年目のサイクルを迎える。館の立ち上げにさいしては、本郷キャンパス内にある博物館本館と小石川植物園内にある分館から、相当量の標本・資材を丸の内の施設内へ運び込んだ。明治の創学以来蓄積されてきた学術遺産のなかで、多くは用無しと見なされてきた物品群である。直近の役割を終えたモノに、展示公開を通じて、新たな息吹を吹き込みたい。そうした思いに導かれての創設構想であった。大雑把な数字であるが、開館時には千七百点ほどの標本が展示に供されていた。延べ床面積にして三千平米を超える施設ということで、バックヤードにはまだ充分な余力があった。仮に収蔵品が増えたとしても、スペースの狭隘化が深刻になるのは、かなり先のことだろうと想定されていた。まさか館内のあちこちに学術標本が溢れかえるような事態が、これほど早く訪れようとは、思ってもみなかったのである。しかし、現実は違った。一万枚を優に超えるジャズレコートのコレクションにはじまり、阿部正直伯爵が残した膨大な気象学関連コレクション、古い蓄音機百五十台、「博士の肖像」の絵画・彫刻約六十点、大量の古い額縁、エジプト彫刻断片、リンガヨニ、鳥の剥製、現代美術記録フィルム二十万点など外部からの寄贈品をすべて受け入れ、かてて加えて、学内諸部局から管理換された古い什器類、新たに入手、製作、購入された標本で、瞬く間に場所が埋まってしまった。いまや館外の複数ヶ所に収蔵スペースを確保せねばならぬ厳しい事態に立ち至っている。寄贈の申し出は館にとって、実に有り難い話である。実際、これら新規収蔵資料の多くはいまも展示等に役立てられている。各種の事情でいまだ閉塞感から脱却できずにいるミュージアム事業に新たな展開をもたらす「起爆剤」。そうした位置づけで博物資源の蓄積を今後も積極的に続けてゆきたいと思う。コロナ禍のもたらした「新たな日常」を生きつつ、今年も謹賀新年。
西野嘉章(インターメディアテク館長・東京大学総合研究博物館特任教授)
Yoshiaki Nishino
冬の発見
A Finding in Winter
秋が過ぎ、木々が葉を落とすと、新たな発見がある。夏の間は見えなかった鳥の巣が見つかるのだ。先日、近所の公園を歩いたら、あっという間に10個以上もの巣が見つかった。いくつかは知っていた。去年、あるいは2年前のカラスの古巣もあるし、今年使っていた巣もある。ハシブトガラスとツミは巣の場所も特定していた。だが、これほどオナガの巣があったとは。オナガは複数のペアが集まって繁殖するから、同じ公園に巣がいくつもあるのはもちろん不思議ではない。この公園には、春から夏の間には何羽ものオナガがいたし、確かに防衛しようとしているエリアもあった。そう考えて思い出してみると、なるほど、オナガが大騒ぎしていたあたりにはちゃんと巣があるのだ。そして、ツミの巣の目と鼻の先に作られた小鳥の巣。これはヒヨドリだろうか? 確かに猛禽であるツミが近くにいれば外敵は近づけない。しかし、ツミはいつ捕食者にジョブチェンジするかわからないのだ。鳥にとって営巣とはそれほどギリギリの選択なのだろう。
松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)
Hajime Matsubara
からだのかたち〈3〉
Body/Form 3
東京では自粛期間が続いた2021年。来館者が少ない館内を随分と目にした一年であった。今年3月初旬より3期にわたる特別展示もとうとう最後の展示期間となり、12月15日より特別展示『からだのかたち〈3〉――東大医学解剖学掛図』がスタートした。一年を通して、解剖図における人体の描画表現について再考する場としてシリーズで開催してきた。学生時代、美術解剖学の講義中に教壇のスクリーンに映された解剖図を自分のノートにスケッチする時間があったことを思い出した。この解剖図を使っていた講義中にも学生はこの解剖図を写し描いていただろうか。過去のコラム「からだのかたち2」で書いたが、この解剖図は西洋の解剖図を縮尺を変えて見事に転写した手描きの絵図である。転写の元図になったであろう図に示されているある部位が、今回展示中の解剖図に無い図が1枚ある。発注時の指示であったのか、転写時に描き手が見落としたのかは今となっては推測の域を出ない。それを知った途端、その図のどこがどうなっているのか他の解剖図と照らし合わせて一生懸命観察した。何が大切か先人に教えてもらえた気がした。
上野恵理子(東京大学総合研究博物館特任研究員)
Eriko Ueno
社会空間モデル
リモートワークが普及し、全員が同じ現場に揃う機会が少なくなった。仕事関連の会議はオンライン開催がとても多い。一方で、街中の人出が徐々に回復し、大学は対面教育に戻ろうとしている。業務や教育の新しいスタイルは定着するのだろうか。写真はコロナ禍以降の人間と空間の関係を示すために試作した社会空間モデルである。中央の空間は主人公X氏の自室である。格子状の棚のように見えるのは、Zoom等のリモート会議ツールの画面であり、これを利用してX氏は他者と交信している。右側に浮いているのは他者の空間群であり、その所在地はバラバラであるが、情報システムを介して時空間が共有されている。一方で、左側に並んでいるのはX氏が属しているコミュニティである。学校や職場や家庭などであり、これらは通常は「場所の空間」として一つの建物にまとまっていることが多い。このように物理的に隣接した「場所の空間」と、情報ネットワークによって結び付けられた「関係の空間」が共存しているのが現代社会の特徴である。つまり、人間どうしの近接性を「距離の近さ」と「つながりの強さ」の両面から考えることができる。これまで、学校やオフィスのような比較的大きな建築類型をベースに都市環境が構築されてきたが、それに加えて、より小さな個人レベルの空間の結びつき、すなわち空間類型の分散連携の可能性を考慮すべきであろう。実空間と情報空間の共存は今後も継続するだろうが、そこで問われるのは実空間の計画ヴィジョンである。この模型は本郷本館で始まった特別展示『空間博物学の新展開/UMUT SPATIUM』で展示されている。
松本文夫(東京大学総合研究博物館特任教授)
Fumio Matsumoto
『Intermedia』発刊記(7)
第六号は「『リデザイン』による世界再構築」の副題をもつ、『ReDESIGN+』なるナンバーとなった。開館から五ヶ月してからの発行ということで、オープン時の館内展示を紹介するものであると同時に、インターメディアテクの進むべき道筋のひとつに、「リデザイン」があることを示す、マニフェストの性格を併せもつようなものにしたいと考えたのである。それは最終号と位置づけられているものとして、自然な流れに沿ったものであった。『Intermedia』全六冊の発行は、多言語併用出版、印刷技術実験、(すべてを自前で賄う)インハウス・エディトリアル、(ヤレ紙などの廃棄物を出さない)資源リサイクル、そしてデジタル撮影技術開発など、自分たちなりに考える各種実験の「アリーナ」でもあった。それが奏功して、通巻六冊で萌芽した方法やコンセプトは、以後の学芸活動で開花、結実することになった。それは出版事業からもたらされた大きな成果であった。また、六冊の発行を通じて外国に送出されたメッセージは、海外から多くの来館者を呼び込む導因となった。現今、かくも大判の、贅沢な「ニュース・レター」はどこを見ても、容易には見つからない。いま、手許にある六冊は、分厚い透明アクリルで造られたボックスのなかに収められている。これを眺めていると、「インターメディアテク」が、すなわち当初思い描いた「ミュージアムを標榜しないミュージアム」の全体が、丸ごとそのボックスにコンパウンドされているように、わたしには感じられてならない。ならば、これをもって「ミュージアム・イン・ボックス」と呼んでみたらどうであろうか。ロサンゼルス北東にあるパサデナ美術館で、ヴィジュアル・アーティストのメイソン・ウィリアムズが一九六〇年代のアメリカン・ポップ・アイコンの一つ、大陸横断グレイハウンド・バスの原寸大版画を折り畳み、小型の段ボール箱に収め、「バス・イン・ボックス」と命名して展示してみせたのは一九六八年のことであった。全体を包摂する一個の箱というコンセプトは、なかなかに魅力的なもののように思えるのであるが、どうであろうか。
西野嘉章(インターメディアテク館長・東京大学総合研究博物館特任教授)
Yoshiaki Nishino
好奇心
ネコ特有の匂いの原因の一つにコーキシンというタンパク質がある。この物質を発見したのは日本人で、名称の理由は「猫は好奇心の強い動物だから」だそうだ。人間は猫以上に好奇心の強い動物だと思うが(でなければ博物館など成立しない)、観察している限り、カラスも大概だと思う。彼らは隙間や穴がとにかく気になるらしく、じーっと覗き込んでいることがしばしばある。そういった場所には昆虫など獲物が潜んでいることはあり得る。手に入れた餌を隠せる場所を探しておくのも意味があるだろうし、ひょっとしたら誰かがその隙間に貯食していて、餌を盗めるかもしれない。何より、そういった面倒な思考や計画抜きに「これなーに?」と目を止めさせ、探索行動を誘発するトリガーとして、好奇心は有効ではある。複雑な演算機能を与えるより、脳への負担が小さいだろうからだ。とはいえ、首をひねってスポットライトを検分するハシブトガラスには笑いそうになるし、「あの行動はつまりこういうことで」と書いてしまうのも、動物に備わった好奇心のなせる技である。
松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)
Hajime Matsubara
『Intermedia』発刊記(6)
抽象絵画に登場するイメージのなかには、地球から遠く離れた惑星の相貌、宇宙空間で認められる諸現象と驚くほどよく似たものが見られる。そのことを教えてくれたのは、フランスの碩学ルネ・ユイグであった。この芸術哲学者は主著『かたちと力』のなかで、次のような論を展開している。芸術家の生み出す「抽象」とよく似たものが森羅万象のあちこちに見出されることにはなんの不思議もない、なぜなら、この宇宙は「ウヌス・ムンドゥス」(「一」なる世界)であり、芸術家である人間もまたその構成要素の一つに過ぎないからである。大胆極まりない論であるが、反証を掲げるのは容易でない。同書の翻訳に携わったということもあろうが、わたしにはユイグの主張に得心するところがあった。アメリカの航空宇宙局が無料公開している惑星写真を見て、美術作品との親縁性を思わずにいられなかったからである。火星表面を動き回る探査船から送られてくる映像のなかには、一九五〇年代のパリ画壇を席巻した非具象絵画(アンフォルメル)の画面と見間違うようなものが見出される。それらは、まさに「コズミック・アンフォルメル」とでも呼ぶに相応しいものであったことから、米国航空宇宙局から入手した高精細デジタル画像を、非具象絵画のフィールドに見立てられるまでに拡大、そのプリントに古典的な額装を施して、ギャラリー風に飾ってみせる展覧会を実現してみたいと考えた。『Intermedia』第五号は、したがって「コスモグラフィア」(宇宙誌)号と命名され、ファースト・サイトのこけら落としの展覧会の図録としての体裁を保つこととなった。すでに鬼籍に入ってしまったが、わたしの敬愛するスペインの画家アントニ・タピエスに本号を贈り届けることができていればどんなに良かったか、と改めて思う。日本の「抽象」の草分けの一人、斉藤義重もそうである。一九五〇年代の仕事のなかに、やはり宇宙開闢誌に通じる作品のあったことが思い出されるからである。
西野嘉章(インターメディアテク館長・東京大学総合研究博物館特任教授)
Yoshiaki Nishino
インターメディアデザイン その七
当館二階の奥にFIRST SIGHTという展示室がある。もともと企画展示室のひとつであったが、2015年より半常設展示の「ギメルーム」となっている。ネーミングの由来からもこの部屋での主役は、フランスのリヨン自然史博物館より輸送した歴史的木製什器である。その繊細で造形的なフレームと薄い手すきガラスはまさに工芸品である。リヨン自然史博物館は1777年に一般公開しているが、1913年に改修されているからその年に製作されたものであろう。これに限った話ではないが、西洋のアンティーク家具というのは当時の職人の技術と美意識の高さに感銘を受ける。さて、この什器をどのように仕立てるか、展示物はともかくとしてまず考えたのは、他の空間では使っていない色で印象をガラリと変えて見せることだった。色の候補はいくつかあったが、最終的にビビッドで飽きのこない色としてグリーンを選んだ。それはこの部屋までの導線にあるダークレッドの補色関係であることも決定に至るひとつの要因である。しかし、印象的なだけに6年も見ていると飽きなくもない。良い機会があればまたガラリと変えてみたいと思う。
関岡裕之(東京大学総合研究博物館特任准教授)
Hiroyuki Sekioka
『Intermedia』発刊記(5)
第四号は「かたちとちから」を特集テーマとするものとなった。各種学術標本のプレゼンテーションの仕方に焦点を当てたいと考えたのである。収蔵庫にストックされた学術標本、なかでも自然誌系の学術標本は、展示具との組み合わせ次第で、「研究資財」でしかないものにもなり、また「アート作品」に近いものにもなる。要は、オブジェをより魅力的なモノにみせるにはどうすれば良いのか、ということである。また、その「見せる」方法を、どのように出版物のエディトリアルに反映させたら良いか。それが編集サイドの問題意識であった。この号の三つ折りの頁には、東南アジアに分布するトカゲの仲間で、最大の大きさを誇る「ミズオオトカゲ」の剥製が原寸大で印刷されている。誌面を仔細に観察すると、画面の明るさは充分なものながら、立体オブジェ特有の陰が、どこにも落ちていないことに気づかされるに違いない。このことは、別な頁にある、古い昆虫標本箱を撮った写真をみると、よりいっそう確かなものになるはずである。普通、虫ピンで固定された昆虫標本を撮影するにあたって、型どおりのライティングを施すと、どうしても陰が生じ、このようにはならない。オーバーヘッド・スキャナーを使ったデジタル撮影写真ならではの効果と言うべきか。スキャナーは高性能な撮影装置すなわち「カメラ」である。加えて、内蔵されているライティング機構が単焦点型でなく、移動焦点型であり、被写界深度のレンジが広いという特徴もある。実際、「ミズオオトカゲ」程度の厚みのモノであれば、パンフォーカスで撮影できる。当初はわれわれも半信半疑であったが、創刊号で簡単な実験的フェイズを経験してからは、様々な局面でオーバーヘッド・スキャナーを利用するようになった。第四号の発行後、「ミズオオトカゲ」を刷った頁ほか、ヤレ紙を印刷工場から回収し、大型の紙袋をリサイクル制作し、ミュージアムショップのグッズ販売に供した。びっくりする人もいたが、実に評判の良い紙袋であった。
西野嘉章(インターメディアテク館長・東京大学総合研究博物館特任教授)
Yoshiaki Nishino
首を長くして
ダイサギという鳥がいる。いわゆる「しらさぎ」と総称される中で最大、長い首を持ったサギだ。コサギのようにせかせか歩き回らず、じっと佇んで獲物を待っているか、水際でゆったりと足を運びながら餌を探していることが多い。餌を見つけるとじっと目を据えて動きを止め、そろそろと首を引き絞るように縮めて、頭を獲物に向けて「発射」するごとく、水中に突っ込む。まるで矢を放つ猟師のようだ。餌は基本的に小魚だが、ダイサギやアオサギはかなり大きな餌でも飲み込んでしまう。さて、ダイサギが水面に目を据えたまま一歩、一歩と歩くのを見ていると、不思議なことに気づく場合がある。彼らは時々、首を横に傾けるのだ。それも、見ている方向とは反対側に倒して、斜めに透かして見るような姿勢をとる。これは波の影響を避けているのか、反射避けなのか、20年も前から不思議に思っているのだが、いまだに「この条件の時は、こちらに倒す」と見定めることができないでいる。
松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)
Hajime Matsubara
『Intermedia』発刊記(4)
第三号ではインターメディアテクの入居する建物そのものを取り上げることにした。一九三一(昭和六)年竣工の五階建ての旧東京中央郵便局舎は、逓信省経理局営繕課の建築家吉田鉄郎によって設計されたもので、昭和初期のモダニズム美学の粋を集めた類稀な建物として知られる。表面上、「建築のモダニズム」の特集号となりはしたが、編集上の関心はそうした歴史的な位置づけ以外のところにあった。根本資料として使うことができたのは、建築工事の最中に記録として撮影された小判モノクロ写真のアルバムであった。これは建物の歴史にまつわる数少ない遺産の一つである。アルバムにある小判写真をデジタル化して、印刷に供する。そのさい、どこまで拡大できるのか。はたして大判の印刷物の使用に耐えるのか。その限界への挑戦に加え、モノクロの出版物として、黒の色をしっかりとした「黒」に印刷するにはどうしたらよいか、「黒色」の探究にも試行錯誤があった。現代の印刷では、真っ黒な「黒色」を実現するのがなかなかに難しいからである。結局、複数の印刷インキを使って、墨刷りを三度重ねて刷るという、通常では考えにくいやり方を採用することとなった。また、使用言語はハングルである。ハングル仕様の印刷物でヤン・チヒョルト由来の「モダン・タイポグラフィー」を実践して見せるものは滅多にない、ならばそれをやってみたらどうだろうか。また、紙面構成は建物竣工の時代の新潮流であった「デッサウ・バウハウス」の流儀か、さもなくは「ロシア構成主義」のそれに倣ったらどうであろうか。わたしは頭のなかで、アレクサンデル・ロトチェンコやエル・リシツキーが、ハングルの字組みで、モノクロ版の大判建築冊子を編集したらどのようなものになるか、そのような妄想を駆け巡らせていたのである。既存の古写真のなかから適当なものを抜き出して、それらのデジタルデータで頁を組むことになった。もっとも、出来上がったものは、偉大な先達たちの足許にも及ばぬものとなった。とはいえ、ハングル仕様の「バウハウス」、ハングル仕様の「ロシア構成主義」を実践してみせた出版物など、わたし以外の誰が思いつこうか。そう考えると、あまり悪い気分もしないのである。
西野嘉章(インターメディアテク館長・東京大学総合研究博物館特任教授)
Yoshiaki Nishino
『Intermedia』発刊記(3)
第二号は総合研究博物館所蔵学術標本コレクションの特集として、「収蔵」号と命名された。使用言語は中国語である。用字は簡体字版ゴチック・フォントとした。以後も、インターメディアテクの出版物にしばしば中国語フォントを採用することになるが、これは私見ながら、国内のデジタル・フォントにない力強い字配りが魅力的に映るからである。「収蔵」号についても、印刷技術的にはいくつか難しい問題を抱えていた。なかでも腰帯の部分である。スカイブルーとでも言うのだろうが、青水色の紙に表題の「Intermedia」をサーモンピンクに近い朱紅色で刷りたいと考えた。あの、マルセル・デュシャンが『浮遊する心臓』という作品で実現してみせてくれたように、「青水色」と「朱紅色」を併置するさい、補色関係に近い組み合わせが出来ると、視覚的なイリュージョンが生まれるからである。しかし、問題は青水色の用紙に朱紅色の特色インキで文字を刷っても、文字の朱紅色はくすんだ色にしかならない。地色の青水色を反映してしまうからである。文字の朱紅色を発色の良いものに出来れば、文字の部分が手前に近づいたり、後方に遠ざかったり、錯視が生まれる。鮮やかな色相を実現するには、腰帯の青水色用紙の上に、シルクスクリーンを使って朱紅色の文字を刷ればできなくはないはずなのだが、コスト計算上、成立しないことがわかった。そこで考えたのは、青水色用紙の上に文字部分を白色インキで刷り、その白色インキ部分に朱紅色のインキを乗せるという方法である。こうすると、朱紅色インキは白色用紙上に刷るとの同じことで、色が沈むことにならない。「毛抜き合わせ」の技術による重ね刷りである。現代の印刷プロセスでは、ほとんど版ズレが起きないのである。戦時下の日本で、発色が良いとされるアート紙の入手が難しくなったときのことである。原色版の発色に拘る、とくに美術系印刷物の出版者は、ザラ紙やボール紙など、地色のある廉価紙に白色インキでベタ刷りを行い、その上にカラー印刷を重ねてみせた。予算の枠、技術の壁、資材の欠、そうしたものを乗り越えて前進するためのヒントは、過去の事跡のなかに見出されたのである。巻末には日英の翻訳シートが挿入され、三ヶ国語をカバーするものとなった。
西野嘉章(インターメディアテク館長・東京大学総合研究博物館特任教授)
Yoshiaki Nishino
展示公開中・担当者呻吟中
Aves Japonicae7は無事に始まった。だが「田雲雀の一 又ヒンスイ」とされた絵が気になる。種名はヒンスイ、すなわちビンズイだ。絵には「だいたいタヒバリと一緒だ」と書かれている。雑な言いようだが、気持ちはわかる。この2種はよく似ている。だが、「腹ニフナシ」つまり「腹に斑がない」ともある。それはおかしい。ビンズイなら胸から脇腹にかけてはっきりした縦斑がある。絵の鳥は背中から雨覆羽にかけて褐色で、黒い羽縁がある。腹は汚白色なのだろう、薄墨で表現されている。ビンズイにしては短い尾羽には黒斑があり、縞模様に見える。今更ながら気づいたが、これはセッカなのでは? 図鑑も、基準となる標本もない時代には、文献にある名や聞き知った名を自分の見た鳥に当てはめる、という作業をしていたはずだ。そのどこかで混乱があったのか? これはキャプションに記すべきだったか、確証もなしに書くべきではないか…… 展示が始まっても悩みは続くのである。
松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)
Hajime Matsubara
イチヨウラン(ラン科)
明治詩壇の先駆的詩人として知られる薄田泣菫は、大正期以降の後年は随筆を多く書いた。随筆集『艸木虫魚』に収められた「赤土の山と海と」では、郷里岡山の水島灘近くの小高い赤土の松山での思い出を回想している。ロシアの詩人・思想家のメレジュコオフスキイの『先駆者』を引き合いに、少年時代にダ・ヴィンチのような導き手をもたなかった泣菫は、一人で松山を歩き学んだとある。そのエピソードに、イチヨウラン(一葉蘭)が出てくる。葉を一つのみつけるというのがその名の由来であるように、葉も花も一つずつの「乏しい天恵」の下でも自分を娯しむ生活を営んでいる姿を、泣菫はイチヨウランに見た。『樹下石上』の「小さき花」にもイチヨウランは登場し、深山の木の下陰にたった一つずつの葉と花をもっているに過ぎない「謙遜な生まれつき」と描写される。山田壽雄の描いた本図のイチヨウランは八ヶ岳産で、図の制作年代は1917(大正7)年7月9日であることが書込みからわかる。植物画家としての山田の仕事とは、植物の構造的特徴を正確に記録することである。それに徹すればこそ、本図には、特に描き手の感情を読み取るようなところはない。しかし、清貧な尼や素朴さを残した無名詩人といった泣菫の例えを重ね合わせることで、林床に生育する葉一つ花一つの小形の蘭というイチヨウランの特徴は、より鮮明に私の脳裏に焼きついた。本図を公開する特別展示『蘭花百姿−東京大学植物画コレクションより』は9月26日で終了。現在は、同名の書籍刊行に向けて準備を進めている。
寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)
Ayumi Terada
『Intermedia』発刊記(2)
創刊号の重要性は論をまたない。後続の方向を決定づけることになるからである。特集テーマは当初の計画通り、「アート&サイエンス」となった。A三判の版型選択は、多分に戦略的なものでもあった。なにか新しい事業を興すさい、それに関する情報のインパクトをどれだけ強く、大きくできるか、それが鍵になる。存在感のある、贅沢な装いが、「ニュース・レター」を標榜する定期刊行物の一般的なイメージを裏切るようにする、それが戦略である。腰帯には次のような惹句を掲げた、「ホラティウスからこのかた、詩と絵画は姉妹芸術と見なすのが習わしである。アートとサイエンスについても、同様の論が成り立たぬではない。両者は互いに助け合う兄弟のごときものなのではないか。とすれば、これはアートなのか、サイエンスなのか、と二者択一を問うてはならない。これはアートであり、サイエンスである、と言い切らねばならないのである。インターメディアテク(IMT)を舞台に、モード、ダンス、演劇、音楽、映画の各分野で、その臨界点を探ろうとする動きがいま始まろうとしている」。学術研究の成果と表現メディアの融合は、一九九六年の総合研究博物館の立ち上げから一貫して掲げてきたテーマである。そのためのプラットフォームを丸の内に用意したい。これが云わんとするところであった。発行日は二〇〇九年一〇月一日。出版が決まってからちょうど六ヶ月後のことであった。用語はフランス語。邦語のテキストは別刷りで、差込とした。A三判の観音開きを二ヶ所で採用し、厚手の舶来用紙「ヴァン・ヌーヴォー」とする、無綴じの冊子である。ために、郵送用の大型封筒を特注する必要もあった。刷り上がった『Intermedia』創刊号を手にして、その、多分に時代錯誤的な容姿から、戦時中に発行された国策宣伝雑誌『フロント』のことを思い出したのは、わたし独りだったろうと思う。国を挙げての出版物であったことから、その堂々たる威風には眼を見張るものがあったのであるが、サイズが大きく、目方が重すぎて、海外配布に支障を来したという逸話が残されている大判雑誌である。今日の流通事情ではそこまでのこともない、と思いたい。
西野嘉章(インターメディアテク館長・東京大学総合研究博物館特任教授)
Yoshiaki Nishino
展示設営作業中
Aves Japonicae7の設営が始まった。諸般の事情により、フライング気味である。7/13には標本だけは設置されているのだが、オープンは7/26だ。お許し願いたい。今回はそんなに珍しい鳥がいるわけではない。だが、日常的な鳥だからこそ取り上げられる話題もある。例えば「うぐいす色」問題。現在のうぐいす餅の色は、果たしてウグイスの色か? 花札に描かれている、梅の枝に止まった緑色の鳥は? あれはメジロじゃないのか? 昔の人はメジロをウグイスだと思っていたのか? 結論から言えば、ウグイスとメジロを混同していたなどあり得ない。どちらもポピュラーな飼い鳥であり、籠に入れて目の前で見ていたのだ。そんなことを考えながら黙々と展示台を置き、標本棚の隙間に体を突っ込んで標本を配置する。だが、棚板の切れ目の位置がうまくない。これはどうやって辻褄を合わせるべきか…… 絵の分量と、提示したい情報量の兼ね合いもある。こういうのは結局、現場で、現物あわせで悩むのである。
松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)
Hajime Matsubara
蘭の趣味と絵葉書
近代日本の工学分野で活躍した田中林太郎・不二・儀一の三代ゆかりの資料群「田中儀一旧蔵品」には、工学系以外の分野の資料も多数含まれている。特別展示『蘭花百姿−東京大学植物画コレクションより』の関連展示物を考えている時に思い出したのが、その中の春蘭の絵葉書であった。これは、帝大工科教授を務めた田中不二が意匠を手がけ、東京神田にあった最古参の有名絵葉書商の一つである上方屋平和堂を発売元として、1906(明治39)年に刊行した『花繪はがき』第三集のなかの一枚である。春蘭の他に、唐菖蒲、香(ニオイ)アラセイトウ、朝顔、菊、香菫菜(ニオイスミレ)の絵葉書がセットとなっている。身近に楽しむさまざまな花の一つとして、蘭が親しまれていた様子がここに窺える。専門の機械設計に留まらないデザイン分野に広く関心を寄せていた不二であるが、この絵葉書制作は、「F、T、生」のペンネーム使用からも、玄人跣の道楽といったところだったのだろう。葉書は日本では明治以降に導入された郵便制度により普及し、1900(明治33)年に私製の絵葉書発行が許可されると、絵葉書制作や収集は一般にも大流行した。表紙のデザインにアレンジして用いるほど第三集のなかでは春蘭の意匠が特に気に入っていたのか偶然かはわからないが、翌1907(明治40)年の息子・儀一の誕生日を祝うために出張先で不二がメッセージを書き入れた同絵葉書が、儀一の絵葉書コレクションアルバムの中に見つかった。1902(明治35)年の法制定により満年齢計算が導入され、一人一人の誕生日という考え方が浸透していくのは日本では明治以降のことである。人々がいかに蘭を愛でたかという趣味の一例として取り上げた蘭の絵葉書からは、ある帝大工科教授の人物像から、私製絵葉書の流行や誕生日祝いの習慣といった近代に登場する文化動向までもが付随して見えてきた。本特別展示は9月26日まで。
寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)
Ayumi Terada
『Intermedia』発刊記(1)
学術文化総合ミュージアム「インターメディアテク」(IMT)の創設を目指し、本格的な準備作業に取り掛かったのは二〇〇九年四月のことであった。真っ先に手掛けたのは、「IMT」のロゴの作成と、レターヘッド、封筒、名刺など、必要な備品の用意であった。それに続いたのが、企画構想を内外に伝えるための広報誌の制作発行であった。広報誌出版の計画は、大概のところ次のようなものとなった。誌名は『Intermedia』とする。二〇一二年に予定される施設竣工までの三年間に都合六冊を刊行し、それらが出揃った段階で帙に収め、六冊ひと揃いのセットとする。竣工後は、定期刊行物として発行を継続するか、館内で開催されるイヴェントに合わせて逐次発行するか、そのいずれかとする。判型はA三判とし、各号二十頁から三十頁を見込む。各号ごとに使用言語を変える。創刊号はフランス語、第二号は中国語、第三号は英語、第四号はハングル、第五号はロシア語ないしイタリア語、第六号は日本語とする。最終号を別として、各号毎に日本語の翻訳を付し、適宜、英語等の翻訳も付す。各号ごとに特集テーマを変える。創刊号は「インターメディアテク」の基幹主題となる「アート&サイエンス」の特集号とする。第二号は「博物学」、もしくは「標本」か「コレクション」、第三号は「建築」として、旧東京中央郵便局舎を特集する。以下は未定。ただし、第六号は「インターメディアテク建設への歩み」(仮称)とし、施設建設のドキュメント・ファイルとする。発行部数は創刊号千五百部とする。国内外のマスコミ、関係諸機関、関係各位に宣伝媒体として送付し、残部は施設竣工後、ミュージアムショップにて販売に供する。広報誌は概ね上記のガイドラインに沿うものとなったものの、露語版、伊語版が実現せず、千五百部発行も貫徹できなかった。これは贅を尽くした雑誌発行にありがちなことと受け止めている。バウハウスのそれを彷彿させるポスターの制作が、それを補うものとなった。
西野嘉章(インターメディアテク館長・東京大学総合研究博物館特任教授)
Yoshiaki Nishino
巻貝の赤—辛螺(ニシ)色—
色の中には、生物から名付けられたものが幾つかある。例えば、キツネ色などは分かりやすい。しかし、時には一目見ただけでは分からない色名もある。私にとっては辛螺色がそうであった。辛螺色は、巻貝(辛螺)の貝殻の内側のような黄がかった赤色を指す。古くから使われていたようで、南北朝時代に洞院公賢によって書かれた『園太歴』には、御随身の装いとして、面が黄香で裏が紅の辛螺色狩衣が登場する。黄香とは、薄い茶のような色合いの香色に黄みを加えた色のことであろう。紅は鮮やかな赤のことで、二色の組み合わせで赤と黄の混ざった色を連想させた。江戸時代に伊勢貞丈が記した『安斎随筆』では、辛螺色は柑子色や甘草色に類するとされている。柑子色は蜜柑系の果実である柑子から、甘草色はユリ科の植物である甘草から名付けられており、いずれも橙系の色である。辛螺とは特定の貝を示す言葉ではなく巻貝の俗称なのだが、貞丈によると、辛螺色はアカニシ(赤辛螺)の色に由来する。画像は、IMTに展示されているアカニシである。普段は外側を見せる形で展示されているが、色彩を確認するために内側を見てみた。思った以上に色が薄かったが、確かに橙がかった色合いをしているのが確認出来る。それにしても、生物の名を冠した色を目にする度に想像力を掻き立てられる。誰が、どのように付けたのだろう。「この色はまさにアカニシの色だ」と言い出した人がいるのだと思うと、昔の人の色彩感覚に感心せざるを得ない。
秋篠宮眞子(東京大学総合研究博物館特任研究員)
シロバナハクサンチドリ(ラン科)
20世紀後半を代表する詩人で、ルーマニア(当時)にユダヤ人として生まれ、母語のドイツ語で詩作を行ったパウル・ツェランの詩「トートナウベルク」のなかに、「ハクサンチドリ、ハクサンチドリ」(1972年、飯吉光夫訳)と繰り返されるフレーズが出てくる。トートナウベルクとは哲学者ハイデガーが大半の著作を執筆した山荘があった場所のことで、この詩はツェランがハイデガーとの対話を期待して彼の地を訪れた後に著し、ハイデガー本人に送っている。晦渋な作品であるが、ナチスとの関係について最後まで沈黙したハイデガーに対するツェランの絶望や批判を含んでいるというのは多くの文学者・翻訳者の言及するところである。ドイツ語の原文では「Orchis」と書かれており、これを「蘭」と訳すか「ハクサンチドリ」とするかは、翻訳者の解釈が加わってのことになる。ツェランが実際に見た花のことを描写する意図をもっていたのか、それが紅紫色なのか、山田壽雄が描いた本写生図のように白色だったのか。本図の裏面には「大正五.六.廿」という制作日や実寸大であることを示す「1/1」の書込み等に加え、「葉の表面は若き緑(一号) 裏は淡ク,稍や濃き并行脈アリ.」という色についての具体的なメモがある。本図の第一印象としては、輪郭線の緻密さに比べ、彩色はさっと簡単に撫でたような筆運びに思えたが、花部の後ろを左右に跨る葉に注目すると、葉の裏に用いられている緑色は表面に比べ淡く、少し濃い色で単子葉植物によく見られる平行脈が描かれているのがわかる。ツェランの詩に隠された意味もこんなふうに見て取れる瞬間のようなものが私に来るだろうか、としばしこの図を見ながら考えに耽ってしまった。現在、本図は特別展示『蘭花百姿−東京大学植物画コレクションより』にて公開中である。
寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)
グリプトドン骨格図
この骨格図は、19世紀後半に教材として使われた教育用掛け図コレクションの一部である。描かれているグリプトドンは絶滅生物で、こうして見ると小さく見えるが、実際には全長3mにも及んだ。図の下部に記されているPanochthus(パノクトゥス)は属名である。上は横を向いた骨格図で、下は装甲に覆われた背中から尾の部分が目立つように描かれている。この図を見た時に、おそらく出典があるのではないかと考えた。調べてみると、古生物学者のカール・アルフレート・フォン・ツィッテル(1839-1904)が編集したText-Book of Paleontologyの第3巻「哺乳類」に掲載されている図123、図124とそっくりである。図123は、アルゼンチンのパンパス(大草原)で見つかったグリプトドンの復元骨格(装甲なし)を、図124は、ブエノスアイレス州のパンパスで見つかったグリプトドンの復元された装甲を描いている。図と共に記載されている文章はグリプトドンの外見描写で、歯から始まり尾で終わる。これらの図がグリプトドンの身体的特徴を説明することを想定したアングルで描かれていることを思うと、実際に教育の場でどのように使われたのか、想像がしやすい。
秋篠宮眞子(東京大学総合研究博物館特任研究員)
蘭解剖図のできるまで
特別展示『蘭花百姿−東京大学植物画コレクションより』のなかに「中島睦子の蘭解剖図」というコーナーがある。ここでは、オランダの旧王立植物標本館にて標本図制作の訓練を積んだイラストレーター・中島睦子の仕事を紹介している。インクで描かれた線画の完成図のみならず、今回の展示で注目してほしいのは、その制作のために参照された東京大学総合研究博物館所蔵のおし葉標本と鉛筆スケッチである。例えば、サギソウ(鷺草)のおし葉標本は、ラベルから1889(明治22)年に小石川植物園で栽培されたものであることがわかる。この標本を参照して、中島が1993(平成5)年に隣の植物体スケッチを描いた。スケッチに参照標本情報のメモがあり、標本にもそのことを記録するラベルが2021年3月に付加されている。明治期の標本が現代においてこのようなかたちで研究に利用されていることに驚く人も多いに違いない。標本とスケッチとを見比べると、標本から植物全体の姿が精緻に写し取られていることがよくわかる。一方で、中島が標本の見たままを写生しているわけではないことにも気がつく。植物画という研究ツールで伝えられるべき情報は植物学者の指示のもと、科学的な信頼性が担保されていなくてはならない。花や葉がどのようについているのか、どの部分に特徴があるのか、科学的な植物画制作のプロセスにおいて、植物学研究に必要な構造を伝えるための再構成がいかに重要であるかが直観的に理解できる。植物画を見たときの引き締まった画面の印象はこれに由来し、われわれの目に格別魅力的に映るのかもしれないと思った。本コーナーの標本・スケッチ・線画を比較できるセットは展示更新があり、前期(-8月1日)は上述のサギソウ(写真右)とムニンシュスラン(無人繻子蘭、写真左)を公開していた。現在は後期(8月3日-9月26日)として、ミヤマフタバラン(深山二葉蘭)とスズムシソウ(鈴虫草)を展示している。
寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)
展示企画進行中
Aves Japonicae7の企画がまとまり、標本もなんとか当てがついた。今回は絵巻物一巻を全て見せる企画であるが、そうすると大問題が一つ。Studiolo内に展示台を並べて行う企画だが、その展示スペースが限られているのだ。この巻物は約16メートルの長さがあるとわかった。まずい、2回に分けても収まりきらない。キャプションを置くスペースなども考えると、3回に分けるしかあるまい。となると切れ目はここか。こうして1回目に公開する鳥が決まり、レイアウトの目算がついた。挨拶文を完成させ、何より、公開期日を決めなければならない。他の展示更新スケジュールも見ないと作業のバッティングが生じる。こうやって流動的な状況に対して仮決定を繰り返しながら、同時進行でプレスリリースと挨拶文を書き、個別のキャプションにかかる。まずはビンズイだ。絵には「田雲雀の一 又ヒンスイ」とある。タヒバリの一種という認識だ。だが、この絵は本当にビンズイなのか? ここからがやっと、鳥類学の出番である。
松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)
からだのかたち〈2〉
7月21日より特別展示『からだのかたち2――東大医学解剖学掛図』がスタートした。特別展示『からだのかたち――東大医学解剖学掛図』は、入替えを行いながら1年を通して東京大学医学部で保存されてきた視覚教材を公開している。掛図は、手描きで描かれており解剖学に関わるものだけで約700点にのぼる。初回で23点、2期目で20点を展示している。掛図の正確な制作年代は明らかになっていないが、1800年代後半から1900年代前半の西洋の解剖学書の図版から転写をして図を制作したと推定している。この掛図を制作する転写の方法として、手本にする解剖学書の図の上に等間隔でグリッドを引き、掛図の洋紙にも等間隔でグリッドを引く、そして、元図のグリッド線に交差する図のポイントを押さえていき、ポイントを繋いで全体の図を正確に転写していく。このような描き方で、見事に正確な図に仕上げている。転写のためのうっすらと残るグリッドの痕跡や講義中に指し示したチョーク痕も掛図をじっくり観察すると見えてきて味わい深い。本特別展示の資料体である掛図は、人が筆や絵の具を駆使して描き、解剖図を描く・使うための痕跡や描き手の個性が見え隠れし、また、掛軸という素材感や質感を持ち合わせ、人間味溢れる魅力的な解剖図である。デジタル時代の今だからこそ「手描きの解剖図から享受することとは何か」、この機会に掛図の前で考えてみたい。
上野恵理子(東京大学総合研究博物館特任研究員)
三足蟾蜍
栗本丹州(1756-1834)が著した『千蟲譜』は、その名の通り虫類についてまとめられたものである。当時の虫類の範囲は現在「虫」と呼ばれているものよりかなり広く、カニ、ナマコ、コウモリ、カエル等も含まれている。実物は既に消失したとされており、画像は二十点以上ある写本のうちの一点とされている。このページに描かれている「三足蟾蜍」は、三本足のヒキガエルの標本である。この三本足の蛙は、宝暦(1751-1764)のときに下野州都賀郡田所村(現在の栃木県)で採集され、薬水で満たした硝子壜におさめられ保存された。壜の口と蛙の口の間に糸のようなものが見えるが、これは蛙が外から良く見えるように固定するためのものであろう。所有者は田村元雄とある。田村元雄は栗本丹州の実父で本草学者である田村藍水(1718-1776)の通称と同一である。田村藍水は、平賀源内の発案で薬品会を主催した際に硝子壜の中の薬水に浸した蛤蚧(オオヤモリ)と鼉龍(だりゅう、カアイマンと併記されていることからカイマンのことと思われる)を出品しており、その図が『物類品隲』に描かれているのだが、硝子壜の口を紙と思しきもので覆いそれを紐で固定している形式は、この図に描かれている壜の様子とたいへん似通っている。液浸標本は今となっては良く知られた保存形態であるものの、江戸時代当時は西洋から伝わった最先端の知識であった。そのような知識に触れ得る人間は限られていたと予想できることからも、ここに記されている田村元雄は田村藍水のことで間違いないであろう。「今ニ於テ其家ニ秘蔵ス一奇ト云フベシ」と書いていることから、栗本丹州は三本足の蛙を直接見て描く機会があったと考えられる。
秋篠宮眞子(東京大学総合研究博物館特任研究員)
シラン(ラン科)
本図は裏面に「明治43. 5. 27」という制作日の書付がある。『牧野日本植物図鑑』(1940年)第2066図のシランは、その刊行より30年前に描かれていた本図が下図であると推定されている。最下部の花に引き出し線で「トル」と書込みがあるように、図鑑原図作成時の修正が見て取れる。特別公開『東大植物学と植物画−牧野富太郎と山田壽雄vol.3』にて本図を展示することに決め、以前からタイトルが目に留まっていたミステリー、乃南アサ『紫蘭の花嫁』を読んでみようと思い立った。連続女性殺人事件を追う刑事・小田垣が行きつけのバーで出会った女性・摩衣子。彼女はカトレア柄のワンピースで登場する。次に二人が会う場面では、摩衣子が着ていた服の抽象画のような柄を小田垣がマスデバリア(熱帯の蘭)だと言い、小田垣が蘭に詳しいことが明らかになる。それから摩衣子は小田垣の関心を引くようにさまざまな蘭の生花を身につけて現れる。エランギス、カランセ、アングレクム。そして、シンジュクと名付けられたセロジネ……。1992年に単行本が刊行されているので、今から29年前の作品ということになる。ダイヤルQ2といった事件の小道具に古さを感じるものの、正体がなかなかわからない複数の登場人物が錯綜して物語が進み、頭がクラクラするような面白さを味わった。私が読む限り、タイトルにある紫蘭は作中には現れなかったと思うのだが、紫という色や「あなたを忘れない」という花言葉からラストシーンの解釈に想像が膨らむ。蘭にはミステリーが似合う、ということかもしれない。
寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)
Keys to Architecture
教養前期の「空間デザイン実習」をオンラインで実施した。土曜日3回の集中式授業で、自分でデザインした建築の模型をつくる実習型のプログラムである。初日に建築概論の講義がある。Keys to Architectureと題して、建築、都市、デザインのキイとなるテーマについて話しをする。キイワードの数は当初は90で始まり、現在は120にまで増えた。最新のキイワードは「近接性」である。パワーポイントは全部で528枚あり、これを4時間でこなすので、かなりの高速圧縮型の講義となっている。全体の内容は12のセクションに分かれている。1.西洋建築史、2.日本建築史、3.言葉の喚起(空間/時間/建築・・)、4.建築家列伝(海外編)、5.建築家列伝(国内編)、6.都市の様相、7.居住の形式、8.かたちと力、9.比例と記譜、10.外部への視座、11.映像と情報、である。短時間に広範囲のスライドに接することで、全体的なイメージをつかむこと、自分の関心分野を見出すことへの期待がある。添付画像は西洋建築史と日本建築史のセクションの縮刷版である。ここでは最後のまとめとして、西洋建築は「回帰しつつ前進」、日本建築は「導入しつつ洗練」というダイナミズムを示している。また建築の永遠性について、パルテノンと伊勢神宮を対比している。思考の端緒になるように、このような図式的な問題提起を行っている。授業のメインとなる「次世代建築」の模型制作では、今年も多様な力作が集まった。自然環境との関係の再構築、コロナ禍を経た人間関係の回復を目指す作品が多く見られた。
松本文夫(東京大学総合研究博物館特任教授)
マメヅタラン(豆蔦蘭)のアウラ
1887(明治20)年に創刊された『植物学雑誌』は日本で有数の歴史ある学術雑誌として知られる。この第1巻第1号の第3版に、マメヅタランの全体図と花の拡大図を示した多色刷り図版が掲載されている。これは、植物学者・大久保三郎がマメヅタに似た蘭の形状について述べた文章に添えられた図である。公開中の特別展示『蘭花百姿−東京大学植物画コレクションより』では、本図版とともに、その原図と推定される植物画2点(東京大学総合研究博物館所蔵)を並べて紹介している。手描きの図を眺めながら、大久保が1882(明治15)年に房州清澄山に植物調査に出かけて初めて見つけた植物を記録した時の胸の高鳴りまでこれらの図が伝えているかもしれないと想像すると、そこに唯一無二のものとしてのアウラが感じられる気がする。一方で、植物学研究のために植物画が果たす役割のなかで、学術論文の図版として印刷出版に用いられることが第一義であるとすれば、原図はその準備過程にあったものにすぎないとも言える。そうすると、印刷物に掲載された図版に目を移した時に、複数存在し流通したこれこそが完成形としての輝きを放っているように思えてくる。このようにオリジナル/コピーを巡るわれわれの認識という興味の尽きない問題にまで考えが及ぶのも、本展で植物画を鑑賞する楽しみのひとつではないかと思う。なお、前期(8月1日まで)の展示では、マメヅタランの標本も会場内で見ることができる。
寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)
明治期に描かれた蘭
東京大学草創期、小石川植物園では近代植物学の導入と発展に力が注がれた。本図は、その最中に大学お雇い画工として活躍した加藤竹斎が描いた「エリデス・クイーンクエブルネラ」という洋蘭である(東京大学大学院理学系研究科附属植物園所蔵)。右下には竹斎の印が見える。右上のラベルの「東京大学理学部」とは、1877(明治10)年に法・文・理三学部体制で設立された東京大学時代(帝大を名乗る以前)を意味する。裏面には「横濱 ヂンスデル氏 蘭科 明治十八年八月」との書込みがあり、海外から横浜に到着した洋蘭が小石川植物園にもたらされ、その珍しい異国の花を植物学研究のために描き留めたものと推定される。左方向に伸びた葉が画面に収まりきらず、一見大胆な構図にも思えるが、花・葉・根のつき方を精緻に描写し、花の解剖図を左上余白に添えている。科学的視点にもとづく植物画として描かれたことの証左である。一枚の植物画がどのように植物学的情報を過去に伝えたか/今日に伝えているのか、さらにそこに見出すことができる大学の歴史や当時の社会・文化状況にまで目を向ければ、次の一枚、また次の一枚へと興味が尽きることなく、何度見ても見飽きることがない。特別展示『蘭花百姿−東京大学植物画コレクションより』(6月19日より公開)の準備中、私は眼福と知的愉悦の日々を過ごした。皆さんにもその幸せを体験してもらえる展示空間になっていることを願うばかりである。
寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)
展示企画構想中
夏に向けて特別展を企画中である。日本画に描かれた鳥と剥製を並べて展示するAves Japonicaeも次で7回目、正直に言うと、そろそろネタが苦しくなって来た。もちろん、日本画はまだあるし、見せ方のアイディアもある。だが、問題は手持ちの鳥類標本だ。対応した剥製がないと展示が成立しないのだ。そうやって考えているうちに、このシリーズではまだ、「一巻の絵巻物をただ全て見せる」ということをしていないことに気づいた。そのつもりで見てみると、ある一巻が目的に合いそうである。最晩年の作品なのだが、身近な鳥を淡々と描き、時に舶来の珍しい鳥に夢中になり、ある時はハトの雛を拾ったのだろうか、ヒョイとその絵が挟まる。決して豪華絢爛な作品ではない。この巻に描かれた季節ごとの鳥たち、その鳥を描き続けた画家の静かな日常といったものが、今この激変した我々の日々において、むしろ輝いて見えたのである。時に無為は作為に勝る。決してネタを考えるのが面倒になって丸投げしたわけではない。
松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)
シュンラン(ラン科)
3階にて特別公開中の「山田壽雄植物写生図」は、特別展示『蘭花百姿−東京大学植物画コレクションより』(2021年6月19日−9月26日)の開催に合わせ、一足先に、ラン科を含む単子葉植物の図を紹介する『東大植物学と植物画−牧野富太郎と山田壽雄vol.3』として展示更新を行い、6月8日より公開する。そのなかの一つである本図の裏面には「明治45. 5. 20 鎌倉産. 牧野先生採集」との書付があるため、植物学者の牧野富太郎が山田のもとへ持ち込んだ花が描かれたものとわかる。小説家で童話作家の小川未明の作品「らんの花」は、お茶の香りの話から始まる。そのお茶には「白いらんの花」が入っている。主人公の詩人は、その不思議な香気に魂を酔わされたように感じた経験から、蘭に興味をもつようになる。最後のシーンも、蘭の香りが印象的に描かれる。友人の故郷の品で「らんの花」を漬けたものを湯に入れて出されたのを飲んで、主人公はそれが採れたという山に蘭を探しに行く。五月半ばのまだ雪がところどころに残る山で、主人公は蘭の芳香をかぐものの、足を踏み外して谷底に転落し、ついぞ花を見ることはなかった。未明は「白」という色に特別な意味を込め、「白いらん」を創作していると思われるが、蘭の花が香り高いことで知られるのは事実である。春蘭(シュンラン)はその名の通り春を告げる花として日本で古くから親しまれてきた植物で、花を塩漬けにしてお茶として香りを楽しむことがある。本図に描かれたシュンランは、花と茎のみ彩色されている。牧野が山田にもたらした花も良い香りがしていただろうか、未明が創作の着想源にしたのはこのような花だっただろうか、画面の大半を占める未彩色の部分にも誘われて、あれこれ思い巡らされる。
寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)
仏像工学
この度、インターメディアテク3階の常設展示部分を更新し、仏像の模刻作品6点を展示する『仏像工学――追体験と新解釈』を開催する運びとなった。今回展示している模刻作品は、作者が制作を通じて当時の造像技法を具体的に追求した研究成果でもある。そのため、「模刻」という言葉だけでは伝わりにくい程に、様々な要素を兼ね備えている。制作を通じて得られた新たな解釈についても、キャプションに加える形で掲載している。立体物を手作業で模刻する作業は非常に複雑で難しい。輪郭線は視点を変えれば無限に存在するため、基準となりにくい。常に様々な視点から観察し、慎重に作業を進める必要がある。作者は、扱う刃物が小さくなる模刻制作の終盤に、先人の技術の高さと、古典美術の造形の奥深さを感じ取る。非常に地道な作業ではあるが、作品が徐々に完成していく様は、作者のみが得られる貴重な喜びの一つであり、その後の活動にも大きく活かされている。このような展覧会を開催する事が、今後の文化財保存にも役立つのではと考えており、継続して開催していきたい。
菊池敏正(東京大学総合研究博物館特任助教)
砂漠の集落
モロッコではアトラス山脈の南側は砂漠気候となる。山脈南麓からサハラ砂漠にかけての一帯に点在する要塞都市や集落を訪れた。25年前のことである。北のマラケシュから路線バスに乗り、南のワルザザートへ抜け、オアシス都市のティネリールに至る。ここで四駆車をチャーターし、広漠としたエリアを移動していく。写真はクサール・メラブという集落の風景である。クサールとはマグレブのベルベル人の伝統的集落であり、その多くは日干煉瓦で造られている。壁で囲われた約200M角のエリアに住居や穀倉が集まっている。内部には街路網があるが、街路の両側は壁となって中の様子を窺い知ることはできない。建物の2階部分が上部をまたぎ、街路に縞模様の強いコントラストを描きだす。私が行ったとき、新たな訪問者を認めて数人の子供たちの笑い声が聞こえた。子供たちのシルエットが動き、街路を折れて消失し、また別所に現れて哄笑が響く。強烈な光と影、出没する子供たち、断続する笑い声・・。このとき遭遇した空間体験は、今でも鮮烈によみがえる。集落や要塞都市において、土着の環境素材を用いて、外部から隔たれた別世界が築かれているのを目撃した。荒凉たる岩石砂漠をさらに車で南下していくと、やがて地面がサラサラの砂に切り替わるところにでる。ここから先はサハラの砂砂漠である。「必ず戻って来いよ」とドライバーに念を押され、砂の上を歩きだす。延々と続く砂の山並みにどんどん引き込まれていく。足元の細粒は微かに流れ続け、地形が定まることはない。4ヶ月にわたる建築調査行の最後にであった砂漠の風景は、深く静かな衝撃として沈潜した。
松本文夫(東京大学総合研究博物館特任教授)
リンドウ(リンドウ科)
3階に展示中の「山田壽雄植物写生図」のリンドウは、裏面に「大正3.10.16」の日付と「赤羽根附近」「牧野先生ト」の書付が確認できる。植物画家・山田が、ある秋の日に植物学者・牧野富太郎と出かけた折に採集したリンドウを描いたことがわかる。リンドウが登場する小説に伊藤左千夫の『野菊の墓』がある。題名の野菊とはヒロインの民子を表すが、主人公の政夫が進学を理由に民子と別れる前に過ごした秋晴れの一日の描写に、野菊とともに登場する印象的な花がリンドウなのである。お互いを慕う思いをストレートに伝えられない二人。政夫は「僕はもとから野菊がだい好き」「民さんは野菊のような人だ」と民子のために摘んだ野菊を介して恋心を表白する。これですぐに何かが起こるわけではない。しばらくおいて、今度は民子がリンドウの花を手に採って「わたしりんどうがこんなに美しいとは知らなかったわ。わたし急にりんどうが好きになった」「政夫さんはりんどうの様な人だ」と返す。この表現の機微は、初読の頃、政夫や民子と同じくらいの年だった私の生硬な心には正直あまり響かなかった。しかし、山田の描いたリンドウから久方ぶりに思い出し、結ばれることのない二人の運命と民子の死という物語の結末を知りながら改めて読むと、あまりの切なさに涙が止まらなかった。
寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)
東京大学の画工――佐々木三六
1885年頃の東京大学理学部生物学科で画工をつとめた一人に洋画家・佐々木三六(1860-1928)がいる。兄は東京帝大の動物学者・佐々木忠次郎として知られる。三六は1875年にイタリアに留学、トリノ王立美術学校にて油彩画を学んだ。その三六が東大画工をつとめた痕跡が、『植物学雑誌』第1巻第5号に載る本図である(東京大学総合研究博物館蔵)。海藻学者・岡村金太郎によると、この図は1887年に生物学科教職員を含む三十人余が伊豆七島を巡航した際に制作されたもので、岡村は「此時伊豆の大島で、Martensia australisを大久保君〔大久保三郎〕が採つたのを、其頃植物学室の画家であつた佐々木三六君が写生して居たのを、自分は見て知つて居るが、実に立派なもので、今でも教室に保存せられて居り、其図は植物学雑誌第一巻第五号に載つて居る」としている(「青長屋―本邦生物学側面史」『科学知識』1922年8月号)。教室に保存された三六の描いた海藻図は、学術調査上の記録であると同時に、伊豆七島巡航の懐かしい想い出としても記憶されたことだろう。
藏田愛子(東京大学総合研究博物館研究事業協力者)
巣ごもり
巣ごもり需要という言葉がすっかり定着した感があるが、春から初夏はまさに、日本で繁殖する大半の鳥にとって「巣ごもり」の時期である。さて、都市部でも多くの野鳥が繁殖しているが、その中にはツミという小型の猛禽も含まれる。ハイタカ属なので見た目はまさに「タカ」だが、大きさはメスでもハト程度、オスはハトよりも小さく、ヒヨドリと大差ない。この歴とした猛禽が、都市の公園でしばしば繁殖している。東京23区内でも。写真は先日、私の家の近くの公園で見かけたツミだ。オナガが大騒ぎしていると思ったら、その真ん中にツミがいた。オナガにとってツミは天敵なので、できれば追い払いたいのである。だがツミも負けずに反撃している。これは…… と思ったら、ツミは折り取った枝をくわえたまま、木立の中へ消えた。これを追って行くと、案の定、樹上に作りかけの巣があった。なお、巣に近づきすぎると繁殖の邪魔になる上、ツミは気が強くてあの鋭い爪で頭を蹴りに来るから要注意である。
松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)
ゲンゲ(マメ科)
森鷗外の自伝的小説『ヰタ・セクスアリス』では、主人公の哲学講師・金井湛が六つの時からの回想が始まるその冒頭に、中国地方の城下町の屋敷隣の空き地で、主人公がげんげを摘む場面が出てくる。「僕はげんげを摘みはじめた。暫く摘んでいるうちに、前の日に近所の子が、男の癖に花なんぞを摘んで可笑しいと云ったことを思い出して、急に身の周囲を見廻して花を棄てた。幸に誰も見ていなかった。」この直後、空き地を隔てた後家宅で、主人公は初めて春画のようなものを目にする。しかし、幼い少年にはわからないから発情することもない。「性」は生まれつきというが、それよりも「男の癖に」という、今で言うところの「ジェンダー」の方が早くから自己意識化されていたということを鷗外が描いているのである。本作は、雑誌『スバル』の掲載号が発売禁止処分を受けるという波紋を広げたことでも知られるが、それは鷗外が当時、軍医総監の立場にあったゆえの批判(社会的地位にある男としてけしからんということか)への対応とも言われている。この発禁事件の数ヶ月後、『予が立場』にて、軍医総監と文学人という二つの立場の葛藤の結果、鷗外が「レグナチオン(諦念)」を表明するのも、げんげ摘みのシーンの描写からつながっているのかもしれないと思える。植物画家・山田壽雄が描いた本写生図の裏面には、「明治45.5.19 Toshi レンゲサウ.(自宅培養)」との書付がある。この記載から、本図の制作年月日と、写生対象が山田の自宅で花を咲かせたものであることがわかる。『ヰタ・セクスアリス』の出版は明治42年であり、鷗外は明治25年から駒込千駄木町の観潮楼に居を構えていた。山田は妻・順子と結婚した明治44年から駒込浅嘉町に住んでおり、本図の制作された明治45年は春に山田の長女・桃子が生まれた年なので、この年も浅嘉町にいたと考えられる。ゲンゲというモチーフでたまたま結びつけた二人は、同じ頃、互いの住居が本郷区内でもかなり近いところにあったという事実に気がついた。
寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)
天洋丸
展示企画のため、IMT所蔵標本の一つを調査する必要に迫られた。工学部造船学科旧蔵の船舶模型である。再現されているのは舵、スクリュー軸受周辺の構造だが、それ以上の情報が何もない。舵は後部が丸く突き出し、現代的な形状ではない。軸受は中心線上に1基、後方左右に2基。3軸推進ということになる。模型を残すくらいだから有名な船だろう。最初は戦艦かと思ったが一致するものがない。舵の形から1900年代初期と当たりをつけ、タイタニック号を疑ったが、これも違う。スケールモデルを作れるのだから日本で建造されて設計図が残っていた船か? 調べていくと、1908年竣工の天洋丸級貨客船に酷似するとわかった。同型の天洋丸・地洋丸・春洋丸が建造されたが、春洋丸は舵が喫水線上まで伸びており、少し模型とは違う。残る2隻は軍艦への転用を考え、舵が被弾しないよう喫水線上に出ない構造だ。ということで、この模型はどうやら天洋丸・地洋丸のどちらかである。国産として初めて1万総トンを超え、蒸気タービン機関搭載で計画された画期的な船であった。
松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)
鋭き棘に注意すべし
インターメディアテク2階[FIRST SIGHT]の壁面に、額装された巨大葉がいくつも展示されている。写真はオニバスの乾燥標本で、近づくとその葉には棘らしきものがみえる。標本作製と額装は東京大学総合研究博物館教員らの手になるもので、2019年の特別展示「メガロマニア植物学」開催時にも複数の巨大葉が整然と並び、ウェブ上では作製工程の艱難の一端が紹介された。ところで、植物学者・三好学の著した『印度馬来熱帯植物奇観』(冨山房/1908年)には、熱帯地方の植物を押し葉にする方法を伝える文章が載っている。それによると、ジャワ島のような多湿な所での植物標本作製においては、日本で行われる乾燥方法では植物が腐敗する恐れがあるため、堅い鉄網に植物を挟み、網の間に多くの吸取紙を入れ、全体を火力で急速に乾燥させるのだという。さらに三好は植物の圧搾方法のみならず、熱帯地方の葉について「鋭き棘を有し、大なる針を備ふるものあるを以て、採集に際して屡々手指を傷くることあり、注意すべし」とも書いている。写真のオニバスの葉の棘も、うっかり手指に刺すとかなり痛いらしい。
藏田愛子(東京大学総合研究博物館研究事業協力者)
オオイヌノフグリ(オオバコ科)
春に道端でよく見かける小さな青い花の名前を子供の頃に覚えようとした時、魔法の呪文のような長い名前だなと思いながら丸暗記した。図鑑か何かを頼りにしたのだと思うが、「オオイヌノフグリ」と片仮名で書かれた文字を見ても、どこで切って読めばよいのかわからなかったし、幼い私には名前の意味を考えようという発想がなかった。時が過ぎ大人になって、山岸涼子の短編漫画『天人唐草』を読み、「大きな、犬のふぐり(陰嚢)」というその花の名前の意味を初めて知った。主人公の岡村響子は、子供の頃、その意味を知らずに、友人から聞いた「イヌフグリ」の名前について母親に尋ねる。しかし、母親は「天人唐草」という別の名前があるからそっちの名前の方がいいとはぐらかしてしまう。「変なの。なんでわざわざそう呼ぶの?イヌフグリがおかしいから?」と響子が言うと、横から父親が「女の子がそんな言葉を口に出すもんじゃない」と怒鳴りつける。一事が万事、戦後民主主義の風潮の中にありながら、男尊女卑で世間体を重んじる父親とそれに従順な母親に育てられ、自分のやること全てに自信をもてずに大人になった響子は、最後は狂気というオリの中に解放される。この物語は、悲劇を通り越してホラーにさえ思えるインパクトであった。オオイヌノフグリは外来種で、日本原産のイヌノフグリよりも大きく、これに似ていることから付いた和名である。植物画家・山田壽雄による本写生図の裏面には「オホイヌノフグリ 自然大 大正3.6.1 田端.」との書付がある。全体図を描いた右には、花が二輪と、貼付の別紙に果実期が描かれている。山岸作品にはイヌノフグリの花しか登場しないが、その名の由来になったのは果実である。本図では若く緑色をしているので「犬のふぐり」にはすぐに結びつかないような気がするが、形からそう呼ばれたのはわからなくもない。私にとっては幸い、名の由来はこの植物をもっとよく知りたいという動機付けとなったが、天人唐草とのみその名を呼び続け、果実を観察する機会を人から与えられることも自ら求めることもなかった響子の人生を、本図に貼られた小さな紙片からそっと思いやった。
寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)
ウグイスの初音
3月になり、ウグイスの初音を聞いたという声が聞こえるようになった(というか、初音といえばウグイスの声である)。ウグイスは古くから日本人に親しまれている鳥で、もちろん、その鳴き声が「ホーホケキョ」であることも、よく知られているだろう。だが、「ホーホケキョ」という聞きなしは「法・法華経」の意味であり、仏教、特に法華経が日本に普及してからのものである。平安時代には仏教はまだ貴族のものであり、庶民にまで広まるのは早くとも鎌倉時代以降だろう。それまでウグイスはなんと鳴いていたか? 実は平安時代の和歌に「自分で名乗るとは律儀な鳥だ」という意味のものがあるらしい。当時、ウグイスの声は「ううくひす」、つまり「ウーグイス」であったようなのだ。そのつもりで聞けば、「ウー……グイス!」と聞こえなくもない。もう一つ、うぐいす餅の印象からか、ウグイスはもっと緑色だと思われていることが多い。実際はこの標本のように、緑がかった褐色である。
松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)
東京大学の画工――西野猪久馬
西野猪久馬(1870−1933)は、明治30年代に東大植物学教室の画工をつとめた経験をもち、その後、動植物の描画を専門とする標本画家として活動した人物である。一般向けの雑誌『少年世界』や植物学書に載せる挿絵の原画を手がけ、1922年からは栄養研究所で救荒植物の写生に従事した。牧野富太郎・入江彌太郎著『雑草の研究と其利用』(白水社/1919年刊行)には、「I. NISHINO del」と記された30点の図版(描かれた植物は119点)が載っている。トベラの描かれた本図(19.1×14.8cm/個人蔵)は、西野猪久馬の家に残されてきた、約200枚からなる植物スケッチの中の一枚である。画面には「葉ニ頗ル光沢アリ」や「葉ノ中央ノ脈ハ白草色」などの走り書きがある。西野家蔵の植物スケッチには、他に花や葉の一部分が着色された図や、鉛筆で描画上の注意が描き込まれた図がいくつも含まれる。おそらく作画依頼を受けた西野は、こうした手元の下図を頼りにもして、数多くの植物を描き分けていたのだろう。
藏田愛子(東京大学総合研究博物館特任研究員)
からだのかたち
肉眼で、ある1つのモノを観察した時、モノに重なりあうものや、モノと背景との間に境界が生まれる。つまり、そのモノ自体の輪郭に実線は存在しないはずである。しかし、我々ヒトがあるモノを描こうとする時、肉眼では存在しないモノの輪郭を描くという行為が洞窟壁画の時代から見られる。これは、手の指でなぞり描くことからはじまるように、身体(からだ)の形状(かたち)につながる。3月6日からスタートした、特別展示『からだのかたち――東大医学解剖学掛図』では、東京大学大学院医学系研究科・医学部二号館の一室に保管されてきた解剖学の講義で使われた掛図を公開している。掛図は、手描きで描かれており解剖学に関わるものだけでも総数にして700点を超える。その中から厳選した掛図を入替えをしながら約20点ずつ紹介する。風で揺れ動く木々やとどめなく折り返す波を眺めその空間に包まれるように、森で虫や動物と出逢い言葉ではない交信をするかのように、「からだのかたち」の絵図を眺めながら別世界へ旅に出る、そういうひと時を過ごしてもらいたい。
上野恵理子(東京大学総合研究博物館特任研究員)
新入りの都市鳥
イソヒヨドリ、漢字で書けば磯鵯。名前の通り海岸の磯や防波堤まわりによくいる。オスは背中が青、腹が赤錆色と目立つ配色で、電柱の上など高いところに止まって囀る。非常に目立つ鳥だ。ただし、青い海と岩場を背景にすると、この色合いも不思議と馴染んでしまう。この海辺の鳥が、ここ20年ほどの間に、どんどん内陸の鳥になりつつある。彼らが目指しているのはビルだ。崖の割れ目などに営巣するイソヒヨドリにとって、大きな建造物は岩山の代用品なのである。営巣に適した隙間も、看板の裏などにいくらでもある。筆者の実家は海から40キロ以上離れているが、ここでも数年前からイソヒヨドリが囀っている。東京駅前でこそまだ見たことがないが、明治安田生命ビル付近でミミズをくわえて飛ぶメスを見たことならある。イソヒヨドリの英名はBlue Rock-Thrushつまり「青い岩ツグミ」で、海岸というより、岩場や崖地の鳥と考えるべきなのだろうが、今後、大都市にどう適応してゆくのか興味深い。
松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)
ネジバナ(ラン科)
「捩花のまことねぢれてゐたるかな」は、水原秋桜子や石田波郷に師事した俳人・草間時彦の句である。私も、図鑑ではなく、初めてネジバナが実際に咲いているのを見たときに同じことを思った。その感動を簡明に伝えてくれているようで、この句に出会った時には何だか心躍るようなうれしさを感じた。本図の裏面には「モヂズリ 大正3.7.10 高萩にて」との書付があり、植物画家・山田壽雄が茨城県の高萩に行った際に描いたものであることがわかる。筆運びの勢いから、その場で短時間のうちに描き留めたのかもしれないと想像できる。「モヂズリ」とはネジバナの別名であるが、百人一首のなかに、河原左大臣(源融)の「陸奥の しのぶもぢずり 誰ゆえに 乱れそめしに 我ならなくに」という忍ぶ恋をうたった有名な和歌がある。ここに出てくる「もぢずり」とは、福島県の旧郡・信夫(しのぶ)群で作られていたもぢ摺り染めのことで、この技法で絹織物を染めると様々な草花の色を写した乱れ模様となる。本図を下図として用いたと考えられている『牧野 日本植物図鑑』(第2075図)で牧野富太郎が書いているように、ネジバナの捩れた(乱れた)花の付き方がもぢ摺り染めの模様を思わせることから、モヂズリの名の由来となっているという。源融といえば、紫式部の『源氏物語』の主人公「光源氏」の実在モデルとも言われる人物である。ほぼ日本全土の野原や田畔など(都市の芝生や土手にも)に咲く、ごくありきたりな野草であるネジバナからこれほど文学にまつわる話題が引き出されるとは、と意外に思いながら、改めて山田の描いた花の「かたち」を見れば、そこに無限に上昇する運動性を象徴する螺旋構造を見出した。
寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)
画工の居場所
東京大学に雇われた画工は、いったい学内のどこで絵を描いていたのだろう。以前から画工の制作現場が気になっていた。同大理学部生物学科に学んだ海藻学者・岡村金太郎は、自身の学生時代を追想した文章を残している(「青長屋―本邦生物学側面史」『科学知識』1922年6月号)。これはそこに載る挿図の一つで、1885年頃の通称「青長屋」と呼ばれた理学部生物学科の見取図である。岡村は当時の植物学教室を「助教授其他書記画工助手などの共同して居る大広間があつて、其処で事務も取れば研究もし、応接もし、雑談もすると云ふ訳であつた」としている。寒くなると大広間にストーブがあったので、学生も教授も皆がそのまわりに集まり、打ち解けた団欒のあたたかみがあったともいう。この見取り図をよく見ると、「松村」(当時の助教授・松村任三)の横に「画家」の机が置かれている。教職員や学生が採集してきたばかりの植物が画工に手渡され、それをすぐさま画工が写生することや、描画対象となる植物についてひとしきり話し込む場面もあったのではないか、とつい想像したくなる。
藏田愛子(東京大学総合研究博物館特任研究員)
シロウマアサツキ(ヒガンバナ科)
独文学者・高橋義孝のエッセイ「春の弥生は」に、酒飲みで町歩きの好きな友人と新橋の一杯飲屋の暖簾をくぐり、「あさつきのぬた」を注文する話が出てくる。高橋と友人は、続いて木の芽和えを注文するが、どちらの肴も香りを嗅ぐ程度に一口、二口しか食べない。「あさつき[原文傍点]のぬた[々]と木の芽和えを前に置いてコップ酒を呷っているわれわれふたりがつまり春そのものなのである」。華はないが、味のある春の描写である。「山田壽雄植物写生図」(3階に展示中)のシロウマアサツキはすっすっと筒状の葉が伸びた姿が写されている。展示はしていないが、別の一点に花をつけた図があり、こちらは書込から大正4年8月12日に白馬山で採取されたものを山田が描いたことがわかる。一方、本図は裏面に「シロウマアサツキ」の書込があるのみで、制作年月日等はわからない。花が描かれていない故に、高橋のエッセイを思い起こしながら本図の二本のアサツキを眺めると、春の夕暮れに薄く霞か靄が立ち込めた東京の何とも乙な風情が立ち現れる気がしてくる。ちなみに、厳密に言えば、シロウマアサツキはアサツキと同じくネギ属であるが、高山に生える多年草で、地方版レッドデータブックに掲載されている場合があるので、ぬたにして食すのは想像に留めておきたいと思う。
寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)
東京大学の画工――渡部鍬太郎
渡部鍬太郎(1860−1905)は、1881年から1893年にかけて、小石川植物園(現・東京大学大学院理学系研究科附属植物園)で植物写生に従事した画工であった。号を金秋といい、東大画工のかたわら明治美術会や挿絵の分野でも活動した。シャリンバイの描かれた本図(1888年制作/東京大学総合研究博物館蔵)は、渡部鍬太郎の手になるものだ。葉の光沢や実の立体感が水性絵具でよく表されているように思う。植物学者・伊藤篤太郎は1881年頃の小石川植物園を振り返って「渡部鍬太郎といふ若い画工が居た。渡部画工は矢田部教授の羊歯類などの画を写生して居た。併し矢田部氏自身は植物園へは来られなかつた様である」と記している(「伊藤圭介翁と小石川植物園」『東京帝国大学理学部植物学教室沿革』小倉謙編/1940年)。画工になって間もない渡部は、依頼主である教授・矢田部良吉が不在の中、どうやって植物画を制作していたのだろう。折しも1881年頃の植物園では、東京大学の員外教授に招かれた伊藤圭介が『小石川植物園草木図説』編纂に向けて、熟練の画工・加藤竹斎に数多くの植物画を作らせていた。植物園の日常に植物写生があった光景が思い浮かぶ。
藏田愛子(東京大学総合研究博物館特任研究員)
展示のオートエスノグラフィー
展覧会は一過性のイベントである。会期が終わると、どんなに話題になり、多くの人が足を運んだ展覧会でも、意外にその全容はわからなくなってしまう。展示図録には、企画趣旨や展示物の画像と解説は収められるが、展示構成は反映されていない場合もある。準備段階でどのようなことがあったか、観覧者がどのように受けとめたか、また関連して開催されたイベントの情報については、大抵は図録の守備範囲外にある。東京大学総合研究博物館では、『真贋のはざま−デュシャンから遺伝子まで』(2001)、『MICROCOSMOGRAPHIA−マーク・ダイオンの『驚異の部屋』』(2003)、『プロパガンダ1904-45−新聞紙・新聞誌・新聞史』(2004)の各特別展示で展示評価報告書を作成している。しかし、展示図録ではないという分類のためか、自館の刊行物データベースに挙げられていない。インターメディアテク研究部門発足後に筆者が編集を担当した『ファンタスマ−ケイト・ロードの標本室』(2011)博物館工学ゼミ活動記録報告書、『Mobile Museum Boxes – The Diversity of Natural History of Mindanao』(2015-16)(フィリピンでのモバイルミュージアム)のプロジェクト報告書も同様の扱いである。「オートエスノグラフィー」とは、語る主体としての自己を顕在化させ、自らの個人的な経験を記述し批判する研究手法である。ミュージアム研究の分野に「展示のオートエスノグラフィー」というコンセプトを浸透させ、展示に関するさまざまな当事者の事後的記録の作成を促すとともに、どこかにアーカイヴできないかと最近考えている。展示図録についてはISBNが付いていなくても国立新美術館のアートライブラリー等、既存のアーカイヴ体制が機能しているが、そこから漏れてしまう形式や小さな証言を「展示のオートエスノグラフィー」では取り込みたい。このコンセプトに当てはまる記録には、上記のような報告書だけでなく、展示空間の写真集、展示に関わった人たちの振り返り記事(ニュースレター記事から学会誌の研究ノートまで)など、既に多様な形が存在する。物理的なアーカイヴではなく、タグをつけて、所在情報をウェブ上にまとめていくという考え方でも良いかもしれない。いいアイディアだと思っているのだが、どうだろうか。
寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)
植物画
数年前に東京大学総合研究博物館のバックヤードで約千枚の植物画がまとめて発見されている。各図には植物の全体図や花の拡大図、花式図などが描き込まれ、洋紙に水性絵具で丁寧な着色が施されている。中心となる制作時期は明治時代半ばと推定され、一部の図にはK.Watanabe(洋画家・渡部鍬太郎)や高屋肖哲(日本画家)の名前を確認することができる。明治時代の東京大学で作られた植物画としては、小石川植物園(東京大学大学院理学系研究科附属植物園)に残る植物画群がよく知られる。博物館で眠っていた植物画はおそらくその仲間で、東大植物学教室や小石川植物園を舞台とした植物研究の中で生み出されたと考えられる。これら明治時代の植物画は、日本植物学の痕跡を現在に伝える貴重な学術標本といえるだろう。そして、当時の画工や植物学者による植物表現の模索をうかがい知ることのできる格好の美術資料としても、大きな魅力をもっているはずである。
藏田愛子(東京大学総合研究博物館特任研究員)
映像の意志
大学ではオンラインの授業が続いた。前期の「空間デザイン実習」に続き、後期は「映像デザイン実習」を開講した。映像制作を通して表現の可能性を探究する教養前期の授業である。最初のレポートは「INSPIRED BY」と題し、既に公開されている動画にインスパイアされた自身の映像作品の企画書を作成した。スピンオフ、コラボ、リメイク、トレイラー、続編など制作スタンスは自由であり、オリジナル作品のラインナップ<YouTube動画やMVから『日本のいちばん長い日』まで>の多様性も興味深い。続いて、15人の学生は2つの課題映像の制作に取り組んだ。課題1は個人による制作であり、テーマは例年どおり「TOKYO STORY」とした。主題の捉え方はさまざまで、見えている実体、意識の対象、操作の題材としての「東京」が扱われる。コロナ禍の都市に応答しつつ、その様相だけに回収されない表現力をもった「Le Masque Jetable(使い捨てマスク)」ほかの作品があった。課題2はグループによる制作であり、今年のテーマは「PROXIMITY(近接性)」とした。メンバー同士のリアルな会合が難しいなかで、ネットワークを活用して作業を分担し、クラウド上での遠隔同時編集を行うグループもあった。提出された作品は力作揃いであった。「色鉛筆」(上図)は夢と現実の近接性、「PISTON TOUCH GAME」(下図)はリアルとバーチャルの相関性、「ヒトコロリ」は時間差を経たつながり、「シマウマとパラシュート」は物理距離と精神距離の懸隔がコンセプトに据えられている。いずれの作品も物語の構成および動態の創出に工夫をこらしている。このような状況下でも、表現の意志があれば道は開かれると感じた。
松本文夫(東京大学総合研究博物館特任教授)
ミュージアムとジェンダー(2)
サウンドレイヤー・アプリ「onIMT」で聞くことのできる音声解説レイヤー「医学生と観る『医家の風貌』展―パート2 脚気研究の歴史」は、2018年に東京大学の現役医学生が特別展示『医家の風貌』の展示空間で実施したギャラリートークを公開したものである。脚気は明治・大正期に多くの死者を出していた病気である。本レイヤーでは、展示空間に並ぶ東大医学部歴代教授の肖像画と肖像彫刻を眺めながら、この中のいかに多くの先人が脚気研究に関わってきたかを諸学説とともに知ることができる。皆がいわゆる脚気の専門医だったわけではない。他の研究テーマをもちながらも多くの医家が当時脚気研究に従事した理由は「人が亡くなることを防ぐ」という医学の根本的な責務にあると医学生が話していた。コロナ禍を経験する今改めてこの言葉を聞くと、よりいっそう心に響いた。医学の責務に言及した医学生の言葉を、性別を超えたわれわれ「人間」の生き方の問題として私が捉えることができたのは、トークの最後に、島薗順次郎(1877-1937)の肖像写真の前で取り上げられた香川綾(1899-1997)の存在が大きい。香川は、脚気研究を行っていた島薗研究室にて同研究に貢献した女性である。会場に展示された、すなわち今日まで東大に残された医家の肖像画や肖像彫刻はすべて男性であり、過去の男性中心社会の遺産の中に、香川の姿をモノとして確認することはできない。しかし、医学生のトークは、エピソードとして東京帝国大学時代に医学研究に従事した女性の存在を浮かび上がらせ、レイヤー状に男性の肖像画や肖像彫刻と共存させた。もちろん、香川一人のエピソードでジェンダーバイアスに関わるミュージアムの問題がすべて解決したなどとは思っていないが、この問題に機会あるごとに向き合い、小さくとも歩を進めていくことの重要性を実感させてくれるには充分過ぎる大きな貢献であったと思う。本レイヤーは、特別展示『医家の風貌』の会期末で公開終了となる(2021年2月21日まで)。終了前にぜひさらに多くの人の耳に届いてほしい。
寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)
コロナ禍中の、謹賀新年
今年、インターメディアテクは開館以来八度目の春を迎える。昨年は春先から「新型コロナウイルス」の感染拡大という、思いもかけぬ事態に見舞われた。そのため社会生活を動かす歯車という歯車に狂いが生じ、世界中が大混乱に陥った。否、いまだ陥ったままにある。「ニューノーマル」などの造語を弄して平静さを繕おうと努めてはみるが、眼に見えぬウイルスの伝播力はいかんともし難い。というわけで、いまだ収束のきざしさえ見えてはこない。「テレワーク」の定着は、日常における新たな労働形態の拡大普及という意味で歓迎すべきものかとも思う。とはいえ、ミュージアムにとっては深刻極まりない事態である。標本、史料、文書など、「モノ」を扱わねばならぬため、リアルな現場仕事を回避できぬ職場だからである。普段から集客のために知恵を出し合ってきた職員たちもまた、「三密」を避ける業態の実現を目指すなかで、その存在の自己否定を強いられている。集客事業の代案として、多くのミュージアムはウェッブ上でのコンテンツ開陳に走り始めた。しかし、それで良いのか、とわたしなどは思う。人類が生存の危機に瀕したとき、ミュージアムにはなにができるのか。そのことと真剣に向き合わぬままにいると、無用論も興りかねない。それが危惧されるだけに、事態は深刻である。年の変わり目であるとないとに関わらず、ミュージアムはいま「冬の時代」、というより「極寒の時代」の真中に立たされている。そんななかにあって、どこからか一条の光が射し込んで来ないものか、そう願いつつ、謹んで新年のあいさつを贈るこことしたい。
西野嘉章(インターメディアテク館長・東京大学総合研究博物館特任教授)
ヒツジグサ(スイレン科)
展示更新した「山田壽雄植物写生図」のなかで、ヒツジグサは大きな葉の緑の色面とその上に配された白い花が一際目を引く一点である。裏面には「ヒツジグサ(自然大)メイヂ43.9.9」との書付がある。『牧野日本植物図鑑』のヒツジグサ(1734図)は、本図を下図として利用したものと推定されている。牧野富太郎は同図鑑の解説に、ヒツジグサの名の由来は羊の刻(現在の午後2時)に咲くことからきているが、開花時間は一定ではなく、これより早い時もあると書いている。梨木香歩の小説『家守奇譚』は、各章題に植物の名を冠し、主人公の文筆家・綿貫征四郎が亡くなった友人・高堂の実家に家守りとして住まうなかで遭遇した不思議な出来事を綴った作品である。ヒツジグサの章は、庭の池で律儀に羊の刻に花を咲かせるヒツジグサが風鈴の音に反応して「けけけっ」と鳴くという音の描写が鮮烈で、とりわけ印象に残っていた。主人公がよくよく水面を見ると、ヒツジグサが群生していると思っていたところに河童のお皿が一枚浮いていた、つまり鳴いていたのは池に迷い込んだ河童であったという展開に、そうかヒツジグサが鳴くなんてと思ったがあの鳴き声が河童のものならさもありなんと、妙に現実味のある納得感を抱かされる。山田の描いた図を今一度よく見ると、長い花梗が葉を囲み、その間が薄水色に彩色されており、葉が水に浮かんでいる様子を表現していることがわかる。葉と花梗の隙間の水面に河童のお皿なるものが写し取られていないか、洒落心半分、「けけけっ」という鳴き声に耳を澄ませながら、さらによくよく覗き込んでみたくなった。
寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)
山中の聖域
サン・マルタン・デュ・カニグー修道院は、フランスのピレネー山中に11世紀初頭に建てられたベネディクト会の修道院である。長らく廃墟と化していたが20世紀に修復された。ロマネスク建築史の書籍でその存在を知り、独自のたたずまいに強く惹きつけられた。数年後、幸運にも現地を訪問する機会を得た。公共アクセスがなかったので、鉄道駅を降りてヒッチハイクし、山麓の集落からはつづら折りの山道を歩いた。登りきると、断崖の淵に寄りそう修道院の全景を見渡せる場所がある。都市の大聖堂に比べれば規模はずっと小さい。教会堂とクロイスター(回廊)が隣接した基本形を保ちつつ、峻険な地形に合わせて建物の平面の角度が振れ、地盤の高さが変化している。高所に置かれた教会堂は翼廊のない2層構造で、クリプトの上部にトンネルヴォールトの身廊と側廊が載る。個性的な柱頭を冠した回廊は、天空の別世界をつくっている。古代技術の流れを汲む石積みは、粗々しくも緻密である。まずはこの地に祈りと共住の場を創ろうとした中世の人々の営為に心を打たれる。さらに初期ロマネスク建築の素朴な意匠に魅了される。分厚い壁面、彫塑的な空間、小さく豊かな光といった感覚的な記憶がよみがえる。しかし、後に続くゴシック建築のような、壁面の減少、構造の自立、垂直の追究といった一貫する特質には還元しにくい。建築が論理的に構成される前段の、身体感覚に直結した空間の力動性がそこにある。カニグー修道院のピクチャレスクな様相は、必ずしも理想型の「変形」ではなく、人間と環境の共生と格闘から生み出されたものである。
松本文夫(東京大学総合研究博物館特任教授)
スイセン(ヒガンバナ科)
特別公開『東大植物学と植物画−牧野富太郎と山田壽雄vol.2』では、東京大学総合研究博物館所蔵の新出資料、植物画家・山田壽雄による植物写生図より、着色画59点を展示更新し、12月8日から初公開している。このスイセンもそのうちの一点で、裏面には「ス井セン 大正2.12.7 Toshi」という書込が確認できる。樋口一葉の代表作『たけくらべ』には、造花の水仙が登場する印象的なラストシーンがある。髪を嶋田に結ってから、今までの遊び友達と一緒に過ごすことのなくなった美登利は、ある霜の朝、水仙の作り花が格子門の外から差し入れ置かれているのを見つける。「美登利は何ゆゑとなく懷かしき思ひにて違ひ棚の一輪ざしに入れて淋しく清き姿をめでける」。誰の仕業かはわからないが、その日は信如が宗学修行のため学林へ出立した当日であったことが読者に明かされて物語は終わる。大黒屋の美登利と龍華寺の信如。遊女の妹と寺の息子という取り合わせは、一見対照的で相容れない。しかし、二人とも「大人になる=自分で選ぶことのできない運命に従う(遊女・僧侶になる)」という定めの下にあった。造花は永遠に枯れることがない。大人になるという時間の流れを止めることのできない哀切がこれに込められているとしたら、われわれの前に時を越えた姿を見せている、山田が描き留めたスイセンの画もまた、淋しく清らかな佇まいで、子供時代を懐かしく思い起こさせてくれるような気がする。
寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)
クロサギ
この標本は山階鳥類研究所より寄託されたうちの一つ、クロサギである。シラサギという言葉があるが、これは白いサギの総称であり、特定の種を指す言葉ではない。一方でクロサギはEgretta sacraという種の標準和名である。海岸によく見られ、どちらかといえば南方に多い。ところがややこしいことに、クロサギには白色型が存在する。クロサギなのに白いなど詐欺同然である。沖縄で黒いクロサギと白いクロサギが並んでいるのを見たことさえある。サギといえば白い−−その認識から「サギなのに黒い」という意味でクロサギとしたのだろうが、なんともやっかいな鳥だ。ちなみに熱帯では白色型が、温帯では黒色型が多いという研究もあり、サンゴ礁の白い砂浜をバックにするか、黒っぽい岩場をバックにするかによって有利な体色が違うのではないかと考察されている。もっとも、先述したように同じ場所に2タイプが共存していることもあるので、絶対的な差ではないのだろう。
松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)
インターメディアテク・レコード・コレクション(21)
ブラック・レーベル
娯楽として発展したジャズにおいて、社会問題などを問う「プロテスト・ソング」は長らく封じ込められていた。しかし1950年代に入ると、黒人中心の公民権運動に呼応する形で政治的な内容を持つ作品が次々と発表される。大手レコード会社による抑圧を避けるべく、インディペンデント・レーベルの歴史を継いで、完全に独立したレーベル運営に挑戦するミュージシャンもいた。ベーシストのチャールズ・ミンガス(1922-1979年)が妻のセリア、ドラマーのマックス・ローチとともに創立したレコード会社「デビュー」は僅か5年で廃業に追い込まれたものの、その短い期間に錚々たるジャズメンの実験的な録音を収めた。LP盤に切り替わる直前に発売された12枚のSP盤には、ミンガスおよびローチを中心に、リー・コニッツ、ジジ・グライス、ハンク・モブレー、ハンク・ジョーンズらが登場する。しかし「デビュー」から出た名盤といえば、LP時代に発売された「ジャズ・アット・マッセイ・ホール」(1953年)に勝るものはない。ミンガスおよびローチに加わり、ガレスピー、パーカー、パウェルが伝説のビバップ・クインテットを形成した。
大澤啓(東京大学総合研究博物館特任研究員)
コケモモ(ツツジ科)
植物画家・山田壽雄によるコケモモの写生図には、画面中央には実をつけた全体図が、上下に貼付された2枚のパラフィン紙には花が描かれている。画面下の1枚には、花の各部から引いた線の先に、「ウスミドリ」、「カーマイン」、「乳白ノ上ニ極ウスアカ」、「極ウスミドリ」との文字があり、これらは印刷用の色の指定と考えられる。裏面には「コケモモ 1/1 大正4. 9. 1. 信州産 本山氏ヨリ」との書付がある。実物大の写生図であること、制作年月日と採集地、そして、植物学者・牧野富太郎と交流のあった本山佗吉という人物よりコケモモが山田にもたらされたのではないかということがわかる。コケモモが出てくる小説に関する私の朧げな記憶を辿ったところ、ブロンテ姉妹の『ジェーン・エア』と『嵐が丘』に行き当たった。両作品とも、英国ヨークシャー州のムーア(荒地)が舞台となっている。コケモモは、前者では、不幸な生い立ちのジェーンがようやく見つけた幸せ(結婚)が崩れ去り、絶望の中ムーアで迎えた朝に、ヒースの茂みで見つけたコケモモの実で空腹を凌ぐという場面に登場する。後者では、錯乱の末、娘を出産して息絶えたキャサリンが、礼拝堂内の婚家や身内の墓碑の下ではなく、教会墓地の片隅に埋葬され、その墓の周りにムーアのコケモモがヒースとともに塀を越えて入り込んでいる様子が描写されている。しかし、今回これらの小説の記述を調べる過程で、「コケモモ」と翻訳された植物が、原文では「ビルベリー(bilberries)」であることを知った。この置換えには、海外文学の翻訳家の苦労と工夫が透けて見えてくる。しかし、山田の図に描かれているように、コケモモ(Vaccinium vitis-idaea L.)の実は赤色であるが、ビルベリーの実であれば黒色である。ジェーンの心情には赤ではなく黒が似合うように思われるし、キャシーの墓の周りに実るのが赤い実か黒い実かは重大な違いがあるのではないかと、今までは想像しなかった色の問題に驚いたのであった。
寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)
インターメディアテク・レコード・コレクション(20)
楽器に電気を通すこと
ジャズにおいて楽器に初めて電気を通したのは、エレクトリック・ギタリストだと言われている。フロイド・スミス(1917-1982年)、レナード・ウェア(1909-1974年)やエディー・ダーハム(1906-1987年)をはじめ、1930年代後半からスウィング・オーケストラ内にアンプ付きのギターが加わり、いずれその地位が確立されていった。ギターはのちにロックやポップスの中心的な存在を担うことになる。しかしエレクトリック・ギターをソロ楽器として定着させたのはやはり、チャーリー・クリスチャン(1916-1942年)によるメロディーが際立った演奏である。あらゆる才能を自身のバンドに吸収しようとしたクラリネット奏者のベニー・グッドマンは、クリスチャンのギターをライオネル・ハンプトンのヴァイブラフォンと組み合わせ、新たな音を生み出すことに成功した。なかでも、セクステットによる「スターダスト」を聴いていただきたい。
大澤啓(東京大学総合研究博物館特任研究員)
スミレ(スミレ科)
旧制第一高等学校の卒業生と在校生による同人誌『世代』に掲載された、加藤周一の「新しき星菫派に就いて」は、若き日の輝く仕事とはかくあるべしという憧れの対象だった。しかし、どんなに努力したとしても、私にはもう同様のことは為しえない。時間は平等であり、残酷でもある。このエッセイでは、加藤が戦争の世代の文学青年らを舌鋒鋭く批判する際に、「星の運命と菫の愛」を唱い賛美する無力・無学の者たちよと、スミレは星と並んでやり玉に挙げられてしまう。3階に展示中の本写生図を眺めながら、スミレが出てくるこのエッセイを思い出したのではあるが、山田壽雄の植物画家としての堅実な仕事ぶりをそこに見出すと、このスミレは「星菫派」などという軟弱な呼ばれ方など意に介さないかのように、凛として見える。1940年に出版された『牧野日本植物図鑑』318頁に掲載されている第952図の「すみれ」は、山田による本写生図とほぼ同じ構図をとっている。牧野富太郎は同書の序文にて作画に関わった三人の画工の名前を挙げており、山田はそのうちの一人であるので、「すみれ」については山田の本図が下図として用いられたのだろう。裏面には「大正14. 5. 5」とあるため、おそらく本図の制作年代は図鑑の出版よりも15年ほどさかのぼる。山田はこの年43歳、図鑑の出版年には58歳であった。同年、牧野はと言えば78歳である。まだまだこれから。いい仕事を目指して努力を惜しんではならない。このスミレはそう私に言っているのかもしれないと考えると、口元がほころびつつも背筋が伸びる思いがした。
寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)
新しい近接性
新型コロナウイルス感染症が流行する状況下では、人的密度を低減し、不要な移動を抑制し、業務や学習を遠隔化し、シールドや隔壁で区分するといった生活様式が提唱されている。今後の社会の本質的な課題は、人間を離し、隔てることではなく、社会環境のなかで人間どうしの「近接性」をいかに再構築するかにあると考えている。近接性の概念は、動物行動学の「なわばり行動」に由来する。なわばりで個体密度を調整することによって種の繁栄が保証される。その観察を参照しつつ、文化人類学者のエドワード・ホールは『かくれた次元』において、人間による空間認識に関わる「プロクセミクス(proxemics、近接空間学)」を提唱した。ホールは人間どうしの関係を、密接距離、個体距離、社会距離、公衆距離という4つの距離帯によって説明した。これらの空間知覚によって人間が独自の「文化の次元」を創りだしたという。プロクセミクスの骨子は「距離の近さ」に応じた人間行動の理解である。現代のコロナ禍における生活様式では、人間が密集せずに社会距離を保つことが要請されている。人間どうしを遠ざけることは、過密な都市環境では容易ではなく、一方でICTを駆使した遠隔や非同期の交流も盛んである。近接性は「距離の近さ」だけで決まるものではなく「つながりの強さ」の選択によって変わる操作可能な概念ではないか。写真は小石川分館で開催中の特別展示『ボトルビルダーズ—古代アンデス、壺中のラビリンス』(企画:鶴見英成助教)における会場配置である。2Mの社会距離を確保しつつ、回遊性というつながりを両立させている。
松本文夫(東京大学総合研究博物館特任教授)
インターメディアテク・レコード・コレクション(19)
舞台装置としての録音再生
1944年4月18日、「バレエ・シアター」による『ファンシー・フリー』がジェローム・ロビンス(1918-1998年)の振り付けでメトロポリタン・オペラ・ハウスにて初演を迎えた。音楽を担当した作曲家のレナード・バーンスタイン(1918-1990年)は当時25歳の若さで、バレエ曲の経験がなく、その音楽は複雑なリズムと驚異的なテンポでダンサーを苦しませた。それが功を奏して、『ファンシー・フリー』は一世を風靡し、アメリカ独自のバレエを確立するうえで歴史的な作品となった。筋書きは極めて単純だった。戦時中に海軍の船乗りが三人でニューヨークに出て夜遊びする。ところが開幕の場面には時代を表す特殊な装置が設けられていた。船乗りたちがバーに入ると、カウンターの奥に置かれたラジオから、ブルースが聞こえてくるのだ。バーンスタインはこの曲を憧れのビリー・ホリデイに歌ってもらいたかったが、当時無名であったため、願いが叶わなかった。名声を得て、ホリデイと同じくデッカ・レコードの所属となったバーンスタインは1946年にホリデイに「ビッグ・スタフ」を吹き込んでもらった。
大澤啓(東京大学総合研究博物館特任研究員)
ザクロ(ミソハギ科)
江戸川乱歩の『石榴』は、ある空き家で発見された死体の顔がはぜ割れた石榴に形容された「硫酸殺人事件」の話である。結末に再び、真っ赤にはぜ割れた石榴の実(もちろん死体)の描写が登場する。初めて読んだ時、死体の頭部の残酷な図像がどんどん脳内で生成されていき、読後にそれを繰り返し思い出してはますます怖くなった。子どもの頃のその体験以来、ザクロは何だか生理的に怖い。しかし、それは果実についてのイメージであって、つい昨年まで、ザクロの花を認識していなかったことに気が付いた。6月初めに近所を散歩していた時に、木に咲いている小さな紅色の花がふと気になり、写真に撮って家に帰った。調べてみたら、そのコロンとしたかわいらしい花がザクロだった。3階に展示中の、山田壽雄によるザクロの花も、早描きのような筆致のせいもあって、乱歩の小説から果実に対して抱いていたおどろおどろしいイメージとは全く異なり、私の目には生き生きとした愛らしい姿に映る。裏面には「大正3. 7. 6. 高萩にて」の書付がある。表面右上には「実花ヲ入ル」とあり、左上には「七. 七. 七.」の日付とともに実花、すなわち果実をつける両性花の断面図を鉛筆で描いた紙が貼り込まれている。
寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)
立体感
「烏」という文字は「鳥」の横棒が一本足りない。これは象形文字の段階で横棒が鳥の目を表しており、カラスは真っ黒で目がどこにあるかわからないからだ、と言われている。確かに烏は黒ベタで立体感がわかりづらい。だから、カラスの顔は平板なものと思われていないだろうか? 写真はハシブトガラスの顔だが、羽毛を寝かせた状態では極めて立体的で、骨格の形がきっちりと見えているのがわかる。眼窩の上後方は出っ張っており、ここに羽毛がかぶさることでさらに「眉」のように強調される。一方、目の前方、特に斜め下に向かっては出っ張りがなく、羽毛の流れのせいもあって溝のようにえぐれている。カラスは餌のある方向、つまり前下方がよく見えるのだ。これが獲物を捕食する猛禽類だと目全体がもっと前を向き、立体視できる範囲を広げている。このように、鳥の顔はその生活史を反映しているが、それ以前に造形物として「絵になる」ことも、しばしばある。
松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)
インターメディアテク・レコード・コレクション(18)
インディーズの先駆け
ニューヨークのレコード店「コモドア」が1938年にレコード製作事業を開始して以来、ジャズ界に多数の小規模なレコード会社が現れた。1940年に起業した「キーノート」は奇妙なレコード会社だった。もともとはソビエトの音源の再発盤を専門的に扱っていたものの、1943年から裕福なアジア系プロデューサーであったハリー・リム(1919-1990年)が加わり、スウィングからモダンジャズに亘る多数の名演を録音し、発売した。リムは私費を投じてまで録音技術と盤質に拘りつつ、傑出した音楽性を持ちながらもリーダーとして録音される機会のなかったミュージシャンを中心にセッションを組んだ。他のインディペンデント・レーベルと同様、オーケストラなど大編成のバンドを雇えなかったため、キーノートは少人数による「スウィングテット」という編成を主に録音した。しかし、大手レコード会社に対抗するには、プロデューサーの情熱だけでは足りなかった。倒産したキーノートは1948年、マーキュリーに買収された。
大澤啓(東京大学総合研究博物館特任研究員)
サギソウ(ラン科)
大和和紀の少女漫画『はいからさんが通る』の魅力は、主人公の花村紅緒だけでなく、彼女を取り巻くさまざまな男性陣のキャラクターにある。山田壽雄の描いたサギソウの花を見て、久しぶりに思い出したのが、番外編「鷺草物語」でその少年時代が描かれていた鬼島森吾である。左頬に傷をもつ、少しミステリアスな隻眼の男性像に、少女時代の私も例外なく心ときめかせたものだった。鬼島少年が儚い恋心を寄せた女性・ゆきのは、恋人を待つために毎日のように通っていた峠に咲くサギソウを見て、死してなお離れることのない「つがいの鷺」の話を少年に語る。しかし、待っていた恋人はついに現れず、ゆきのは命を落とし、彼女を助けようとした時に鬼島少年が片目を失った過去がわかるという切ないエピソードであった。3階に展示中の、山田によるサギソウの写生図は、裏面に「明治43. 8. 30」という制作年代の記載があり、画面には三個体が描かれている。右はミズトンボ(下に「ミヅトンボ」の書付あり)、その他二つがサギソウ(下と左に「サギサウ」の書付あり)で、左が正面から見た花を、中央が側面から見た花を示している。左の正面から見た花は部分的に背景色まで塗られており、観賞用でもおかしくないほど完成度の高い写生図のように見えるが、鬼島少年に対する感傷的な気分を投影して眺めると、背景色の水彩絵具の滲みは、何となく涙の痕のイメージにも重なり、情感たっぷりに思えてくる。
寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)
外出自粛中のカラス
春から夏は鳥類の野外調査のハイシーズンだ。だが、外出自粛に伴い、今年の調査は全てキャンセルになった。その代わりと言ってはなんだが、人間の活動の変化がカラスに影響を及ぼしているかどうかを都内で調査している。その一環として自宅の近所で定期的にセンサスを行なっているが、意外にゴミは荒らされていない。だが、一箇所、毎回ひどく散らかされている場所がある。おそらくカラスの「いつもの餌場」になっているのだろう。面白いのはカラスがゴミ袋を破って中身を引きずり出した後、ハトやスズメ、ムクドリまでもが細かい残滓を食べに来ていることである。餌を食べているライオンの後ろにハイエナが、その後ろにリカオン、ハゲワシなどが控えているのと同じく、ゴミ漁りにも順序があるのだ。先日はゴミ袋の中から缶チューハイの空き缶を引っぱり出したカラスがいた。撮影した写真を見ると、まるでカラスが酒を飲んでいるようにも見えて面白かった。
松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)
休館日の小旅行
ある日、ふと、誰もいないIMTの展示室を歩きたいと思い立ちオフィスを出た。その時のことを書いてみようと思う。最初に足を踏み入れたのはCOLONNADE2(ギャラリー2)、下の階の1番大きな展示空間であった。電気が消えており、普段と違う雰囲気を新鮮に感じた。来館者のいない状態で展示を観たことは何度もあるが、電気が点いていない中で歩き回ることはあまりなかったのである。COLONNADE2には大きな窓が並んでおり自然光が差し込んでいたため、暗くはなかった。骨格標本の間をゆっくりと歩く。標本たちは悠然と佇んでおり、まるで、ここは自分たちの縄張りだぞと言っているように見えた。大地球儀の方へと足を進めると、あたりが段々と暗くなってきた。ギメ・ルームが近づいてきたのである。ギメ・ルームは、IMTの中でも「驚異の部屋」の要素がひときわ色濃く出ている空間と言えるであろう。しかし、明かりのない状況下では、それが怖さに拍車をかけていた。鮮やかな緑の壁は闇に埋もれ、見慣れているはずの展示物は暗がりに沈み込んで輪郭がつかめず不気味であった。とそこに、ぼうっと白く浮かび上がるなにかが目に飛び込んできた。美しく優美に螺旋を描き、輝いているのかと錯覚するほどの存在感を放つそれは、クーズー角。私の今までの人生の中で、1番、クーズー角に魅せられた瞬間であった。クーズー角に励まされながらそそくさとギメ・ルームを回り、自然の光に満ちたCOLONNADE2へと戻る。さて次はどこへ行こうかと思った瞬間に電気が点いた。わずか十数分の小旅行は終了し、見慣れた風景が戻ってきた。それはまるで時計の針が再び動き出したかのような感覚で、しかし私は、いつもと違うIMTも結構好きだった・・・などと、思い返すのである。
※ギメ・ルーム・・・IMTの地図上でFIRST SIGHT(ギャラリー1)と記されている展示空間の通称。窓が壁で覆われており、自然光が入らない。
※クーズー角・・・クーズーはアフリカ東部から南部にかけて生息する大形のレイヨウ。この標本はクーズーの角の骨芯部分である。
秋篠宮眞子(東京大学総合研究博物館特任研究員)
インターメディアテク・レコード・コレクション(17)
カット、スタンプ、プレス
ネット配信が定着するまで流行ったMTVのミュージック・ビデオは、長い前史を有する。20世紀初頭からヴォードヴィルやジャズの人気奏者たちは「サウンディーズ」という短編映画に出演していた。なかでも1937年にアーヴィング・ミルズが製作した5分弱の映画「デューク・エリントンとともにレコードを製造する」は興味深い。エリントンがバンドとともに「デイブレーキ・エクスプレス」および「メイビー・サムデイ」をスタジオで吹き込んでいる姿が映り、その音源をもとにレコードが製造される過程の各段階が紹介される。即興音楽であるジャズの録音は、各テイクが唯一無二の記録となる。その貴重なマスター録音が複雑なプレス作業を経て、彫刻のように無数のレコード盤に刻み込まれるプロセスが明確に説明されている。映画をよく見ると、映っているレコードは全て「ヴァーシティ」というラベルが附されている。これはアーヴィング・ミルズが同年に立ち上げたレコード会社であり、この短編映画はそのPR映像として作られたのであった。ところが映画が発表される前に「ヴァーシティ」は倒産してしまい、映画は純粋な教材として残っている。
大澤啓(東京大学総合研究博物館特任研究員)
セキショウ(サトイモ科)
植物画家・山田壽雄によるセキショウの写生図(3階に展示中)の裏面には、「花ハ大正十三.四.二九. 露子千駄木ニテ採集.」「葉ハ元年八月九日植物園ニテ」とある。花は山田の次女・露子が自宅近くにて採集したもので、植物園とは小石川植物園のことで間違いないだろうから、葉は植物学者・牧野富太郎から提供されたものかもしれない。すっと伸びた一つの葉以外の他の葉と根は、花が描かれた、S字に配されている部分を隠さないように貼り込んだ紙に描かれている。山田が写生対象の植物のパーツを入手した時間差ゆえに、そのような作りの写生図となったのだろうか。永井荷風の短編『妾宅』では、町なかの裏通りにある、日の差さない古びた借家の内部の情景描写の冒頭に、連子窓に置かれた「石菖の水鉢」が登場する。正直に言って、この随筆風小説の内容はまったく好きになれないのだが、妾宅の情景や主人公がそこで過ごす時間の「趣き」の描写が素晴らしいことは理解できる。そのなかでセキショウは、翳りを帯びた慎ましい(平凡な)妾宅の構成要素としての役割をきちんと果たしているように思われ、私にとっては真面目な(地味な)優等生という印象の植物であった。一方、この山田のセキショウは、構図に動きが感じられるからか、物理的な紙の厚みより二つの時間層でのやり取りがさまざまに想像されるからか、生命力あふれた明るさを放っている気がして、この植物に対する個人的な印象がずいぶん変わった。
寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)
続・高千穂の謎
さて。山階鳥研よりIMTに寄託された標本の中に、明治27年に天皇に献上された「高千穂」かもしれない標本があることを、前回述べた。実は、この標本と対をなすようなハヤブサの剥製がある。仁王像の阿形・吽形のように、ポーズや全体の作風がそっくりなのだ。どちらも端正なガラスケースに収められ、台座の作りも、鳥の面立ちも同じだ。おそらくこの時期の著名な剥製師であった坂本福治の手になるものだろう。こちらには「グアルダフィ」のラベルがある。そして、明治時代に御苑で飼われていた猛禽の中に、アデン湾で朝顔丸に飛来し献上された「グアルダフィ」の名がある。してみるとこれは防護巡洋艦に飛来したという「高千穂」と、同時期に飼われていたと思しき「グアルダフィ」であり、死後も仲良く2羽で並んで剥製となっていたのだろうか? そう考えることはできるが、真相を知るのは、黙して語らぬ彼らだけである。
松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)
図版LXXXIX—F.B.とA.H.W.
「図版LXXXIX」の図1、3、4を描いたR.M.は、ウィリアム・カーマイケル・マッキントッシュ(1838-1931)の妹、ロベルタ・マッキントッシュ(1842-1869)であった。それでは、図5を描いたF.B.と図2を描いたA.H.W.は、それぞれどのような人物であったのか。半断面図に各器官が細かく書き込まれている図5は、「F・ブキャナン女史の図より」と説明されているため、引用した図であると推測できる。F・ブキャナン(F.B.)は、図5で描かれているStreblospio shrubsoliiの命名者でもある、動物学者フローレンス・ブキャナン(1867-1931)のことである。ウィリアム・マッキントッシュは、1900年に出版された『総説・英国の環形動物 第1巻第2部』にて支援者の名前を列挙し感謝の意を述べているが、ブキャナンもその中に名を連ねている。図2を描いたA.H.W.ことエイダ・ヒル・ウォーカー(1879-1955)は、『総説・英国の環形動物』のために数多くの図版を描いた。セント・アンドリュースに拠点を置き美術教師をしていたこと、地元の風景画を描いていたことなどが知られているが、詳しいことはあまり分かっていない。どのような経緯でマッキントッシュのために絵を描くことになったのかも不明なようである。ただ、マッキントッシュの故郷がセント・アンドリュースであることが関係しているのかもしれない。
秋篠宮眞子(東京大学総合研究博物館特任研究員)
図版LXXXIX—R.M.
この色鮮やかな図版は、1915年にレイ・ソサエティより出版された『総説・英国の環形動物 第3巻第2部』に収録されている、「図版LXXXIX」である。セント・アンドリュース出身の海洋生物学者、ウィリアム・カーマイケル・マッキントッシュ(1838-1931)が中心となって書かれた同書は、環形動物のなかでも多毛類についての図版と解説をまとめたものである。本図版には5匹の多毛類が描かれているが、これらは1人の画家によるものではない。左下にイニシャルで小さく作者が記されており、図1(1番下), 図3(1番左), 図4(1番右)をR.M.が、図5をF.B.が、図2をA.H.W.が描いたと読み取れる。R.M.は、ウィリアム・マッキントッシュの妹、ロベルタ・マッキントッシュ(1842-1869)のことである。ウィリアムは妹の絵の才能をたいへん誇りに思っており、環形動物の絵の展示を開けるよう手配したこともあったという。ロベルタが残した写真帖には、顕微鏡を前に作業する兄を描いたページがある。研究に集中する兄の姿は、その研究を支えていた妹にとってお馴染みの光景だったのであろう。ロベルタは、動物学者アルベルト・ギュンター(1830-1914)と結婚し1868年にロンドンへ引っ越したが、すぐに若くしてこの世を去った。1873年に出版された『総説・英国の環形動物 第1巻第1部』の冒頭には、美しい飾り文字で、「本著のアーティストであり同志かつオブザーバーであった私の妹、R.の思い出に捧げる」とある。
秋篠宮眞子(東京大学総合研究博物館特任研究員)
インターメディアテク・レコード・コレクション(16)
検閲
洋楽レコードの普及とともに、日本ではその歌詞の和訳が徹底的に進められてきた。ところがヒップホップを中心に暴力的もしくは性的な内容の歌詞が流布すると、1990年には定型のラベル「親への勧告-露骨な内容」がジャケットに貼られ、歌詞の和訳も減った。しかし「露骨な内容」は新しいものではない。おそらく、文学同様、人間が歌を歌うようになって以来、露骨な歌詞はつきものである。SP盤が普及した20世紀初頭のブルースは、そういう歌詞に満ちている。カウント・ベイシーと共演したブルース歌手ジミー・ラッシングは、レコード会社による自主的な検閲を逃れるために、俗語や暗号を多用していた。しかし検閲にまつわる伝説のなかで最も有名なのは、ルイ・アームストロングが1927年5月に録音した「S.O.L.ブルース」だろう。無難な別れ話をテーマにした曲だが、題名の頭字語に卑猥な言葉が潜んでいる可能性があるとされ、お蔵入りとなった。しかしアームストロングらは懲りずに翌日、「ガリー・ロー・ブルース」のタイトルでほぼ同じ曲を収録している。原曲は1942年に、若きプロデューサーのジョージ・アヴァキアンによって発掘され、サッチモのアルバムの一面として発売された。
大澤啓(東京大学総合研究博物館特任研究員)
オンライン授業
大学の授業はオンラインで行われた。オンデマンドではなくリアルタイム配信である。筆者が担当する教養前期の「空間デザイン実習」は、受講者が空間のデザインを考えて模型を制作する授業である。実習作業のオンライン化には不安もあったが、意外にも順調に進めることができた。むしろ双方向的かつ個別的な対応が必要な授業に適したスタイルかもしれない。課題の「次世代建築」のコンセプトを立案し、空間的造形物を設計し、模型として実体化する。このプロセスをどのようにフォローするか。デザインのように正解が一つではない課題では、他者の考え方を知ることも重要である。各学生は全員に対して中間/最終のプレゼンを行い、またエスキースに臨む。エスキースは学生と教員の1:1のデザイン面談であるが、今回はそれもオンラインで共有された。不慣れなペンタブレットで描画しながら、学生との対話を重ねていく。他の学生はその様子に触れつつ、自分の制作作業を進めていく。結果として受講者25人の作品が完成した。「次世代建築」の解釈には、今の時世への意識が垣間見える。行為の場所、建築の形式、空間の様相、環境の応答、動態の創出に関わる提案がみられた。さて、オンライン授業に課題がなかったわけではない。それは扱われる題材の「尺度と質感」の欠落である。模型や図面などのスケールが捉えにくく、マテリアリティが伝わらない。実体物に帰着する教育では致命的ともいえる。これはリモート化社会の時空間と身体性に関わる根本的な課題であろう。
松本文夫(東京大学総合研究博物館特任教授)
ワレモコウ(バラ科)
植物画家・山田壽雄によるワレモコウの写生図(3階に展示中)の裏面には、「ワレモカウ 大正2. 9. 10 於高萩」との書付があり、山田が茨城県の高萩に出かけた際に描かれたものと推定できる。精密な図というよりは、対象の特徴を捉えて手早く描き留めたように見える。裏面の右隅には、「吾亦紅あはれや花のたぐひとも見えずわびしく秋の野に咲く」という歌が書き込まれている。山田自身がワレモコウをスケッチした際に詠んだものであろうか。「吾亦紅」とはワレモコウに漢字を当てた名であり、その名の由来には諸説あるそうだが、カタカナからはわからなかった哀愁のようなものを感じる。秋の赤い花は他に多くあれども、吾もまた、一見花にみえないかもしれないが紅の花をつけているのをお忘れなく、といったところだろうか。『ホトトギス』の俳人・高浜虚子は「吾も亦紅なりとひそやかに」とワレモコウを詠んでいるのが思い出される。虚子の句には短い言葉の凝縮具合に俳句や短歌の心得のない私でもさすがであると感じるものがあるが、裏面の歌も、植物学者を支えた植物画家である山田のスケッチを眺めながら味わってみると、「写生」の精神が素直に現れている気がして、なかなかに好感のもてる歌に思える。
寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)
近刊予告篇(三)
出版は本年十一月中旬になりそうであるが、待望の写真集が出せることになった。国立台湾大学の構内風景をテーマとするもので、題して『學舎景——國立臺灣大學逍遙』という。台湾語、英語、日本語の三ヶ国語の併記本である。いまから十年近くも前になるが、台湾大学でいくどか展覧会を開く機会があり、以来、彼地の人々の気性、街並、自然、食事にすっかり魅了されてしまった。とくに台湾大学構内に残されている、帝大時代のレトロな建物の佇まいには心惹かれるものがあったことから、写真家の萩倉英樹さんに同伴を願い、大学構内各所で写真を撮ることにした。萩倉さんは魚眼レンズを駆使した三百六十度パノラマ写真のパイオニアで、構内景観や建物内観を精緻なデジタル写真に納めてくれた。昨年、機会があり台湾大学図書館長陳光華さんに写真集の話をもちかけたところ、出版について快諾する旨の返事を頂き、晴れて出版の見通しが立った。アジアの「クラシック建築」や「アール・デコ建築」を魚眼レンズでパノラマ視化する。すると、戦前の帝大建築が文字通りの「バロック建築」に化ける。その変容振りは想像を超えるものであった。表紙を決めていないが、迫力のあるものにしたい。
西野嘉章(インターメディアテク館長・東京大学総合研究博物館特任教授)
首都のお暇
外出自粛が要請され、東京駅前が静まり返っていた4月、5月。この時期は鳥たちの繁殖シーズンでもある。カラスも例外ではない。東京駅前、丸の内側には1ペアのハシブトガラスが住んでいる。個体識別はできていないが、おそらく、何年も同じペアがいるのだろう。このペアは毎年営巣しようとするのだが、雛を連れているのを見たことがない。おそらく、どこに営巣しようとも撤去されてしまうからである。駐車違反と同じく、東京の「顔」たる丸の内界隈はカラスの営巣に極めて取り締まりが厳しい。ところが2020年6月30日、私は丸の内南口の換気塔に止まる、3羽のハシブトガラスの雛を確認した。もう巣立ちから3週間ほどたっているだろう。とすると、巣立ちは6月9日頃、産卵は4月15日頃となる。東京駅前が普段の雑踏にお暇していた2ヶ月、巣を見上げる人間がいなくなった隙に、とうとう繁殖に成功したのだ。これもまた「新しい生活」の一つである。
松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)
大野雲外と模様集
考古学者の大野延太郎(1863-1938年)は東大人類学教室にて学術標本を専門に描く画工でもあった。号は雲外。1893年から1904年頃の『東京人類学会雑誌』には、大野のサイン入りの図版をいくつも見ることができる。大野の重要な仕事の一つに、1895年頃に開始された「模様集」の制作があげられる。1916年刊行の『人種紋様(先住民の部)』(芸艸堂蔵版/多色木版刷り/18.7×27.8cm/書名は当時のまま)には、土器や土版の文様を単純化し、土器本来の色とはことなる彩色を施した模様の数々が載っている。ここで繰り返される曲線的な文様は、土器表面に施された文様を横方向に展開することで見出される。各模様のもとになった考古遺物には、東大人類学教室や東京帝室博物館(現東京国立博物館)の所蔵品が含まれる。考古学者兼画工であった大野は、研究対象である土器類の形や文様に雅致を見いだし、それを染織物や工芸品の図案に応用することを思いついた。学術標本をデザイン化して世に出そうとした大野の試みに興味を惹かれる。
藏田愛子(東京大学総合研究博物館特任研究員)
スケッチ
旅行にはカメラとスケッチブックを持っていく。フィルムカメラの頃は、長旅だと荷物の過半がフィルムになることもあった。それでも撮るときはアングルを厳選してフィルムの使用を抑制した。デジタルカメラになって装備は身軽になり、撮影枚数は1日で500枚に及ぶこともある。情報総量はデジタルが圧倒するが、1枚の決定力はフィルムに分がある。写真に比べると、手描きのスケッチの頻度はずっと少ない。描くのに多少なりとも時間がかかり、そう立て続けには使えない。しかし描きたくなる対象に出会うことは旅の大きな喜びである。位置を決めて腰を据え、スケッチブックを開き、ホルダー鉛筆を走らせる。スケッチは観察の記録である。描き始めると、見えていなかった様々な構成や細部に気づかされる。写真ではシャッターを押した瞬間に忘れてしまうが、スケッチは描いたときから記憶が始まる。少し時間を置いて宿に戻ったときなどに、同じ対象について別のスケッチを描くこともある。実際は見ていない俯瞰図や断面図など、半ば想像の産物のような図像である。昨今は外に出かける機会がぐっと減り、日常世界は均質な情報画面の集積になりつつある。手描きのスケッチを見ていると、対象とのリアルな距離感が鮮明によみがえる。(添付図はレバノンのバールベック神域で描いたもの)
松本文夫(東京大学総合研究博物館特任教授
高千穂の謎
明治27年、黄海海戦に勝利した日本帝国海軍の防護巡洋艦「高千穂」に1羽のタカが飛来し、マストに止まった。これを身軽な水兵が捕らえ、吉兆として明治天皇に献上し、高千穂と名付けられたという。当時広く報道されたようで、「高千穂艦霊鷹図」と題した日本画にはオオタカと思しき鳥が描かれている。もっともこういった絵は写生とは限らず、飛来した鳥がオオタカであったとは言い切れない。ある「献上之図」に描かれた鳥は真っ白な体で目の回りが赤く、あんな鳥はこの世に存在しない。さて、高千穂はその後、新宿御苑で他のタカと共に飼われていた。そして、山階鳥研から寄託された皇居由来の標本の中には、「高千穂」というラベルのついたハヤブサがいるのだ。もしや!? だが、名前以外の情報が不明である。台座の裏まで確かめたが、制作年代も由来も記されてはいなかった。残念ながら、これがかの高千穂だと言い切ることはできないのだ。
松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)
ラピッド・レスポンス・コレクティング
暴動や災害など大規模な異変が起きると、まずは救急隊と治安部隊、そして記者とカメラマンが駆けつける。その間、学芸員は博物館の収蔵庫に籠もってお宝を守る。これが緊急時のそれぞれの役割とされてきた。しかし近年、学芸員のなかでこの鉄則に逆らう動きが生じている。緊急時だからこそ外へ出て、その時にしか入手できない、出来事の物証なるモノを収集する。例えばデモであれば、ビラやプラカード。一時的な役目を終え、時の流れとともに消えて行くモノ(とりわけ印刷物)を「エフェメラ」と呼ぶ。書籍や標本と違って保存されないので、100年前のエフェメラは希少である。半世紀前の学生運動のビラ類がそのようにして再評価され、一部は高価なミュージアム・ピースとなっている。50年後のミュージアムを想像して、モノがタダ同然で手に入るうちに収集する方法を「ラピッド・レスポンス・コレクティング」という。今回のパンデミックのなかでも、社会に迷惑をかけない範囲で象徴的なモノの収集を呼びかけ、画像や言葉による証言を募る館が多い。臨時休館もしくは厳しい制限を伴う開館を余儀なくされるミュージアムにとって、マンネリ化した従来の運営を理想とした限定的な復旧を目指すのではなく、斬新かつ肯定的な活動を見出すタイミングでもある。
大澤啓(東京大学総合研究博物館特任研究員)
近刊予告篇(二)
以前、玄風社から出版した『装釘考』のカウンター・パートが近刊予定となっている。『書姿考——拙著造本篇』なる単著がそれである。他人の本の装釘について云々するのはひとまず中止して、拙著では自分がこれまでに手掛けてきた本を吟味してみる。デザインはどうか、造本はどうか、というわけである。このように言うと、業腹な話にも聞こえるかもしれないが、約言すれば、書物はいかにあるべきか、それについてどのように考えるか、私なりの考えを開陳したいと思ったのである。一九七〇年代初めの同人誌から昨年の近刊書まで、タイムスパンでいうと半世紀に亘る拙著出版史であり、拙著造本批判である。外装には半世紀ほど前に制作した作品を使いたいと考えている。右に掲げた『装釘考——拙著篇』の表題は仮のもので、最終的にどのようなものになるのか、まだ決まってはいない。図版と本文の割付を画定し、外装について思案しているところである。このところモノクロ図版の活用について考える機会が多く、拙著についても外装をモノクロ写真とし、小口墨染めにできないだろうかと考えている。もちろん、コストとの兼ね合いを考えねばならないわけだが。
西野嘉章(インターメディアテク館長・東京大学総合研究博物館特任教授)
三宅秀宛書簡集成(3)――実業家・益田孝(1848-1938)
三井物産初代社長で、三池炭鉱社の設立など実業家として活躍した益田孝から三宅秀へ宛てた昭和4年(1929)5月14日付の書簡である。冒頭「旧知の友であるあなた様に一書を差し上げるのは、光栄のみならず、歓喜に他なりません」と始まり、三宅の写真を見て、「昔(65年前)と変らない御容顔のまま御健勝でいらっしゃるのを知り、慶賀の念を禁じえず、一書を差し上げました」と書簡を認めた理由が述べられている。大仰ともいえる書き出しであるが、実は益田と三宅は65年前の1864年、幕府が派遣した遣欧使節団の随員として同船していた。益田は父で外国奉行支配定役元締益田鷹之助の従者、三宅は外国奉行田辺太一の従者であった。二人とも嘉永元年(1848)生まれで、当時16歳と最年少であった。書簡には昔を思い出すたびに、一度会いたいと思っていたとある。二人の歩んだ道は違ったが、互いに80歳を迎えた旧来の知己の長寿を知り、再会の念を強く持ったことであろう。この二人、奇しくも没年も同じである。
白石愛(東京大学総合研究博物館特任助教)
インターメディアテク・レコード・コレクション(15)
ジャズ組曲の限界
1943年1月23日、ニューヨークの名会場カーネギー・ホールは満員だった。来場者はデューク・エリントンが作曲した組曲「ブラック・ブラウン・アンド・ベージュ」の初演を聴きに訪れていた。エリントンにとってこの大イベントはキャリアの標石であり、黒人としての勝利でもあった。マエストロとされていたものの、短い「ソング」というジャズの定型を超えて、クラシック由来の複雑な形式に挑戦するのは初めてだった。ところが、翌日から新聞に載った批評は容赦なかった。「無形にして無意味」、「曲の寄せ集め」「虚偽のクライマックスに満ちている」。最も問題視されたのは、エリントンの異端の作曲法であった。短いメロディーを繋いでも大作にはならない。エリントンはこの屈辱を払拭することなく、1943年以降、ライブで本作を通しで演奏することがなかった。しかし1945年には前年末の録音が同じ題名でヴィクターから発売された。12インチSP盤4面に亘る、名曲の文字通りのコンピレーションである。これを聴くと、エリントンの作曲法がどこまでSP盤の時間的制限に影響されたのかが気になるところである。
大澤啓(東京大学総合研究博物館特任研究員)
サクラソウ(サクラソウ科)
サクラソウで思い出すのは、いがらしゆみこ作画・井沢満原作の『ジョージィ!』という少女漫画のなかのエピソードである。オーストラリアの牧場で育った少女ジョージィがオーストラリア総督の孫息子ロエルと恋に落ち、ロンドンへと海を渡り、二人は駆け落ち同然で下町生活を始めることになる。新たな暮らしを目前にして、これからのことを心配するお坊ちゃまのロエルに向かって、ジョージィがどんな所でも「桜草が咲いていればいいわ」と言うシーンがある。泣かせるのが、ジョージィはさらに別れ際に振り返って「ほんとは桜草じゃなくてあなたがいればいいの」とロエルに言うのである。しかし、育ちの異なる二人の恋は実らない。この少女漫画にどっぷりとはまっていた小学生の頃の私は、サクラソウという花にキュンキュンとした思いを抱き、近所の花屋で見つけたサクラソウの苗をプランターに植えて水やりに勤しんだことがあった。3階に展示中の、山田壽雄が描いたサクラソウの写生図の裏面には、「サクラサウ. 自然大. 大正3. 5 .6. 壽雄培養」との書付とともに、花が落ちた後の萼のスケッチが見られる。そこに、植物学者・牧野富太郎と仕事をした植物画家としての科学的な目を感じるとともに、勝手ながら、山田が自分で培養して可憐な花を咲かせたサクラソウへの愛着のようなものも想像してみたくなるのであった。
寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)
近刊予告篇(一)
新型コロナウイルスの感染拡大で出版の見通しが立たなくなってしまった本がある。出版社が決まり、頁割付けも終わった。外装を含む全体のヴィジュアル構成も画定し、文字校正も済んでいるが、社会生活のメカニズムがほぼ全的にダウンして、刊行がいつになるのか見当もつかぬ事態に立ち至ってしまった。というわけで、溜まりに貯まったフラストレーションを解放する方法はないか。そこでカバーの試案をここに掲げてみることにした。今日普通に流通している上製本では、本体の上にブックカバーを掛け、その上に惹句を掲げた腰帯を巻く形式のものが多い。しかし、私はそのスタイルに首肯できない。カバーの上に腰帯をかけるのは、どう見ても「屋上屋」を重ねることになる。スマートでない、と思う。拙著『雲の伯爵——富士山と向き合う阿部正直』で挑戦してみたいのは、カバーと腰帯をひとつに統合する形式である。様々な制約があり、実現は容易でない。とはいえ、資源と経費の両面で節約が可能な形式は、試してみる価値がありそうに思うのだが。
西野嘉章(インターメディアテク館長・東京大学総合研究博物館特任教授)
小さな空間を開く
京都鷹峯の太閤山荘に「擁翠亭」という茶室がある。寛永年間に加賀藩主・前田利常が京の金工師・後藤覚乗の屋敷に建てた草庵茶室で、設計は小堀遠州による。明治初期に解体された古材が140年ぶりに発見され、2015年に現在地に再建された。千利休の弟子・古田織部に学んだ遠州は、利休のわび茶の精神を継承しつつ、茶室の建築を新しい次元に引き上げた。それは「陰から陽へ」、「閉から開へ」の広がりを獲得することである。すなわちこの茶室は、人間と空間の多様な相互関係を包含している。擁翠亭は別名「十三窓席」と呼ばれ、大きさや高さが異なる十三の開口部がある。過日見学の機会をいただき、躙口から茶室の中に入り、三畳台目のやや暗めの室内に座した。やがて簾が外され、障子が開かれ、小襖が引かれると、空間の様相は劇的に変化していく。連子窓や下地窓ごしに庭園の翠(みどり)が見え、野趣に富んだ格子の抽象美が展開する。全開状態は通常の茶会のしつらえではない。しかし、この極小空間では、内部と外部を隔てるだけでなく、それらを個別につなぐことができる。モダニズム建築の透明性の先を行く、環境共生型建築としての繊細な振るまいを感じさせる。点前座は躙口の正面、茶室のほぼ中央部にあり、写真は点前座からの内観である。遠州がこの建築に込めた、開かれた世界観をみる思いがする。
松本文夫(東京大学総合研究博物館特任教授)
鳥の視点
一昨年から、カラス研究の一環としてドローンを飛ばしている。営巣条件の調査のためだ。ハシブトガラスは一般的に、巣を見られることを嫌う。そこで、「どの角度からなら見えるか、どの程度見えるか」を確認したかったのである。だが、カラスが巣を隠したがっているとすると、巣を狙ってくる外敵は地上だけにいるのではない。上空を飛ぶ猛禽や、枝伝いに樹上にやって来るテンやヘビなども相手だ。となると、地べたからの視点だけでは足りない。そこでドローンを導入し、あらゆる高さから見ることにしたのである。これを飛ばしてみると、発見しづらかった巣が上からは丸見えとか、逆に上空からはまったく見えない、といった例が出てきた。調査結果は悩ましいものだったが、カラスと同じ視点で世界を見るというのは、面白い経験である。彼らが飛ぶ高度からは、地上など取るに足りぬちっぽけなものにすぎず、遥か遠くまで一望にできるのだ。
松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)
インターメディアテク・レコード・コレクション(14)
音の収集癖
1940年春、ラジオ局に勤めていた録音技師モージズ・アッシュ(1905-1986年)は、第二次世界大戦のヨーロッパ開戦を機にニューヨークでレコード会社を立ち上げ、ユダヤ系コミュニティのために録音制作活動を始める。その後、ジャズやブルースへと活動範囲を広げるが、プロデューサーとしてのデビューは困難に満ちていた。有名アーティストに賭けたレコードが損失を生み出し、戦時体制でレコードの原材料まで制限され、最終的に無名の左翼系レーベル「スティンソン」との連携に追い込まれた。1945年、新レーベル「ディスク」を創立したアッシュは、戦時中の教訓を活かして独自の制作方針を定めた。敢えてヒットを作ろうとしない。他社が関心を持たない音楽を徹底的に録音する。レコードが売れなくても廃盤にしない。いわゆる隙間産業を専門としたアッシュはわずか数年でユニークなカタログを形成する。この経験をもとに1949年のLP盤登場とともに、ライフワークとなる事業「フォークウェイズ・レコーズ」を開始する。彼は40年に亘って、人類が生み出す「音の世界」を2200枚以上のLP盤に収録した。この類のないコレクションは現在、スミソニアン博物館の中心的なコレクションとして活用されている。
大澤啓(東京大学総合研究博物館特任研究員)
シロツメクサ(マメ科)
宮沢賢治の短編作品『ポラーノの広場』にシロツメクサが出てくるのをご存じだろうか。モーリオ市の博物局で標本の採集や整理を受けもつ下級役人キューストが、少年ファゼーロと出会い、祭りが開催される伝説の場所「ポラーノの広場」を探すという話である。初めてキューストが「ポラーノの広場」を探しに行った夜に「つめくさ」(シロツメクサのこと)の「番号」を数える場面が出てくる。「なるほど一つ一つの花にはそう思えばそうというような小さな茶いろの算用数字みたいなものが書いてありました」。3階に展示中の、植物画家・山田壽雄の植物写生図のなかにあるシロツメクサは、小さな用紙の枠内に非常に緻密に描き込まれた着色画で、台紙に貼付されている。裏面には「明治45.6.」という書付があり、制作年代が確認できる。何か用途があって描かれた完成品のよう見えるが、それが何かはよくわかっていない。その「謎」のためだろうか、私には下部にある筆記体のローマ字「Shiro Tsume Kusa」の書付も、小さな用紙の枠内に収められている様も、何だか実際以上に特別に見えてきて、「ポラーノの広場」に行くために数える「番号」でも読み取れるのではないかという気がしてくる。
寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)
それは何?!
野外で鳥を観察していて、しばしば出くわす困難がある。それは「何を食べているのかわからない」問題だ。明らかに採餌はしている。何かくわえているし、嘴も動いている。上を向いて「ごくん」と飲み込む動作まで見える。なのに、くわえていたのが何だったかが、わからない。多くの場合、それは小さすぎ、遠すぎ、素早すぎるのである。写真を撮るにも、よい条件で撮影できることは非常に希だ。見つけた瞬間にスナップショットで撮影する場合、ブレていたり、暗かったり、小さすぎたり、フォーカスが甘かったり、角度が悪くて判別できなかったり、と問題は山積している。ここに挙げた写真はなんとか識別できた例で、冬の水田で採餌していたミヤマガラスが、スズメガの蛹をくわえている様子である。これ以外にヨトウガの蛹らしきものやジャンボタニシを食べているのも見た。害鳥扱いされることも多いカラスだが、農業害虫もちゃんと食べているのだ。
松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)
インターメディアテク・レコード・コレクション(13)
ジェローム・カーン対ビバップ
ジャズメンが演奏する曲はその作曲者によって、トラディショナル、スタンダード、ノベルティ、オリジナルなどに大別できる。その中で「スタンダード」は曖昧な範疇で、曲の由来がジャズ、クラシック、ミュージカル、映画または異国のポップスであれ、演奏され続ければジャズの定番となる。当然、ある曲が作曲者の意に反してジャズ・スタンダードになることもある。作曲家ジェローム・カーン(1885-1945年)は、ジャズの要素を自身のミュージカルに取り入れたのにも関わらず、ジャズメンが彼の曲を原作から切り離して演奏することを大に嫌っていた。不幸なことに、1939年のミュージカルで発表された「オール・ザ・シングス・ユー・アー」はその年の失敗作であったのに、カーンが最も警戒していたビバップ奏者によってジャズの定番たる資格を得た。ディジー・ガレスピーらの1945年の名演に始まり、ソニー・ロリンズらハードバップの流れに乗って、モダンジャズやフリーまで吸収し、今でもスタンダードとして愛されている。
大澤啓(東京大学総合研究博物館特任研究員)
救荒植物図譜の行方
『救荒食品図鑑』(第一輯、1944年、厚生省研究所国民栄養部研究会発行、非売品)という、簡素なつくりの本が私の手許にある。見開きの左ページには植物の名称と「異名・科名・産地・分布・可食部・採集時期・食用方法・薬用・各種成分等に関する諸事項」が記され、右ページには図版が載っている。本のサイズはA5判、図版は全部で70点。植物の「可食部」に目がいくように、各図の植物の配置には工夫がみられる。同書は1944年12月5日に発行された。栄養研究所が編纂公刊を企図するも実現せずにいたのを、厚生省研究所国民栄養部研究会が、国民の栄養状態と食料事情の緩和に役立てようと刊行したものである。凡例には「故西野猪久馬画伯が精魂を傾けて写生せる実物大彩色の救荒植物図譜中より70種を選出して」とある。西野猪久馬(1870-1933)は東大植物学教室勤務の経験を有し、植物学者の三好学や牧野富太郎のもとで植物画を描いた人物である。1922年、西野は牧野の紹介で栄養研究所に入り、晩年まで植物写生に従事した。西野が精魂を傾けて写した実物大彩色の救荒植物図譜は、今もどこかに残されているだろうか。
藏田愛子(東京大学総合研究博物館特任研究員)
スノードロップ(ヒガンバナ科)
3階の常設展示の一部を更新し、『東大植物学と植物画—牧野富太郎と山田壽雄』と題して、「山田壽雄植物写生図」を展示することになった。本写生図の多くは、『牧野日本植物図鑑』など、牧野が著した図鑑の下図や参考図として山田が描いたものと考えられており、われわれに親しみのある植物をそのなかに見つけることができる。このスノードロップを眺めていて、子どものころに読んだ、ロシアの作家サムイル・マルシャークの『森は生きている』を思い出した。主人公の少女が大晦日に、12月には咲いているはずのない春の花であるスノードロップをほしいと言った女王のわがままのために、意地悪な継母の言いつけで雪深い森の中にそれを探しに行くというお話である。このスノードロップの画面右下には「マツユキソウ 一名 ユキノハナ」との書付があるが、私の読んだ翻訳児童書にも花の名前は「マツユキソウ」と書かれていた。外国の本の中に出てきた花が、ある時自分の家の庭先に咲いていると知り、興味深く眺めたことを印象深く記憶している。裏面の書付には「スナウドロップ. (実大). 大正4.3.2 動坂町122. ニテ.」とあることから、山田が同日に自宅で採集した花を実物大でスケッチしたと推定される。表面下部の「其果実. 五月五日.」とは、後日、同じく自宅で採集した実を描き、貼り付けたものだろう。山田家の庭先にこのスノードロップが咲き、実をつけていた様子を、自分の思い出と重ね合わせて想像してみた。
寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)
床の記憶
インターメディアテクの内装仕上で古式を残すのは床である。保存棟2階の展示室を歩くと、木製の床は硬く締まっていて、木造家屋の根太床のような軽やかさはない。ここで使われているのはフローリング・ブロックとよばれる材料である。木の無垢板を並べた30cm角の床材ユニットで、裏面に防水処理を施し、下地モルタルに金脚をくい込ませ、市松状のパターンに固定している。材質としては木であるが、湿式工法による頑丈な床仕上である。東京中央郵便局の1階から3階までの大半の空間は、郵便の仕分業務等を行う現業室であった。郵便物を積んだ多数の台車が局舎内を行き交っていたはずで、その動線を示す床サインの痕跡がいまも残っている。ただし、この木製床は創建当初のものではない。建築雑誌582号(建築学会、1934年3月)の巻末附図を見ると「各現業室の床はアスファルト、シート」と書かれている。初期にはアスファルト混合物だった床材が、酷使に耐えるフローリング・ブロックに早い段階で改修されたものと思われる。東京中央郵便局の壁のない大空間は、おそらく日本でもっとも苛烈な物資流動の現場であった。その歴史的空間の一部が、いまは文化的資料が定着する博物空間に生まれ変わった。往時の記憶を伝えるフローリング・ブロックは、展示物のように一つ一つが固有の表情をもっている。(なお、3階展示室の木製床は新たに敷設し直している)
松本文夫(東京大学総合研究博物館特任教授)
仮住まい
ここにいるアオボウシインコは、仮住まいの身だ。本来は台座と台木があったのだが、他の剥製に流用してしまったからである。鳥の剥製は足の中に針金が通っており、足の裏から下に針金が突き出している。これを台木に開けた穴に通し、針金の先を枝の裏側で曲げて固定する。逆に、この針金を伸ばしてやれば、剥製は台木から引き抜けるのである。さて、問題は残った剥製の処遇だ。足の裏に針金が出ているので、そのまま立たせることはできない。第一、剥製の足指は枝を軽く握る形に整えられており、きちんと立つように作られていない。さらに、尾羽が下方に突き出すため、平面に置こうとすると尾羽がつっかえる。さりとて寝かせておくと羽毛が傷みがちだ。ということで、このようにポリスチレンや発泡スチロールのブロックに針金を突き刺して仮置きしておくことがある。本当はいい台を見つけてやるべきなのだろうが、これはこれでコンパクトで扱いやすいので、今日もそのままである。
松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)
帝室の工芸
生物学御研究所由来の古い標本には、おそらく明治期に献上された、由緒正しい設えのものがある。典型的なのは、一連の漆塗りの木枠にガラスを嵌めた、風雅なケース入りのものだ。木枠は仏壇や家具にも見られる細工を施してあり、繊細な面取りや削りが入っている。漆はシンプルな黒漆が多いが、生地を生かした透き漆の例もある。背面にドアを備えた現代的な日本人形のケースとは違い、台座の上からカバーを被せる構造になっており、ガラス部分が枠ごとすっぽり外れる。だが、その合わせ目はガタ一つなくピタリと嵌っており、外す時には隙間にスパチュラを差し込み、傷をつけないようそっとこじる必要がある。ガラスは薄い端正なものだが、波打った表面を見れば一目瞭然、古い時代の手吹き板ガラスだ。指物師など、江戸から続く高い技術を持った職人が一つずつ手作りしたケースに、足指の曲げ方まで精密に再現した剥製が収まる様は、まさに工芸の粋でもある。
松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)
赤門の隣に
古い映画を見ていると、今とは異なる風景に瞠目することがある。豊田四郎監督の『雁』(1953年)を見る機会があった。原作は森鴎外の同名小説で、心ならずも囲者になったお玉(高峰秀子)の、東大医学生(芥川比呂志)への淡い慕情を描いた作品である。不忍池と東大鉄門を結ぶ無縁坂にお玉の家があるという設定で、美術の伊藤熹朔らによって無縁坂の壮大なセットが組まれた。映画の中では、東大赤門がロケーション撮影で二回出てくるが、このとき赤門ごしに旧東京医学校本館(現在の総合研究博物館小石川分館)の実物が見えているのである。旧東京医学校本館は現在の鉄門近くに創建され、のちに赤門の脇に移築され、さらに小石川植物園の現在地に移築された。赤門脇にあった頃の古写真は目にしていたが、高峰や芥川が歩く動画で見るのは眼福の極みである。撮影当時、1953年頃の状況であろう。森鴎外の原作がスバルに連載されたのは1911〜1913年、旧本館が赤門脇に移築されたのは1911年。ただし、物語の時代設定は1880年頃なので、旧本館はまだ創建の地にあった頃である。この辺りはご愛嬌だろう。映画で見る限り、外壁の上下階の塗り分けはなく、全体に薄めのトーンに見える。赤白の塗り分けは赤門脇への移築後に行われているが、複雑な経緯を辿っている。そのいっときの記録にはなるだろう。今は別々の場所にある赤門と旧本館の現状写真を、映画の見え方にあわせて合成してみた。
松本文夫(東京大学総合研究博物館特任教授)
インターメディアデザイン その六
現代において「白」という色は、プロダクトやファッション、建築に至るまで、モダニズムの象徴として、もはや崇拝に値する色であり、かつ認識以前の存在としてあらゆる場面に登場する。それは善意や純粋の意に留まらず、斬新さや無機質感、清潔感といった現代社会において必要とされる要素を、人間の根幹的な感性であるかのように意識付けられてきたからだ。ミュージアムという公共空間に目を向けてみれば、モダニズム建築が台頭した20世紀初頭から内部空間はホワイトキューブが主流となった。つまり斬新、無機質といった要素が、あらゆる様態の美術に対するニュートラルな対比として定着したためだ。インターメディアテクを設計するにあたり、まずその既成概念からの解放を図った。もうひとつ、ホワイトキューブに白い什器といったいわゆる美術館スタイルでは展示物の数量に関わらず希薄感は免れない。そこで白という色をアクセントとして、つまり反転してみせることで、白への再確認を試みた。
関岡裕之(東京大学総合研究博物館特任准教授)
三宅秀宛書簡集成(2)――楢林建之(1862-1932)
三宅秀の父艮斎(1817-1868)は天保年間に長崎でシーボルト門弟の楢林栄建(1801-1875)のもとで蘭方医学を学んだ。楢林家は代々オランダ通詞で、蘭商館医に学んだ楢林鎮山(1648-1711)が楢林流外科を創始した。書簡は秀が問い合わせた豊後国日出(ひじ)藩の砲術家関讃蔵についての回答である。讃蔵は日出藩家老の関勝之の長男で、建之の養父建吉(1832-?)の兄にあたる。讃蔵は長崎で高島秋帆の下役山本物次郎について「火技研究・大小砲製造・築城・築砲台及蘭書ノ翻訳製図ヲ為シタル人」とある。山本物次郎は「蘭人ニ就テ大小砲戦術及火技ヲ研究、当時長崎ニテ一二ヲ争フ人物」と記されている。山本家には福沢諭吉が食客として住み込んだことでも知られる。安政5年(1858)に英医ホブソンの中国語の西洋医学書『西医略論』を関讃蔵編集、桃樹園(艮斎)蔵板で翻刻していることから、秀が編集者の讃蔵について調べたものと推察される。なお、三宅コレクションには楢林家から贈られた「伝シーボルト使用の皿」がある。
白石愛(東京大学総合研究博物館特任助教)
サイズ問題
収蔵展示室Studioloは、通常、標本保全のために室内を消灯している。ただし、「覗き込めばうっすらと中に標本の集積が見える」状態にはしてあり、隠れたアイキャッチとして、大型標本も配置してある。代表的なのは山階鳥類研究所所蔵のクマタカだ。クマタカは翼開長が最大170センチほどになる。この標本はそこまでの大きさではないが、150センチは確実に超えている。流木を磨いた台座もどっしりと大きく、それだけでもかなりの重さがある。Studioloのスチールラックには全く収まらない。外に出そうにも、これを収めることが可能なカバーもケースもない。極めて残念なことだが、見事な大きさの剥製なのに、見事すぎて展示に生かすことができないのである。うまい方法を思いつく日まで、収蔵室の主として君臨してもらうよりない。そして、室内で作業している時、目が合うたびに、「おい、出番はまだか?」と言われているようでもある。
松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)
ガラスでできた学術模型
特別展示『十九世紀ミラビリア博物誌−−ミスター・ラウドンの蒐集室より』では教育資料を展示しているが、その中に、ボヘミア出身のレオポルド・ブラシュカ(1822-1895)とルドルフ・ブラシュカ(1857-1939)親子が製作した模型が数点ある。これらは基本的にガラス製であるが、実物に近づけるため、ガラスの特徴を時には消し、時には活かしながら作られている。例えば、この「カンザシゴカイの一種」を見てみよう。うねるような棲管は、まるで粘土か何かで作ったような外見をしている。一部が壊れて半透明のガラスがのぞいているため、ガラスに分厚く彩色したことが推測出来るものの、初見でこれをガラスと見破るのは困難であろう。一方、アサガオの蕾のように見える殻蓋は、赤味がかった色ガラスと白味がかった色ガラスを用いて造形したものと思われる。ブラシュカ一族の起源がヴェネチアにあることを考えると、ヴェネチアのワイングラスに似ているような気もしてくるのである。
秋篠宮眞子(東京大学総合研究博物館特任研究員)
二〇二〇謹賀新年
「2020」にしても「二〇二〇」にしても、まさにデザイナー泣かせの綺麗な数字である。滅多にない数字の並ぶ年を、恙なく迎えることができた。まずはそのことを言祝ぎたい。「インターメディアテク」は早いもので七年目を迎えた。初年度を別として、二年目以降、来館者数は高止まりしたまま、ほぼ横這いの状態にある。これは滅多にない現象で、ミュージアムとして誇ってもよい。目立つのは、やはり海外からの来館者である。その動向を知りたいと思い、昨年春から、タッチパネルによる調査を始めた。来館者の自主性に委ねて得られた有効回答は、月毎に千件から二千件。そのデータを基に、海外からの来館者は三割近くに上り、出身地も世界各地に広がっていることがわかった。無料公開施設として安定軌道に乗っていることは実感できる。しかし、事業規模が膨張し、学芸業務が多様化し、ネットワークが拡大するにつれ、ある種の「慣れ」が生じてきている。このままでいたら、マンネリ化が進み、受動的になり、冒険心を失い、臆病になり、結果として、凡百の施設へと転がり落ちてゆくのは早い。そもそもが大学の実験施設として立ち上げられた「インターメディアテク」である。未知への「投企」を怠るようなことになれば、これまで育んできた存在意義など、たちまち雲散霧消してしまうに違いない。いまこそ新たな「シーズ(種)」を蒔かねばならぬ時なのである。それにしても、「オリパラ年」と呼ぶより、「グラフィック・イヤー」とでも命名したくなるような西暦年ではないか。未来に向かうヴィジョンを、眼に見えるかたちで示す、格好の年がやってきた。
西野嘉章(インターメディアテク館長・東京大学総合研究博物館特任教授)
名無しのペンギン
IMTが収蔵する鳥類標本の中に、明治44年に採集されたと考えられるシュレーターペンギンの本剥製がある。この標本は白瀬矗による日本人初の南極探検の際に捕獲され、マスコットとしてしばらく船上で飼育されたが死んでしまったので皮だけを持ち帰り、南極探検を後援していた大隈重信を通じて明治天皇に献上され、その後は皇居にあって生物学御研究所の所蔵となり、1995年に山階鳥類研究所に移管された後、2013年にIMTに寄託されてやって来たが、ある研究家のおかげで由来が判明したのである。2014年に「あるペンギンが辿った歴史」として特別展を行なったが、私としては英語タイトルとして付けた「The History of an Anonymous Penguin(名無しのペンギンの歴史)」の方が気に入っている。標本ラベルには「イワトビペンギン」と記入されていたが、由来がわかったことで採集場所が特定され、その知見に基づいて同定し直した結果、実に102年ぶりに正しい名で呼ぶことができたからである。
松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)
建築空間と身体
欧州最古の大学といわれるボローニャ大學。様々な建物に分散されていた法学部(民事法、教会法学)と学芸学部(哲学、医学、数学、物理学、自然科学)とを一つの建物に統合しようと1563年最初の大學棟として建てられたのがArchiginnasio館。今も残されている解剖学教室とボローニャ大學旧教室[現市立図書館]が一般公開されている。資料調査に初めて訪れた図書館内部で強烈な体験をした。門をくぐりポーチを眺め、真ん中がすり減った階段を上がり、ノートなど必要品以外のカバン類はすべてロッカーに入れ、さらにIDを預けてから入室をする。そこをくぐり抜け、この空間に入った。外部からのアプローチ、内部の装飾が施された空間、目の前の木製の閲覧テーブルには数百年前の埃を被った資料、日本から調査をしに来た自分の身体が1本の軸でつながった。その実感がゆっくりゆっくりと身体に充満し、言葉にし難い不思議な時間を過ごした。歴史的建築空間に居座ることで場が身体通して我々自身の存在を定義してくれていること、残し遺されたモノたちがバトンになり、ただ静かにつないでくれたのである。
上野恵理子(東京大学総合研究博物館特任研究員)
成長のデザイン
小石川分館で特別展示『貝の建築学』を開催中である。佐々木猛智准教授の学術企画による展示で、筆者は展示デザインを担当した。世界各地で採集された貝殻標本400種以上を展示しており、なかでも佐々木研が作成した150個におよぶ「切断標本」の公開は前例のない試みである。貝殻は貝がみずから形成した住処であり、成長のための構成原理(=アーキテクチャ)を内包している。切断標本はその驚異の内部構造を見せてくれる。佐々木准教授によれば、貝殻の成長は「等角螺旋」と「付加成長」という2つの原理で説明できる。等角螺旋は螺旋の中心に対して一定の接線角度で拡大する形式であり、付加成長は殻の縁辺部に結晶を追加して成長する形式である。本展の会場設計においても「螺旋」のフォルムを採用している。展示室の既存柱の中心を通る螺旋の基準線をまず設定する。汎用性を高めるために曲線ではなく直線を組み合わせた多角形の螺旋として展示ケースを配列していく。螺旋の中心部では巻きが強く尖った貝類が、螺旋の末端部に向けて巻きが緩く平たい貝類が列品される。増殖でなく付加による成長は、建築の特性に通じるところがあり、「成長のデザイン」に多くの示唆を与えてくれる。建築家のル・コルビュジエは「無限連鎖美術館計画」を提案したが、四角い螺旋状の建築は付加成長を前提としていた。
松本文夫(東京大学総合研究博物館特任教授)
インターメディアテク・レコード・コレクション(12)
狂気のハープシコード
エレキギターの鬼才ジミ・ヘンドリックスが南部の教会でゴスペルを弾いている姿を想像してほしい。ステンドグラスは破れるかもしれないが、参拝者のなかで未曾有の熱狂が生まれるだろう。今年80周年を迎える名レーベル「ブルーノート」が1941年に出したSP盤19および20号を聴いた時に、その情景が浮かんだ。これは、1939年1月に同レーベルの初録音を行ったピアニスト、ミード・ルクス・ルイス(1905-1964年)がチェンバロを弾いている録音だ。一斉を風靡したピアノ奏法「ブギウギ」の特徴を活かして、ルイスはレコード4面に亘って「主題による変奏曲」を即興で展開している。我々の記憶のなかでピアノと結びついているブギウギを他の鍵盤楽器で奏でることによって、なんとも言えない違和感が生じる。同時にルイスはチェンバロから前代未聞の音を引き出している。珍しい楽器をバンド編成に取り込むジャズメンの「多楽器主義」は、チェレスタを弾くモンクや100以上の楽器をステージに持ち込んだアート・アンサンブル・オブ・シカゴを通じて、現在も受け継がれている。
大澤啓(東京大学総合研究博物館特任研究員)
インターメディアテク・レコード・コレクション(11)
奇妙な果実
歌手ビリー・ホリデイが1939年4月20日に吹き込んだ曲は、彼女自身にとってもジャズ史においても特別な意味を持つ作品となった。当時ニューヨークのライブハウス「カフェ・ソサエティ」に出演していたホリデイはアンコールとして、ポップソングとは一線を画す、ある新作を歌っていた。その題名は「奇妙な果実」。白人の教諭エイベル・ミーロポルが作詞作曲したこの曲は、ホリデイが専属契約を結んでいたコロンビア系列のレーベル「ヴォーカリオン」に録音を却下されたため、ミルト・ゲイブラーが経営していたインディー・レーベル「コモドア」から526号として発売された。というのも、人種差別が厳格に実施され、リンチも絶えなかった米国社会において、その状況がメディア等に露出することはほぼなかったからだ。ホリデイが歌った「奇妙な果実」とは、南部のポプラの木にぶら下がっている、へんてこな血まみれの果実、リンチされた黒人のことであった。これをもってホリデイは娯楽を逸して、「プロテストソング」の原型を作った。526号の裏面には「ファイン・アンド・メロー」が収録され、大ヒットとなった。
大澤啓(東京大学総合研究博物館特任研究員)
夜間飛行
先日、帰宅中の夜空から「チーチーチー」と聞こえる鳥の声がした。この時期になると聞くことのある声、渡り途中のツグミの声だ。鳥の多くは昼行性で、夜間は行動しない。ただし、行動「できない」わけではない。夜の間にねぐらを移動するカラスもいるし、小鳥だって寝ている間に危険が迫れば飛んで逃げる。ただ、昼ほどのパフォーマンスを発揮できないが故に、夜は無駄なエネルギーを使わずに寝ているにすぎない。一方、これは夜間なら猛禽類の目を逃れられる、ということでもある。よって、渡り鳥はしばしば、夜の間に飛ぶ。今はレーダーを用いて夜間の鳥の渡りを観察することもできるが、かつては満月の夜を選び、月面を横切って飛ぶ鳥の影を数える、という調査方法もあった。遊びで試してみたこともあるが、やってみると秋の地面は冷たいわ、双眼鏡で見る満月は眩しすぎて目に痛いわ、双眼鏡を支える腕は震えだすわ、なかなかに過酷なものであった。
松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)
内田祥三
博物館本館の耐震改修工事のため、近くの医学部一号館に仮住まいしている。内田祥三の設計により1931年に竣工した校舎である。鉄骨鉄筋コンクリートの堅牢な構造で、スクラッチタイルに覆われた「内田ゴシック」の建築群の一つである。建築学科教授と営繕課長を兼務していた内田は、関東大震災後の本郷キャンパスの復興計画を主導した。その基本構想は、正門から大講堂(安田講堂)に向かう軸を設け、それに直交して左右に図書館と博物館を配するものであった。明治の辰野金吾、大正の佐野利器に続き、昭和の建築界を牽引した内田祥三は、建築家・研究者・教育者・組織人として大きな手腕を発揮した。建築家としてはモダニズムと一線を画したネオゴシックで復興を推進し、研究者としては音響、構造、防災、都市計画など多分野の学を興し、教育者としては建築実務を講座に取り込んで数多の後進を育成し、組織人としては教授と課長を兼務したのちに総長に就任した。総長として、終戦前後の陸軍と米軍の接収要請を拒絶したのは特筆すべき功績であろう。弟子たちが編纂した『内田祥三先生作品集』には、その縦横な活躍のエッセンスが集約されている。医学部一号館のスクラッチタイルの壁面を見ていると、芋目地の基本構造を介して多様なテクスチャの共存可能性が見えてくる。それはまさに内田の際立った特質のあらわれのようだ。
松本文夫(東京大学総合研究博物館特任教授)
インターメディアテク・レコード・コレクション(10)
ピアノ・ロールとレコード
ニューオリンズ・ジャズ・ピアノの祖ジェリー・ロール・モートンの初期録音をSP盤で聴くと、彼の滑らかにして複雑にリズミカルな演奏とは無縁なものが聴こえてくる。よく聴くと、そのピアノの音はモートンの手によるメロディーではなく機械から流れているものだ。録音が普及する以前に、音楽とりわけピアノ・ソロの伝播方法として、楽譜以外に「ピアノ・ロール」というものがあった。メロディーが穿孔された巻き紙を自動ピアノに差し込むと、オルゴールの原理に従ってその穿孔をもとにピアノは曲を再生した。それがのちにSP盤に収録され、発売されることもあった。また、ミスを起こしかねない演奏家の吹き込みに対し、音の羅列を完全に再生する物理的な原理を重要視し、この機械的発展に音楽の未来を見出した人は当時少なくなかった。実際にピアノ・ロールを聴けばその見解の稚拙さに誰もが気づくが、ピアノ・ロールは再生音楽を離散的な情報に分解するうえで実に重要な第一歩だった。実際のところ、若きファッツ・ウォーラーは師のジェームス・P・ジョンソンが作曲した『カロライナ・シャウト』を習得するために、ピアノ・ロールをゆっくりと再生し、自動ピアノでそのコードを一つ一つなぞっていったと言われている。
大澤啓(東京大学総合研究博物館特任研究員)
床と石材と私
2年前、出張でスウェーデンを訪れた時のこと。ウプサラという街に数日いたのだが、最後の一泊だけ、宿泊先を引っ越した。それまで滞在していた宿が、予約の都合でそれ以上の連泊ができなかったのだ。移動先は古めかしく、もっと大きなホテルだった。石造りの螺旋階段を上って行きながら、私はふと足元に目を止めた。そこには角ばった「C」の字を並べたような模様が、白く浮き上がっていたからだ。いや、これはただの模様ではない。ベレムナイトの殻の内側にある隔壁だ。ベレムナイトは日本語では直角貝といい、中生代末に絶滅した頭足類の一種である。ものすごく大雑把に言えば、巻いていないアンモナイトだと思えばいい。大理石は海洋性プランクトンである放散虫の死骸が海底に降り積もってできるものだから、いろんな海洋生物の化石が含まれることも多いのだ。そうやって這いつくばるように階段を検分していたら、フロント係に怪訝な顔で「ミスター、どうかしましたか?」と声をかけられてしまった。
松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)
インターメディアテク・レコード・コレクション(9)
ありがたき海賊盤
ストリーミングやダウンロードの時代に、レコード会社は権利を守って従来の利益を上げる方策に苦慮している。ところが音楽産業黎明期は随分デタラメな時代だった。サンプリングはおろか、引用や盗作は当たり前で、レコードを違法に複製した「海賊版」も大量に出回っていた。しかし、ありがたい海賊版もある。1939年8月にベニー・グッドマンのバンドに入団したチャーリー・クリスチャンは、SP盤が許す短い演奏時間内で、驚異的なソロを残している。しかし一日の仕事が終わると、クリスチャンはハーレム地区の「ミントンズ・プレイハウス」でケニー・クラークら若き仲間と夜明けまで共演していたという。グッドマンの束縛や録音の制限から解放され、より自由に実験していた。そこに、若きジャズ・ファンのジェリー・ニューマンが録音装置を持ち込み、その録音をレコードとして発売した。当時、権利をクリアしたとは到底思えないが、この海賊版はいまや、急死したクリスチャンの本来のスタイルを知るうえで欠かせないものになった。
大澤啓(東京大学総合研究博物館特任研究員)
インターメディアテク・レコード・コレクション(8)
テナーサックスの誕生
ミュージアム・コレクションに漆黒のSPレコードが数千枚並ぶなか、特別な重みを持つアイテムがいくつかある。なかでもどのジャズ・ファンでも敬愛する一枚が、ブルーバードB10523番として発売された10インチ盤である。紺色のラベルには蓄音機に耳を傾ける犬の絵(ヴィクター社のロゴ「ニッパー」)、レーベル名とコールマン・ホーキンス・オーケストラの名前、そして曲名「身も心も」が金色で印字されている。レコードに針を落とすと、3分間の完全なる至福がくり広がる。1939年10月11日、5年に亘る欧州滞在を経たホーキンスがニューヨークのスタジオで吹き込んだのは、当時スタンダードの格にまで至ってなかった1930年作曲のバラードだった。ところがホーキンスは曲の主旋律にほぼ言及せず、熟練の技量を披露すべく、重層的な即興に臨んだ。曲が終わると、「身も心も」がようやく最終形に至ったという実感とともに、ここでモダン・テナーサックスが生まれたことが分かる。A面があまりにも有名なので、B面の「ファイン・ディナー」をそっくり見落としてしまう人は少なくない。
大澤啓(東京大学総合研究博物館特任研究員)
エクス・リブリス
フレデリック・ワイズマン監督の映画『ニューヨーク公共図書館 エクス・リブリス』(2017年)。本館を含む計92館からなる図書館システムの舞台裏を取材したドキュメンタリーである。図書館に関わるさまざまな立場の人間にフォーカスすることで、公共施設の実態と課題をさぐり出す。「図書館は単なる書庫ではない。何かを知りたい人々が集まる場である」 作中の建築家の発言が本作の性格を言いあてている。ワイズマンは施設の事前リサーチをしないという。205分の作品を貫く制作者のポリシーを二つ感じた。第一に「言葉の連なりの抽出」である。会議や講座などの諸活動での発言を、主張への評価を交えずに次々にすくい取る。これらの言葉は作品内で徐々に連関し、多様な課題に気づく契機となる。第二に「顔の表情の描写」である。喋る人間のみならず、それを聞く人間の風貌も実におびただしい。多様な人種、民族、職能をめぐる生きたコミュニケーションの記録である。「言葉の連なり」と「顔の表情」は、絶妙な相互作用によって、映像に不断の持続性と固有性をもたらしている。公共性とは何かという単独の結論には向かわない。ワイズマンの驚異的な統合の直観によって再構築された、多元文化に開かれた場所への讃歌である。「エクス・リブリス」の名の通り、この見応えのある分厚いホンも図書館の蔵書の一つになる。
松本文夫(東京大学総合研究博物館特任教授)
博物館とフィジカル
と言っても、美術における身体表現とかそういう話ではない。展示設営はひたすら手作業と力仕事、つまりフィジカルだという話。現在開催中の「Aves Japonicae5」を例にとろう。バックヤードからテーブルの脚と天板を運び出す。邪魔になりそうな標本を一時避難させる。棚板の高さを変えてある場所、棚板を抜いてある場所は、元に戻す(棚板は木材と鉄板で、かなり重い)。スチールの脚を棚とガラス壁の間に設置し、天板を抱いて同じ隙間に入り、標本をはたき落とさないよう細心の注意を払って天板を置く。これを3回繰り返す。そしてやっと、棚の裏から棚板の間に上半身を突っ込んで列品作業である。だが、収蔵展示室で作業するものとして、フィジカル面で最も重要なのはそこではない。展示室の角、オナガドリの後方にある棚の隙間、ここに体をねじ込んで通り抜けられるかどうかが、行動の自由度を大きく左右する。これ以上太ることは許されないのである。
松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)
インターメディアテク・レコード・コレクション(7)
アルバムの可能性
クラシック音楽では数十分に及ぶ作品はごく当たり前にある。10インチSP盤には3分半しか収録できないことから、レコード会社は早くも一つの作品を分割して複数のレコードに収めた「アルバム」という形式を採った。ジャズメンは逆に、一枚のレコードに収まるように演奏自体を構成した。一方、クラシック音楽のアルバムに倣って1933年にブランズヴィック社が企画した『ブラックバーズ・オフ1928』を発端に、ミュージカルやジャズのSPを束ねたアルバムも普及した。アルバムには表紙があり、ライナーノートが付く。それまでレコードのラベルに範囲が留まっていたグラフィック・デザインが、レコードという商品に全面的に施されるようになる。ジャズ・アルバムの金字塔は、SP時代末期の1949年にノーマン・グランツが制作した『ザ・ジャズ・シーン』だ。グランツは、このコンセプト・アルバムを同時代のジャズの「鏡」と見なし、選んだミュージシャンを自由に演奏させ、曲に自身が解説を添え、ジョン・ミリの写真とデイヴィッド・ストーン・マーティンのイラストを挿入した。しかし不思議なことに、SP盤の技術的限界から解放された現在でも、大抵のポップソングはいまだに3-4分を超えない。
大澤啓(東京大学総合研究博物館特任研究員)
ブルーノ・タウト
高崎の碓氷川を臨む少林山達磨寺の境内に「洗心亭」という建物がある。もともとは東京帝国大学の佐藤寛次教授の別荘として建てられた2間(6畳・4畳半)の庵である。ドイツの建築家ブルーノ・タウトは、パートナーのエリカ・ヴィティヒと共に、2年2ヶ月をここで過ごした。タウトは表現主義的モニュメントや集合住宅の設計で知られる気鋭の建築家であったが、ナチス政権の台頭により逃亡を余儀なくされた。1933年5月から約3年半にわたって日本に滞在し、その間、日本の文化や美について多くの論考を残した。日光東照宮と対比して桂離宮を賞賛したことはよく知られており、また新しい建築では東京中央郵便局(現KITTE)を高く評価した。タウトの著書『日本の家屋とその生活』の仔細な観察からは、洗心亭での慎ましい生活を心から楽しんでいたことがうかがえる。「貧は今でも日本人には無意識的に一種の理想的状態とせられており、従って美学の真の基礎をなしているのだ」と述べている。「いかもの」を嫌い、ミニマルな美に豊かさを見出したタウトらしい言葉である。奇しくも高崎の地は、実業家・井上房一郎らを介してブルーノ・タウトやアントニン・レーモンドが足跡を残し、日本のモダニズムの揺籃を支える固有の場所となった。
松本文夫(東京大学総合研究博物館特任教授)
新建材
鳥は自然にあるものを使って巣を作る。だが、それは自然物だから使うわけではない。長さ、強度、弾力性など、機械的特性を満たしていれば巣材として使える。例えば、ヒヨドリやスズメは藁など枯れた植物を使って営巣するが、代わりにビニール紐を使うこともよくある。実際、巣を調べると、ビニールの切れ端やティッシュペーパーまでもが巣材に混じっていることはよくある。彼らの目を通すと、そういった人工物も「使えそうな巣材」なのだ。新建材の利用で有名なのはカラスで、彼らは針金ハンガーをよく利用する。だが、近年はハンガーの材質がプラスチックに変わり、クリーニング屋がつけてくるのも簡易なプラハンガーになった。ところがカラスもこれに適応し、新・新建材としてプラハンガーも使い出したようである。ただ、それでも針金ハンガーの利用は非常に目立つ。プラハンガーの普及度に比べて利用頻度が低いのは、やはり針金の方が自在に曲げられて使いやすいのかもしれない。
松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)
インターメディアテク・レコード・コレクション(6)
スキャット伝説
ジャズ演奏のなかで独自のスタイルを持った歌唱が定着し、ヴォーカル・ジャズがジャンルとして成立したのは1920年代後半のことである。1925年末にバンドを立ち上げ、積極的に歌い始めたルイ・アームストロングの貢献は少なくない。当時流行していた白人のポピュラー音楽における滑らかにして古風な歌に対し、「サッチモ(アームストロングの愛称)」のざらざらした声が一世を風靡したこと自体が象徴的な現象だった。ところが歌手サッチモにはもう一つの業績がある。1926年2月26日、オーケー社のシカゴ・スタジオで、ヴァイオリン奏者ボイド・アトキンズ作曲の「ヒービー・ジービーズ」が吹き込まれる。これは録音に立ち会った伴奏者たちやプロデューサーものちに裏付けた話だが、アームストロングの回想によると、彼は歌詞が書かれた紙を手にして歌っていたが、紙を落としてしまい、録音を無駄にしないために、応急処置として無意味の音を羅列して歌い続けた。そこで「スキャットが生まれた」という伝説がいまだに根強い。実際のところ、クリフ・エドワーズやドン・レッドマンが先にスキャットを吹き込んでいるのだが、彼らはこのような「伝説」を産むには至らなかった。
大澤啓(東京大学総合研究博物館特任研究員)
鳥の眼
日本画家が極めて写実的に鳥を描けたのは、粉本を見れば明らかである。ただ一つだけ、不可解なほどに定型的に描かれているのが、眼だ。日本画の鳥の眼は必ず眼輪に囲まれ、ややアーモンド型をなして、白い虹彩に対して瞳が小さく黒い。つまり、コワモテな三白眼である。実際の鳥の眼は虹彩の色が様々で、カラスのように暗色の虹彩を持つ場合、全体が黒く見える。つまり、決して一様な三白眼ではない。この点はリアルさを欠くと言えよう。だが、鳥の眼がカワイイものと思い込むのも間違いだ。進化的に見れば鳥は恐竜の一派であり、その意味ではまぎれもなく、爬虫類と深い関係がある。ウロコ状の皮膚に縁取られた眼はイグアナにも似て、鳥が決してカワイイだけの存在ではないことも、物語っている。目の周りの白いリングで知られるメジロだって、かわいく見えるのは遠目に見た時だけだ。あなたがメジロを覗き込むとき、メジロもまた、あなたを覗き込むことを忘れてはいけない。
松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)
インターメディアテク・レコード・コレクション(5)
ブルーノートに謎のピンク色
新商品のシリーズを展開するにあたって、その内容はどうであれ、まずは統一的な「ヴィジュアル・アイデンティティ」を定め、購買欲を促すのは、いまや当然なことである。だがレコード産業黎明期においてはそうでなかった。早くもマーケティングのプロトコルを定めていたエディソンを除くと、多くのレコード会社には様々な迷いがあったようだ。同時期のレコードのレーベルに複数のロゴや相性の悪いフォントを載せるなど、製作者の方針は、いっそ羨ましく思えるほどいい加減だった。そこに、妥協のない音楽制作と徹底したモダン・グラフィック・デザインで新たな風を吹かせたのが、アルフレッド・ライオンらが1939年に設立した伝説のブルー・ノート社である。SP盤の丸いラベルの右上には白地の長方形に青字でレコード情報が掲載され、残りの青地の部分には会社名が白字で大きく載っていた。LP盤時代に入ると、フランシス・ウォルフらの写真が飾るジャケットがさらに有名になる。ところが、ブルーノート社でさえ、そのヴィジュアル・アイデンティティが定まるまで、初期はグラフィック・デザインに迷いがあったようだ。目録番号1番の12インチ盤のレーベルは、白地の部分がなぜかピンク色で埋められ、2番以降も10枚ほど、その部分が黄緑になっている。
大澤啓(東京大学総合研究博物館特任研究員)
再び、君の名は
特別展示『Aves Japonicae5 〜色彩の迷宮〜』が開催中である。今回は河辺華挙による「鳥類写生図」の他に、作者未詳の「鳥類真画」を展示に加えることにした。この絵画の特徴は、とにかく「フカワリ」すなわち色彩変異にこだわって記録されていることである。現代の鳥類学的な興味というよりも、変わり朝顔や金魚、あるいはチャボの変種を楽しむような雰囲気が伝わって来る。ところが、肝心の鳥の種類がわからないのだ。例えば「ツグミフカワリ」とあるのは、作者はツグミの色彩変異だと思っている。しかし、単色で描かれた背と翼、黒い頭、赤っぽい腹は、あきらかにツグミではない。赤い腹を素直に解釈すればアカハラで、多少、赤に誇張があるとすれば、脇腹にやや橙色味のあるシロハラかもしれない。どちらも頭が黒っぽい変異もあるのだ。さらに言えば、頭が明確に黒いアカコッコの可能性さえある。アカコッコは伊豆諸島に行かないといないから、知らなくても不思議はない。さあ、この「フカワリ」は誰だ。
松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)
コンポジション
芸術家の名前を聞いて、その作品のイメージを思い浮かべる。瞬時に想起できる場合もあれば、漠然として結像しにくい場合もあるだろう。ピエト・モンドリアンは、明瞭にイメージしやすい作家の一人ではないか。水平・垂直の線と赤・青・黄色などの領域で構成された図像がすぐに呼び起こせる。しかし実際に描こうとすれば、見かけほど単純ではないことがわかる。領域の大きさ、線の太さ、交差と停止、白の抜け、色の配置、端部の始末。これらは、モンドリアンが試行錯誤を繰り返してきた部分である。初期の樹木のシリーズからデ・ステイルの活動、そして渡米後の「ブギウギ」に至るまで、彼は常に「抽象」と向き合ってきた。それは何かをただ視覚的に省略することではない。「知覚をとびこえて直接、精神に働きかける」(岡崎乾二郎)という抽象の具体的な力が、モンドリアンの作品がもつ喚起力の原点にある。だからこそ、他の芸術家や、建築、モード、デザイン等の分野に大きな影響を与えてきた。写真は教養学部前期課程の授業「空間デザイン実習」における学生の作品である。「赤・黄・青・黒および窓のコンポジション」(藤堂真也)では、キューブ型の住居がモンドリアン的なグリッドで分割されている。色のパターンは各部屋に呼応しているが、内外の立体的な相互関係はむしろ流動的である。抽象の力が空間の拡張可能性につながっている。
松本文夫(東京大学総合研究博物館特任教授)
インターメディアテク・レコード・コレクション(4)
スーパーグループの誕生
チョコレート・ダンディーズ、ブルー・デヴィルズ、マッキニーズ・コットン・ピッカーズ、ニューオリンズ・フィートウォーマーズ。初期ジャズにおけるバンドの命名は黒人文化特有の不条理に満ちたユーモアを表している。レコードのラベルに印字された愉快なバンド名を読むと、それが20世紀音楽の行方を変えたとはとうてい思えない。なかでも、とりわけ間抜けな名前を与えられた伝説的なバンドを選ぶなら、迷わず「レッド・オニオン・ジャズ・ベイビーズ」を挙げる。ジャズにおける初の「スーパーグループ」となったこのクインテットの実績は、1924年末にジェネット社が録音した四曲に過ぎない。しかしその顔ぶれは申し分ない。クラレンス・ウィリアムズの企画で、ルイ・アームストロングがコルネット、バスター・ベイリーがクラリネット、リル・アームストロングがピアノを担当している。そして12月22日に吹き込まれた「ケークウォーキング・ベイビーズ」では、シドニー・ベシェがベイリーに代わり、初めてアームストロングと共に録音に臨んだ。初期ジャズの最も個性的な二人のソリストが再びスタジオで顔を合わせるのは1940年のことだった。
大澤啓(東京大学総合研究博物館特任研究員)
Lost in translation
カラスの撮影のために日本に来た海外の映画チームを案内して、渋谷を歩いた。といっても監督とカメラマン、音声、そして日本側コーディネイターの4人で、フットワークはすこぶる軽い。朝、ゴミを漁るカラスを撮影した後、私たちはセンター街のビルに登り、カラスと同じ視点から街を見た。眼下には人間のビジネスアワーが始まりつつある大都会。数時間前までは、歓楽街として賑わっていた辺りだ。そして、その二つの時間帯が切り替わる夜明け、徹夜で飲み歩いた人々が始発電車を待って引き上げる頃、ゴミを求めてハシブトガラスがやってくる。人間は地べたを、カラスたちは上空を、2つのレイヤーが重なり合うように、言葉の通じない2種の動物が、お互いを微妙に避けながらすれ違ってゆく。スイス人の監督がこの街を撮影したのは、ソフィア・コッポラの映画「Lost in translation」のスクランブル交差点のシーンが念頭にあったのではないか、と考えてしまった。
松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)
空間と図法
空間や立体物を2次元で表現するにはいくつかの図法がある。仮に直方体を描くとして、もともと平行な線を平行に描くのが平行投影法、点に収束するように描くのが中心投影法である。前者の例としては、真上から見た平面図、真横から見た立面図、斜め上から見た軸測投影図がある。一方後者は、線遠近法としても知られる透視図である。さまざまな図法は我々の空間概念の多様性に呼応している。先史時代のラスコー洞窟壁画では既に動物の並列/前後関係が描かれている。エジプト美術では人物を立面的に描き空間を上下に重ねていく。日本美術では平安以降の絵巻物等で軸測投影に近い図法が頻用される。西洋では中世以降に遠近表現が生まれ、ブルネレスキとアルベルティによって透視図法が理論化された。同じ大きさの物でも遠くにあるほど小さく見え、平行線であっても点に収束して見える。絵画における空間表現の展開は、このような実体と認識を架橋する方法の歴史でもある。フィレンツェのウフィツィ美術館には4人の画家による「受胎告知」がある。古い順に見ると、マルティーニでは物の前後関係が意識され、バルドヴィネッティでは遠近表現が顕在化し、ダ・ヴィンチにおいて透視図的な空間が完成し、ボッティチェッリでは空間の分割が精緻化する。図法は空間を発見するツールでもある。
松本文夫(東京大学総合研究博物館特任教授)
インターメディアテク・レコード・コレクション(3)
10インチと12インチの差
1920年代、録音が持つ可能性を自覚していなかった演奏家は少なくない。のちにポピュラー音楽のカリスマとなり、無数のレコードを出したファッツ・ウォーラーもその一人だった。若きウォーラーは、定職として映画館で上映の伴奏し、作曲したメロディーを音楽出版社に安価で譲り、生演奏で生計を立てていた。ところが1930年代からレコードが爆発的に売れるようになると、ウォーラーは気に入らないポップス・ソングを次々と吹き込まされるようになる。嫌気がさしたウォーラーはそのメロディーが崩れるまで大げさに歌うことが多々あったが、皮肉なことに、曲を崩せば崩すほど、レコードはよく売れた。とはいえ、ウォーラーは真剣な録音にも取り組んだ。1937年には4分半に及ぶ名演奏を2度吹き込んだが、その曲は10インチSP盤に収まるように約3分にカットされ、ヴィクター社25779盤として発売された。アンカットの録音が12インチ盤で発売されたのは、ずいぶん後のことだった。その理由は単純だった。1937年にはまだ、12インチはクラシック音楽の特権であり、ウォーラーの音楽は大判レコードに収録する価値がないとされていたからだった。
大澤啓(東京大学総合研究博物館特任研究員)
インターメディアテク・レコード・コレクション(2)
黒鳥が「カラー・ライン」を超えた時
ジャズ史は様々な観点から語られてきたが、ジャズの成長とともに生きた当事者たちは、生演奏のほか、ラジオとレコードを介してこの新たな音楽と接した。いまいちど「レコード」というものに立ち戻り、それを基軸にジャズ史を辿ると多くの発見がある。まずは、その黎明期においてジャズを実際に生み出した黒人ミュージシャンに録音の機会がほぼ与えられなかったことが分かる。ニューヨーク・ハーレム地区の「コットン・クラブ」をはじめ、名会場が黒人ミュージシャンと褐色の肌のダンサーを舞台に立たせながらも白人客のみを受け入れていたように、レコード会社も明確な差別を行っていた。1920年大ヒットしたマミー・スミスの「クレイジー・ブルース」を皮切りに黒人音楽のレコードが普及しても、それらは「レース・レコード」として別扱いされた。しかし、米国社会そしてジャズの基本条件であった「カラー・ライン」を早くも超えた男がいた。音楽出版社ハリー・ペースは1921年にハーレムで初の黒人経営によるレーベル「ブラック・スワン(黒鳥)」を立ち上げ、レコーディング・マネジャーとしてフレッチャー・ヘンダーソンを起用した。これが黒人によるいわゆる「インディー」系の先駆けとなった。
大澤啓(東京大学総合研究博物館特任研究員)
オーチユーの謎 その2
さて、以前にカラスバトの剥製台座に書き込まれた「オーチユー」という謎の言葉について書いた。オーチユー、という鳥は思い浮かばないが、よく似た名前の鳥ならいる。オウチュウである。オウチュウはアフリカから東南アジア、中国南部にかけて分布する鳥だ。全体に黒っぽいものが多く、長く二股になった尾の先が巻き上がっているのが特徴。さて、この鳥、中国語では「巻尾(チュンウェイ)」である。英語だとDrongoだが、もとはマダガスカル語だそうだ。学名はDicruridaeで、ギリシャ語のdikros(二股の)が起源らしい。いずれもオウチュウにはほど遠いが、なぜ、本人が分布もしない日本でだけ、オウチュウなどという名前がついているのか。ここで妄想をたくましくしてみよう。台湾や南方でオウチュウを見た日本人と現地人の間で「あの黒い鳥はなんだ」「烏鳩のことか? あれはオーチューだ」といったやり取りがあり、勘違いの果てに「オウチュウ」として定着した、というのはどうだろう。
松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)
インターメディアテク・レコード・コレクション(1)
「史上初」のジャズ録音
歴史は「出来事」を好む分野である。音楽史においても同様だ。「ジャズ」はその歴史から、起源も名前自体の由来も不明であって当然。しかし、誰もが合意できる「誕生日」を求める人は少なくない。定説によれば、ニューオリンズの白人オーケストラ「オリジナル・ディキシーランド・ジャス・バンド(ODJB)」が1917年2月26日にニューヨークで吹き込んだヴィクター社18255盤が史上初のジャズ・レコードとされている。その根拠として、レコードのラベルに初めて「ジャズ」(正確には「ジャス」)という単語が載ったことが挙げられる。ところがこのバンドはそれより一ヶ月早い1月30日にすでに二曲を録音しているが、ヴィクター社はそれらをすぐ発売しなかった。そもそも、19世紀末ニューオリンズの黒人やクレオール人の間で誕生したジャズは、白人が動物の叫び声を真似しながら黒人の音楽を演奏するODJBを待たずに、「ラグタイム」や「ブルース」の名ですでに録音されていた。ただ、そのレコードには「ジャズ」という単語が印字されていなかったのである。
大澤啓(東京大学総合研究博物館特任研究員)
考える模型
模型を作る目的は二つあると考えられる。一つはすでに存在する事物を正確に記録することであり、いま一つは未だに存在しない事物のイメージを示すことである。すなわち模型は事物の再現と予示に関わる。たとえば、図面資料に基づいて精緻な縮小版をつくる「完成模型」と、設計プロセスで無数に生み出される「スタディ模型」がある。前者は実物のフォルムやマテリアルの複製が主眼となり、熟達の専門家が制作することもある。かたや、後者はアイディアをカタチにする手段であり、設計者が自ら手を動かすことが多い。コトバやスケッチといった手段に比べて、模型は対象を突き放し、視点を客体化するところがある。制作途中の模型をいろいろな角度から見回し、納得できなければ延々と試作を繰り返す。これは何かを真似る模型ではなく、考える模型である。スタディ模型の制作はスピード勝負なので、作り方は意外とシンプルである。カタマリ系の手法とボード系の手法に大別できる。ボリュームを検討するときは、スタイロフォームに熱線カッターをあてて立体を直接切り出す。内部空間があるような模型では、スチレンボード等の厚紙を切って組み立てて作る。デザイン系の学生が最初に学ぶのは、こういった考える模型の方法である。
松本文夫(東京大学総合研究博物館特任教授)
オーチユーの謎
山階鳥類研究所より寄託されている標本の中に、カラスバトの剥製がある。この標本は明治時代のものと思われるが、台座に「土語 オーチユー」と墨書されている。はて、オーチユーとは? そんな地方名は聞いたことがない。第一、このユは小さいユの可能性もある。しばらく考えて、漢字で烏鳩と書いて中国語で読めば「オーヂュウ」「オーチュウ」「オーチョウ」などと聞こえるであろう、と気づいた。そうか! この鳥は山東省にも分布するから、これはきっと中国産で、現地語を書き込んであったのだ。ところがラベルには「アカガシラカラスバト」とも書いてある。これは困った。アカガシラカラスバトは小笠原固有亜種で、中国には分布しない。では小笠原に中国語が伝わって? 1826年から50年ほど、小笠原には様々な国の人が来ては去っていたようであるし、中国語が持ち込まれていたことも、あっただろうか? それとも、「アカガシラ」の方が間違い? 古い標本にはこういった謎と悩みが尽きない。
松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)
ラベル
標本には情報を示したラベルがつけられている。標本の管理用のものなので、展示状態で見えるとは限らないが、情報が読めなかったとしてもラベルが語ることは色々ある。書式の違うラベルが複数ついていれば、おそらく、複数の所蔵先を渡り歩いた結果である。種の同定が改められれば、「以下の理由で同定を改める」と書き込んだラベルも付く。書き方も様々だ。タイプ打ち、活版印刷、手書きと各種あるし、手書きの場合もその筆記具は鉛筆とペンがある。流麗な筆記体で描かれたペン字は味があるが、鉛筆にも大きな利点がある。鉛筆はアルコールや水で滲みにくく、また筆圧が高いので筆跡が残りやすい。液浸標本にラベルごと入れてしまうことも可能だ。ブロック体か筆記体かにも議論がある。ブロック体は万人に読みやすいが、筆記体は個人差があるため、誰が書いたものかを特定しやすいのである。当館で私が受け持つ標本には、IMT用に古風な二重枠線のラベルを作って取り付けることにしている。
松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)
デジタル時代の借景
現代美術館の展示会場に作品が並ぶなか、白い箱が空中に浮いている。長さ5メートルのスクリーン4面が箱を形作るように天井から吊られている。その内側に入ると、富士山の山頂に漂う雲の古い映像が連続的に投影されている。ある笠雲がスクリーンからスクリーンへと流れ、そしてまた他の雲が現れる。気象学者・阿部正直(1891-1966年)が1926年から継続的に撮影した雲のフィルムをアーカイブ化するなかで、「CLOUD BOX」と題した映像インスタレーションを構想した。空中に浮いている画面にあらゆる種類の雲が浮かび、屋内にある展示会場に一つの窓を切り開き、新たな時空間を生み出す。立ち位置によっては、雲が投影される画面が空中に浮いているように、もしくは壁に穴が開けられたように、あるいは天井自体が雲で覆われているようにも見える。日本庭園の基礎概念である「借景」をデジタル時代の現代美術館の会場で再解釈したものだ。写真は2017-2018年にニュルンベルク新美術館で開催された、日本の美学をテーマにした特別展示の会場風景。
大澤啓(東京大学総合研究博物館特任研究員)
牙の行方
IMTには今年の干支、イノシシの頭骨がいくつかある。イノシシは成長すると犬歯が長く伸び、口の外まで斜め上に突き出して来る。ではイノシシの牙は下顎から生えているのか? 答えは「半分正解」だ。イノシシの牙は上下にあるが、どちらも同じ向きに伸びる。こればかりは実物を見ていただかないと意味がわからないと思うが、上顎の歯槽の一部が横方向にはみ出して捲れ上がり、上顎の牙も横向きに生えて来るからだ。また、上下顎の犬歯は前後に並んでおり、しかもピタリと合わさるようになっている。口を閉じていると1本の牙のようにも見えるが、実際は2本だ。そして、合わせ目が常に磨かれているがゆえに、そのエッジは鈍角ながらも触れれば切れそうな鋭さを保ち、鉈や鎌といった「道具」としての凄みを漂わせている。もう一つ、奇怪な牙を持つのが東南アジアに住む、イノシシに近縁な動物であるバビルーサだ。これはもう、ここに書くよりも展示中の頭骨を見ていただく方が早い。何がどうなっているのか首をひねるのも一興である。
松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)
インターメディアデザイン その五
特別展示「アートか、サイエンスか」より
展示されている機器には、当時の最先端の技術を備えたドイツ、フランス、アメリカ製などの舶来品がある。文部省が交付したいわゆるオリジナルである。これらの高価であった機器の財政負担の軽減と普及のために、国内の数社によって模造が始まった。全てがコピーできたわけではないにせよ日本の物理学と技術発展に大きく貢献したのだ。そこには職人たちの試行錯誤と創意工夫、平たく言えば職人魂があったに違いない。なぜなら、教育用実験機器である限り、その成果が得られなければガラクタでしかない。言ってみれば、解のある方程式の公式を「製作」するようなものである。一方、その技量が別のベクトルを示したものが工芸や美術であり、ガラクタさえも意味を与えればアートになるのだ。そして、その中間には何があるだろうか。中間といっても分類上ではなく融合として。少なからず展示デザインはその部分に接触する。三角形の展示ケースに入れられた三角プリズム、旧式のエレベータ内に置かれた電話機、職人魂を魅せるには時に遊び心も必要である。人間はモノや構図を5分以上見なければ詳細に記憶できないらしい。深い洞察をもって見なければ、如何なる価値をも見い出すことはない。自己への教訓である。
関岡裕之(東京大学総合研究博物館特任准教授)
出版計画再構築中(13)
書物が好きで、しかも蒐集癖がある。すると身の回りの各所に本が平積みされ、やがてそれらが柱状に成長し始めることになる。私の場合、もっとも太い柱をなしているのが雑誌である。明治初めから戦前にかけ発行された美術雑誌を片端から集める。そう考え始めたのはかなり以前のことである。動機は紛れない。国内には本当の意味で頼りになる美術雑誌アーカイブがどこにも見当たらないという事実に気がついたからである。有力な出版社であるなら、少なくとも自社発行の雑誌くらい、社内のどこかにコンプリート・セットを保持していて不思議でない。否、そうあるべきであり、それが出版社の負うべき社会的な責任というべきものであろう。そう思っていたのであるが、その考えは見事に裏切られた。以来、文献については、公的機関、出版社、いずれにしても他者を当てにするのは止めよう。そう考えるようになったのである。古い雑誌を手許にして初めてわかることがある。巻末の編者・出版者の後記、彙報、投書、交換録といったものから読み取れる雑情報がそれである。神は細部に宿るの喩えを引くまでもない。
西野嘉章(インターメディアテク館長・東京大学総合研究博物館特任教授)
映画のような建築
建築を映画のように設計できるだろうか。建築も映画も「空間」が基調となり、そこで人間の活動が展開する。映画監督が執心しながら、建築家にはコントロールしがたいもの。それは「動き」と「時間」ではないか。フランスの哲学者ジル・ドゥルーズは、『シネマ1』および『シネマ2』において、運動イメージと時間イメージという概念を提起した。リュミエール兄弟による列車到着シーンのような時間が運動に従属する「運動イメージ」から、運動が時間に従属する光学的音声的状況としての「時間イメージ」への転換が映画のなかで起きているという。この考え方を受けとめるなら、おそらく建築側の関心は、運動や時間を今いちど空間に結びつける可能性を探ることにあるだろう。機能的なプログラムを一つの建築に対置させるのではなく、人間の意思と行動に依拠して「運動、時間、空間」を再編成し、ある種の「時空間連続体」を組み立てる。そのような建築は、道のような流れがあり、網目のような繋がりをうみ、モザイクのような多様性をもち、雲のような曖昧さをはらみ、そして何より、映画のような運動/時間の自由度があるものかもしれない。法政大学大学院の下吹越武人さんと、以上のようなテーマでデザインスタジオをやることになった。
松本文夫(東京大学総合研究博物館特任教授)
インターメディアデザイン その四
特別展示「アートか、サイエンスか」より
5年前に訪れた金沢県立自然史資料館の収蔵庫にて、思いがけないものに遭遇した。思わずこれは何ですか?と質問する。現在の金沢大学にあたる旧制第四高等学校で使用されていた教育用物理実験機器だという。その形状といい、色といい、その不思議なものは、自然界における不思議を垣間見せる装置であった。そして5年後に展示を実現することができた。それが本展である。展示デザインは、質感や色彩、モノのフォルムと展示造作とを対比させるのが常套手段である。確かにこれらが真白い空間に置かれていれば、それだけで美しい展示であろうことは容易に想像できる。しかしあえて逆手にとった。モノを構成しているのは、いわゆる鉄、ガラス、木材といった素朴な素材であるのに加えて、人の手といくつもの時代を経た「ほこり」をまとっている。当時の高価で貴重な教材に、多くの学生は食い入るような眼差しで実験を見守ったであろう。故に哀愁を醸し出している。そこには本物の時間が血液のように流れているのである。それと同調するように錆びた鉄枠の台座、ガラス板、飴色の壁面が空間を構成する。当時、文化祭があったとすれば、資金も資材もない学生たちは、こんな展示をしたのではなかろうか。そんな後味が残ればよいと思う。
関岡裕之(東京大学総合研究博物館特任准教授)
豚足から骨を取り出す28の方法 (1)お湯に浸ける
皆様平素よりご来館まことにありがとうございます。平成最後のクリスマスはいかがお過ごしでしたか? 自分は胃炎で苦しんでいました。1個目の豚足は、自分が博物館の標本として骨を取り出す際によく用いていた「お湯に浸ける」方法で対処しました。皮や筋など刃物を使って取り除き、指一本ごとネットに包み下処理をした豚足を水にいれ、一緒に70℃~75℃まで温度を上げていきます。沸騰はダメです。この方法は、料理で出汁を取る方法とほぼ一緒です。出汁を最後までとり切って骨だけが残る、それが「お湯に浸ける」方法です。今回の機材は特別なものではなく、炊飯器の保温機能を利用しました。7日ほど浸けると硬い筋や軟骨まで溶け、外側の軟部組織を取り除くことができますが、内側にある骨髄を取り除くためにはもう2週間かかります。温度変化で骨が割れないように4日おきにお湯を交換しながら浸けて、骨髄の脂も可能な限り抜いていきます。残念ながらそれでも完全には抜けきらないので、この後有機溶剤に漬け込んで脂を抜く必要があります。劣化が少なく、安心して触れる骨が得られるので、自分は好きな方法です。
中坪啓人(東京大学総合研究博物館特任研究員)
出版計画再構築中(12)
出版計画のなかには、近く刊行の約束されているものもなくはない。『前衛誌——未来派・ダダ・構成主義』の日本編二冊本がそれである。外国編二冊本を出版してから、すでに一年以上が経ってしまった。二〇世紀の両世界大戦間に実在した前衛芸術運動のネットワークをグローバルな視点から記述し尽くす。その大風呂敷な論題と取り組みを始めたのは、一九九〇年代のことであった。一部は国際芸術センター青森の年報に掲げられており、この連載を創刊以来二十年ものあいだ受け入れ続けてくれている同センターには感謝の言葉もない。書き続け、書き続け、気づいてみると、四百字詰め原稿用紙で五千枚、図版二千点超にもなっていた。出版が具体化するなかで、外国編と日本編の二部構成が現実的であるとの考えに至り、各々をさらにテキストと図版で二分冊化することになった。長い時間を費やした本には強い思い入れもある。装釘をどうするか、悩み始めればきりがない。中身を生かすも殺すも外装しだい。そう思いつつも、やはりエイッ、ヤァーと一気呵成の勢いで、腹を括らざるを得ないのである。
西野嘉章(インターメディアテク館長・東京大学総合研究博物館特任教授)
頭上の影
先日、冬鳥を観察に行った帰りに、埼玉県内の国道を通った時のことである。フロントガラス越しに頭上を横切る鳥の群れが見え始めた。カラスだ。だが、なんとなく尾が短い。その時、運転していた共同研究者が「電線!」と叫んだ。見上げると電線にずらりとカラスが並んでいる。私は窓にへばりつくように見上げ、小柄なカラスが混じっていることを確認した。「コクマルいます!」と告げると、ドライバーは国道を外れて左折し、裏道を通ってカラスが止まっていたあたりまで車を戻した。そこで見たのは、久しぶりの、冬の使者だった。ねぐらに戻る途中のミヤマガラスとコクマルガラスが集団で電線に止まり、休憩している。彼らは冬になると日本の田園地帯に飛来し、越冬する冬鳥だ。ミヤマガラスはハシボソガラスより少し小さく、コクマルガラスはうんと小さくてハトほどでしかない。個体数、成鳥/幼鳥比などを数えていると、ミヤマガラスたちは「からら」「からら」と鳴きながら次々に飛び立ち、ねぐらへ向かって行った。
松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)
東京大学の画工――近澤勝美
東京帝国大学が刊行した大学紀要に、論文筆者である大学研究者だけでなく、画工、つまり学術上の研究対象を専門に描く人物が深く関与していたことはあまり知られていない。特別展示『医家の風貌』(MODULE)に展示されている『帝国大学紀要医科』第四冊(1900年/東京大学総合研究博物館所蔵)の図版の片隅には、「K. Tikasawa del.」や「Lith. Y. Koshiba」の文字が小さくみえる。これによりこの図版はK. Tikasawaが描いた原画をもとに、小柴英創業の印刷会社で石版にされたものであることがわかる。私はK. Tikasawaとは近澤勝美のことだろうと考えている。近澤は静岡の士族出身で、東京医学校や東京大学に勤務し、『美術応用解剖学』(1892年)や『アヂソン氏皮膚病図』(1897年)等の医学分野の図を専門に手がけた人物であった。1874(明治7)年5月の東京医学校雇入に関する伺文書には、外科手術につき截断の形状を「生冩」し、薬物学の講義や薬局で扱う草花を「眞模」する要員として近澤を雇い入れたい旨が記されている(「職務進退」東京大学文書館所蔵)。図版にあらわされた腫瘍の断面や拡大した組織の描写は細密を極める。大学に奉職した画工が残した確かな仕事の痕跡をみることができる。
藏田愛子(東京大学総合研究博物館特任研究員)
豚足から骨を取り出す28の方法
皆様平素よりIMTへのご来館誠にありがとうございます。まだ来館されていない方は、ご来場をお待ちしております。ところで、平成最後の夏、皆様は何をされましたでしょうか? 私は豚足を10kg買いました。数えたら28個ありましたので、それぞれ別の方法で骨を取り出したいと思います。「骨を取り出す」は言い換えれば、骨の周りについている、軟骨や筋、筋肉、脂肪、皮膚、そして骨の内側の骨髄これらの軟部組織をすべて取り除いて、リン酸カルシウムの塊のみを取り出すことです。そして博物館としては、その骨を文字情報と共に標本として半永久的に保存したり研究などに用いるわけですから、薄い骨、細い骨尖った骨でも極力いたまないようにちょっと手間をかけて取り出します。一方ちょっといたんでもいいから簡単に安く骨を取り出せる方法もあり、そちらも合わせて試してみます。マニュアルとしては、書ききれないので"やってみた"程度のことしか書けませんが、日常生活にも「骨」っていっぱいあるんだなって思ってもらえれば幸いです。
中坪啓人(東京大学総合研究博物館特任研究員)
三宅秀書簡集成(1)――植物学者・白井光太郎(1863-1932)
当館所蔵三宅コレクションの書簡の一部を紹介していく。白井光太郎は東京帝国大学農科大学教授(1907-1925)で、わが国の菌学特に植物病理学の開祖である。森林植物学の開拓にも貢献、本草学史研究の先駆者でもある。白井から三宅秀(1848-1938)宛ての書簡は、阿部檪斎翁の事蹟についてご教示を賜ったことにより、取調の方針を得たとの礼状である。江戸後期の本草家・阿部檪斎(1805-1870)は採薬使として知られる阿部将翁の曾孫で、岩崎灌園に学び、文久元年(1861)咸臨丸による幕府の小笠原諸島調査に加わった人物である。白井の未完の著書『本草百家伝』(木村陽二郎編『白井光太郎著作集第VI巻』科学書院、1990年)に「阿部檪斎」の項目があり、そのための質疑応答であろう。白井は1910年、三宅が古道具屋で購入した腊葉帖の鑑定を依頼され、渋江長伯が文化年間に作製したものと判断している。後年には三宅の講演筆記寄贈に対し、白井は天明飢饉が黒砂糖の需要の契機であると教示するなど、分野を超えた二人の交流は長く続いた。
白石愛(東京大学総合研究博物館特任助教)
森の建築
植物学の大場秀章東京大学名誉教授に小石川分館の建築博物教室でご講演をいただいた。『生物共生のアーキテクチャ −−多様な生き物と共生する建築を考える』と題し、共生という視点から建築のあり方を根本から問い直すお話しであった(→ご講演のハンドアウト)。人間社会が自然と対立するのではなく、ヒトが生物多様性の一員であることを再認識し、自然との共生の途を探ることを提唱された。大場先生は、森に還るにふさわしい地域作りとして、建築が森に散在する岩や石のようにみえる修景をイメージされている。今回のご講演に合わせて、住居の変遷を示すモバイル展示が制作された。時計回りに、森林、洞穴、始原の小屋、竪穴式住居、高床式倉庫、組積造建築、ドミノ・システム、緑化建築が並び、再び森につながる円環状の構成をなしている。屋根をかける(小屋)、床をはる(高床)、壁をたてる(組積)といった技術によって、人間は自然から空間を獲得した。それを閉鎖・拡大・集積することで人工環境を増やしてきた。このような「囲い・隔てる」という建築の従来の役割に対して、「開き・結ぶ」ことで空間とその境界のあり方を再考することが求められているのではないか。自己完結的ではない相互依存的なアーキテクチャはどのようなものか。それを考えさせられる示唆多きお話しであった。
松本文夫(東京大学総合研究博物館特任教授)
出版計画再構築中(11)
書きかけたまま放置されている原稿がある。「雲の伯爵」こと阿部正直の評伝である。遺品が博物館へ寄贈され、展覧会を企画立案するなかで、阿倍の類稀な人物像に打たれ、世に知らしめずにいられないとの思いに囚われた。東京下町の料亭の大広間で「キネマトグラフ」の初上映会に立ち会い「動くイメージ」の魅力に取り憑かれた。齢八才のときのことである。十代半ばには自作の箱形カメラで、静止画だけでなく動画の獲得に成功している。今日云うところの「ドローン」に近いものを工作し、高いところから地上を見下ろす写真まで、大正時代に考えていたのである。江戸幕府で筆頭老中を務めた福山藩主の家を継ぎ、御一新後に「伯爵」となった正直は、一代で家督のすべてを富士山頂に生成する山雲の研究に費やした。「殿様の酔狂」と揶揄されながら、最終的に、雲の生成過程を動画で記録し、3Dで可視化してみせた正直の功績は、世界的に見ても画期的なものであった。「戦前」ということで忘却させるのは、あまりにもったいない人物なのである。
西野嘉章(インターメディアテク館長・東京大学総合研究博物館特任教授)
移動基地
IMTには年に2度、1週間の特別閉館がある。この間に行われるのが、標本点検。館内にある全ての展示ケースを開け、標本をじっくりと見る。破損や変化がないか、虫食いやカビの兆候がないかを確認し、害虫トラップを交換し、気になる「何か」があれば顕微鏡で正体を確かめる。単なる埃なら良いが、生物由来のものである場合、カツオブシムシなど標本害虫が発生している可能性もあるからだ。木造品の歪みやクラックの点検も行われる。さらに別班はバックヤードを含めて館内の清掃、整頓を行い、キャプションの追加・訂正・更新なども行う。この作業の間、標本点検に活躍するのがキャスター付きの作業テーブルだ。ここに工具箱、防虫剤、アルコール、ピンセット、柄付き針、文房具、掃除道具、館内マップ、ノートパソコンなど一切合切を乗せ、館内を縦横に移動しながら作業を進める。この1週間、作業テーブルの行くところが仕事場になり、テーブルは移動基地、あるいは防虫母艦となるのだ。
松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)
チャンディガール
インドに行ったのは2000年である。脳裏に深く刻まれることの多い旅だった。到着地のニューデリーでは無方向的な交通のカオスに驚愕し、ヴァラナシでは日常的な生と死の共存に感じ入り、ジャイプルでは宇宙観察の精緻な造形に瞠目し、ジャイサルメールでは砂漠を臨む高密都市に胸躍らせた。当時も垣間見えた急速な変化の流れに、今ならば圧倒されるだろう。一方、北部の都市チャンディガールには、他所とは異なる存在感があった。インド・パキスタンの分離独立によって生まれたパンジャーブ州の新州都は、ル・コルビュジエによって1950年代に計画された。巨匠建築家が晩年を費やした作品群は、インターナショナルでありながらリージョナルであり、パーソナルな世界観に裏打ちされている。コルビュジエ自身が世界に示したモダニズムの方法論が、地域や環境との応答を経て変容したさまを空間体験できる場所といえようか。当館小石川分館では特別展示「チャンディガールのル・コルビュジエ」を開催中である。東京大学建築学科の千葉学研究室の監修により、同研究室が制作したチャンディガール中枢部の建築模型3点と、コルビュジエのスケッチが展示されている。並びたつ安田講堂の模型からスケールが推し測れるが、その空間の大きさと密度に現地で身震いしたことを思い出す。(展示は2月11日まで。写真の総合庁舎の模型は継続展示)
松本文夫(東京大学総合研究博物館特任教授)
出版計画再構築中(10)
しばらく前のことになる。「プロレタリアート(無産者)」という言葉を「プロレタリ(ア)・アート」と読んでみたらどうか、という説に出合ってびっくりしたことがあった。この面白くも意味深な解釈を唱えたのは、あの荒俣宏さんである。戦前のプロレタリア文芸は言われるほど教条主義的なものでない、けっこうイケていて、とんでもないものがゴロゴロしている。それが荒俣さんの云わんとするところであった。私は私で、「プロレタリ(ア)・アート」という言葉を見て、我が意を得たり思った。荒俣さんが再評価したプロ文芸群の、それらの中身でなく、書籍としての外装に、尋常ならざるものを看取していたからである。大正末期から昭和初期にかけて、国内の無産者運動は、革命後の「新ロシア」にその範を求めた。印刷メディアがそうである。おそらく広く世界を見渡しても、当時の日本で印行されたプロ文芸書・労農雑誌のグラフィクスほど、「ロシア革命的なもの」は滅多にない。ということで、このまま過去の歴史として埋没させていまうのは惜しい。「赤(コミュニズム)」と「黒(アナーキズム)」の図版満載の本になると思う。
西野嘉章(インターメディアテク館長・東京大学総合研究博物館特任教授)
丸の内カラス事情2
丸の内のハシブトガラスペアは今年も元気だ。この春はまたしても、並木に巣をかけている。だが、今年は5月になって葉が十分に展開するまで待ったので、まだバレていないようである。撤去もされていない。だが、IMTのオフィスの、私のデスクの後ろの窓からは巣が見えている。もちろん裸眼では厳しいが、そのつもりで見れば「あれが巣」とわかるものは見える。双眼鏡なら完璧だ。時々観察していると、親鳥が給餌に来るのが見える。先日からは巣の中に頭を差し入れているので、中に雛がいるのだろう。せっかくなので三脚を立てて望遠鏡を乗せ、同僚にも見てもらった。ところが、「どれが巣かわからない」「葉っぱが茂りすぎて見えない」と大いに不評であった。鳥類学者としては、あれほど明確に見えていれば御の字なのだが…… それどころか、見上げるのではなく、水平方向に見えるだけでも大助かりなのである。
松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)
君の名は
館内に「カエル骨格標本コレクション」と銘打ったコーナーがある。キャプションには「明治10年代?/佐々木忠次郎か?」とある。博物館のキャプションがかくも曖昧なのはお叱りを受けそうだが、実際、こうとしか書きようがない。わかっていることは僅かだ。まず、この一連の標本は理学部から出たものである。一体だけ、ヨーロッパアカガエルの標本があるが、他のカエルたちは、鼻面の形状や頑丈な前足などから、全てヒキガエルとわかる。現在なら解剖実習にはウシガエルを用いるが、これは1920年代に日本に持ち込まれた移入種だ。それまで日本で入手しやすい大型のカエルはヒキガエルだった。つまり、この標本はウシガエルがいない時代のものだろう。その他、台座の特徴などを比較して、明治時代、それもかなり古いものと判断した。その時代にカエルを解剖し続けたというと、モースやホイットマンの下で動物学を学んだ佐々木忠次郎か? とまあ、こういう推論をしてのことである。
松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)
展示空間としての図録
特別展示『石の想像界』の図録は、展示の延長線上に考えられた。石の外皮のように、図録の外装はグレーでザラザラしている。表の写真は石器、裏の写真は結晶模型。この対比が、銀色の縦型の帯に印字されている展示のタイトルを示唆する。帯を外し、本を開くと、貴石の内側のように輝かしい、青い内表紙が見える。ポートフォリオのようにページは全て未綴じで、不用意に開くとバラバラになる。斜め読みするのに決して便利ではない。本文が銀の冊子に纏められ、図版ページはポスター仕様の白い紙に印刷されていて、折られた状態で六枚収まっている。個々のポスターを広げると、テーマ別に分類されている図版が自由に配置されており、綴じられた本のページに連続的に掲載される図版とは異なる、より複雑な関係性を持っている。この特殊な仕様によって、展示の空間的体験を紙上に再解釈してみせた。展示空間を自由に歩き回るように、読書体験は直線的な展開から解放される。
大澤啓(東京大学総合研究博物館特任研究員)
改めて、謹賀新年。
施設のオープンから丸五年が経過し、つつがなく六年目の春が迎えられることを、スタッフ一同で言祝ぎたい。光陰矢の如し、とはよく言ったものである。たしかに、過ぎ去りゆく時間の流れは捉え難い。とはいえ、その経過を可視化できないものだろうか、そのような考えに端を発して始められたプロジェクトがある。それは、長期に亘る「展示」が標本にどのようなダメージを与えるかという問いと通底し合う。たとえば油彩画の場合、長時間に亘る光の照射がいかなる経年変化を作品にもたらすか、それを光学的に実証してみせようとする試みである。高橋勝蔵の描いた医学部解剖学教室初代教授『田口和美像』は、学内に残された最古の公的肖像画と目される貴重な学術遺産であるが、画面の劣化が進み、保存上、危機的な状態にあった。開館時から展示されていたが、洗浄修復を経て、見事に生まれ変わった。この間の変容するさまを、カメラで定点観測し続けてきたのが松本文夫特任教授である。画面の表情の僅かな変化を定期的に記録し続けるには、多大な労力と忍耐が求められる。ミュージアムは、表立った、華やかな事業ばかりでなく、このような地道な活動にも支えられている。五年間の安定した運営の基盤もそこにある。この一年も、国内外の機関・個人から実に多くの支援と鞭撻を賜った。この場を借りて御礼申し上げるとともに、新たな気持ちで新年を迎えることのできる幸せを感じている。改めて、謹賀新年。
西野嘉章(インターメディアテク館長・東京大学総合研究博物館特任教授)
用途不明の機能美
バナーストーンは、縦長の穴の空いた、左右対称の磨製石のアーティファクトであり、北米に出土する。北米考古学において、平たいベースに斜めの穿孔が二つ開けられ、抽象化された鳥や動物を表すバードストーンとともに用途が究明されていない「問題の形」である。祭儀物として埋葬され、時には装飾品として使用されていたというのが定説である。1939年に発行された先駆的な研究書で、バイロン・ノックブロックはバナーストーンを8つの原型に属する32のタイプに分類した。展示中のバナーストンには、砂時計型、三日月型、鞍型、蝶型がある。完成度の高い磨き、ビュアな輪郭、そして石の豊かな模様。完全なる造形美を持ち合わせたこのアーティファクトは、用途が不明であるがゆえに、抽象的彫刻の原型にも見える。
大澤啓(東京大学総合研究博物館特任研究員)
彫刻の記憶
石といえば石彫。古典美術においてごく当たり前であったこの公式が、現代美術において通用しなくなった。美術の古典的なジャンルが崩壊し、「インスタレーション」や「ミクストメディア」など複数のジャンルを横断する作品が増えるなか、石を淡々と彫刻作品に仕上げる作家が減ったからである。モデルをスキャンし、そのデータから3Dプリンターで立体物を自動的に製造できる時代には、彫刻技術自体が工業化している。一方、失われつつある彫刻技術への哀愁を漂わせる作品が多く観られる。シャルロット・モフの石版シリーズ『思考する作業、作業する思考』(2012-2013年)は、パリの広場に設置されたジュール・パンダリエスの大理石彫刻作品『労働者の休息』を部分的に撮影し、反復的にプリントしたものである。
大澤啓(東京大学総合研究博物館特任研究員)
大槌文化ハウス
東日本大震災から7年9ヶ月がたった。東京大学総合研究博物館は、岩手県大槌町の復興支援のために2013年9月に「大槌文化ハウス」を設営した。中央公民館の一室に人が集う大テーブルと3500冊の寄贈図書を配した小さな文化施設である。オープン後の中核的な活動の一つとして、社会教育プログラム「東大教室@大槌」を実施してきた。東京大学の研究者を講師とする教室が合計60回開催され、地元の熱心な参加者の方々に支えられた。東大教室を開始して5年を経て、今年の10月にその活動を一旦終了した。今までの教室のテーマは、自然誌系から文化誌系、海洋資源からまちづくりまで多岐に渡った。ここで紹介された先端研究が、大槌の地域資源の再発見や創出に結びつくことを願うばかりである。この間、復興事業の進展によって新しい街の姿が少しずつ現われてきた。盛土された中心市街地が整備され、鉄道が再び敷設され、高さ14.5mの防潮堤が建ち上がる。一方で、保存問題で揺れた旧役場庁舎は惜しくも解体が決まり、貴重な湧水・自噴井の多くが姿を消した。未来の大槌の姿はまだ構築途上である。最終回の東大教室では、大槌文化ハウスの設立起案者である西野嘉章特任教授(元当館館長)にお話しをいただいた。西野教授はノルウェーの北極圏で進められている文化事業「アートスケープ」を紹介しつつ、防潮堤などを含む被災地の新たな居住環境を積極的に文化芸術活動に取り込むことを提言された。被災地では長い時間を経て、震災復興から日常回復へ、そして文化蓄積へと徐々に向かいつつある。
松本文夫(東京大学総合研究博物館特任教授)
トロンプルイユ
スウェーデンなど大理石資源の乏しい地域では、城や豪邸の室内壁を大理石に見せかけるように、騙し絵(トロンプルイユ)の技術を持って木版を塗装していた。さらに時代を遡ると、ファン・エイク兄弟による『ヘントの祭壇画』(『神秘の子羊』)など多翼祭壇画のパネルには、空間の奥行きを表現するために建築的要素や彫刻が騙し絵で表現されている。騙し絵は文字通り絵画の技法であり、平面を観ながら奥行きや素材感の錯覚を覚えるように工夫されている。ではトロンプルイユを絵画以外の分野に用いたらどうなるか。開催中の『石の想像界』展には、さまざまな「石」が展示されている。その「石」は銅、ポリウレタン、紙、食品用着色料などありとあらゆる素材でできてある。鑑賞者が「石」という概念を念頭にそれらと向き合うと、期待が外れる。トロンプルイユの偽石は極めて軽量であったり、極薄であったり、溶けたりすることもある。これらの作品は、石の外見を保持しつつ、石を石として認識するうえで最も重要な特徴を除外している。
大澤啓(東京大学総合研究博物館特任研究員)
自然界のレディメイド
小石、石、岩、露頭、岩壁。ミュージアムや画廊に行くと、規模や形状を問わず、様々な「石」が原形のまま、「作品」として展示会場に置かれている。数千年にわたる複雑な気象要因によって形作られた石は、それぞれ固有のフォルムを持つ既成の彫刻である。マルセル・デュシャンが日常的な工業製品を「レディメイド作品」として美術展に運び込んだように、石が「自然のレディメイド」としてそのまま作品に組み込まれている。天産物である石を環境と文脈から切り離すことによって、その形とテクスチュア、その影やその生成方法は新たなイメージや物語を生み出す。工業製品と違って、石には人間の想像を絶する時間性が宿る。「ファウンド・オブジェクト」としての石を作品に組み込むことによって、その作品自体が、人類を超越する次元に開かれる。しかしそのなかで、芸術家の仕事は一体とこにあるのか。石を細かく刻み込む彫刻家とは対照的に、レディメイド作家は物質の移動と組み合わせ、そして脱文脈化によって「作品」を生み出す。写真はシグルドゥール・アルニ・シグルドソン作の『隠れた世界の陰(犬)』(2018年)。
大澤啓(東京大学総合研究博物館特任研究員)
地上13mのサバの頭
と書いてもなんの事やらわからないと思うが、起こったことをありのままに話そう。オフィスで作業中、私のすぐ後ろの窓をかすめて黒いものが飛んだ。カラスだ! 近い! と思ったら、2メートルほど離れた窓辺にヒョイと止まった。ガラスの向こうに20センチほど、平らな場所があるからだ。カラスはそこに止まって、くわえていた物を置いた。そして、つつこうとして顔をあげ、私がじっと見ているのに気づいた。カラスは慌てて逃げ出し、オフィスの外を旋回しながら「カア、カア、カア」と未練たらしく鳴いた。こういう時、カラスは餌を捨てて逃げる。やはり命の方が大事である。それはともかく、カラスが置いて行ったのは、サバの頭であった。切り口がきれいなので、包丁で捌いたもの……居酒屋のゴミ袋からでも持ってきたのであろう。このサバの出所がわかれば、カラスの行動圏が推測できるはずだ。野外調査は大手町のガード下から始めてみよう。
松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)
出版計画再構築中(9)
いずれは出版にこぎ着けたい、そう考えていた本の一つがキリスト教図像学に関するものであった。専門家向けの浩瀚な書物など、もはや望むべくもない。一般の人がキリスト教美術について理解を深められるようなコンパクト版で充分なのである。実のところ、キリスト教美術に特化された概説書が、国内では見当たらない。ましてやデジタル媒体全盛期の今日である。人文学としての美術史学に対する関心は、ゆるやかな下降曲線を辿りつつある。その上、キリスト教美術である。興味がない、と言われればそれまでなのかもしれない。しかし、キリスト教美術は、神学という巨大な「知」の体系を背景にもっている。ために、その図像学もまた、繙きがいがあって飽きない。理解が及べば、及ぶほど面白い。この実感を読者と分かち合える本を書き上げたい。弘前大学へ奉職して以来の宿願なのである。
西野嘉章(インターメディアテク館長・東京大学総合研究博物館特任教授)
石のインデックス
長さ5センチ、幅3センチのガラス板が800枚も並ぶインスタレーション『石のインデックス』。写真スライドにも見える、多様な模様が鮮やかに映るこれらのガラス板は、実は石である。1959年頃から1970年頃まで岩手県野田玉川鉱山、群馬県花輪鉱山、愛知県田口鉱山など国内各地で採集され、偏光顕微鏡で観察するために0.03ミリ程度の厚さに研磨した石の薄片から、石の知られざる「内面」がうかがえる。しかし、現代美術の文脈で展示されると、これら鉱物学標本は、インスタレーション作品となる。各プレパラートには、地図あるいは航空写真あるいは小宇宙のように、謎の「風景」が現れる。鉱物の同定や構造解析に役立った標本が、美的な視線の対象となった途端、詩的な表現のインスピレーション、抽象的な視覚表現の見本に見えてくる。文字通りの「石の想像界」である。
大澤啓(東京大学総合研究博物館特任研究員)
アートとアーティファクト
特別展示『石の想像界』の会場には、三つの「石器」が並んでいる。ひとつは、縄文時代前期のものと思われる、埼玉県ふじみ野市川崎遺跡で発掘された、正真正銘の磨製石斧である。もうひとつは、木製の手のマネキンに樹脂製の石器レプリカがはまっている彫刻、マチュー・メルシエの新作『アカデミア』である。三つ目は、人の右手が磨製石を延々と回している、ループ映像作品。ガブリエル・オロスコの有名なビデオ『丸石と手』である。だれもが片手にスマートホンを握っている時代に、石器を握るという原始的な仕草に改めて注目する作品が多く見受けられる。しかしこれらの作家は、いったいどのような「石」をもとにこの作品を考えたのか。「アート」と「アーティファクト」が混在する展示会場では、人類にとっての石の機能が問われるだけではなく、普段ホワイトキューブで発表される現代美術作品が人類学的なテーマを取り上げるうえで、どのような空間、展示方法、文化的文脈を前提とするのか、改めて考える機会となる。
大澤啓(東京大学総合研究博物館特任研究員)
「山越」のウシ解剖模型
IMTの2階に、ウシ解剖模型がある。紙製のそれはホルスタイン牛を象った縮小模型であり、背中を開くと、取り外し可能な臓器の模型が収められている。左半身の筋肉はむき出しで、教室にある人体模型を思い起こさせる。ラベルには「合資会社山越教育標本器械製作所製作」の文字。詳しい情報はほとんどないが、同じくIMTの2階にあるキノコ模型を製作した「山越工作所」と似た名前であるのが気になった。「合資会社山越教育標本器械製作所」の名前は、昭和14(1939)年の『帝国銀行会社要録』に初めて記載が認められるが、翌年に姿を消している。本模型の作成された年代は昭和14(1939)年頃と見て間違いないであろう。『帝国銀行会社要録』では、その前年の昭和13(1938)年から、『日本全国銀行会社録』では、昭和14(1939)年から、「山越工作所」の改組で誕生した「株式会社山越製作所」の記載が始まっている。2つの記録を見ると、合資会社は「滝野川区田端新町二ノ二九」、株式会社は「下谷区御徒町三ノ一」と、異なる住所が記されている。しかし、「山越工作所」の目録では、同営業所の住所が「東京市下谷区御徒町三丁目」、同工場の住所が「東京市滝野川区田端新町二丁目」となっていることから、両者が同一組織である可能性は高い。
秋篠宮眞子(東京大学総合研究博物館特任研究員)
比喩としての石切場
地球上に鉱物的世界が存在するとしたら、洞窟がそのイメージに最も近い。ラスコーやショーヴェ洞窟の壁画は原始絵画の傑作として賞賛されるが、同様に、洞窟そのものも、人類の最初の住居そして原始彫刻の傑作として見なすことができる。植物のない洞窟は、岩の多い不毛の地と同じように、人類の原風景を想起させる。石の想像界の根底には、独自の時間性を有する地殻、有機的な生命界から独立した物質のイメージがある。この物体には特定の形がないため、人間が無形の物質に対して感じる恐怖の対象にもなる。豊かな土壌に育つ植物界と有機物は常に、その底に広がる無機の露頭に飲み込まれ、無形の状態に戻る恐れがあるからである。ヒトが石に施す基本的な行為は、まず石を石として無形の地殻から切り離すことである。その瞬間に、石切場が生まれる。露頭や岩から破片が切り出され、意図的なフォルムを与えられた途端、石が誕生し、有益な材料として人間の活動域に組み込まれる。その意味では、石切場はヒトによるあらゆる創造活動を連想させる。ヒトが無形の物質を有形のものに加工する基本的活動であり、抵抗する物質を材料に変えるプロセスである。とはいえ、地殻から切り出された石はその後も、本来の特徴を続けて持ち合わせる。地質的世界の名残として、石は人間の意図に抵抗し、人間の活動域に置かれても反応しない。
大澤啓(東京大学総合研究博物館特任研究員)
インターメディアデザイン その三
同じことを言っているようにも思うが、あえて言い換えるなら、大方の博物館はすでに体系化されたモノを「見る・知る・学ぶ」をテーマに視覚的に再構築されたもので、社会あるいは来館者にとっての知的好奇心を、もっとも正当な方法論で応える場となっている。それは人間社会における「秩序」でありながらも、人間であるからこそ避けられない結論でもあろう。しかし、その秩序のなかでは「発見」は難しい。なにも専門家に向けたアンチテーゼではなく、一度シャッフルしたなかでこそ垣間見える新しい価値や創造性は、インターメディアテクが多くの人々に刺激を与える所以ともなっている。「見たことがあるようで見たことがない」そのことが人々を感慨に導く重要な要因であり、それは、唯一無二というよりも現代版温故知新というべきかもしれない。
関岡裕之(東京大学総合研究博物館特任准教授)
展示とインテリアのはざま
展示空間と建築インテリアとは同じ空間でありながら性格や表情に違いがある。展示空間は資料や標本の観覧が目的であるため、主役は展示物であり、建築インテリアとはそもそも訴求ポイントが違う。当館本館では現在「珠玉の昆虫標本」というタイトルの展覧会を開催中である。本展では壁という壁の全てを標本箱に入った昆虫標本で埋め尽くしている。デザインとしては、まぎれもなく生き物である昆虫が壁になって空間を構成するとすればどのような空間になるのかを極限にまで近づける実験だ。面白いことに近づいて見ると一つひとつは当然のことながら凝視に足るリアルな標本であるが、空間としては迫力あるインテリアにも感じられる。考えるに、びっしりと並んだ美しい標本の集合がある種壁紙のようであり、そこに一様に施されている標本箱のガラスカバーが均一化された内装素材の役を果たしているように感じられるのである。本展はまさしく展示とインテリアのはざまのようである。撮影:フォワード・ストローク
洪恒夫(東京大学総合研究博物館特任教授)
石の想像界
特別展示『石の想像界――アートとアーティファクトのはざまへ』がオープニングを迎えた。インターメディアテクの新しい試みとして、学術標本と現代美術作品とを組み合わせた実験展示である。美術史においてこれまでただの「材料」として扱われてきた石がなぜ、多くの現代美術作品の主題となり、またほぼ未加工の状態で作品に組み込まれるようになったのか。石の材質、かたちや模様に想像力が喚起された作家の作品を展示するだけではなく、人間の想像力を絶する、極めて長い時間性を有する「石」が人間の活動域に導入されていく過程を検証する展示である。この企画のひとつのアイコンとなるのが、前近代的な「驚異の部屋」の定番であった「廃墟大理石」(パエジナストーン)である。ロジェ・カイヨワの名著『石が書く』(1970年)をもって、パエジナストーンは石の美的鑑賞の中心的存在となる。自然の力で不随意的に生成される大理石の複雑な面に人間は必ず風景あるいは具象的なイメージを投影する。この想像力的原理が20世紀半ばの詩的表現に著しい影響を与えた。
大澤啓(東京大学総合研究博物館特任研究員)
出版計画再構築中(8)
だいぶ昔のことになる。編集者に企画書を届けて、結局、「ボツ」にされてしまった出版計画があった。築地小劇場の舞台写真集である。「築地」では、大正末期から昭和初頭にかけて、新興芸術が勃興した。小山内薫が興し、土方与志の率いた「ハイカラ」文化の拠点の一つであったのである。幸いにして、小山内をはじめ、築地関係者の残した資料体が手許に揃っている。1千点とは言わないが、5百点を超える写真で、ほぼすべての演目をカバーした資料集の刊行を目指し、デジタル化を進めていたのである。舞台芸術は一過性のものであり、役者の姿や美術の外観は写真にしか記録されていない。加えて、築地の全盛期は新興写真の勃興期でもあった。そのため、写真芸術における「モダニズム」の生成を探るフィールドにもなる。今日のデジタル画像処理技術が力を発揮するのは、このような出版企画ではないか。ただ図版を掲げるだけでは駄目である。画質で妥協することのない、美麗な出版物を産み落としてみたい。
西野嘉章(インターメディアテク館長・東京大学総合研究博物館特任教授)
ファサード
旧東京中央郵便局のファサードのデザインは、簡明かつ精緻である。東京駅前に建つ中央郵便局としての安定感を確保しつつ、古典的意匠に依存しない清新な現代性を実現している。逓信省営繕課の吉田鉄郎による外観設計の特徴は、以下の三点に認めることができる。まず「垂直と水平の均衡」である。柱梁の構成において、垂直をわずかに優先して神殿のような柱型のパターンを出し、一方で上部を走る胴蛇腹や1階の肉厚壁によって水平の連続性も表現している。次に「部分の対称性の導入」である。北側の立面に配された大時計と中央玄関のように、建物の立面ごとに対称性を考慮したまとまりを与え、全体が単調な繰り返しになるのを回避している。最後に「建物の階高の漸減」である。断面図に示す通り、下階から上階に向けて階高を徐々に減らして立面を落ちつかせており、これは現業室・事務室・吏員室という機能配置に応じた合理的な対応でもある。入念な設計は細部にも及び、外壁面は二丁掛タイルと役物の割付によって埋めつくされる。吉田鉄郎のファサードのデザインは、ヨーロッパのモダニズムの理念と構法に由来するものだが、同時にそれは、日本的伝統の中で培われた構成と抽象の美を継承するものである。ブルーノ・タウトの絶賛の核心もそこにあるだろう。
松本文夫(東京大学総合研究博物館特任教授)
北欧カラス事情
先日訪れたスウェーデンで見かけたカラスは3種。日本のハシボソガラスに近縁だが白黒模様のズキンガラス、日本でも冬になると大陸から渡来するミヤマガラス、そして向こうの街なかで目に付くのがニシコクマルガラスだ。ニシコクマルガラスは最新の分類ではカラス属(Corvus属)ではなくColoeus属とされているが、概ねカラスと思って間違いない。東京によくいるハシブトガラスと違い、ハトくらいの大きさなので、威圧感はない。色も真っ黒ではない。集団生活しており、公園や街の広場によく群れている。そして、人が座って何か食べ始めると、目ざとく見つけて意味ありげに近寄ってくる。ニシコクマルガラスは虹彩が白銀色なので、瞳が非常に目立つ。これは集団内でのアイコンタクトを容易にし、ある個体が見ている対象を回りに伝えているのではないかと示唆されている。そのせいか、彼らが隣のテーブルに止まってこちらの一挙手一投足をじっと見ていると、妙に落ち着かないのである。
松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)
出版計画再構築中(7)
出版社に原稿を届けてあって、いまだ刊行するに至らぬままになっている本もある。表題を『遊覧的彷徨——東西文献ミュージアム』とすることにした。2012年に出版した拙著『浮遊的前衛』の姉妹編とすべく、書籍、文献、出版について、これまでに書き溜めてきた原稿を全面改稿したものである。多くの人の感じるところであろうが、パソコンを使うようになって作文量が飛躍的に増えた。結果、A5判3百20頁の前拙著をさらに上回るものになりそうである。とはいえ、造本意匠で「姉妹編」であることは判るようにしたい。前拙著は「朱夏(赤)」でくるんだ。今度の本は、眼にも鮮やかな「青春(緑)」を基調色にしたい。もし後続があるようなら、「白秋(黄)」として、最後は「玄冬(黒)」で止めにする。谷崎潤一郎は創作にあたって五色の原稿用紙を用意していたと言われるが、文豪のダンディズムに倣う出版計画を実現したい。
西野嘉章(インターメディアテク館長、東京大学総合研究博物館特任教授)
二重らせん
遺伝子の本体をなすDNAは「二重らせん」の構造をもつ。らせん状の2本のヌクレオチド鎖が相補的結合をなし、片方の鎖を鋳型として新たな2本鎖を複製する。遺伝情報の継承と発現をにない、生命の連続性をもたらす根本の仕組みである。一方で二重らせんは、事例は少ないものの、人工物の構成原理にも採用されてきた。イタリアのサンパトリツィオの井戸では地下に降りる二重らせんの通路を設け、フランスのシャンボール城では城館中央に二重らせんの大階段を置く。これらの二重らせんは、上下の動線を交えることなく分離し、全体行程を連続した一つのシークエンスに仕立てている。その類例の中でも出色なのは、福島県にある旧正宗寺三匝堂(通称さざえ堂)であろう。六角形平面の塔状建物の内部には、二重らせんの斜路が組み込まれている。建物に入って右回りの斜路を上がり、頂上から左回りの斜路を降りて元に戻る。順路に沿って三十三観音が祀られており、上がって降りるだけで西国巡礼をしたことになる。すなわちここで二重らせんは、世界の縮図を表現する基本構造なのである。写真の模型は、教養学部前期課程の授業「空間デザイン実習」における学生の作品「KOMOREBI書房」(大島一武輝)である。さざえ堂の二重らせんにインスパイアされ、有機的な外壁と木漏れ日の光に特徴をもつ。
松本文夫(東京大学総合研究博物館特任教授)
Province
IMTに展示されているが、しばらく「由来不明」となっていたオオカミの頭骨がある。正確に言えば、「理解不能」だったのであるが。Canis lupusと書いてあるから、オオカミと考えていい。額段や口蓋を見てもオオカミのようだ。だが、理解しがたいのは、「Central Province」と読める走り書きがあることだ。中央プロヴァンス? フランスの? あんなところにオオカミが? もちろん、古い時代にはいた。15世紀にはパリ市内にまで侵入した「狼王」クルトーというのもいたくらいだ。だが、そんな古いものには見えない。しかもラベルの一部にキリル文字が印刷されている。なぜフランスでキリル文字? 待て。Provinceには英語で「地方」という意味もあるではないか。ならば「中央地方」という意味にすぎないかもしれない。調べた結果、モンゴルのトゥブ県は「Central Province」とも呼ばれていることがわかった。それ以外の情報を突き合わせても矛盾がない。これは、モンゴル産のオオカミの頭骨だったのである。
松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)
自分が面白いと思うことを人に伝える
大学生ボランティアが担う「アカデミック・アドベンチャー」という小中学生向けの展示案内プログラムでは、普段の準備や練習の時から、解説や説明という言葉を敢えて使わないようにしている。というのも、展示物に関する知識を伝達することが主目的ではなく、双方向的なコミュニケーションを通じて、子どもたちが展示物を自分の目で見て、それについて自分の頭で考える体験をするための手助けを行うことを重視しているからである。それを実現するためにどのようなアドベンチャーを作るのか、取り上げる展示物を決めるのも、リサーチを行いながら内容を組み立てるのも、大学生自身である。毎週、ボランティア活動日に集まる学生たちの試行錯誤に立ち会う立場にある私の目から見て、詰まるところ一番大切なのは、学生自身が「面白い」と思った最初の気持ちを子どもたちが追体験できるアドベンチャーになっているかどうかという点であるように思う。ひらめきや情熱といった感覚的なものを含めて、自分が面白いと思うことを「人に伝える」のがいかに難しいことか。学生たちの日々の努力に接し、私自身はそれができているかと研究に取り組む自分の姿勢を時折振り返る。
寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)
藪の中
普段は博物館勤務だが、鳥類の野外調査も行っている。本来はそっちが本職といってもいい。やはり野外調査がないと精神が乾涸びる。研究テーマはカラスの生活史であるが、近年、山の中でハシブトガラスを探していることが多い。丸の内にも普通にいるカラスだが、本来の生息地は森林だからである。森林のハシブトガラスはシャイで用心深い。生息環境を調べるために巣を探そうとすると、とんでもなく大変であった。カラスの行動を観察し、音声をプレイバックし、定点観察し、ICレコーダーで録音した音声から探索範囲を狭め……、それでも最後はカラスが巣に戻るのを実際に見て確かめるしかない。迷彩服を着てコソコソと林内に入ると、下生えの中に這い込み、偽装ネットを被って、息を潜めてカラスを待つ。それでも、枝に止まったカラスがじっとこちらを見て大声で鳴き始めたら、見破られているのである。
松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)
ザルツブルクに行ってきました
平素よりご来館いただきまことにありがとうございます。今年2月にザルツブルクで行われた『THE 11TH OPEN EUROPEAN TAXIDERMY CHAMPIONSHIPS® 2018』に交連骨格を出品し、同時に催されるセミナーを受けに英語ができないのに一人で行ってきました。これまで一冊の本を頼りに試行錯誤しながら一人でやっては来たが、はたして剥製や交連骨格の製作技術が発達している場所でも通用するのか? それを確かめるために、実際に審査員や他の出品者に評価をしてもらうのと、セミナーに参加して考え方や技術などを学ぶのが目的です。出品作品が並ぶ展示会場は、一般公開される前夜に参加者のみが内覧できる時間帯があり、出品者はそこで自身の作品の審査結果を知ります。開場とともに歓声を上げながら入場する参加者は自身の審査結果を確認し、お互いほめたり慰めたりします。幸い私が出品した作品は、交連骨格部門の専門家クラスで優秀賞をいただくことができました。会場では技術や表現について活発に議論し、気になる作品を観察する様子が見られましたが、これこそが技術が発展していく理由なのだと感じました。日本でもここ数年で実際に作られる方も増え裾野は広がったように感じます、そこから高みや深みを目指す人が多く現れるのを願ってやみません。ところで初めの海外、めちゃくちゃきつかったです。あと、食事がみんなしょっぱい!!
中坪啓人(東京大学総合研究博物館特任研究員)
出版計画再構築中(6)
傲慢と言えばそうかもしれない。書けるのは自分しかいない、否、そのように信じたい、と思う内容の本が、「インターメディアテク」構想とそれが実現に至った経緯を記録として綴ったものである。われわれが丸の内に開設した文化施設は、なにゆえ「ミュージアムを標榜しないミュージアム」であり、「インターメディアテク」を自称することになったのか。この根底にある考えは、やはり文字のかたちで書き残しておくにしくはない。「ミュージアム」の呼び名で市民社会のなかに定着してきた社会教育施設に、収蔵、調査、研究、展示、発信の機能充足を果たさせるだけでなく、独自の芸術的創造の苗床を定位させることはできないか。モノの保管場所は、いつの時代にあっても、イデア創発の触媒に満ち溢れている。ポスト「オリパラ2020」をどうするのか、それが問われている今こそ、そのことを改めて問うてみたいのである。
西野嘉章(インターメディアテク館長、東京大学総合研究博物館特任教授)
AIからIへ
小石川分館の建築博物教室で、高村大也先生※に『ことばのアーキテクチャ −−人工知能による言語の理解』という講演をしていただいた(→概要レポート)。高村先生は自然言語処理と人工知能の先端的な研究者である。この講演を通して人工知能研究について多くを学び、また自分なりに考えるきっかけを得た。そのポイントは三つある。第一に、人工知能の目的は人間の知性の置き換えか、あるいは人間の知性の支援・強化なのか。人知の置換と考えれば社会全体への脅威にもなるが、ボトムアップ的な視点から見れば個々の生き方が開かれる可能性を感じる。第二に、人工知能との対話における受容(解析・認識)から創出(推論・生成)への展開。この後段のプロセスは特に興味深く、デザインや創作ができ、仮説形成や価値創造に結びつく人工知能に期待したい。第三に、人工知能の中枢をなす機械学習の方法論の逆活用。ディープラーニングの多層的な方法論を人間の日常行為にリモデル化して導入し、知の外部化に逆行する「知の再内部化」ができるのではないか。時間とともにAIのAが徐々に消えて、新たなIが立ち上がるかもしれない。講演に合わせて作られたアーキテクトニカ・コレクションは「語彙のネットワーク」の3次元モデルである。(※ 東京工業大学教授、産業技術総合研究所人工知能研究センター研究チーム長)
松本文夫(東京大学総合研究博物館特任教授)
水中を飛ぶ
IMTの2階に、二足歩行する動物の骨が集まっている。この中に、マジェランペンギンの骨格もある。ただでさえ奇妙なペンギンだが、骨格にするともっと奇妙だ。まず、こんなに体幹が直立した鳥はいない。大腿骨は脊椎と直角、地面とほぼ水平に伸びる。そして膝を直角に曲げ、ふしょ節(鳥のくるぶしから指の付け根までを構成する骨)と指骨をべったりと地面につけて立っている。ペンギンは立っている間じゅう、空気椅子状態なのである。さらに、飛びもしないくせに妙に頑丈で長い胸骨、発達した竜骨突起も目に付く。そして何より、恐ろしく丈夫そうな烏口骨、そして太い腕の骨格。ペンギンの翼(正しくはフラッパー)は大変な力を持っていて、コウテイペンギンに思いきり殴られれば骨折しかねない。これらは全て、抵抗の大きな水中を飛ぶように泳ぎ、かつ氷の上を延々と歩くためだ。あのコミカルな見かけの下で、ペンギンだって苦労しているのである。
松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)
出版計画再構築中(5)
欧米の古書店から送られてくるカタログは、好個の読み物の一つである。内容は、もちろん古書店の専門に拠って様々であるが、あるときから「本に関する本」という下位分類項目の存在を意識するようになった。これをもって「書誌学」的な視点、などと大げさなことを言うつもりもない。しかし、本を好きな人は本を書く、あるいは本について書くのも好きである、という単純な事実の発見は、自分にとって案外意味深いものであった。いまにしてそのように思う。結果的に、本好きが高じて、本についての原稿をいくつも書くことになったばかりか、本についての講演会もあちこちで開くことになったわけである。これらのテキストや資料は、他者の本に関するものと自分の本に関するものに大別できる。ということで、前者は『拙稿集』、後者は『拙著考』の表題で出版したいと考えている。それがいつの日のことになるか、先の見通しの立たぬ日々が、当分のあいだ続きそうである。
西野嘉章(インターメディアテク館長、東京大学総合研究博物館特任教授)
録音再生の起源
人間の声を封じ込め、それを異なる時空間で再生しようとする願望が技術的に実現したのは19世紀後半のことである。エドゥアール=レオン・スコット・ド・マルタンヴィルが1857年3月25日に録音機「フォノトグラフ」の特許を取得し、シャルル・クロが1877年4月30日に録音再生機「パレオフォーン」の設計を科学アカデミーに提出するなど、録音技術の黎明はフランスにあった。しかしこの発明を実用的な技術に結びつけたのが、1877年12月24日に米国で「フォノグラフ」の特許を申請したトーマス・エジソン(1847-1931)である。フォノグラフの原型は真鍮の輪胴に溝の切られた錫箔を巻きつけ、二つの雲母製の振動板によって録音と再生をそれぞれ行う装置であった。1878年4月24日に設立されたエジソン・フォノグラフ社はレコード産業の道を切り開いた。シリンダー・レコードを中心に音質を追求したエジソンは縦振動型の録音再生に拘ったが、主流はエミール・ベルリナーが発明した横振動型のディスク・レコードとなり、エジソン社が蓄音機製造から撤退した1929年にはディスクを中心とした市場が確立していた。インターメディアテク3階に展示しているエジソン蓄音機コレクションからは、エジソンが19世紀末から改良を重ねて追求した「音のデザイン」の系譜がうかがえる。
大澤啓(東京大学総合研究博物館特任研究員)
日本画の鳥たち II
「鳥類写生図」(河辺華挙 編纂)のうちの一巻には、小鳥たちの動きを捉えるためのスケッチが集められている。ここに描かれた鳥は(想像で描いたのでなければ)全て生きた状態で観察されたはずだ。驚くべき事に、江戸末期から明治中期に描かれたにも関わらず、カナリア、サトウチョウ、ホンセイインコなど、外国産の飼い鳥も描かれている。どれほど貴重で高価であったことだろう。一つ、特に気になる鳥がある。体は黒く、頭は真っ白で、嘴と脚が赤い。画材が限られているので完全に天然色ではないかもしれないが、こんな色合いの鳥は日本にはいない。コムクドリかとも思ったが、どうも描きぶりが違う。これはシロガシラツグミの台湾亜種ではないか。この鳥は東南アジアの島嶼に住み、台湾亜種は頭が真っ白で特に美しい。今や希少になってしまったこの鳥も、はるか昔、日本まで運ばれて来て、絵師の家の縁側の鳥籠の中にいたのだろうか。
松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)
痛風
北海道出張中に、右足の親指に激痛が走り、骨折かと思って医者に飛び込んだ。痛風の発作であった。長年の豊満な食習慣のために尿酸が身体中にたまり、それが一部瓦解することによって発作が起きる。この発作と同時に、私の体の中で、免疫機構の一斉蜂起が起きたのだろう。いままで経験しなかったような体調の変化が始まった。あるときは、体の中をナメクジのような生物がにょろにょろと這いずり回り、あるときは、ピキピキ体のあちこちがしびれる。ナメクジとピキピキがお互い忍び寄り同期し、勢い高調に達すると、二度目の発作。その話を京都の医者にしたところ「どうもあんたの言っていることは痛風ではないみたいだ」という。北海道の医者の結果をもう一度、ちゃんと調べようということで、血液検査をしたが、北海道の医者の言う通り痛風という結果になった。ピキピキを音楽に例えるならば、「くるみ割り人形」『金平糖の踊り』だ。チェレスタの旋律は一見平和だが、直後に不穏なファゴットの下降音階が続く。一方、ナメクジと発作のムーヴメントは「展覧会の絵」『バーバヤガの小屋』と、家内はこれを聞いていて、「ああ、いずれもロシアものだね」と言う。この話を東京の医者にしたところ「どうもあんたの言っていることは痛風ではないみたいだ」という。京都の医者の結果をもう一度、ちゃんと調べようということで、血液検査をしたが、京都の医者の言う通り痛風という結果になった。それからおおよそ半年、治療も生活習慣改善も甲斐あって、かなりよくなってきた。いまではときどき、ウォトカをぐびとやっている。医者の言っていることはどうもいい加減だ。
森洋久(東京大学総合研究博物館准教授)
建築の時間
歴史的建造物の「転生」がよく見られるようになった。当初の役割を終えた建築が、その空間特性を維持しつつ、以前とは異なる機能をもった施設に生まれ変わる。2000年に開館したロンドンのテート・モダンは、旧バンクサイド発電所を改修してつくられた近現代美術館である。スイスの建築家ユニット、ヘルツォーク&ド・ムーロンは、大胆かつ抑制されたデザインによってこの設計コンペを制した。旧発電所のタービン・ホールを巨大な吹抜として残し、現代美術のインスタレーションの場として活用している。建築の転生の身近な事例を探せば、インターメディアテクは旧東京中央郵便局のオフィスを、当館小石川分館は旧東京医学校の校舎を出自とするミュージアムである。時間の流れの中で建築資産を柔軟に使い続けることは、持続可能な社会をめざす上で避けて通れない課題であろう。すなわち「建築の時間」のデザインが必要とされている。それは建築を静態ではなく動態のシステムとして捉えることにつながる。時間推移は単調で予定調和的なものとは限らず、予測不能で突発的な変化も起きる。建築の空間継承は保存と創造の営為である。
松本文夫(東京大学総合研究博物館特任教授)
出版計画再構築中(4)
一九八〇年代初めのことだったと思う。『ヤヌス學大全』というタイトルの本を出したいと一念発起し、古代から現代に至るまでの「ヤヌス現象」について書き連ねることを始めた。いくつかの雑誌にそのテーマで連載をおこなったことで、原稿の蓄積が進みはしたものの、様々な要因が重なって、いつの間にか書き続けることを止めてしまった。ということで、この本もまた中途半端なままになっている。原稿を整理するなかで、「大全(スンマ)」という言葉が気になり出した。トマス・アクイナスの『神学大全』がそうであるように、「大全」を名乗るなら、それが何についてのものであるにせよ、全体を包摂してみせるとの意識を堅持しつつ、事を進めねばならないはずである。ならば、自分の考える本ではどうか。古代から現代まで、というのはあまりにも大風呂敷な課題設定で、とうてい「大全」を名乗る資格などない、ということになる。その意味での反省はある。しかし、タイトルだけはえらく気に入っているのである。
西野嘉章(インターメディアテク館長、東京大学総合研究博物館特任教授)
ミュージアムとジェンダー
ウプサラ博物学三代、ルドベック、リンネ、ツュンベルクの活躍した時代の学術界は男性中心であった。その中にあって、今回の特別展示出品物の作者名に見える唯一の女性が画家アンナ・マリーア・テロット(1683-1710)である。父親に手ほどきを受け、兄弟とともに様々な出版物や美術の仕事に携わったが、女性である彼女には自分の才と技により独立した美術家となる環境は与えられなかった。『「花と果実」スケッチブック』が展示に組み込まれていることは、この事実に思いを至らせ、当時の男性中心社会を生きた女性の存在を無視していない点において、意義をもつ。インターメディアテクに展示している帝大時代の学術遺産もまた、いかに「マッチョ」な世界にあったかという事実は、例えば館内の肖像画や肖像彫刻がすべて男性像であることからわかる。歴史的事実を変えることはできないが、現代的な問題意識をもってそれを眺める観点はミュージアムが新たに創出し得る。東京大学の歴史を伝える資料体をいまここで公開し、未来に残していく意味を問うために、ジェンダーの問題をどう扱うのか。考えるだけではなく、行動に移していかねばならない。
寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)
建築模型の復元模型
昨年秋に「雲の伯爵——富士山と向き合う阿部正直」展の設営のためウプサラ大学博物館「グスタヴィアヌム」へ訪れる機会があった。当時、私はロンドンに滞在していたため、スウェーデンへは飛行機にて2時間程のフライトである。時差の影響もさほど受けず、日本からのメンバーと合流するまでに数時間あったことから、空港からウプサラへ向かう前にストックホルム市内の美術館を訪れた。ストックホルム近代美術館には多くの20世紀前衛作家の作品が並んでいる。中でも「第3インターナショナル記念塔」の建築模型を復元したレプリカは想像以上に大きく、加えて複雑な構造からは100年以上前に構想されたものとは思えない新鮮な印象を受ける。ウラジミール・タトリンによって構想されたこの記念塔が実際に建築されることは無かったが、模型を復元することによって、当時の構想の壮大さを現代に伝えている。このような前衛的な作品を肌に感じつつ、今後の新しい芸術の潮流が北欧の地から生まれる予感さえも感じた。(写真はストックホルム近代美術館)
菊池敏正(東京大学総合研究博物館特任助教)
博物学の等角図
開催中の特別展示は、リンネを中心にスウェーデンのウプサラで生まれ、近代博物学の王道を築いた学術資料を直に観る絶好の機会である。リンネの弟子ツュンベルクが1775-1776年の日本滞在から母国へ持ち帰った工芸品など10点あまりの小物も、「里帰り品」として展示されている。ツュンベルクが帰国後に著した『ヨーロッパ、アフリカ、アジア紀行』(1770-1779年)の図版で詳細に描かれ、ジャポニズムに先がけて欧州に「日本趣味」を普及させるうえで重要な役割を担った民族学標本である。ツュンベルクに代表される西洋の学者を通じて近代西洋博物学が日本に導入され、従来の本草学の学術的枠組みを抜本的に革新したことは周知の通りである。一方、彼らが母国に持ち帰った日本の工芸品や絵には、19世紀ヨーロッパの美的感覚を一新させる造形美とそれを支える独自の美術的手法が凝縮されていた。特に、本草学の和本に収められている水彩画や木版を観ると、遠近法を用いない、平たい空間表現が特徴的である。等角図に基づくこの大胆な空間表現は、標本描写に新たな可能性を与えただけではなく、空間認識そのものを変えるものであった。そういう意味で、本草学資料の国際的な再評価の時期が来たともいえよう。
大澤啓(東京大学総合研究博物館特任研究員)
紙に描かれた生物たち
4月24日から、特別展示『ルドベック・リンネ・ツュンベルク――ウプサラ博物学三代の遺産より』が始まった。スウェーデンの誇る自然史学者、ルドベック、リンネ、ツュンベルクにまつわる貴重な資料を展示しており、それらスウェーデンより来た資料に加えて、東京大学所蔵の資料も関連展示として公開している。全体を見て感じるのは、生物が生きている時の姿をうつしとった図譜や図版の存在感の大きさである。写実性という点でいうと、スウェーデンのオロフ・ルドベック(子)が1693年頃から1710年にかけて出版した『鳥類図鑑』の図版は、今回剥製と並べて展示しているため、よりその精密さが際立っている。特に色彩の再現力や細やかな羽の表現には目を見張るばかりである。色彩といえば、明治10年頃に描かれた『梅園魚譜』(元は毛利元寿によって江戸後期に描かれたもの)も素晴らしい。魚のきらめきを表現するために、雲母や金粉と思しき画材を用いて描かれている。展示ケースの上からだけではなく横から見てみると、魚が照明を反射して更に生き生きとして見えるのである。描き手たちの工夫に思いを馳せながら眺めていると、あっという間に時間が経っていることに気がつくに違いない。
秋篠宮眞子(東京大学総合研究博物館特任研究員)
頭文字L
ウプサラ大学博物館裏の公園で鳥を見ていたら、ひとりの老人がやって来て、同じベンチに座り、ワインを煽りながら私に話しかけてきた。残念なことにスウェーデン語なので一言もわからない。すると老人は英語に切り替え、「バードウォッチングか」と尋ねた。双眼鏡の話をしたり、手笛の吹き方を教わったりしていると、目の前のゴミ箱に1羽のカササギが舞い降りた。驚いたのはその時だ。老人がカササギを指差して、「ピカ・ピカだ。知っているか」とサラリと言ったのである。Pica picaはカササギの学名。スウェーデン語ではSkataというので全く違う。この老人は別に鳥類学者というわけではなく、せいぜいちょっとしたバードウォッチャー程度のようなのに。だが、考えてみたらカササギの学名を命名者まで書けばPica pica L. 1758だ。命名者は「L.」、イニシャルだけで済ませてよい唯一の人物、リンネその人である。さすがウプサラはリンネのお膝元と言うよりなかった。
松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)
日本画の鳥たち I
日本画に描かれる鳥は、お世辞にもリアルではないことがある。だが、それは必ずしも、画家の観察眼そのものの限界を示してはいない。絵とは「その時代とその技法のお約束」でしか描かれないものなのだ。近代科学発祥の地であるヨーロッパとて、18世紀の博物画を見てみれば、そこにとんでもないデフォルメを見て取ることができようし、年代を追ってデフォルメが変化してゆくのも追うことができる。河辺華挙の編纂した「鳥類写生図」を見ると、絵師が研鑽を積むための、完成された絵の背後に隠された観察眼というものがよくわかる。そこには明らかに死骸とわかる、ダラリと横たわった鳥が描かれ、色合いやサイズ、羽毛の枚数までが記入されているのである。種名も書き込まれているが、それを読まずとも、絵だけで十分に同定できる精度である。こういった精緻なデッサンを理解した上で、型式通りの日本画の構図に落とし込んだのであろう。
松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)
“時”と協働するデザイン
エイジングされたもの、つまり自然に経年変化したものは、時間の経過でしか現わせない趣きや力がある。“インターメディアテク”も80余年が経過した昭和初期の建築と、古くは明治の初めに作られた標本、そして学内等で使用されていた家具や什器など、エイジングされたものによるハーモニーが魅力を生み出し、訴求効果を高める要因となっている。新造の施設はゼロから施すデザインが空間の表情をつくるが、リノベーションは新築では決して出せない魅力の創出が可能である。それはデザイナーの感性と“時”がすり合って生まれるデザインといえよう。小学校の廃校をミュージアムに改装した長野市の戸隠地質化石博物館、高校の廃校を活用した静岡県のふじのくに地球環境史ミュージアムなど、学校建築のリノベーションは初めから学び舎の記憶を持った建築がミュージアムに更なる雰囲気を与える。時間が経過したものとの協働は“時”がデザインの一翼を担うのである。(写真は戸隠地質化石博物館)
洪恒夫 (東京大学総合研究博物館特任教授)
スフィンクスの謎
もう、いまではそう珍しいことでもないが、ホンダのアシモくんが初めて二足歩行ロボットとして登場した時は驚いた。アシモくんの開発チームのメンバーは、開発にあたって、このような人間の似姿を製作しても宜しいだろうかと、ローマ法皇にお伺いを立てたそうだ。「はじめ四本足、次に二本足になって最後に三本足になる動物はなにか」というスフィンクスの謎かけがまさにそうであるように、「歩く」ということは人生を表している。そして、「歩く」ことと対になるのが「知恵」である。ホモサピエンスは、アフリカで二足歩行をはじめたことによって「知恵」を得た。「歩く」ことが人生を表している一方で、歴史的に見て「知恵」が超越者を表すことはそう珍しくない。代表的なものに、古代エジプトの思想や、ユダヤのメシア思想などがある。「知恵」の似姿としての人工知能はいま、ゲームの世界では超越者となりつつある。医療の世界では難しいガンの早期発見をやってのけたりする。ゲームや画像認識の世界にとどまらず、これから、社会全般にありがたい超越者として、人工知能が広がってくるのであろうか。だが、世の中を眺めているとイカサマ人工知能も多い。つまりは霊感商法的な....。
森洋久(東京大学総合研究博物館准教授)
サウンドレイヤー
サウンドレイヤーとは、音による現実拡張の試みを多層的に展開する革新的なコンセプトと技術である。インターメディアテクでは、株式会社THDのアイディア提案と技術協力により、ミュージアムにおけるサウンドレイヤーの可能性を探求するプロジェクトを2017年7月から始動させた。来館者が専用アプリを入れたスマートフォンを持ってインターメディアテクの各展示エリアに入ると、コンテンツ――展示空間デザインについての音声解説、展示物や空間に合わせてカスタマイズされた音楽・音響等――が自動再生される。これら複数の音がレイヤー状に積み重なり、来館者一人一人がその時に聞きたいものを自由に選択できる。このような構想を実現させるためのシステム開発とコンテンツ制作が現在進行中である。通常、ミュージアムを訪れた人は、展示物を見る、あるいはその脇に付けられたキャプションを読むといった視覚をはたらかせる行為に注力する。従来のオーディオガイドがこの視覚的行為の補助的な役割を担ってきたのに対し、サウンドレイヤーは聴覚をメインの感覚器官とすることで、人々のミュージアム体験そのものを変革する。インターメディアテクを実験場として、人々の認識世界を音で変えるプロジェクト、聴覚分野の最先端テクノロジーを用いた「音のメディア芸術」と言ってもよい。
寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)
横浜港鎖港談判使節団の「面貌」
写真左は江戸時代末期の外国奉行池田長発(28歳)、右は日本初の医学博士の一人三宅秀(16歳)である。両者ともに、文久3年(1863)12月から翌年7月にかけて派遣された幕府遣欧使節団の一員で、滞在先のフランスで撮影された。通称横浜港鎖港談判使節団とよばれ、安政五箇国条約によって安政6年(1859)に開港した横浜港の再鎖港要求を目的として派遣された。当時目付兼外国奉行の池田はその正使として交渉にあたったが、結局失敗に終わった。池田は攘夷論者であったが、帰国後は開国論者に転じ、幕府からは役目不履行を理由に蟄居を命ぜられ、不遇の余生を送った。一方、三宅は組頭田辺太一の従者として随行した。滞仏中に「解剖場」や外科道具の店を訪れ、大いに見分を広めて帰国し、明治から昭和初期にかけて日本の近代医学の普及と教育発展に寄与した。同時期に撮影された写真の「面貌」から、その後の異なる命運にも思いを致すことができる。
白石愛(東京大学総合研究博物館特任助教)
インテリジェンス
教養学部前期課程で映像制作の授業を担当している。今年度の制作課題のテーマは「インテリジェンス」とした。AIの進歩が現実化し、シンギュラリティの到来が予測される中で、私たちの知性はどうなっていくのか。人間と社会の次なるイメージを映像で表現したい。2つのグループが作品を制作した。「知外法権」(高倉・石井・中尾・新井)は、高い知性をもつ人間が国家に抹殺される近未来社会で、システムの解体に立ち向かう3人の大学生を描いた作品である。国民の知性を集約した巨大な権力システムに対する闘争の物語であり、知性の外部化と制御の問題に着眼している。もう一つの「Minds, Brains, and Manuals」(星野・中畑・増渕)は、人々の日常的な会話や行動が「マニュアル」に依存することを発見した主人公が、自分の手引書と訣別するまでを描く作品である。チューリングテストに続く有名な思考実験「中国語の部屋」を出発点として、人間の内面や意識の不可知性を扱っている。どちらの作品も、AI のバラ色の未来予測に加担するというよりは、人間の知性に対する批判的な自問自答をベースにしている。骨太の問題意識を感じさせつつも、映像としてはスリリングで没入できる作品であった。(写真は「知外法権」)
松本文夫(東京大学総合研究博物館特任教授)
出版計画再構築中(3)
いくつもある出版計画のなかで、最初に具体化したいと思っているのが『村上善男●頌』である。弘前大学で教員生活を送るなかで、知り合い、以後長くつき合いのあった美術家村上善男との交流を綴ったもので、書簡や原稿によって、村上の人となりや、考えを語らせたいと考えたのである。美術家が没するまで多くの手紙をやりとりした。村上の送り届けてくる手紙や郵便物は、文章のかたちで表明された精神においても、また書簡や小包のかたちに込められた造形においても、実に美しかった。だから、すべて捨てずに取っておいたのである。もちろん、それが一冊の本に纏まるだろうなどとは、つゆほども思わなかったわけであるが。村上から教わった言葉に「荷姿」というのがある。いまや、郵便小包の時代ではない。ために、紐の掛け方にも、切手の貼り方にも、美学的な判断の介入する余地などなくなってしまった。しかし、「荷姿」には送り主の人と成りが現れる。だから心せねばならないのである。
西野嘉章(インターメディアテク館長、東京大学総合研究博物館特任教授)
絵画修復
アカデミア内の壁面に設置している肖像画(油画)の内、2点が現在修復中である。アカデミア以外でも、インターメディアテク内には複数の肖像画が展示中であり、その中には修復を終えたばかりの作品も存在する。絵画修復の専門家により、クリーニング作業が進められ、状態の悪い作品については複数回、クリーニング作業を繰り返しつつ、カンバスの補強等も行われている。作業が進むにつれて、描かれた当初と近い色彩になり、随分と違った印象に変化してくる。しかしながら、修復前のイメージを覚えている人は少なく、大きな色味の変化に気づかれることは殆どない。これは修復が違和感のないよう順調に出来ているとのことでもあるだろう。絵画作品に限らず、展示中の標本については常に劣化を続けており、時間の流れに逆らい、それらを完全に止めることは出来ない。しかし、日々のメンテナンスや定期的な修復により、劣化のスピードを可能な限り遅くすることは可能であり、今後も継続的に進めていきたいと思う。
菊池敏正(東京大学総合研究博物館特任助教)
鳥類繁殖調査
東京都鳥類繁殖調査に参加して、丸の内界隈の鳥類の様子を調査して来た。皇居ならいざ知らず、東京駅前や銀座に鳥なんかいるのか、と思われるかもしれない。だが、鳥はどこにでもいる。確かに多くはないが、都市とは、人間が勝手に考えているほど不毛な場所ではない。大手町オアゾから新丸ビルに向けて歩き、内幸通に入ったところで、スズメを見つけた。人間が歩いているすぐそばまで来て、しきりに鳴いている。口には何かをくわえている。そして、すぐ近くで「シリリ、シリリ」という声が聞こえる。この騒がしいのは、スズメのヒナだ。どこかにスズメが巣を作っていて、親鳥が餌を持って来ている。邪魔しないよう少し離れて見ていると、スズメはイチョウの枝の折れ口に開いた洞に潜り込み、また出て来た。ここがスズメの巣だ。この日、大手町から銀座まで約2キロを歩いて見た鳥は11種、84羽だった。
松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)
インターメディアデザイン その二
インターメディアテクをインターメディアデザインならしめている最たるものは、空間自体の体感性にある。よく「体験型…」と耳にするが、自身の行動的充足を促しているのではなく、ここでは感性への刺激的実感と捉えている。そこには物体性と空間性の両立があり、物体性を例えるなら、宝石や生物(ここでは標本であるが)は、カタログや図鑑で見るよりも実物を見る方が感動的であるし、空間性でいえば寺院や教会に実際に訪れることまた然りである。つまり、「見る」「知る」の前に「感じる」ということ。この両立がモノと対峙するだけにとどまらない視野を与えてくれる。さらには、窓から望む東京駅舎との親和性や高層ビル群とのコントラスト、また隣接する商業空間とのギャップは実際に訪れてみなければわからない。そんな「価値観」という名の違和感は「自分」や「現在」に対する客観的な眼差しを提示してくれる。
関岡裕之(東京大学総合研究博物館特任准教授)
モバイルミュージアム・ボックス
2015年から16年にかけ、トヨタ財団の助成を受け、フィリピンにて移動型展示キットを制作した。箱の中に展示物を搭載してどこにでも出かけていき、蓋を開ければ展示が出来上がるというコンセプトをもつ「モバイルミュージアム・ボックス」は、ミンダナオ国立大学イリガン校等のキャンパス内で公開され、学生が日常の大学生活を送る中で、意図しなくてもミュージアムに接する機会を作り出した。重要なのは、プロジェクト期間終了後の展示キットの運命である。私のような外部の人間の関与や外部予算がなくなった途端に「モバイル」しなくなるようでは、現地の人たちにとって本当に必要とされていたとは言えない。フィリピン人の共同研究者とともに、展示キットの継続的な活用をいかに可能にするかを見据え、展示内容や箱のデザインの決定といった、本プロジェクトのさまざまな進行段階で、現地の人たちを巻き込むことをプロジェクト・デザインの柱にした。幸いにして、その後も、このキットはミンダナオ島内で「モバイル」しているとの報告が届いている。
寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)
生きるとは、行動することではない。呼吸することである。
「お元気ですか」「はい。元気です。」 何気ない挨拶の言葉の中に「気」がある。儒教では、元気とは天地の間にあって万物生成の根源となる精気だそうだ。「気」という語が、「大気」や「気体」、「電気」や「蒸気」といった物質的な根源を表すものとして使われる一方で、「気になる」「気をつける」「気力」「気合」など、精神的な活動の表現としても使われる。この物理的世界と精神的世界を結びつけるものが呼吸であると言える。たとえば、キリスト教においてプネウマが神とその子を結びつける聖霊として現れる。東洋だけではなく、西洋、あるいは、それより広い世界で、息、気息は流れるものであり、世界を構成する要素を結びつけ、お互いのエネルギーとエントローピーの交換する役割を担っている。特に、生命と宇宙の根源をつなげるものとなれば、霊的な存在としてしばしば認識される。「生きるとは、呼吸することではない。行動することである。」と言ったのは、偉大な思想家、ジャン・ジャック・ルソーである。彼の時代は科学や市民社会の時代であり、行動が世界を変えようとしていた。しかし、そういう言葉を言わしめた彼の人生は、数奇で運命的であり、大きな時代の流れの中で、ルソーも、思う存分呼吸をしていたのだ。
森洋久(東京大学総合研究博物館准教授)
八角形の柱
インターメディアテクの柱型は八角形である。KITTEのアトリウムにも八角形の柱とそのモチーフが残されている。なぜ八角形なのだろうか。一つの手がかりは当館のIMTロゴマークに示唆されている。1931年に竣工した旧東京中央郵便局は、相対する東京駅の配置に呼応して外壁が「へ」字型に折れている。45°屈曲したこの外形に対して、八角形の独立柱ならば向きを変えずに整然と配列できる。かたや1914年開業の東京駅には八角形の大ドームがあり、既往の計画でも45°の配置が生かされていた。「八角形」は中央郵便局が東京駅とうまく共存するための幾何学だったのではないか。あらためて展示室の柱を見上げると、八角形の一辺の長さと天井の梁幅が一致したスマートな納まりである。実用面においても、角が面取りされた柱は現業室での円滑な搬送業務に適していた。1階の現郵便局に立ち並ぶ黒大理石の八角柱は、逓信省技師の吉田鉄郎が敬愛したストックホルム市庁舎にも見いだせる。八角形の柱には、設計者のしなやかな合理主義と意匠へのこだわりが凝縮されている。
松本文夫(東京大学総合研究博物館特任教授)
「キノコ」
「コロナード」の什器に、キノコ標本が数点、並んでいる。一見、展示室に棲息しているのかと見間違うほどのリアリティを醸し出しているが、れっきとした人工物である。展示されている模型は、明治12年に初代山越長七が創業した山越工作所で作られたものである。使用されているムラージュ技法は、明治43年(1910)年頃、長男の山越良三(二代目山越長七)が、ウィーン大学で習得してきたものである。ムラージュ(日本語で鋳型の意)とは、蝋製模型のことで、雌型に蝋を流し込んで出来た立体物を彩色して作る。初代山越長七の方は紙製の人体模型を得意としていたという。したがって山越工作所では、紙製模型も蝋製模型もどちらも作れたはずである。蝋を選んだのは、本体から型をとれるという利点があったからなのかもしれないし、キノコの瑞々しさを再現するのに、紙より蝋の方が適していると考えたからなのかもしれない。ところで、あくまで個人的な感想だが、この写実的なキノコ模型、見て美しいとは感じるものの、美味しそうと感じないのが不思議である。もっとも、本模型はすべて毒キノコとのことである。
秋篠宮眞子(東京大学総合研究博物館特任研究員)
謹賀新年。
国内外の多くの方々からご支援を賜り、一年を大過なく過ごすことができた。ここに迎える新しい年もまた、実り多き年になるよう願うばかりである。来る三月末、インターメディアテクは開館以来、五年目の節目を迎える。企画展、講演会、音楽会、上演会、ワークショップなど、多種多様なイベントに忙殺された月日であった。図録、目録、写真集、(不定期刊行)冊子を出版し、併せてグッズ開発もおこなってきた。支援と連携の環も着実に拡がっている。国内の篤志家からは、ジャズSP盤コレクション、蓄音機コレクション、自然史学標本コレクションの寄贈があった。国外からは歴史的展示ケースの寄贈、国有コレクションの長期ローンの実現があった。協働企画展の申し入れも各所から頂き、なかのいくつかは実際に海外展として実現した。海外からの来館者の評判も頗る良い。「入館無料」の文化施設、その公益性を外国人の方が高く評価してくださっているのである。今年も職員一丸となり、社会から付託された使命を全うしたいと思う。
西野嘉章(インターメディアテク館長、東京大学総合研究博物館特任教授)
劇場という教育現場
9月に訪れたウプサラ大学博物館「グスタヴィアヌム」の建物は1620年代にウプサラ大聖堂の真向かいに建てられ、3世紀に亘って増築された。建物の象徴は、それとわかるドーム型の屋根である。そこには、1662年にオラウス・ルドベック(1630-1702年)によって構想された「解剖劇場」がある。今でもグスタヴィアヌムの玄関から石畳の階段を屋根裏まで上ると、来館者を唸らせる空間が見えてくる。中央に配置された解剖台を囲むように6列の階段席が段々にそびえている。階段席といっても、座る場所はないほど窮屈である。そこでルドベックらが一般公開の解剖を行うなか、階段席に立つ学生たちは吐き気を抑えつつ勉強し、最上階の特別席では上流階級のマダムらがパフォーマンスを観覧していた。解剖劇場の音響も特殊である。解剖台周辺の音は全空間に響くが、階段席から質問があったとしても中央からはよく聞こえない。インターメディアテクにも階段教室「アカデミア」が設置されている。教育現場の建築を考えるよいきっかけとなった。
大澤啓(東京大学総合研究博物館特任研究員)
登り龍
IMTの正面玄関から入った瞬間、目に飛び込んで来るのが、壁に直立する巨大な骨格だ。しばしば恐竜と間違われているが、ワニである。全長は7.6メートルほど。これはマチカネワニ、大阪大学吹田キャンパスを造成中に発見された化石のレプリカで、原野農芸博物館より寄贈されたものだ。マチカネワニは40〜50万年前、日本にも分布していた。現在はマレーガビアルと同じ
松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)
丸の内カラス事情
丸の内には1ペアのハシブトガラスがナワバリを持っている。オフィスの窓から見えるので、時々観察している。丸の内なんてお洒落で小綺麗なところで、どうやって餌を取るのかと思っていたが、人が暮らしている限りゴミは出る。丸の内のカラスも、朝一番に北口のガード下辺りで何か拾って来たのを見かけた。このペア、一昨年は丸ビルのド真ん前に営巣したが、さすがにこれはすぐ撤去された。その次は換気塔の中に営巣したようだが、これも失敗したらしい。去年は東京駅の中に営巣したが、これも失敗。そして、今年はどこに営巣したのかさっぱりわからない。営巣しても営巣しても人間に「ここはダメ」と撤去されてしまうので、絶対に人間に見つからないような場所に巣を作ったのかもしれない。丸の内はカラスにとっては、あまり住みやすい場所ではないようだ。
松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)
出版計画再構築中(2)
いずれ単行本にしたいと考えているもののひとつが「対談集」である。対談の中味は、まったくもってバラバラである。もちろん、誰か相手のいる話であるし、また場を設定してくれた出版社の都合もある。ということで、その都度ごと、テーマに一貫性がないのは致し方ない。しかし、それにしても、と改めて思う。かくも多様な分野に頭を突っ込んできたとは我ながら驚きではある。好奇心に富むとか、関心領域が広いとか。たしかに、そのように言えば聞こえは良い。が、ありていに言えば、対談企画を持ち込む出版社の意のままに、なにからなにまで無節操に引き受けてきたことの結果なのである。話相手を眼の前にもつことで、普段の自分と違った世界へと誘われる。そこが対談の面白いところである。また、どのような喋り方をしているのか、自分にとって反省の機会にもなる。ということで、是非とも出版したいと思うのであるが、多人数にわたる対談相手の許可が得られるかどうか。そう考えると、やはり気の滅入る仕事ではある。
西野嘉章(インターメディアテク館長、東京大学総合研究博物館特任教授)
インビトウィーン・ワールド
なぜ演劇創作プロジェクト「Play IMT」を続けるのかと自分に問うならば、この取り組みを始めた時から答えに変わりはない。死して動かない動物や人工物ばかりが並ぶミュージアムに、生きて動く俳優たちの身体が加わった時に生み出される新しい世界が見てみたい。インターメディアテクの空間と展示物とそこに集まる人々に着想を得た、ここでしか実現できない独自性ある創作活動をしてみたい。このような「演劇×ミュージアムの実験」に対する期待と意欲があるからである。演劇パフォーマンス『Play IMT (7)—インビトウィーン・ワールド』のタイトルに用いた「インビトウィーン」という言葉は、ミュージアムと演劇という「二つの世界をつないだ間に生まれてくるもの」を意味している。俳優という存在がそのための「媒介役」であることに注目してほしいという思いも、この言葉がもつ二重の意味に込めた。館内の天井に翻る布のインスタレーションと、肖像画の額縁の中に俳優がうつし出された映像インスタレーションは、このコンセプトを暗示する仕掛けとなっている(12月3日まで公開)。
寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)
たかが展示、されど展示
展示づくりに携り30年以上になる。「展示とは何だろう?」、こうしたことに自問自答する機会も増えた。展示は文字通り、展(ひら)き、示(しめ)すこと、つまり、しまい込んでいたり、畳んでいるものを表に出して露わにすることが基本である。そういう意味ではただ単に収蔵庫にある標本を展示室に持ち出して解説を施すことも展示である。しかしながら「展示」は見せ方如何によって観覧者に対する訴求力が大きく変わってくる。ある意図をもって(コンセプトといってもよい)伝えたいメッセージを最適な見せ方で展示すると、感じてもらえるものが大きく違ってくる。当館本館では「オープンラボ」と銘打った展示を行っている。収蔵がテーマであり、その導入部ではガラス張りの収蔵庫を象徴的に配置している。そこでは収蔵庫らしく雑然としながらも標本の存在感を高めるにはどうしたらよいか、そんなことをあれこれ構想した末のかたちを展示に仕立て配置している。
洪恒夫 (東京大学総合研究博物館特任教授)
溶接のこと
日ごろからご来館誠にありがとうございます。こっそり始まりました研究者コラムお楽しみ頂けてますか? 華の無い画像で大変恐縮でございますが真鍮の什器、館内で展示物を載せているアレ、の製作を本郷本館の地下でしている様子です。什器は、載せる物の固定・転倒防止をし展示物の保全のためもありますが、載せる展示物の魅力をそっと引き出だす目的もございます。ご観覧される方に自分からどんどん魅力を主張できる展示物もありますが、その一方それらの陰に隠れてなかなか自分を主張できない展示物もございます。そんな主張の弱い展示物の背中をそっと押すような気持ちで製作した什器に載せております。ご観覧の際は、そんな展示物にも目を留めていただければ幸いです。なので 什器としては、“自分が目立たない”のが正解、注目されたら負けなんです。※ロウ付けのため真鍮の部材をステンレスの針金で仮留めします。耐火ブロックは、直前に粉砕しました。
中坪啓人(東京大学総合研究博物館特任研究員)
エアトン教授の机 <東京大学 木製什器1>
インターメディアテクの窓辺にひっそりと佇んでいる木製の机がある。この机に近づくと自らの身体感覚によって、ほんの僅かな違和感を感じ取ることができる。この机は、1873年にイギリスより工部省工学寮工学校に招かれた世界最初の電気工学教授、W・E・エアトン教授が自ら設計し大工が製作した執務机である。床から天板まで780mm。インターメディアテクでは、東京帝国大学・東京大学の講義室や研究室で使用していた木製机を収蔵展示しているが大半は床から天板まで755mmである。2017年現在、大手家具メーカーで販売している既製品のオフィスデスクは天板まで720mm。自分の身体に合う家具の身体性とは、想像を越える心地良さに集中力は増すばかりであろう。「身体」つながりでいうと、エアトン教授と一緒に来日した夫人のM・C・エアトンは医学研究者で滞在中に『日本人の体格と身体の形成』という論文を書いているのが興味深い。時代を超えて、この机から様々な身体性に馳せる時が味わえる。
上野恵理子(東京大学総合研究博物館特任研究員)
イギリスと日本の漆
2017年5月より、ロンドンに滞在し研究活動をおこなっている。ヴィクトリア&アルバート美術館にて、イギリスにおける油性塗料と漆の比較研究をするためである。とりわけ、18世紀頃に、西洋で流行した「ジャパニング」と呼ばれる漆を模した油性塗料は興味深い。ロンドンでは調査に加え、日本から様々な材料を持ち込み、現地で調達した材料と合わせて、実験的な制作も進めている。この度、制作物の一つが同美術館にて開催される「Lustrous Surfaces」展に展示される事となった。本展覧会は、日本、中国、韓国おける漆器を含む作品の表層に着目した展覧会である。日本の風土に適した素材とも言える漆をイギリスで使用することに、多少の不安も感じつつも制作を進めたが、特に問題もなく乾燥する漆を見て、改めて素材の強さを実感している。まもなく滞在を終え日本に帰国する予定である。日本食が恋しくなる一方、いささか名残惜しい部分もある。
菊池敏正(東京大学総合研究博物館特任助教)
鏡の中の自分はなぜ左右が逆さ?
理科の先生にこんな質問をして困らせたことがあった。理科の先生は、光の反射の対称性を懇切丁寧に説明してくれたのを記憶している。しかし、問題が対称であればあるほど、上下が逆さにならず、左右だけが逆さになるという非対称性に矛盾を感じるようになるばかり。しかし、数日たってほどなく、理科の先生に質問したのは誤りであることに気づいた。国語の先生に質問するべきだった。問題は光の原理にあるのではなく、「上・下」と「左・右」という二つの言葉の性質の違いにあることに気づいた。「上・下」は自分が見ている方向によらず、常に方向が保たれる絶対的な性質をもつ語である。一方、「左・右」は、見ている方向に基づき、方向が決まる相対的な性質を持つ語である。改めて鏡をのぞきこむと、鏡は、本来物理的には左右を逆さにするものではなく、前後を入れ替える道具であり、前後が入れ替われば、その言葉の性質によって自ずと左右が入れ替わる。「私から向かって右」というように、前方を明示的に規定すれば、鏡の中でも入れ替わることがない。少々気張っていうならば、物理学的な問題は往々にして言葉の問題であったりするものだ。
森洋久(東京大学総合研究博物館准教授)
富士山の雲、ウプサラの雲
先月、スウェーデンのウプサラ大学博物館「グスタヴィアヌム」にて特別展示『雲の計測――阿部正直が見た富士山』を設営してきた。富士山の山頂に現れる雲を絶え間なく撮影し、その生成過程と種類を分析し続けた阿部正直(1891-1966年)の先駆者は、実はウプサラにいた。1896年にパリで初めて出版された『国際雲アトラス』は、ウプサラに研究拠点を置いていた気象学者ヒューゴ・ヒルデブランド・ヒルデブランドソン(1838-1925年)の主導のもとで構想された。今でも日本の雲を見慣れた目でウプサラの秋の空を眺めると、独特な広がりと濃度を持つ雲が目立つ。雲はどこでも雲であるが、地域によってその形が限りなく変化しているように見える。19世紀末にヒルデブランドソンとともに世界各地の雲の共通点を探り、普遍的な雲の定型を定めたラルフ・アバークロンビーやアルベルト・リッゲンバッハの斬新な着想と偉大な計画に改めて感心した。
大澤啓(東京大学総合研究博物館特任研究員)
インターメディアデザイン その一
おそらく多くの研究者がそうであろう。私の場合は自身について名告るとき、まず“デザインの研究を…”と述べる。誰もがわかるその語句と曖昧模糊としたその語意に、消化不良でもあれば “デザインの研究とはなにか?”と問われる。矢継ぎ早に“様々なデザインの…云々”と補足こそするが、内容に踏み込むほどに難解にもなりかねない。むしろ、名刺代わりに展示室を一巡りするのがいちばんだ。“百聞は一見にしかず“でなければ相手にとって得られるものは何もない。デザインの仕事を物証なしに語ることはほぼ不可能だからだ。インターメディアテクに存在するデザインを私は「インターメディアデザイン」と称している。元来デザインの領域とは、まるで星座のごとく形成されるもの。ひとつのジャンルで語ることはできない。あらゆるジャンルを架橋する、あるいは統合する、それがすなわちインターメディアデザインである。
関岡裕之(東京大学総合研究博物館特任准教授)
阿部正直のガラス乾板写真
昭和初期の気象学者阿部正直のガラス乾板を整理している。概ね縦120mm、横164mmのキャビネ判約1840枚のほか、手札サイズ335枚がある。阿部が昭和3(1928)年から16年にかけて御殿場から撮影した富士山にかかる雲の記録写真の他、著書や論文の図版に使用した撮影器具・計測器具の写真、気流実験の写真などである。状態は良好で、簡単なクリーニングをし、スキャナーでスキャンをしている。現在約1680枚のスキャンを終えた。その後フォトショップで角度を直し、白黒を反転させる。1枚あたり計10分ちかく要する根気のいる作業だが、反転させて現れる写真は自然の織りなす美しい造形の数々であり、霊峰富士の名に相応しい雄姿をみせてくれる。阿部正直が富士山と千変万化の雲に魅せられたのも肯首できる。
白石愛(東京大学総合研究博物館特任助教)
建築の記憶
建築の記憶を一つの造形物にまとめたらどうなるか。その実験試行として制作した模型である。古代エジプトから現代までのさまざまな建築を立体的にコラージュし、3Dプリンタで出力している。カルナック神殿、パンテオン、ランス大聖堂、東大寺南大門、桂離宮書院、サヴォア邸、森山邸など作者の記憶に残る内外30以上の建築が、おおむね古い順に下から組み上げられた。ファサード、外観形態、内部空間、骨格構造といった、その建築の特徴的な部分を縮尺1/300で表現している。建築単体を再現した「縮小模型」、建築の部分を抽出した「空間標本」に続く、建築を集成統合する第三の模型表現の試みである。ここで選択された建築群は、建築史の流れを網羅的にカバーするものではない。しかし時代の推移とともに、建築の物象においては量塊的なものから繊細なものへ、空間においては閉じたものから開かれたものへ、という大きな変化の流れが見えてくる。(模型『建築の記憶』は東京大学総合研究博物館小石川分館で常設展示中)
松本文夫(東京大学総合研究博物館特任教授)
インドに咲く花、あるいはインドに散る花
特別展示『植物画の黄金時代—英国キュー王立植物園の精華から』の会場で、注目していただきたい植物画がある。イギリス人植物学者がインドで現地の画家を雇い入れて描かせた「カンパニー画」である。この呼称は、絵画制作の依頼主がイギリス東インド会社(=カンパニー)社員であったことに由来する。インドとヨーロッパとの混合様式である、とその絵画様式の特徴を一言で説明はできるものの、ムガル帝国が没落し、イギリスが商業的・政治的にインド支配を進めた当時の社会状況からわかるように、両者は決して対等な関係ではない。主観的な印象を述べることが許されるならば、ヨーロッパの自然主義的表現を求められたインド人画家の筆先から、封印したはずの自分のルーツとなる伝統的美意識が図らずもほとばしり出た瞬間が留められているような気がする。そのような名もなきインド人画家を主人公にした小説をいつか書くとしたら、「インドに咲く花」というタイトルにしようか。いや「インドに散る花」がよいか。植物画を前に、想像の花も開いた。
寺田鮎美(東京大学総合研究博物館特任准教授)
IMT特別展示「植物画の黄金時代—英国キュー王立植物園の精華から」に寄せて
キュー王立植物園より28点の植物画を借りて、展示を行うことになった。植物園というと、緑あふれる憩いの場を想像する人も多いに違いない。しかし、キューがキューたるゆえんは、大規模な研究機関として存在感を示し続けていることにある。古くから植物に関する豊富な資料を蓄積してきており、植物画もその一部である。植物は、乾燥させて標本にすると、本来の色彩や立体感を失う。乾燥標本も情報を残す貴重な手段であり、見た目にも美しいとはいえ、「植物の素顔」を後世に伝えようと思うなら、植物画家の技に頼らざるを得ない。白の紙を背景とするなど、一定のルールに基づき、紙面という限られた空間に、どう植物を配置し情報を散りばめるか、そこが工夫のしどころである。「生きている植物」をいきいきとした姿で伝えるのが植物画だ。本展の図録表紙やポスターに使われている、著名な植物画家ゲオルク・ディオニシウス・エーレト(1708-1770)のチューリップ図を見れば一目瞭然だろう。まさに平面から飛び出して来んばかりではないか。
秋篠宮眞子(東京大学総合研究博物館特任研究員)
「ジャズ・ディスコブラフィー」の迷宮
2013年から蓄音機音楽会を定期的に開催している。その間「湯瀬哲コレクション」のデータベース化に向けてSPレコードの整理を進めてきた。SPレコードのシングル盤約5000枚、アルバム約380冊を含むコレクションは、インターネットのない時代に個人によって構築されたとは思えない。現物を見ながらレコードの各面に収録されている曲の録音情報を調査し、データとして纏めると多くの発見がある。湯瀬氏がレコード蒐集に没頭していた時代は、個人の調べそして国内外のアマチュアとの文通がジャズ史に関する基本情報を得る唯一の方法だった。しかし主要大学に「ジャズ・スタディーズ」部門が設立されている現在、レコードのデータ目録に「ビッグ・データ」が導入されつつある。万単位でレコード情報を分析すると、戦後日本におけるジャズ市場の動向や流通状況が見えてくる。今まで静かに佇んでいたコレクションの個々のレコードの間に、新たな関係性が生まれつつある。
大澤啓(東京大学総合研究博物館特任研究員)
夏鳥の季節
インターメディアテク(IMT)のStudiolo(収蔵展示室)には多数の鳥類剥製がある。階段を上がった正面に見える部分は、山階標本の定位置であり、当館の「顔」の一つであろう。IMTのオープン以来、この鳥たちの配列は変化し続けている。分類群で並べるか、色味や見え方を意識するか、何かテーマに沿って配置するか、それは我々の意図であり、企画であり、時に遊び心である。今、Studioloの角、オナガドリの左側部分には、夏鳥が到来中だ。キビタキ、オオルリ、サメビタキ、コチドリ、コアジサシ、アオバズク、ヒメアマツバメ、ショウドウツバメ、オオヨシキリなど、東南アジアから飛来して日本で繁殖する鳥たちが並んでいる。棚の上の、ライオンのようなタテガミを持った2羽は、渡りの途中で日本に立ち寄ったエリマキシギ。残念ながら日本ではこの繁殖羽をまとった姿は見られないが、せめて、標本で確認して行って頂きたい。
松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)
鳥たちの森
インターメディアテク(IMT)の大階段を登りきったところに広がるガラス張りの収蔵展示室、それがStudioloである。ここには山階鳥類研究所よりの寄託、(旧)老田野鳥館よりの寄贈を含む鳥類標本約500点が収蔵されている。一部では京極夏彦氏の小説になぞらえて「由良伯爵の部屋」と呼んで頂いているようだが、デスクと椅子とタイプライターと羽ペンもあって、確かにそんな雰囲気はある。デスクは法学部の教授室備品だったもの、タイプライターも学内でかつて使われていたローヤル製のものだ。私の中で、あのデスクは「先生の机」であり、姿を見せない謎の教授がいる、という設定である。先生は今、日本産の鶏の一品種である天草大王の標本を山階鳥研から借りて研究中らしい。足にまで生えた正羽が特徴だ。机の上にはハシブトガラス(骨格)も止まっている。なお、羽ペンは私が先生にお貸しした。
松原始(東京大学総合研究博物館特任准教授)
出版計画再構築中(1)
この三月末で定年を迎えた。インターメディアテクの館長職はいま少し継続することになった。博物館勤務は都合二十三年になるが、その間、傍らに置き去りにしてきた関心事がいくつもある。ひとつは「十五世紀プロヴァンス絵画史研究」と「キリスト教図像学」の宗教美術研究。この研究課題では、戦前の日本人の残した南仏古画紀行の先見性、宗教美術における「ことば」と「イメージ」の相関性、美術作品に有する物理的な組成など、語りたいことが山ほどある。しかし、出版環境は絶望的である。部数のでない専門書の出版を敢えて引き受ける、勇気ある書店がどこにも見当たらないからである。この点では、欧米の方がいくらかましかも知れない。売れない本は出さないとの考え方に違いはないが、しかし、内容が有意であると見れば、少部数の刊行に踏み切ってくれるところもなくはないからである。問題は論法を欧米風に切り替えねばならないこと。これがかなり大変、と言えば大変である。
西野嘉章(インターメディアテク館長、東京大学総合研究博物館特任教授)